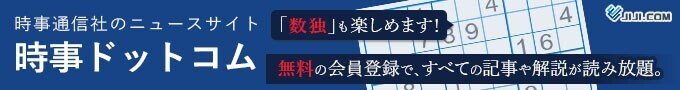「デジタルGメン」知られざる闘い◆レベルアップする海賊版、次の標的は…【時事ドットコム取材班】(2022年08月28日08時00分)
正義のハッカーや国際弁護士が所属する、海賊版専門の民間調査チームがある。ウェブ上で他人の著作物を無断公開している人物を特定し、警察にも情報提供する彼らは、いわば「デジタルGメン」のような存在だ。Gメンの活躍もあって、国内では著作権侵害の摘発が相次いでいるが、海賊版との闘いはここへ来て困難さを増してきている。(時事ドットコム編集部 太田宇律)
悪質さ増す海賊版
デジタルGメンは、海賊版対策団体「コンテンツ海外流通促進機構」(通称・CODA)を中心に結成された。活動の実態を取材するため、2022年8月、東京都中央区の築地市場にほど近いCODA本部を訪ねた。
取材に応じてくれた後藤健郎・CODA代表理事は、1985年から海賊版対策に従事する大ベテランだ。「あのころは家庭用ビデオデッキが普及した影響で、違法コピーを貸して荒稼ぎする『ビデオショップ』が至る所にあった。47都道府県を全部飛び回り、一軒一軒『もうしない』と誓約書を書いてもらった」と振り返る。

当時、海賊版と言えば、ビデオのダビング(複製)や漫画のコピー本など、正規品より劣化したものばかりだった。だが、90年代に家庭用パソコンが普及すると、海賊版の流通主体はウェブ上へと移行。データ化された海賊版は正規品とほとんど品質が変わらず、簡単に世界に拡散してしまうやっかいな存在になった。その後のスマートフォンの普及も被害に拍車を掛け、後藤代表理事は「今は小中学生でも海賊版にアクセスできる時代になってしまった」と話す。
最新技術で対抗
国際化・高速化・高品質化が進む海賊版にどう対抗するか。CODAは経済産業省や賛同企業と連携し、2021年4月に「国際執行プロジェクト」を始動させる。善意のIT技術者である「ホワイトハッカー」や、著作権問題に詳しい国際弁護士に協力してもらい、海賊版サイトの運営者特定から国際的な権利執行までを一括して行うというもので、このプロジェクトの下、Gメンの活動が本格化していった。
CODAによると、現在活動しているGメンのハッカー班は3つ。班のメンバーはサイバーセキュリティー企業の技術者たちで、悪質性の高い海賊版サイトの運営者を追跡している。このほかに、法律家の班や、動画投稿サイトなどの違法コンテンツを目視で探し当てる削除申請班もあり、申請班は24時間体制でウェブ上を監視しているという。

ハッカー班は違法なハッキングを仕掛けるのではなく、ウェブ上に公開されている情報を解析し、運営者を追い詰める。サイト設計書に当たる「ソースコード」や、IDに使われた文字列、SNS上の古い投稿など手掛かりに、身元特定につながる「隙」を見つけるやり方だ。運営者は海外のサーバーや匿名で使えるドメイン(ネット上の住所)で巧妙に身元を隠しているが、利用しているサーバー業者などが判明すれば、弁護士による情報開示請求につなげることができる。
「逃げ得」は許さない
映画を勝手に短く編集する「ファスト映画」の撲滅は、Gメンが挙げた大きな成果だ。投稿先のユーチューブ本社がある米国の裁判所に発信者情報の開示命令を求め、得られた情報を日本の警察に提供。違法動画で広告収益を得ていた「ポケットシアター」や「ファストシネマ」といった主要アカウントの運営者らの逮捕につなげた。
摘発の報道後、最盛期は55件あったファスト映画のアカウントのほとんどが自主的に削除された。だが、Gメンは削除前の投稿を保存しており、「逃げ得」を許さなかった。

「趣味の夜釣りをしているとき、逮捕者が出たという記事を見て、『いけないことだったんだ』と初めて気付いた」と話す岡山県の20代男性会社員もGメンが特定した一人。男性は報道に動揺し、その場でアカウントを削除したが、後日、自宅にCODA側から封書が届き、同居の母親にも違法行為が露見することになった。
男性は動画から広告収益を得ていなかった。深く反省していることも踏まえ、刑事事件化は見送られたが、賠償責任までは免れない。「自分の軽率な行動で、映画制作に携わる人たちに大きな損害を与えてしまった」と肩を落とした。
漫画村の「負の遺産」
ファスト映画や漫画海賊版サイト、漫画のせりふを丸写しする「ネタバレサイト」などが次々に摘発され、好調にも見える海賊版との闘い。しかし、違法サイトの摘発はむしろ困難さを増しているのが実情だという。
出版社などでつくる海賊版対策団体「ABJ」の伊東敦広報部会長は「全ての発端だったのは漫画村事件だ」と指摘する。2019年9月に運営者が逮捕された「漫画村」は、海外のサーバーが使われていたものの、日本人運営者による日本人向けのサイトだった。ところが、事件が大きく報じられたことで「『日本のコンテンツはもうかる』と世界中の悪人が考えるようになった」といい、海外に住む外国人が日本人向けに運営する海賊版サイトが急増。その典型例が、約2000億円相当のただ読み被害が生じたとみられている巨大サイト「漫画BANK」だ。
中国当局を説得せよ
「トップページに作品検索用の窓しかないシンプルなデザインだったが、漫画のタイトルを打ち込むと、最大6万点を超える作品をただ読みでき、出版業界に衝撃を与えた」(ABJ・伊東広報部会長)という漫画BANK。漫画村運営者の逮捕後間もない19年11月に開設されると急激にアクセス数を伸ばし、集英社などの出版大手4社は連携して撲滅に動いた。

当初試みていた検索サイトへの削除要請は難航したが、サイト情報の解析などを基に、漫画データの保管先が米国の通信社であることを特定。現地裁判所が発信者情報の開示を認め、21年12月、中国・重慶市に住む中国人の男がサイト運営に関わっていることが判明した。
さらに手ごわい「レベル3」とは。後半では、デジタルGメンの「次の標的」を解説します。