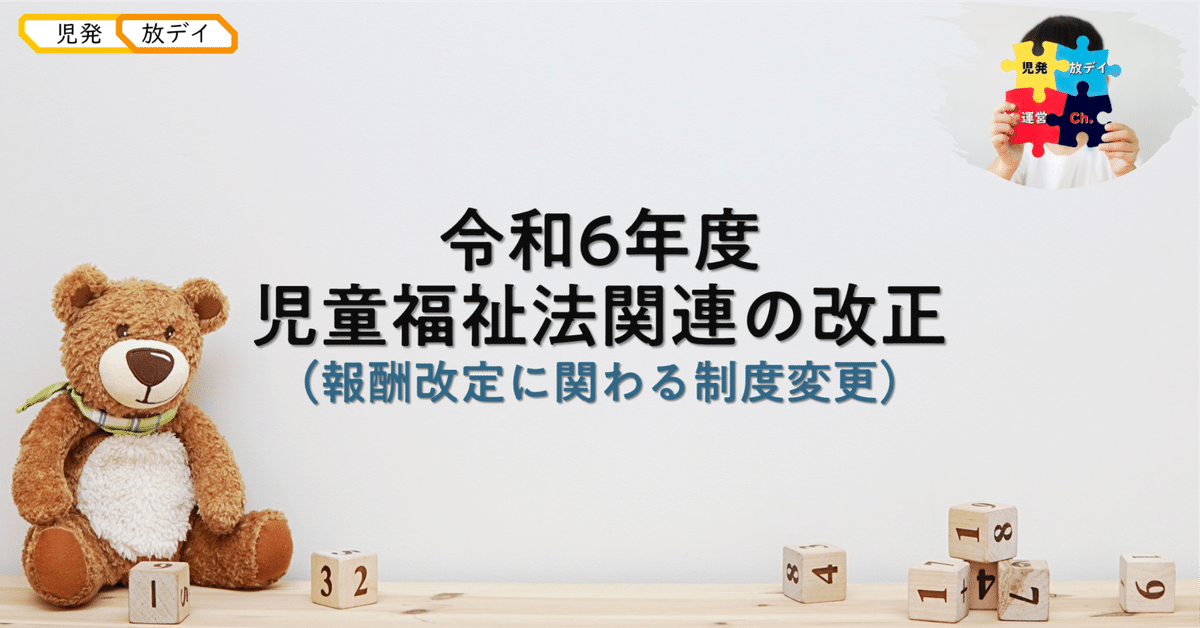
令和6年度 児童福祉法関連の改正
児童発達支援や放課後等デイサービスの報酬改定が目前に迫ってきました。先行して4月1日からの児童福祉法関連の府令が発表されましたので、改正内容を確認していきます。
児童発達支援や放課後等デイサービスの運営情報を中心に配信していきます。ぜひコミュニティにご参加ください。
改正対象府令
児童福祉法施行規則の一部を改正
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正
児童福祉法関連がこども家庭庁の管轄となりましたので、厚労省の省令から、内閣府の府令へ変更となっています。
概要
用語改定
指導、訓練など → 支援
指導訓練室 → 発達支援室
心理指導担当職員 → 心理担当職員
心理指導 → 心理支援
屋外訓練場 → 屋外遊技場
保護者 → 通所給付決定保護者(最下部に詳細)知識技能の付与 → 知識技能の習得
制度面
意思をできる限り尊重するための配慮(意思の尊重)
指定児童発達支援の提供に当たっては、心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行わなければならない。(5領域支援)
指定児童発達支援プログラムを策定しインターネット等で公開(令和7年3月末まで経過措置)
インクルージョンの推進
個別支援計画書
心身の健康等に関する領域の支援が必須(5領域支援)
インクルージョンの観点が必須
担当者会議において「障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保」
指定障害児相談支援者へ個別支援計画書の交付が義務化
相談支援専門員 または セルフプランでは市町村担当者
児発管の責務として、「障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない」。(意思決定の尊重)
指定更新時に、情報公表対象支援情報の公開(WAMネット)を指定権者が確認することを必須
医療型児童発達支援の廃止に伴い、支援(旧指導及び訓練)に併せて「治療」が追加
管理者の勤務について、同一敷地内の兼務が可能でしたが、「同一敷地内」を削除
改正について
発表と関連法令について
詳細は、発表された官報などをご確認ください。下記では省略している部分などございます。
現行の法令リンク
条文が省略や参照されていますので確認しながら読んでください。
(障害児入所施設・障害児相談支援も改正の対象です。必要に応じて e-Gov法令検索 から現行の法令をご確認ください。)
用語について
障害児通所支援に関する検討会などでも指摘されておりました、訓練・指導などの用語が支援などに改定されています。(上記概要に一覧を示しています。)
これに伴い、規則・基準においてすべて用語が置き換えられています。訓練・指導などを個別支援計画書や運営規程で使用されている場合は、変更が望ましくなります。
他の用語についても、指定通所支援基準に基づく用語が望ましいため、1度見直しが望ましいです。
意思の尊重
障害児及び保護者の意思をできる限り尊重するための配慮が求められるようになりました。障害者総合支援法(大人のサービス)では意思決定支援が求められるようになりましたが、子どもにおいては保護者が居ることから、意思の尊重になっています。
指定児童発達支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するための配慮をしなければならない。
意思の尊重は、事業所の方針・個別支援計画書の担当者会議・児発管の責務で定められています。
個別支援計画書の策定にあたっては、障害児及び保護者の意思確認を十分にしているかが大切になってくるかと思います。
5領域支援
指定児童発達支援の提供に当たっては、心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援が義務化されました。
指定児童発達支援事業者は、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援の確保並びに次項に規定する指定児童発達支援の質の評価及びその改善の適切な実施の観点から、指定児童発達支援の提供に当たっては、心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行わなければならない。
心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援が、次の5領域支援を示していると考えられます。児発と放デイは、検討会において新ガイドラインで詳細を示す話がありましたが、令和6年4月までに発表されることはないと思います。
健康や生活
運動や感覚
認知や行動
言語やコミュニケーション
人間関係や社会性
支援プログラムの公表
指定児童発達支援プログラムを策定しインターネット等で公開が義務化されます。(令和7年3月末まで経過措置)
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに指定児童発達支援プログラム(前条第四項に規定する領域との関連性を明確にした指定児童発達支援の実施に関する計画をいう。)を策定し、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
前条第四項に規定する領域は、「心身の健康等に関する領域」(5領域)を指しています。
関連性を明確にした指定児童発達支援の実施に関する計画とありますので、5領域に対応した支援プログラムを公表することが求められています。
公表方法は、自己評価・保護者評価をインターネットで公表しているはずですので、同じ場所で公表することになると考えられます。
インクルージョン
児発・放デイを利用することで、保育・教育等の支援を受けることができるようにすることで、全ての児童が共に成長できるよう、地域社会への参加と包摂の推進が努力義務になりました。
指定児童発達支援事業者は、障害児が指定児童発達支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、障害児の地域社会への参加及び包摂(以下「インクルージョン」という。)の推進に努めなければならない。
「地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにする」という文言が気になりますが、学校へ通うという文言から不登校への配慮など緩やかになった気はします。
個別支援計画書
意思の尊重、5領域支援、インクルージョンが個別支援計画書の策定に盛り込まれました。
アセスメントと意思の尊重
児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(以下この条において「アセスメント」という。)を行うとともに、障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
原案作成(5領域とインクルージョン)
児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、第二十六条第四項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならない。この場合において、障害児の家族に対する援助及び当該指定児童発達支援事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて児童発達支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
第二十六条第四項に規定する領域は、「心身の健康等に関する領域」(5領域)を指しています。
担当者会議(意思の尊重)
児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。
個別支援計画書の交付(相談支援専門員又は市町村給付決定担当者)
児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画を作成した際には、当該児童発達支援計画を通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者に対して指定障害児相談支援(法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。)を提供する者に交付しなければならない。
障害児相談支援またはセルフプランの場合に市町村給付決定担当者への個別支援計画書の交付が義務づけられました。情報交換の方法を含め、今後調整が必要になります。
自己評価・保護者評価の明確化
これまで、自らによる評価と保護者による評価と記載されていた条文が、自己評価・保護者評価と明確に規定されました。
指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、その提供する指定児童発達支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、指定児童発達支援事業所の従事者による評価を受けた上で、自ら評価(以下この条において「自己評価」という。)を行うとともに、当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児の通所給付決定保護者(以下この条において「保護者」という。)による評価(以下この条において「保護者評価」という。)を受けて、その改善を図らなければならない。
規定されただけで、従前とやることは特に変わりません。
児発センターについて
福祉型・医療型が統合されることによる、医療型に関する規程が削除されました。
医療型児童発達支援の廃止に伴い、支援(旧指導及び訓練)に併せて「治療」が追加されています。
治療(上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童に対して行われるものに限る。)を行う場合は、医療法に規定する診療所として必要とされる数の従業者と設備が必要となります。
難聴児に関わる規程が削除されました。聴力検査室が必須でなくなり、静養室が必須になりました。(指定済みの事業所は当分の間は従前の規程で良い)
重症心身障害児に関わる規程が削除されました。遊戯室、屋外遊戯場、医務室及び相談室が設けないことができるという条項がなくなります。(指定済みの事業所は当分の間は従前の規程で良い)
あわせて、定員の規程も変更され、児発センターについては10名以上となります。(令和9年3月末まで猶予期間)
令和9年3月末まで、医療型・難聴児に関わる規程・重症心身障害児に関わる規程は経過措置となります。(設備など一部は当面の間とし期間が設けられていません。詳細は附則をご確認ください。)
管理者
管理者の勤務について、これまで同一敷地内の兼務が可能でしたが、「同一敷地内」が削除されました。
指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定児童発達支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
従前通り、事業所内の他の職務の兼務または、同一法人の事業所などで兼務ができます。同一敷地内が無くなったことで、近隣の施設との兼務が可能になりました。(これまで道路1つ挟むだけで兼務ができなかった。)
児童発達支援管理責任者
児発管の責務として、障害児及び保護者の意思の尊重が義務づけられます。
児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。
事業所の方針・個別支援計画書にも意思の尊重が義務づけられましたので、すべての業務において障害児及び保護者の意思を大切にするよう、支援する側の考えを押しつけないように求められています。
指定更新時のWAMネット公表確認
指定の更新は6年に1度ありますが、情報公表対象支援情報(WAMネット)での公開情報が適切に報告されているかを指定権者が確認することが義務づけられました。
WAMネットへの情報公開ができていない場合に、指定の更新を拒絶されることになります。
その他
居宅訪問型児童発達支援では、個別支援計画書において、インクルージョンの関連は問われていません。
保育所等訪問支援では、個別支援計画書において、心身の健康等に関する領域(5領域)との関連は問われていません。
総量規制において、都道府県(指定権者)の意向のみならず、市町村の意向を反映できるよう変更されます。
記事をお読みいただきありがとうございました。
今後も、児発・放デイの運営に関わる情報を配信していきますので、ぜひコミュニティを継続いただき支援いただけると幸いです。
ありがとうございました。
追記: 「通所給付決定保護者」 は用語変更ではありませんでした(2024.2.1)
通所給付決定保護者については、従前から使用されており、新しく変更があった用語ではありませんでした。
大変お騒がせし申し訳ございません。
次の保護者評価の変更を見て勘違いしたわけですが、なぜここで通所給付決定保護者に変更してきたのかが気になる所です。
指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、その提供する指定児童発達支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、自ら評価を行うとともに、当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児の保護者による評価を受けて、その改善を図らなければならない。
指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、その提供する指定児童発達支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、指定児童発達支援事業所の従事者による評価を受けた上で、自ら評価(以下この条において「自己評価」という。)を行うとともに、当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児の通所給付決定保護者(以下この条において「保護者」という。)による評価(以下この条において「保護者評価」という。)を受けて、その改善を図らなければならない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
