
流行のAI技術を障害福祉サービスに使える?
ChatGPT/Copilot/Bardと複数の生成AIが流行っていて、学校などでも活用しようという動きがあります。児発や放デイで活用できるのか、なにが嬉しいのか、なにが危ういのか、考えてみました。
児童発達支援や放課後等デイサービスの運営情報を中心に配信していきます。
記事前半を読むだけで十分な情報となるように心がけていますが、記事後半の深掘りはコミュニティ限定とさせていただいています。ぜひコミュニティにご参加ください。
生成AIってなに?
生成AIと言う名前で、OpenAI ChatGPT / Microsoft Copilot / Google Bard を中心に、2023年から急速に社会進出した技術です。
説明を書いても良いのですが、せっかくですのでChatGPTに「生成AIってなに?」って聞いてみました。
生成AI(Generative AI)とは、新しいコンテンツを生成することができる人工知能の一種です。このAIは、既存のデータを学習して、新しいテキスト、画像、音楽、ビデオなどを作成します。生成AIの特徴としては以下のような点が挙げられます。
- データからの学習: 生成AIは大量のデータを解析し、そのデータのパターンを学習します。この学習により、新しいコンテンツを生成する際の基礎となる知識を得ます。
- コンテンツの生成: 学習したデータを基にして、テキスト、画像、音楽などの新しいコンテンツを生成します。例えば、ChatGPTはテキストを生成し、DALL-Eは画像を生成します。
- 多様な用途: 生成AIは様々な分野で使用されています。マーケティング、芸術、エンターテイメント、教育、研究など、多岐にわたる領域で活用されています。
- 創造性の強化: 生成AIは人間の創造的プロセスを支援することができます。アイデアの創出、デザイン、物語作成など、創造性が求められる作業において有効です。
- 自動化と効率化: 一部の作業において、生成AIは大量のコンテンツを迅速に生成することができ、時間とコストの節約につながります。
生成AIは非常に強力なツールですが、倫理的な使用、著作権の尊重、偏見や誤情報の防止など、多くの課題にも直面しています。これらの技術を使用する際には、これらの点にも注意を払う必要があります。
なんだか難しい回答をしてくれましたが、全体像をつかめてますし、問題点の指摘もしてくれています。
これで終わりません、ChatGPTの使い方として「小学生でもわかるように説明してください」と続けて聞くことができます。
もちろんです。生成AIについて、小学生にもわかるように説明してみますね。
生成AIは、コンピューターがいろんなものを作り出すことができる魔法のようなものです。たとえば、こんなことができます。
- お話を作る: あなたが「宇宙に行く物語が読みたい」と言えば、生成AIはそのお話を作ってくれます。まるで、お話を作る作家さんのようにね。
- 絵を描く: 「きれいな花の絵が見たい」と頼めば、生成AIは色とりどりの花の絵を描いてくれます。絵を描く画家さんみたいです。
- 音楽を作る: 「楽しい歌が聴きたい」と言えば、生成AIは楽しいメロディの音楽を作ってくれます。まるで、音楽家さんが作ったような音楽です。
この生成AIは、たくさんの本を読んだり、絵を見たり、音楽を聴いたりして、いろいろなことを学びます。そして、その学んだことを使って、新しいものを作り出すんです。
でも、生成AIが作るものは、いつも完璧とは限りません。だから、人間のお友達が、その作ったものを見たり聴いたりして、どうだったか教えてあげることも大切です。また、生成AIはただのコンピューターなので、人に優しくする心や、正しいことをする心は持っていません。だから、人間が正しい使い方をしてあげることも、すごく大切なんですよ。
小学生が興味を持つように、たとえ方も言い換えた文章を生成してくれます。私たち人間も相手に合わせて言葉を選ぶように、生成AIも条件を付けると合わせてくれる機能(能力?)があります。
生成AIを大まかに言えば、「新しいテキスト、画像、音楽、ビデオなどを作成」してくれます。作成には、校正したり、言い換えたり、要約したりすることも含まれます。
生成AIが何か、なんとなくわかってもらえたかと思いますが、Copilotに聞いてみると大切なことを回答してくれましたので最後に一部を引用しておきます。
ただし、生成AIはあくまで情報提供のためのツールであり、医療的なアドバイスや、法的なアドバイス、個人情報の提供など、専門的な知識が必要な場合には、専門家に相談することをお勧めします。
活用例
アイディア出し
遊びや活動、季節のお便りのアイディアを聞くことができます。
bardに「保育園で雪を使った遊びのアイディアをください」と聞いた例を下に一部引用しておきます。
あたりまえなことから、それは無理やろうと言いたくなることまでアイディアをくれます。そして、1度聞くのではなく、「もっと教えて」というとさらに出してくれます。何度も聞くと良いかもしれませんし、回答を見て方向性が決まると、「感触遊びをもっと教えて」のように具体化して聞くこともできます。
保育園で雪遊びをする際に、子どもたちの年齢や体力に合わせて、以下の点に配慮するとよいでしょう。
乳児クラス
雪の上を歩いたり、転んだりしながら、雪の感触を楽しむ。
雪に手を触れて、その感触を確かめる。
雪に顔を埋めて、その感触を体験する。
幼児クラス
雪だるま作りや雪の城作りなど、雪を使った製作遊びを楽しむ。
雪で雪だるまや動物などの形を作る。
雪で絵を描く。
また、雪遊びの際には、以下の点に注意しましょう。
雪が降る前に、防寒対策をしっかりとする。
雪が濡れていると滑りやすいので、転倒しないように注意する。
雪の中に穴が空いていると、転落の危険があるので注意する。
雪に触れると、風邪をひく可能性があるので、手洗いやうがいをしっかりする。
要約と言い換え(大人向け)
「次の文章を200字以内で要約してください」や「次の文章を中学1年生がわかるように200字以内で要約してください」と書いて、一行開けてお知らせの全文をつけるとわかりやすい要約を作成してくれます。
「中学1年生が」を付けることで、わかりやすく言い換えもしてくれます。
要約を文面に入れることは、次の3パターンの人に情報を届けるのにとても大切です。
忙しい人
お知らせを読むかを要約で判断できるようになります。
(パッと見て要約がない長文であれば、後回しにされたり、忘れられる可能性が高くなります。)非母語話者
英語などの非母語話者にとって、要約は長い文書を理解するのに役立ちます。日本語を話せても、読むのはひらがなと簡単な漢字だけという保護者も増えています。障がいがある方
非母語話者とおなじですが、長い文書を理解するのに役立ちます。
これはグレーゾーンといわれる方も含め、知的だけではなく発達障害や精神障害などにおいて、理解力や集中力に難がある人の手助けになります。
中学1年生ぐらいの言語力が、どんな人にも読みやすく失礼のない要約になりやすいので、オススメです。「かんたんな日本語で」もオススメです。
要約と言い換え(子ども向け)
児発や放デイの支援者であれば、子ども向けにわかりやすく言い換えたりするのは得意だと思います。では、AIの出番がないかと言えば、意外と使えます。
興味の偏りが大きい子へ
伝えたいことを「~を○○で例えてください」「~を○○に関連させて言い換えてください」がうまく行くことがあります。
新しい情報を持っていなかったりするので流行のアニメに対応してなかったり、ウソをついたりするので注意が必要です。AIからのキーワードを元にチェックしましょう。
文書作成
生成AIの得意とするところで、「次のキーワードで300字以内の保護者宛のお知らせを書いてください」とかで、キーワードの単語や箇条書きを提示するだけで文章化してくれます。
相手に合わせて書いてくれますので、メールやお手紙などの下書きをお願いするのにとても便利です。
AIはウソをついたりしますので、人が確認するのは大切です。
挿絵

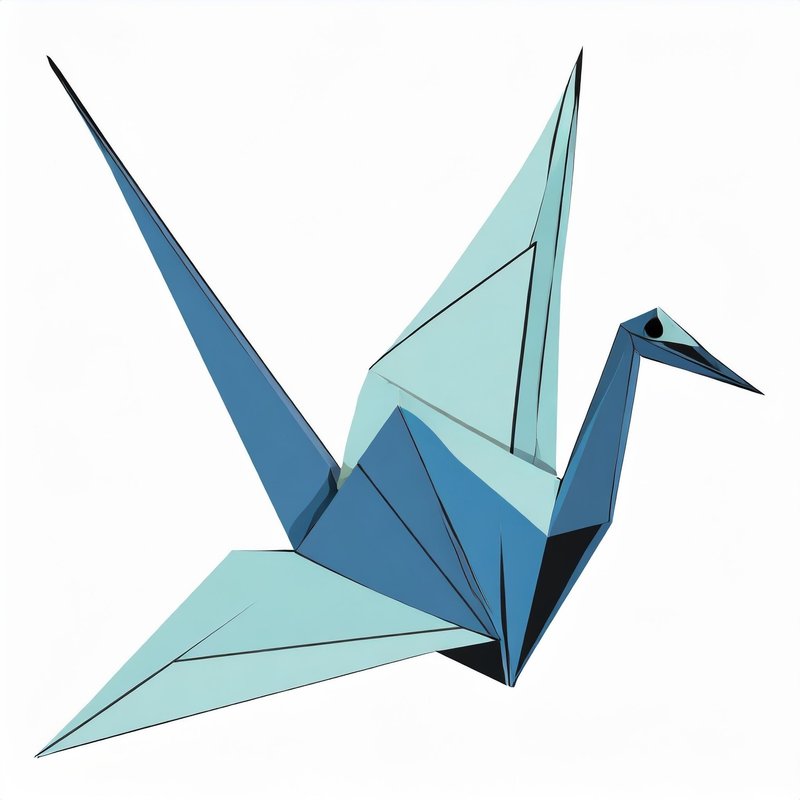
お便りとかに入れるちょっとした挿絵などをAIに生成してもらうこともできます。著作権とかを一応クリアしているはずですので使いやすいです。
気をつける点
ウソ・知ったかぶり
ハルシネーション(Hallucination:幻覚)とよばれる現象がAIにあり、もっともらしいウソを答えてくることがあります。対策されているAIもありますが、まだまだ難しい課題です。
すべてを真に受けずに、ちゃんとチェックしてください。
ハルシネーションがあることもひとつの要因ですが、専門家に聞くことをAIに聞いて真に受けないようにしてください。専門家に聞くということは、自分では真偽の判断ができない内容が多いため、正確性が保証できないAIに聞くのはやめておきましょう。(もしくは、キーワードを聞き出して自分で調べ直してください。)
聞き方・コミュニケーション方法
AIに入力する部分を「プロンプト」と呼び、どのようにAIに聞くかで回答が大きく変わるうえに、AIとやりとりを何度かすることでより良い回答が得られるようになります。やりとりを工夫したノウハウが「プロンプトエンジニアリング」とよばれ、いろいろな手法が開発されているので、興味がある人はググってみると良いです。
注意点としては、聞き方は大切です。この記事では丁寧に聞いてますが、「キーワード教えろ」とかでも回答は変わらないです。
個人情報は禁止
個人情報や機密情報を入れることを禁止していたり、設定をしないとダメとするAIがほとんどです。そのため、個人を特定できるような情報を入力するのは注意してください。
再学習の危険性
AIと会話した内容は、AIの再学習に使われる可能性があります。(設定でしないようにできるAIもある)
上記の個人情報に関連しますが、非公開の情報をAIに渡して、AIが別の人にその情報を話してしまうことがあるので、設定をしていない時は気をつけてください。
前半記事おわりとお礼
ここまでを前半の記事とさせていただきます。お読みいただきありがとうございました。
後半はコミュニティ限定で、もう少し深掘りした記事を配信しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
