
読売ジャイアンツから学ぶ「強いプロスポーツチームの3原則」
セリーグを制した読売ジャイアンツ。
今年の巨人で真っ先に話題になったのは「補強」でした。炭谷、丸、クック、ビヤヌエバ、ナカジ…「金の力で勝っている」とはどこかのファンの弁。「吸収合併を繰り返す大企業」なんて声も聞こえます。
しかしながら私は、今年の巨人がお金「だけ」で勝ったとは到底思えないのです。大金を使って低空飛行に終わったチームは数多く存在します。なぜ巨人はしっかりと好成績を残すことができたのでしょうか?
強いプロスポーツチームには共通して優れた要素があります。
「補強」「メンタリティ」「育成」です。
これらが全て揃って、初めて強いチームと呼ばれる条件が満たされると私は考えています。3つわかりやすいスローガンを挙げるとすれば
「競争は平和である」
「メンタリティは意識付けである」
「補強は力である」
これより先は一つ一つ解説を。
COMPETITION IS PEACE
「競争は平和である」は育成面のスローガンです。ポジションの競争を常に行うことで強さの維持を図ります。
野球において有名な例が森政権、黄金期ライオンズのレフトです。オールスター級のメンバーが揃う中で、あえてレフトに入るメンバーを固定しなかったことにより「レフトであればレギュラーになれそう」というロジックの元で、選手技術のレベルアップを図りました。
レフトに入るメンバーはいずれも準レギュラーで併用、オールスター級のメンバーではありませんでしたが、それでもこの競争によって高い技術と勝者のメンタリティを持つ選手に成長させることができました。例を挙げるとシリーズ男と言われた安部理など...
サッカーでは川崎フロンターレの高卒・大卒選手獲得方針が有名な例でしょう。強化部スタッフの伊藤宏樹氏は動画内でこう語っています。(05:37~)
"宮代大聖なんかは去年から経験積んでトップの練習してますけど、大聖だけだったら同年代っていう意味でももう一人欲しかったんですよね。そういう意味で去年から僕もスカウトしてましたけど、同じぐらいやっぱり刺激しあえる選手がほしいなぁというところでずっといろいろ探してたんですけど、原田というのがすごい目に留まったというか、将来性を考えた今強いフロンターレに入ってきて、今、もちろん即戦力で出て欲しいですけどしっかり経験積んで成長していけば3年後4年後とかに関わってこれるようになる可能性を持った選手かなっていう意味で。大聖に刺激を受けてもらいたいっていう意味でも。そういう意味での未来を見越した補強っていう意味ではあるんですね。
(同世代のライバルが意識刺激し合う存在っていうのはプロサッカー選手にとって大きいかと聞かれて)そうですね、それはすごい大事なことだと思ってるんで、そこをあえてうちのアカデミーから上がってきた選手と高体連から来る選手っていうのを一緒に競い合わせるっていうのがいいかなと。
世代屈指の選手にポジションの近い選手を競わせて、技術向上やメンタリティの強化を図るというのがこの話の骨ですが、過去フロンターレは大島良太と福森晃斗(2011)、谷口彰悟と可児壮隆(2014)、三好康児と板倉滉(2015)、といったように、同世代(+で世代屈指の選手)でポジションの近い選手を複数人必ず獲得しています。これらの競争によって、(移籍後も)いずれの選手もチームを支える柱に成長しています。
さて巨人はどうでしょうか。原監督は以前Numberのインタビューでこう話していました。
「本当に選手を育てようと思ったら、ポジションを与えてもダメだということ。選手を育てるために、一番必要なのは競争であり、競争がないところでチームの活性化はないということです」
今年の巨人で最も競争が促された施策は「ファーム制」です。
今年から巨人は2軍と3軍を「ファーム」として統一し、合同練習や自由なコーチの移動などを実現しました。これにより、コーチ同士の意見のすれ違いがなくなり、活発な入れ替えができるようになったことにより、3軍にいるルーキーや育成選手の"プロ相手の"実戦での実力試しを楽に行えるようになりました。
その主たる成果が増田大輝でしょう。2軍で研磨を積んだ彼は1軍の代走のスペシャリスト、また優勝決定試合でのV打などで大活躍。元々内野外野問わず様々な場所を守る彼は、この制度についてスポーツ報知の記事でこう語っています。
「コーチの方も一人一人考え方が違う。この人はこういう風に思っていて、こういうやり方、使い方をしてるんだっていうのを聞ければ自分の引き出しになる」
MENTALLY STRONG IS AWARENESS
「メンタリティは意識付けである」はメンタル面でのスローガンです。いわゆる勝者のメンタリティとかいうあれ。
ちょっと興味深い記事を見かけたのでこれをぜひ。
優勝決定試合などの場数を多く踏むことも大事ですが、それ以前に普段から意識付けしておく、というのがこの記事では触れられています。自信を継続して持つことは大事ですが、過剰にならないバランスでいるのも大切。あとは「お股本」でもあったように「まず勝つことでスタートする」、というのは結構見落としやすいのかも。

勝者のメンタリティを広めた人物と言えばかつての世界最強監督ジョゼ・モウリーニョでしょう。彼は戦術家というより人心掌握の達人です。直接的に選手の琴線に触れ、厳しい規律の基に「勝てる」という気持ちを叩きこむ。常にポジティブでいられるように、愛の鞭と優しい声掛けを使い分けて勝利へと導く。モウリーニョはかつてフランク・ランパードとこういうやりとりをしたことがあります。
「お前はジダンやヴィエイラ、あるいはデコと同格だよ。ただ、それを証明するには勝たなければならない。お前が世界最高の選手であることを、優勝して証明するんだ」-『モウリーニョのリーダー論』 より
ただ頑張れ、ではなく「勝つことで得られる幸せ」を理解できるように根付かせられるようにすることが、勝者のメンタリティを持てるようになる大事なポイントではないかと私は考えています。
さて巨人で勝者のメンタリティを持つ人物と言えばもちろん原辰徳監督。かつてはWBCのイチローのあれとか「ハシ、いいボールいってるぞ。腕もふれてるねー、いいねー」とか。とにかく選手を立て、時には飴と鞭を使い分けながらチームをいい方向に持っていく。大がかりな選手の入れ替えも時に行い、常に選手に競争の意識を持たせながらペナントを進めていく。そういった手腕の元で、優勝へと導くことができました。(この説はまだまだ書き途中です。情報が入り次第追記をやっていきます)
ADDITION IS STRENGTH
「補強は力である」は補強面のスローガンです。私は補強には3つの側面があると考えています。
①相手チームの戦力を削ぎ、戦力差を生じさせる。
②育成する選手の技術向上の速度増加に貢献する。
③自分のチームの長所をさらに伸ばし、短所を克服ことができる。
補強の成功例をひとつ。プロスポーツ史上に残る、"現在進行形で"20年もの長きに渡る王朝を築いているアメフトのプロリーグ、NFLのニューイングランド・ペイトリオッツの例。ペイトリオッツは選手獲得において、戦術をよく理解でき献身的な選手を多く獲る傾向があります。ドラフトで知能指数テストなんてやるのもかなり有名な話。
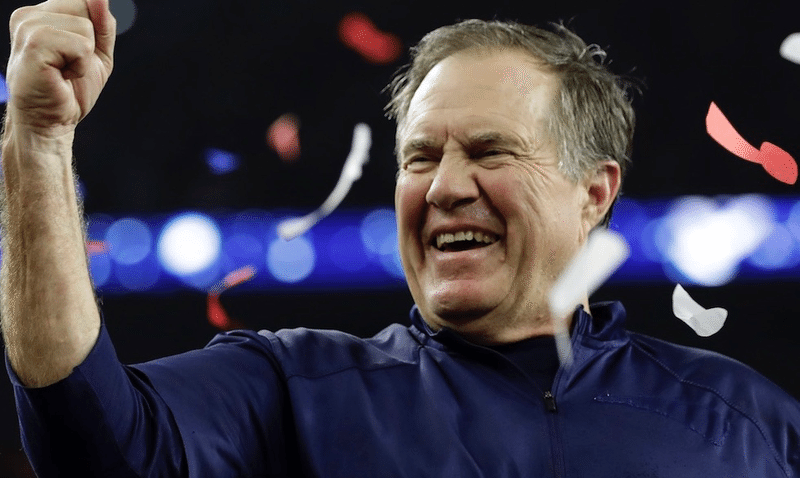
王朝形成に大きく貢献したビル・ベリチックGM/HCは選手獲得において2つの哲学を持っています。「タレントより貢献」「低コストで価値ある選手」。有名な例がスーパーボウルMVPに輝いたWRジュリアン・エデルマンでしょう。大学時代の彼は有名ではなく、スカウティングコンバインにも招待されず、Patsが独自に行ったワークアウト後にドラフト7巡目で獲得した選手でした。しかしながら相手のマークを外すルートランニングに特筆した技術を持つ選手であり、これまた特筆したパスIQを持つQBトム・ブレイディとの相性は抜群。"③自分のチームの長所をさらに伸ばすことができる"を最大限生かした補強になりました。
さて巨人はどうかというと、というのをちょっと表に。

これは2016年オフ以降、巨人のFA・助っ人補強した選手を「こんな感じじゃないかな?」とタイプ別に振り分けたものです(主観がかなり入っているので要注意)。巨人の主な補強は「助っ人は主に長所伸ばし・短所カバーの補強、日本の選手は技術向上ブーストにあてる」といった特徴があるのではと私は考えています(もちろん本当はそういうの問わずですが)。+でドラフトで獲得した選手は、こういった技術向上ブーストにある選手から学んだり、同世代や一つ上の世代らの選手と競争していくことで「がっしりとした土台」の元で強くなっていくとができる、のではないかと私は思います。また、「お股本」でも触れられていましたが、もともとこうした補強によって若手をじっくり育成できる時間が増えるといったプラスの面もあります。それで勝つことによってメンタリティも育つしね。
主たる例が「岩隈塾」の存在と丸でしょう。岩隈塾は春のキャンプで若手投手陣に岩隈が開いた「若手投手陣のアドバイス」のことで、桜井、田口、鍬原、大江、坂本工が受けたことが記事にもなっています。鍬原はカットボールの握りを教わり、その後ファームで40試合防御率2.95を記録するなど、着実に力を伸ばしつつあります。(もっともこの塾がどのように影響したかは今後のスポーツ紙の記事などで明かされるのではと思ってたりします)丸は言わずもがな。ストレートにめっぽう強いことは巨人の支えになり、3番打者として申し分ない働きを見せるとともに、元々「ジェネリック山賊」と言われていてストレート系に強かった巨人の打線を支えました。
やっぱりお金は必要?
ここまで書いてきて言うのもあれですが、やはり「お金」は大事です。かといっても量だけではなく「使い方」が大事であると私は考えています。大金があるのは当たり前、そこから優秀なコーチを揃え、優秀な選手を揃え、いい設備を揃え、それらを時と場合によって動き方を変える。強いチームが強くありつづけるのは、これらの3原則が備わっているとおもに「使えるお金の量」と「頭の良さ」が優れているからではないかと私は考えています。3原則とこれらの要素は、決してどれか一つを軽視していいわけではないのです。
最終的に身も蓋もない結論になってしまったかもしれませんが、本当はまだ整理できていないところも多いです。現在は85%のところまで完成したところで公開しており、分かったことがあったらどんどん追記していこうと思います。
それでは今回はこの辺で。
じはんき
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
