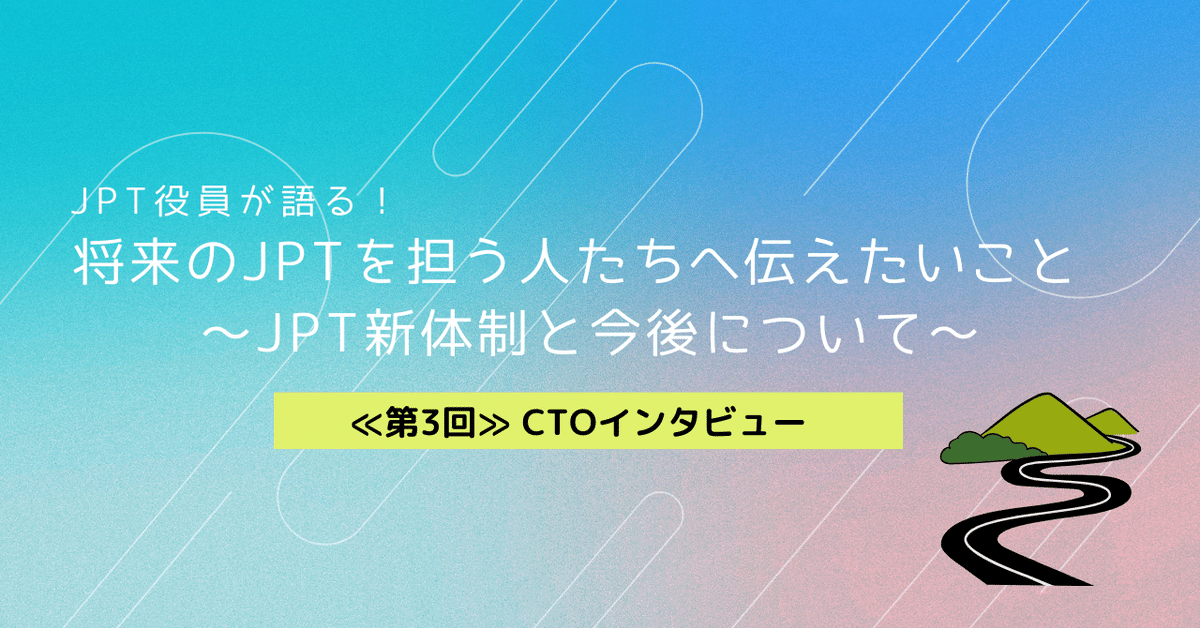
JPT役員が語る!将来のJPTを担う人たちへ伝えたいこと~CTOインタビュー第3回:JPT新体制と今後について~
本企画では、CTOの長尾さんにご登場いただき、JPTへの熱い想いを語っていただきます!
JPTは2024年3月から新体制がスタートしました。長尾さんはどのようなJPTの未来を描いているのでしょうか?今の心境に迫ります!
(執筆:JPTアンバサダー ぽり)
全4回でインタビュー内容をお届けします。
- 第1回:CTO就任から今までを振り返って
- 第2回:CTOが考える“面白さ”とは
- 第3回:JPT新体制と今後について(本記事)
- 第4回:従業員のさらなる活躍のために
ー3月付でJPTの社長が成川さんから阿渡さんに交代となりました。今の心境を教えてください。
JPT設立から4年目に入りましたが、JPTの文化というものが形作られ、それが従業員の姿や言動からも感じられるようになったと思います。これは凄いことで、他社が真似しようと思っても時間がかかることだと思います。自分はこの文化のコアを継承し、またさらに醸造させていければなと思っています。
そして阿渡さんが社長になること。これは特例子会社としての文脈から考えると大変意義のあることだと思います。社外への発信力が更に高まることが期待されますし、阿渡さんは実務を大事にする方なので、JPTがより足腰の強い企業になっていくと期待しています。
僕自身の役職は引き続き「CTO」ですが、“その会社が現在の成長段階で必要としている戦略的技術幹部”という定義からして、果たすべき役割はまた変わっていくだろうと確信しており、それは楽しみでもあります。今時点では、「成果物」に向き合うことから「価値・利益」に向き合うことに徐々にシフトしていくのかなと考えています。価値向上に至るストーリーは一朝一夕には生まれませんが、「これは面白い!」と思われるものを描ききって見せたいと思います。
ちなみに前社長の成川さんは「パッと聞くだけでは非合理的だけど、よくよく考えるとそれだ!」という話が多かったように思います。簡単に言えば話が面白いんですよね(面白そうに話すから騙される?)。この能力はすごく属人的で、だけど重要なものだと思うので、ストーリーづくりの能力は成川さんをベンチマークにして磨いていきたいなと思っています。
ー長尾さんから見たJPTの今後の課題は何でしょうか?
2年間は日揮社内(顧客)としてJPTを見てきましたが、この3年間で会社らしくなってきたなぁ、という印象を持っています。バリバリのエンジニアも出現し、そのエンジニアが働く環境も情シスチームが支えてくれています。私が参画してからの数字で言えば、例えばMicrosoft Azure関連の業務数は新規で10件実施し、Azure関連資格保有数は0→32件に増えました。また情シスチームは262件のJPT社内業務を完了しています。(2023/12末時点)
このように数字で語れるようになってきているのは実務として良い傾向ですね。
直近の課題としては、「価値・利益(売上)創出に向けた脱皮」だと捉えています。何を利益とするかは大事なテーマで、金銭的な意味合いでの利益もそうですが、僕はそれだけではなく「損して得取れればいい」という考えをもっています。障害という属性を無理に消す必要はなく、JPTという特例子会社ならではのポジショニングは大事にする。障害があるからこそ気づけるフィールドが必ずあるのでそこで勝負すべき、ということを考えています。PRを通して世の中にどんどんJPTが認知されたり、JPTのサービスを他の企業さんに横展開したり、自社のノウハウでコンサルティングすることも非常に意味のあることですね。
直近の技術戦略として、ある程度標準化された業務パッケージの構築や、入社後から実務アサインまでのリードタイム短縮(=OJT業務)なども進めていく必要があると考えています。
普通の営利企業だとできないことにチャレンジすること、そしてそれは何か、このストーリーを描くことは私含めJPT経営陣の大事な宿題だと捉えています。
▼Azure関連資格についての記事はコチラ
CTO持ち込み企画!「Azure Skilling Program」の実践とこれから|日揮パラレルテクノロジーズ公式note
ー5年後、10年後を見据え、長尾さんはどのようなJPTの未来を描いていますか?
正直に言うとここは今まさに描いているところですし、今後も考えていくテーマではあります。
まだぼんやりとしていますが、「社会実験場」をJPTがより体現していく未来がきたら面白いのかなと思っています。
例えば、JPTでは当たり前の「フルリモート・フルフレックス」は障害の有無にかかわらずユニバーサルな取り組みだと思います。障害特性があるからこそ気づける課題という切り口で、それをユニバーサルな解決方法に落とし込んで、実際に自分たちで実験してみて世の中に問う。こういった活動の手段として、私たちの現在のスキルセットであるアプリ開発、AI活用、自動化などが活かされていくんじゃないかなと思います。
「社会実験場」をもう少しわかりやすく言うと、大学の研究をイメージしてみてください。「それ面白そうだね」と投資してくれる人がいて、それに対して実験していくイメージです。自分たちでサービスを立ち上げ、自分たちで運用してお金を稼ぐ、というよりは、技術を持っていて自分たちだから気づける課題がある。それに対して挑戦してみるのでそこに投資したい人いますか?という感じです。
日揮の中では実践を通して技術を持ったエンジニアを育てて、外に向けては大学のラボみたいな形で発信していく社会実験集団になる。実験といっても色々あって、従業員によって挑戦したい実験も違うと思うので、そこのポートフォリオとキャリアパスは大事にしたいですね。もしある企業向けの実験が成功して、JPTのエンジニアがその企業に転職する、となっても僕はいいと思っています。
ただこれは5年後、10年後の「長尾のきてほしい未来」の1つであり、直近は日揮社内で「○○はJPT!」というポジショニング確立と価値提供をしっかり継続する事が大事ですね。日揮社内への価値提供が自分たちの強い足腰になり、新たな事にチャレンジしていけるという感覚です。
ーCTOとしてこれから取り組んでいきたいことはありますか?
成川さんと阿渡さんがこれまで築いてこられた「重要だけど緊急ではない仕事」「1人1プロジェクト」といった強いコンセプトや、セーフティネットを厚くし過ぎない人事制度など、尖った施策があるからこそ自由の余地がたくさんあると思っています。これからも残したい大事なところですし、大事にしないと自分がやりたい施策も出来ないと学びました。
そのうえで、着実な成果が見える場所や売上を上げ利益を生み出せる組織、面白そうなイベントなどに企業が投資してくれる仕組みを作っていきたいです。実験について大事なのは、JPTだからできる、という点です。
JPTがユニバーサルなアイデアを提供できれば、誰もがもっと過ごしやすい世の中になると思います。僕は、障害者のための施策ではもう時代遅れだと思うので、障害の有無に関わらず良いことをやっていきたいですね。

--------------------------------------------------------------------------------------「価値・利益(売上)創出に向けた脱皮」や「社会実験場」など、今後のJPTの道標となるような重要なキーワードがたくさん出てきた回でした。
自分たちだから気づける課題を、自分たちならではの視点や方法で解決していく。それを良いと思い、応援してくれる人たちがどんどん増えていく。こんな未来が実現されれば、従業員のみなさんそれぞれがさらに自分らしく、自信を持って働くことができると感じました!
長尾さんへのインタビュー記事は次回が最終回となります。どうぞお楽しみに!!
