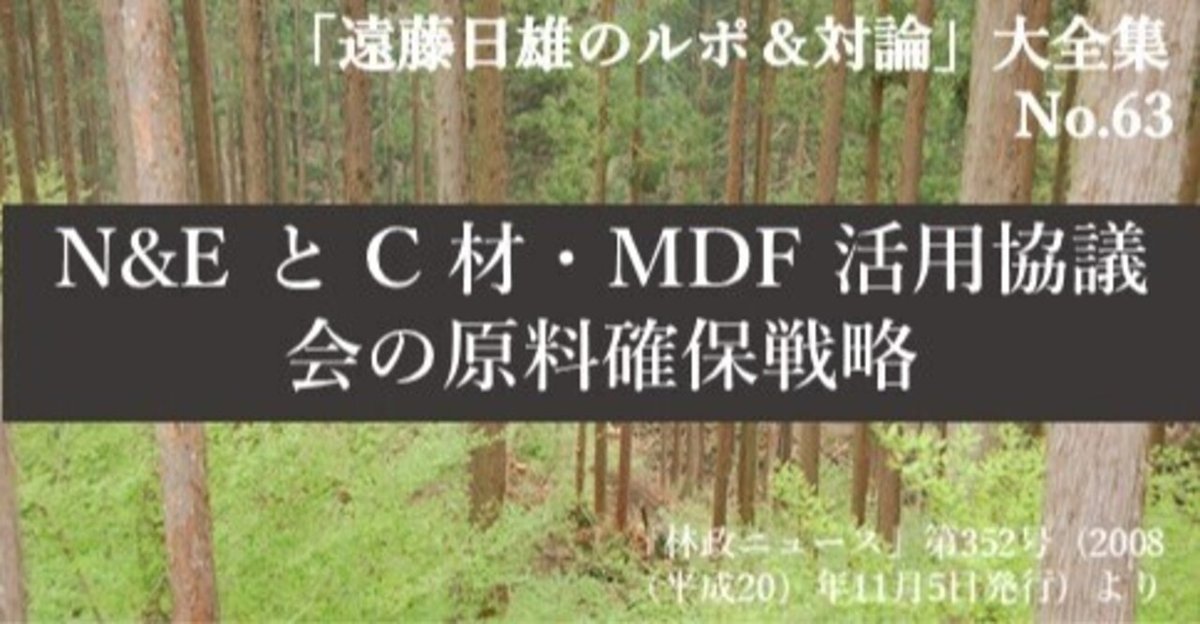
N&EとC材・MDF 活用協議会の原料確保戦略
日本の林材業界が急変している。つい4、5年前までは、製材業(A材)を軸に展開していたが、その「林材蜜月時代」に終焉を告げるかのように割り込んできたのが、集成材・合板(B材)とチップ(C材)である。情報化時代の今、時代の変化に疎い山側も、C材まではなんとかイメージできるようになった。しかし、その先のD材(その他枝・葉)やそれに近いC材になると未知の世界だ。ところがここでも激変が起こっている(第348号(中越パルプ(株))、第349号(永大産業(株))参照)。そこで遠藤日雄・鹿児島大学教授は四国へ渡った。訪問先はMDFメーカー大手のエヌ・アンド・イー(株)(徳島県小松島市、小林良一・代表取締役社長、以下「N&E」と略称)。社名のNは日本製紙(株)、Eは永大産業(株)のイニシャルを合わせたもので、両者の共同出資で誕生した会社だ。
MDF原料の安定確保へ、C材の供給目標1万m3
遠藤教授を出迎えたのは、上野実専務取締役。事前に取材の趣旨を伝えたところ、MDF原料用C材供給で大きな役割を果たしている「徳島すぎC材・MDF活用協議会」(以下「C材・MDF協議会」と略称)の主要メンバーも、それぞれの持ち場で待機しているという。遠藤教授は早速、吉野川沿いを西へと向かった。行き先は、美馬市のC材丸太の伐採・搬出現場。同行するのはN&Eの堀智弘・製造部長、大泉信一・チーフアドバイザー、そして徳島県林業振興課の市瀬雅志・技術課長補佐だ。以下、車中談。
遠藤教授
C材・MDF協議会の内容について教えてほしい。

林道端に積まれたヒノキC材とロングアームのスイングヤーダ試作機
市瀬課長補佐
今年7月に徳島県の「林業飛躍プロジェクト」の川下対策として、間伐事業で発生するスギC材をMDF原料として安定的に供給することを目的に協議会を設立した。メンバーは徳島県森林組合連合会(窓口)、徳島県木材協同組合連合会、日本製紙木材徳島営業所、そしてN&Eだ。今年度(平成20年度)のC材供給目標は1万m3だ。
遠藤
国の補助事業は受けているのか。
市瀬
昨年度は「木質バイオマス利活用地域モデル実践事業」を、今年度は「木質資源利用ニュービジネス創出モデル実証事業」を受けている。これから行く現場は、その実証事業箇所の1つだ。
補助なし間伐でチップ工場着値は6500円/m3
車は、伐採・搬出現場に到着した。剣山の北側山麓に広がるヒノキ人工林。尾根筋で地味が乏しいせいか、40年生にしては成長が芳しくない。4000〜5000本/haもあろうか、相当の密植だ。待機していたのは、美馬森林組合の七田義貞・専務理事。
遠藤
伐採現場を説明してほしい。
七田専務
4・6haの間伐作業中だ。「実証事業」箇所はこの他にもあるが、伐採・搬出に共通しているのは、プロセッサ・スイングヤーダ・フォワーダの高性能林業機械3点セットで補助なしの自力間伐事業を行うことだ。最寄りのチップ工場着値が6500円/m3というのが条件だ。
遠藤
伐採方法は?
七田
2残1伐(3列に1列の割合で伐採)の列状間伐だ。チェーンソーで伐倒した立木をスイングヤーダで集材し、プロセッサで玉切り(4m)する。それをフォワーダで林道端に巻立てしたものを10トントラックが最寄りのチップ工場へ運ぶという作業手順だ。
遠藤
チップ工場着値6500円/m3という条件はどうか。
七田
厳しい条件だ。森林所有者に残る立木代は1000〜1500円/m3程度か。
大泉アドバイザー
ただ、ここの現場にように、初回間伐の場合は作業道開設のコストがかかる。これが2回目、3回目の間伐になると違ってくる。また、素材生産コストは1箇所の間伐現場ではなく複数の現場をトータルして考える必要がある。したがってC材・MDF協議会のビジネスモデルができるのは2回目間伐からということになろう。
七田
素材生産費縮減の一環として、スイングヤーダの集材能力を上げるため、ロングアーム(8m)の試作機も導入している。
協議会からの間伐チップ納入は月1700トンに増加
間伐箇所を視察した遠藤教授たちは、MDFの製造拠点であるN&E本社へ向かった。MDFとはMedium Density Fiberboard(中質繊維板)の略称で、木材チップから繊維(ファイバー)を取り出し再構成した木質ボード(繊維板)の一種である。製材廃材、合板廃材、間伐材など従来あまり利用されていなかった木材を利用して優れた特性をもつボードを製造することができ、建材、造作用基材、家具・木工用芯材などの用途で需要を定着させてきた。とくに一昨年、南洋材合板のフロア台板やプリント化粧板基材価格が高騰したことで、MDFを採用する動きが急速に高まった。また、木造住宅の壁下地材などとしてもユーザーから大きな関心を集めている。
上野専務らは遠藤教授を同社のチップヤードへ案内した。
遠藤
MDFの原料チップの材種別内訳はどうなっているのか。
堀製造部長
弊社のMDF月間生産量は1万m3。その原料チップは月間6000トン(丸太換算の場合は2・2を掛ける)。このうち外材は10%、残りの90%が国産材チップだ。さらに国産材チップの22%が間伐材チップになる。いずれは100%国産材チップにしたい。
遠藤
C材・MDF協議会からのN&Eへの間伐材チップ納入実績は?
堀
今年7月からの実績で示すと前期が月間1000トン、今期に入って月間1700トンに増加した。一時は2500トン納入された月もあった。

林地残材のカスケード利用について力説する上野専務(右)
戦略商品はNEOボード、ヒノキチップが増えていく
遠藤
N&EがC材・MDF協議会に加わったのはなぜか。
上野専務
輸入チップの安定供給に不安の兆しが見え始めたからだ。外材価格の高騰、船運賃の高騰、製紙メーカーの使用量の増加、発電・熱利用施設の需要増などで、チップ需給は逼迫している。

NEO ボード
遠藤
国産材チップを利用した貴社のMDF製品とは?
上野
NEOボードという商品だ。これには針葉樹チップを原料にしたSタイプと広葉樹を原料にしたKタイプがあるが、今後このSタイプにスギ、ヒノキなどの国産材チップを使い市場を拡大してきたい。そのためには林地残材(C・D材)の集荷増がポイントになる。(チップの山を指さし)これがさきほどご覧になったヒノキ間伐材チップだ。ヒノキのチップ需要は、今後増えていくだろう。
遠藤
どうしてか。
上野
白いMDFが製造できるからだ。例えば、住宅のフローリングは白色系が多く、V溝加工面も白っぽいものがフローリングメーカーに喜ばれる。そのためにはヒノキの白いMDFが必要だ。
遠藤
そういえば家具の産地・大川などでは「MDF=白」というイメージが強い。
上野
弊社の企業経営の基本理念はマーケット・イン方式だ。つまり、顧客のニーズを的確に把握してそれにふさわしい商品を供給する。その原料チップとして、今、どのような樹種が求められているのか。それを山側へフィードバックしていく。木質ボードの市場競争は厳しい。不況などの煽りで需要がシュリンク(縮小)することがあるが、質の高い製品はシュリンクしない。その1つの答えがヒノキの白いMDFだ。
遠藤
MDFの新製品開発と原料チップの開発はメダルの裏表の関係にあることがわかる。企業と山側の連携の必要性の根拠がここにある。
N&Eは、NEOボードSで「間伐材マーク」や「サンキューグリーンスタイルマーク(3・9マーク)」の認証を取得するなど環境対策にも意欲的に取り組んでいる。国産材のリサイクルとカスケード利用(高レベルから低レベルへと多段階で活用すること)のビジネスモデルを構築してもらいたい。
(『林政ニュース』第352号(2008(平成20)年11月5日発行)より)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
