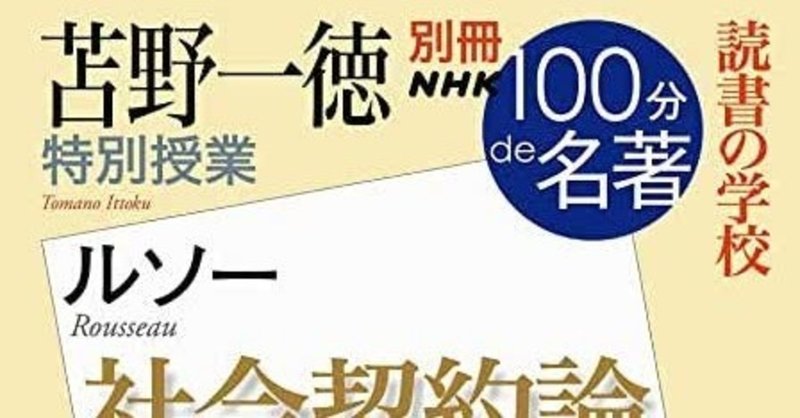
ルソー『孤独な散歩者の夢想』解説(2)
はじめに
新刊『NHK100分de名著 苫野一徳特別授業 ルソー「社会契約論」』出版記念として、ルソー最晩年の哲学エッセイ『孤独な散歩者の夢想』解説第2弾をお届けします。(『エミール』や『人間不平等起源論』『告白』の解説もしています。)
苫野一徳オンラインゼミで、多くの哲学や教育学などの名著解説をしていますが、そこから抜粋したものです。
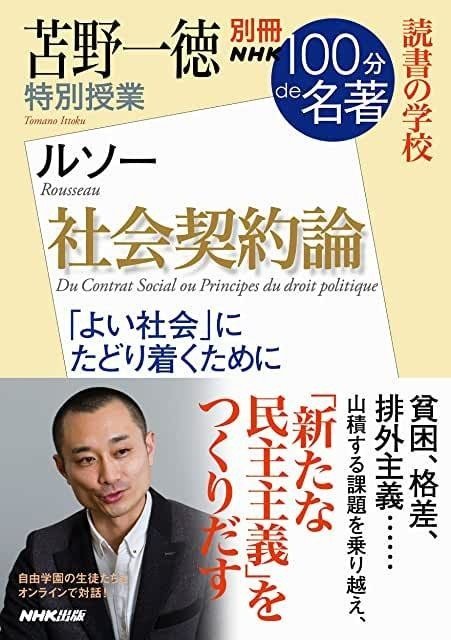
【第5の散歩】
「第5の散歩」で、ルソーは、逃亡の途中で2ヶ月の間だけ住んだサン・ピエール島を懐かしく思い出します。(『告白』でも、この島への愛情が語られています。)
「今まで何軒もの家に住んだし、なかには魅力のある家もあった。だが、そのなかでもビエンヌ湖の中央に浮かぶサン・ピエール島の住まいほど私を幸福な気分にさせてくれた家、今なお恋しく思う家はない。」
この時期の「至福」の体験から、ルソーは「幸福」について思索を深めます。
「最高の快楽のなかにあってさえ、「ああ、この一瞬がずっと続けばいいのに」と本気で思う瞬間などめったにありはしない。私たちの心に不安や空しさを残し、あっちのほうがよかった、いや、この先もっといいことがあるのではと思わせる、こんな儚い一瞬を幸福と呼んでいいのだろうか。」
『NHK100分de名著 苫野一徳特別授業 ルソー「社会契約論」』にも書きましたが、このルソーの幸福論は、のちのニーチェの思想と非常に対照的で、わたしの興味をそそります。
ニーチェは、「ああ、この一瞬がずっと続けばいいのに」という恍惚的な幸福を味わうことができれば、それだけで、もしもこれまでの人生における苦悩が永遠に続くとしても、その人生を何度でも繰り返し味わうことができるといいました。
「永遠回帰」の思想——より正確には、「永遠回帰」に耐えるための思想——と呼ばれるものです。
それに対してルソーは、瞬間的な恍惚や熱狂など、結局のところ不安や空しさを残すだけだといいます。そうではなくて、
「喜びも苦しみも、欲望も不安も感じず、ただ感じるのは自分の存在だけ、しかも、その存在感だけで自分が満たされる状態。もし、そんな状態が続くならば、それを幸福と呼んでもいいだろう」。
そうルソーはいうのです。
実際、波乱に満ちた人生の果てに、ルソーはそのような静謐としての幸福を手に入れました。そしてひっそりと、死んでいきました。
ニーチェはわたしの好きな哲学者で、永遠回帰も、これまでわたしをしばしば救ってくれた思想です。ルソー的幸福とニーチェ的幸福とは、相反するものというよりは、人生においてわたしたちが味わいうる、幸福の二つの類型と考えるのがよいだろうと思います。
ただ、ニーチェ自身は、生前はほとんど誰にも認められることなく、晩年には発狂し、おそらくは不幸の中で死んでいきました。
だからというわけではありませんが、いまのわたしにとっては、ルソーのいう幸福こそがめざしたい境地です。
以前はどちらかといえばニーチェ派で、ニーチェから大きな影響も受けた、フランスの哲学者ジョルジュ・バタイユの言葉を借りれば“蕩尽”こそが至福であると考えてもいましたが、若い頃に求める幸せと、壮年期以降に求める幸せとは、少し質が変わってくるのだなと感じています。
【第6の散歩】
続いての思索テーマは、「善」とは何か。
ルソーは言います。自分は好んで善行をするが、それが義務になると途端に嫌な気持ちになってしまう、と。
それは、ルソー自身に幾度となく降りかかった、苦い体験によるものでした。
著名人になったルソーは、多くの人たちからさまざまな救いを求められました。
最初のうちは、善意からそれらに応えていたルソー。しかしやがて、人びとはそれを当たり前のことと思うようになり、ルソーの善行は義務になってしまったのでした。
ルソーは言います。
「義務の重圧を感じるとどんな甘美な喜びでさえ重荷となってしまう。」
しかしだからこそ、彼はこう思うのです。
「本当の徳とは、義務によって命じられたときに、自身の性向に抗ってでも、なすべき善をなすことにある。 そしてまた、これこそ、私が人並みにこなすことができないことなのである。」
人は、欲するからでなく、義務であるから善行をなす。そのような善こそ、本当の善である。
のちのカントに大きな影響を与えた思想です。
とはいえ、自分にはそんなことは不可能だともルソーは言います。
「だが、自分の性向に反した行動をとることは私にはどんなときも不可能であった。世間がそうしろと言うから、義務だから、もしくは必要だからということであっても、心が応じない場合、意思が耳をふさぐ場合は、諾として従うわけにはいかない。」
だからこそ、義務に従うものとしての善に、ルソーは憧れたのかもしれません。
触れられている程度ですが、本書における「自由」についてのルソーの思想にも、面白いものがあります。
「人間の自由はやりたいことをやることにあるのではない、と私は常々考えてきた。「嫌なことはしない自由」こそが自由である。それこそ私が求めてきた自由であり、しばしば守り通してきた自由である。この自由を守ってきたがゆえに、私は同時代の人間に非難されることになったのだ。」
ルソーは、いわゆる「積極的自由」(〜への自由)ではなく、「消極的自由」(〜からの自由)を自由の本質と捉えていたと言えるでしょうか。
【第7の散歩】
「第7の散歩」で主に論じられているのは、ルソーが晩年に夢中になった植物学について。
ルソーは、植物を薬草づくりなど「実利」の観点からしか見ない当時の植物学を次のように批判します。なかなか面白い視点です。
「こうして医学的効能ばかりを考えていると、植物の研究があまり楽しいものではなくなる。色とりどりの花が咲く牧草地も、花たちの輝きも色あせ、瑞々しい樹木も朽ち、草原や緑陰も味気ない、不快なものになってしまう。植物の構造は実に魅力的で優美なのだが、どんな植物でも乳鉢ですりつぶすことしか考えていない者にとっては、何の意味もないことなのだろう。」
なぜルソーは植物学に夢中になったのか。それは、植物の観察が自分の心を穏やかにしてくれるからだとルソーは言います。
植物学は、孤独で怠惰な暇人の趣味にぴったりなのだ。観察に必要なのは、ピンセットとルーペだけ。散歩に出て、野をさまよいながらあれこれと植物を見てまわり、それぞれの花を興味と好奇心から調べていく。花の構造が分かってくると、それを眺めているだけで、不思議と嬉しくなってくる。しかも、それが苦労のすえに得た喜びと同じぐらい心躍る喜びなのだ。
この無益な趣味には、情念がうずまくなかでは決して感じることができない魅力がある。この魅力こそ、日々の生活を幸せで穏やかなものにするために必要なただ一つのものなのである。だが、地位のことだとか、本を出すだとか、利益だの名声だのという不純な動機が混じったり、もしくは、他人に教えることだけを目当てに学ぼうと考えたりしようものなら、この穏やかな幸せは姿を消す。
【第8の散歩】
「第8の散歩」では、自分がいかに諦念によって幸福を得たかが再び語られます。
「こうした無心の境地に至ったのは、私自身の生きる知恵というより、敵どもがくれた贈り物だ。彼らのせいでひどい目にあったが、こうして得るものもあったことを認めようではないか。」
【第9の散歩】
「第9の散歩」では、子どもとの関わりについてが語られます。
『告白』でも告白されていたように、自分の子どもを5人とも孤児院に捨ててしまったルソー。(当時のパリにおいては、それほど珍しい風習ではありませんでした。また、ルソーの内縁の妻〔のちに結婚〕のテレーズの母親たちの暴虐のために、ルソーは子どもを自宅に置いておくことはできないと判断したのでした。)
この事実は、その後、ルソーの「敵」たちの格好の攻撃材料になります。
しかしルソーは言います。
「私は自分の子供を孤児院に預けた。それだけで、私は「異常な父親」と見なされてしまった。そしてその偏見を引き伸ばし、こねくりまわした結果、人々は当然のように私を子供嫌いだと決め付けたのだ。徐々に事実を変容させていく、人々の思考の連鎖をたどっていき、私は、なんとまあ人間は白を黒にすりかえる巧妙な術をもっていることだと感心してしまった。というのも、私ほど、子供たちがはしゃいだり、皆で遊んだりするさまを眺めるのが好きな人間はいない。」
若干、言い訳めいて聞こえなくもないですが……。
ルソーは次のようなことも語ります。
「だが、年をとるにつれ、私の老いた形相が子供たちを怖がらせることを知り、私は彼らを怖がらせないよう、子供たちとのふれあいを遠慮するようになった。自分の喜びを優先させるよりは、彼らの無邪気な喜びを損ねないようにしようと思ったのだ。以来、私は、彼らの遊びや戯れを見守るだけで満足するようになった。」
老いた顔つきが子どもたちを怖がらせる……。少し切ない話ですが、そんなわけで、ルソーは、子どもたちと少し距離を取るようになったというのです。
でも、自分ほどに子どもを理解している者はそうはいないとルソーは言います。
「私の書いたものを読めば分かるはずである。あれだけ細やかに子供について考えることができたのは、よほど子供が好きだからに違いない。子供嫌いの人間に『新エロイーズ』や『エミール』が書けるはずがないではないか。」
【第10の散歩】
最後の章は、ルソーが生涯愛してやまなかったヴァランス夫人との思い出が語られます。内容としては、『告白』に書かれたこと以上のことはありません。
「私は自分の心にふさわしい女性を求め、そういう女性と暮らすことができた。田舎に住みたいと願い、住むことができた。服従の義務に苦しむこともない。私は完全に自由だった。いや、自由よりもっと恵まれた状態にあった。」
以上、ルソー最晩年の著作を紹介しました。
どの著作を読んでも、ルソーという人の人間がにじみ出ずにはいられないのが、彼の作品の大きな特徴です。
嘘のない、どこまでも真っ直ぐで、不器用で、激しい愛と、それゆえの悩みを抱え続けた人。
それがルソーという人だった。
わたしはそう考えています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
