一人男の娘AC-10:パブリックイメージの話
ティーカップ横綱 一人 Advent Calendar 2020 十日目の記事です。
https://adventar.org/calendars/5488
思えば例年であればまだ期末レポートもないですし内職がてらアドベントカレンダーを書くこともできたのかもしれませんが、今年はほぼ全科目に課題がある状況ですし難しい部分もあるのかもしれません(ほんとか?)
いくら同人文化が盛んになろうと、商業の方がジャンルを確定していると思わなくもないです。というのもそれを耳目にする人間の数が桁違いだからですね。例えば今でも古典として語られる「ストップ!! ひばりくん!」はどこの雑誌掲載だったかご存知でしょうか。「週刊少年ジャンプ」です。この作品より手塚治虫作品「七色いんこ」が男の娘作品の祖として有名になるとしかるべきですが、「週刊少年チャンピオン」だったからか有名にはなりませんでした。雑誌という力は偉大なんだなぁと思います。でも最近有名になった「連ちゃんパパ」の掲載誌は「パチプロ7」というそもそもパチプロ業界ですら派遣とは言えない雑誌だったので何とも言えませんが。でもジャンプで次に掲載された女装系の漫画って「プリティフェイス」だったけど10年以上後だったうえに1年で連載終わってたんだよなぁ…因みに最近だと男の娘キャラが出てくるジャンプ系の漫画としては「早乙女姉妹は漫画のためなら!?」とかがあります。脇役ですが。でも実際に人々の「男の娘」パブリックイメージはどれから生まれてきたのでしょうか?少し考えてみました…
バーコードファイター
性癖として植え付けたという意味だと「ジャンプ」の読者より下の年齢層に訴えかけるのが効果的ですね。何しろ掲載誌が「コロコロコミック」なので。というか原作あるし(バーコードバトラー、タイアップみたいな感じですが)しかもひばりくんの様に別にそのキャラがタイトルコールされたりそれがメインテーマというわけでもなかったのですが…

温泉回で唐突にヒロインの「有栖川桜」が男であることが発覚するんですね。容姿も完全に美少女キャラで、それまでそれを匂わす描写もなかったのに。どちらかというと男の娘というより性同一性障害キャラとして扱われていたようですが作者本人が続編で書いた同人誌「アナルエンジェル」とかの描写を見ている限りは当時まだ適切な用語が存在していなかったから便宜上付けたものに過ぎないという感じですかね。でも主人公がヒロインを守る理由や、ライバルキャラが桜に対して恋心を抱いてしまい悩む描写、そして桜自身が自分の性別に対して思い悩んでバーコードの影響もあり囚われのヒロインになってしまう終盤の展開など、テンプレートはほぼ固まっていると言えます。
ちなみに件の同人誌で仮にもコロコロのキャラをとんでもない変態として描いてしかも続編と言い張るという点で少年少女にさらなる別の性癖を植え付けたことでも知られています。しかもそのことを小学館直々に「コロコロアニキ」でいじってくるという。
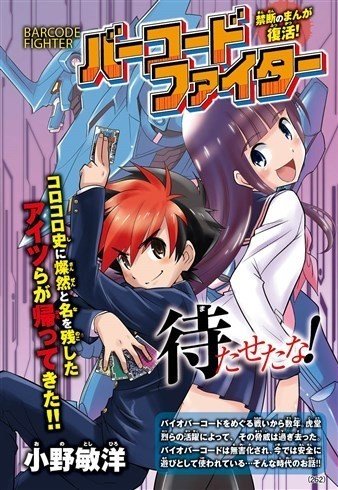
そのかわり同人誌とは別軸の続編を読みきりで書かせることで何としても正史にはさせないという感じなのはうかがえましたが、でも同人誌の「性別が不安定な桜が人体をも書き換えるバイオバーコードの騒動の渦中にいた(ボンテージで拘束されてた)影響で、その後バイオバーコードをめぐる戦争が起きた後人類に男の娘やふたなりが増えた」というのは単純にストーリー構成としてうまい気がしました。
バカとテストと召喚獣

近年の「男の娘」ブームの立役者と言えるのはやはり…ライトノベル「バカとテストと召喚獣」シリーズに登場する「木下秀吉」ではないでしょうか。「バカテス」は過去2度アニメ化され、そしてどちらもかなり中途半端のところで終わり、そして再アニメ化の予定は未だにありません。多分死ぬまでアニメ化の話は聞くことはないでしょう(でも世の中には「フルメタル・パニック!」とかいう3期から4期の間に10年以上かかったうえで未だに原作が完結しないとんでもないライトノベルのアニメ化があったりするので、何とも言えませんが…)
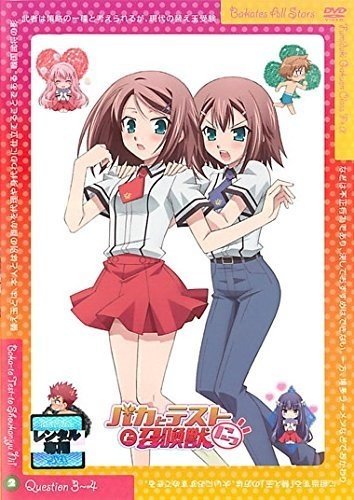
しかし、あの秀吉は意外と設定としては「男の娘」からは離れているように思えます。双子である姉にそっくりな容姿を持っていて(姉の方も美少女であり、容姿が美少女的であることの明確化)、性自認は男性ながら周囲からは美少女としてしか認識されない、かつ演芸部なので不自然な展開なく頻繁に女装シーンがある…とここまではよいのですが、その割にはつるむのはもっぱら男友達とだけであったり、「秀吉更衣室」「秀吉風呂」などという(半ばネタに近い)個別的配慮…というより「性別:秀吉」という扱われ方をされていたりしてて、王道というより覇道を歩んでいるキャラだと言えます。バーコードファイターみたくそのことに悩んでいる描写も薄いし。

まあ、そもそも「バカテス」という作品自体主人公の「アキちゃん」しかり「ムッツリーニ」しかり、可愛い女装男子キャラが多く登場するのも特徴的なので、その後のアニメ化作品に対して「男の娘」のフォーマットの一種として捉えられたのは案外そっちなのかもしれません。
僕は友達が少ない

これはサブヒロインの「楠幸村」が初登場時男の娘だとされていたのですが、実際には女の子だった…という事例でした。こういったトリッキーなことができる(つまり、エロゲにありがちな明らかに女の子女の子しているキャラが男であると言い張る的なのではなく、視聴者すらふるいにかけるような容姿のキャラを出してくる)のは「男の娘」に対するパブリックイメージがある程度固まってきたからだと思います。それを利用してストーリーを作るのは少し感心しました。
ただキャラ萌えが重要な作品より多分ミステリとかでやった方がいい作劇だった気がする。
一方で、当時その展開が判明したときの評価は散々でした。そもそもサブヒロインなのでストーリーの本筋とはあまり関係がなく、ただ男の娘好き(つまるところ属性萌え)のオタクを釣って途中まで本を買わせようという魂胆の方が強く見えたからでしょうかね。まあさんざん「男の娘」のことを性別の壁を超えた云々言ってますけど結局壁の存在とそれを実際には超えられていない点に対して性欲をぶつけてしまっているのかもしれません、反省。でもアニメ化するにあたって原作の展開としてわかってるのにそこを伏せ続けたのはどうかと思いますよ。メガレックウザのタイプが初報で「???・???」になってた時くらい視聴者は何も感じない。
最後に
ミステリーの下りで思い出したのですが、そういえば金田一少年の事件簿にも女装キャラって出てきていました(犯人役で)。そういったゲストキャラとして出てくる女装キャラが男の娘のパブリックイメージにどの程度影響したのかについても、調べていく必要がありそうですね…(麻里愛とか)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
