
『Is This It』前史 その1
前書き
ザ・ストロークスの1stアルバム、『Is This It』がリリースされてから今年で20年になります。
ストロークス、並びに『Is This It』は2000年代初頭にガレージロックリバイバル、ポストパンクリバイバルを巻き起こし、21世紀以後のインディーロックに大きな影響を与えた...という風に『Is This It』を語るものは数多くありますが、それ以前のストロークスがどのような過程を経て、『Is This It』までたどり着いたのか、それについて書かれたものは(少なくとも日本語では)中々見つかりません。
それもそのはずで、彼らが初ライブを行った1999年9月14日からアルバムをレコーディングした2001年3~4月まではおよそ1年半という短い期間しか経っておらず、その間に彼らが残した正式な音源は3曲入りのデモEPのみでした。
『Is This It』がリリースから20周年を迎えるにあたり、一体、彼らがどのようにしてこの傑作を生みだし得るに至ったのか。その背景には何があったのか。これを今一度明らかにしていきたい。幸いにも、最近の資料ではこの時期のストロークスについて取り扱ったものがいくつか見られ、また数年前、ストロークスが属していた当時のニューヨークシーンを扱った書籍も出版されました。このような資料を参考にしつつ、これまで語られにくかった『Is This It』以前のストロークスについて書いていきたいと思います。
ここに書かれるものの大体の情報元は『Meet Me In The Bathroom : Rebirth and Rock and Roll in New York City 2001-2011』からのものです。

左から
Ba. ニコライ・フライチェア
Dr. ファブリツィオ・モレッティ(ファブ)
Vo. ジュリアン・カサブランカス
Gt. アルバート・ハモンド・ジュニア
Gt. ニック・ヴァレンシ
ストロークス結成まで
ザ・ストロークスはアメリカ、ニューヨークで1998年ごろに結成されました。ニコライとジュリアンは小学生の時からの付き合いで、ジュリアンが15歳のときにマンハッタンのドワイト・スクールでニックとファブに出会いました。アルバートは出身はロサンゼルスですが、スイスの寄宿学校でジュリアンと知り合ったのがきっかけで後にストロークスに加入することになります。
ニックは元々ギターを弾いていて、ファブはたまたま家にドラムキットがあった、ニコライは祖父からベースを誕生日プレゼントにもらい、ジュリアンはパール・ジャムの曲を歌いたかった...という理由で各パートが決定していきました。
彼ら4人はパール・ジャムやニルヴァーナ、サウンドガーデンのようなグランジのバンドに熱中し、ニックはストロークスの前のバンドでHR/HMに近い音楽をやっていたそうです。
ジュリアンら4人がグランジとメタリカの衣装をごちゃ混ぜにしたような服を着て、ドアーズに影響を受けたような曲をやろうとしていた1998年の9月、映画学校に進学するためにアルバートがジュリアンの父親が経営しているモデル事務所の向かいの通りに引っ越してきたことからアルバートとジュリアンが再会し、ストロークスに加入します。
アルバートがストロークスの面々と初めてセッションしたとき、ニックは「アルバートが現れた時に何かが起きているのは明らかだった」と語っていますが、大体のメンバーがTシャツとジーンズのスタイルの中、年下ながらもスーツで現れたアルバートがストロークスにファッション面でもたらしたクールさと演奏のヴァイブス、ダイナミックなグルーヴが『Is This It』のサウンドの原型が作り出された瞬間だろうと思われます。
それからはストロークスはスタジオでの猛練習とライヴを中心に活動し、彼らの元来のルックスの良さも相まって、その評判は徐々に知られるようになっていきます。
ザ・ヴェルヴェット・アンダーグラウンドとの出会い
ストロークスの最も大きな音楽的インスピレーションとして挙げられるのが、ザ・ヴェルヴェット・アンダーグラウンド / ルー・リードでしょう。ジュリアンとヴェルヴェッツとの出会いはある年の12月にニコライの兄からクリスマスプレゼントとしてもらったヴェルヴェット・アンダーグラウンドのベスト盤が始まりでした。
これは恐らく年代的に『The Best of The Velvet Underground : Words and Music of Lou Reed』であると思われます。
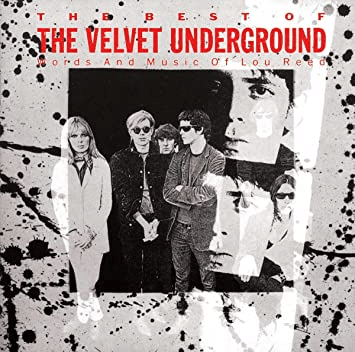
ヴェルヴェット・アンダーグラウンドといってもその音楽は「Sunday Morning」、「Rock and Roll」から「Sister Ray」まで多様に渡りますが、ストロークス、もといジュリアンが大きく影響を受けた曲の1曲にはこのベスト盤の1曲目である「I'm Waiting For The Man」が挙げられるのではないでしょうか。
この曲はニューヨークのハーレムを描写した歌詞を吐き出す、低温度なルー・リードのボーカルと、単調なまでにひたすら8ビートを刻むモーリン・タッカーのドラム、録音状況の悪さからかもはやノイズと化しつつある中で一定に刻み続けるギターリフなどが特徴的な曲ですが、何度も繰り返されるフレーズが退屈から熱狂に変わる、そんなヴェルヴェッツ由来のクールさが後の「The Modern Age」に受け継がれていったように思えてなりません。
元々、ドアーズの影響も大きかったことから、複雑な曲への志向性も当時はあったようですが、ジュリアンが「The Modern Age」という曲をリハーサルに持ち込んだことで状況は一変します。
ニックは当時の状況を「The Modern Ageは’’うわ、ヴェルヴェッツの曲みたいだ!‘’って感じでとてもクールでシンプルだった。」「突然、’’こういう曲がもっと必要だ。俺たちは他の曲を捨てるべきだ。’’というようになったんだ。」と振り返っています。
「The Modern Age」以前にも『Is This It』に収録される曲は書かれていたものの(「Trying Your Luck」の原型である「This Life」や「Alone, Together」もかなり初期の時点で書かれた曲)、大きな方向性としてはこの曲が出来たことで固まっていきます。
また、この次に「Last Nite」が続くなど、ストロークスを代表する名曲がどんどん出来上がっていたのがこの時期でした。
2000年4月29日に行われたストロークス最初期のライブ映像。この時点では後に『Is This It』に収録される曲からは「Soma」、「Trying Your Luck(This Life)」、「New York City Cops」「Alone, Together」の4曲が披露されており、他3曲はボツとなったよう。ニックのギターの位置が高いことや、ジュリアンのパフォーマンスも後のものと比べると粗野で激しく、バンドとしても発展途上であったことが伺われる貴重な映像。
ライアン・ジェントルズとマーキュリー・ラウンジ
ニックはその当時のストロークスの目標はマーキュリー・ラウンジ(ニューヨークにある250人収容のクラブ)でライヴをすることだったと語っています。彼らの当初の目標がガイデッド・バイ・ヴォイシズのようになることだったというのは有名な話ですが、マーキュリー・ラウンジではニューヨーク以外の地域の有名バンドの公演が行われていたこともあり、音楽で生計を立てる上での一歩としての目標だったのだと思われます。
当時、マーキュリー・ラウンジで出演バンドのブッキングをしていたのが後にストロークスのマネージャーとなるライアン・ジェントルズでした。他にもストロークスのマネージャーを申し出る人はいましたが、彼らはそれを全て断り、ライブのブッキングに精通し、既に友人関係で年齢も近かったライアンに拘っていました。
ジュリアンやアルバートがライアンにバンドのマネージメントをしてほしいと交渉し、何度か断られた末にライアンはストロークスのマネージャーとなります。
そして、『Is This It』に収録される曲がいくつか出来上がって、ライブの経験を重ねていくことで、2000年8月31日に初めてマーキュリー・ラウンジのステージに立ちました。
その頃にはライアンのおかげでニューヨーク以外でもライブする機会を得て、2000年12月には遂に当初の目標であったマーキュリー・ラウンジでソールドアウトすることに成功。12月には毎週水曜日にマーキュリー・ラウンジで定期演奏することを任されており、インターポールのダニエル・ケスラーは地元のバンドがマーキュリー・ラウンジで毎週演奏するだけの需要があること、ソールドアウトさせたことにとても衝撃を受けたと語っています。
MTVニュースの記者であったギデオン・イェーゴはこの時のストロークスのライブの感想として次のように述べています。
「このバンドは本当にタイトだ!と思ったことをとても覚えている。グランジからまだ間も無く、ディストーションペダルに重点が置かれ、一つの音が他の音に滲み出ていたのに対し、彼らはコードチェンジや曲の中の一瞬をお互いに切り分けていた。他のみんなはテレヴィジョンがどうだとか話しているが、私はずっとバズコックスのことを考えていた。パーティーミュージックだ。ふさぎ込んだような音楽では無かった。ダンスミュージックなんだ。」 『Meet Me In The Bathroom』P151より
「Last Nite」のイントロに代表されるシャッフルビートからもわかりますが、ストロークスは原始的なロックンロールのダンスミュージック性を体現していました。
マーキュリー・ラウンジでのライブを成功させ、その翌月にEP『The Modern Age』をリリースしたあたりから、音楽メディアやその記者たちが退屈なシーンを変えてくれるロック・スターの誕生と彼らを評し始めます。リンプ・ビズキットやトラヴィスなどのバンドがやり玉に挙げられ、ストロークスは当時アメリカでのメインストリームだったヘヴィロックへのカウンターや勢いを無くしていたブリットポップの代わりとなる存在として捉えられていきます。
EP 『The Modern Age』、ラフ・トレードとの契約
2000年の8月のある日、スタジオオーナーでありエンジニアでもあるゴードン・ラファエルがルナ・ラウンジというクラブでのライブでストロークスと初めて対面します。
当時のストロークスの印象をゴードンは「彼らは僕の好きな何かを持ってはいたが、納得はできなかった。彼らは自分たちのことを誇りに思っていたし、スタイリッシュだったが、まだ音楽的な側面を持っていなかった。」としています。
その時、ゴードンは数日後にあるパーティーに出席するお金を工面するためにデモをレコーディングするバンドを探しており、ストロークスを自身のスタジオに誘います。その後、アルバートが完璧主義でレコーディングに消極的だったジュリアンと話し合い、ストロークスはゴードンと初めてのスタジオ音源を制作することになりました。これが後にイギリスまでストロークスの存在を知らしめることになる、EP『The Modern Age』に繋がることになります。
ゴードンのスケジュール上、『The Modern Age』の製作にかかった日数はわずか3日というハイペースで、1日目に基本テイクの録音、2日目にボーカルとミキシング、3日目に細部の修正というスケジュールでライブと同じ体制で録音されました。
ジュリアンはそこまで経験があったわけではないスタジオでの作業にも関わらず、ゴードンに多くの注文を投げかけました。ハイハットやスネアの音にこだわり、ボーカルの音量について意見を交わしあうことで、ゴードンとジュリアンの信頼関係が深まっていきます。ゴードンはこの3日間でジュリアンの天才的なセンスに驚き、これをきっかけに心を開いて、「ジュリアンが納得するまで」というのを信条にしてともに作業するようになります。
『The Modern Age』のレコーディングでは、マイクが8つしか使えなかったこともあり、ドラムに3つ、ギター、ベースに1つずつ、ボーカルに1つ、ルームマイクに1つという構成で、これはゴードンのベルリンの友人、モーゼス・シュナイダーからインスピレーションを受けたものでした。
ゴードン・ラファエル「彼が見せてくれたのは、ハンザ・スタジオで学んだ昔ながらのテクニックで、使用するマイクの数は非常に少ないのだが、適切なマイクを適切な位置に配置することで、人々を魅了する非常に暖かくクラシックなサウンドを得ることができる。」 Sound on Sound : DIFFERENT STROKES より
ハンザ・スタジオはドイツのベルリンにあるレコーディングスタジオで、デヴィッド・ボウイのベルリン3部作のうちの『Low』、『Heroes』、イギー・ポップの『Lust For Life』などが制作された場所ですが、そこでアシスタントとして働いていたモーゼスが学んだテクニックがこれでした。
余談ですが、このボウイやイギーによるベルリン録音のアルバムはポストパンクというロックのサブジャンルを考えるにあたって、同じ1977年の作品でもザ・クラッシュやセックス・ピストルズの1stよりも重要とされており、当時バズコックスのボーカルであったハワード・デヴォートを最初期のポストパンクバンドであるマガジン結成の道へと誘ってもいます。ストロークスとポストパンクとの接点がここで伺えますね。
モーゼス・シュナイダーは「ドイツのスティーヴ・アルビニ」と呼ばれるほど、生のバンドサウンドをどう音源に落とし込むかにこだわっており、その経験が国を超えてストロークスにも生かされることになります。
大抵、他により多くのマイクを使うためにドラムとベースを一緒に録音していたそうですが、ストロークスのレコーディングでは上記のようにライブの感覚を残すためにこのようなセッティングになりました。
バンドからの多くの細かい注文に難儀したゴードンでしたが、出来上がった感想自体はそれまでにレコーディングした、ニューヨークのいくつものバンドのデモと同じようなもので特に思うところも無かったそうです。
そうして「The Modern Age」、「Last Nite」、「Barely Legal」の3曲を収録したデモEPが完成し、これがメンバーやライアンの手によって様々なところへ送られます。この時点ではまだライアンはストロークスのマネージャーでは無かったものの、ライアンは彼らの手助けをしたいという気持ちがあったため、50枚ほどコピーし、各所に送りつけていました。
そして、ストロークスがマーキュリー・ラウンジに送った分のEPがライアンの上司でもあるマット・ヒッキーの手に渡ります。マットは当時、イギリスのインディレーベル、ラフ・トレードのA&Rとして働き始めたばかりということもあり、ラフ・トレードの創設者、ジェフ・トラヴィスに電話越しでEPからの曲を10秒ほど聴かせたところ、ジェフはストロークスとの契約をほぼ即決。マットはライアンに「ジェフ・トラヴィスにEPを送るべきだ。」と伝え、2000年の後半の時期にラフ・トレードのオフィスに『The Modern Age』が届きます。その時のラフ・トレードは再建中でオフィスには7人ほどしか働いていなかったようですが、ストロークスとの出会いがラフ・トレードの未来をも大きく変えることになります。
ジェフはEPが送られた翌日にはライアンに契約の話を持ち掛け、すぐさまニューヨークに飛んでいき、ストロークスの面々と初対面しました。その場でジェフは契約とイギリスでのツアーをセッティングすることを提案。ジュリアンは仕事で欠席だったものの他のメンバーは多くのレーベルから無視されていたこともあり、この提案に驚いていたようです。ラフ・トレードとの契約の話を機にライアンはストロークスのマネージャーに就くことになります。
2001年1月29日にEP『The Modern Age』はラフ・トレードからリリースされますが、その前後にストロークスは初のイギリスツアーを行っています。
イギリスでのステージは初めてだったのにも関わらず、会場は大幅に定員をオーバーしており、それにジュリアンが怯えて直前に吐いたほどでした(上の動画のMCのときに「風邪をひいたんだ、けど大丈夫。」と明らかにナーバスになっている様子を誤魔化す?場面があります。)。1時間ほど遅れてスタートしましたが、ライブ自体は大熱狂のうちに終わりました。
同じく2021年1月にはイギリスの音楽メディアであるNMEのオフィスにも『The Modern Age』が届いたことで、NMEなどのメディアはこのイギリスツアーの模様を大々的に報道しました。
ちなみに、この時のライブのセットリストを見てもらえればわかりますが、この時点で『Is This It』の曲順通りに演奏していたようです。「Someday」が2000年12月にラジオに出演した時点で新曲として扱われていたのでこのあたりの時期に『Is This It』に入る曲がほぼ完成したと見られます(歌詞は全然違いますが)。
2度目のイギリスツアーとメディアのハイプ
2001年6月、NMEがストロークスを表紙に起用し、バンドにとって初めての大型インタビューを掲載します。
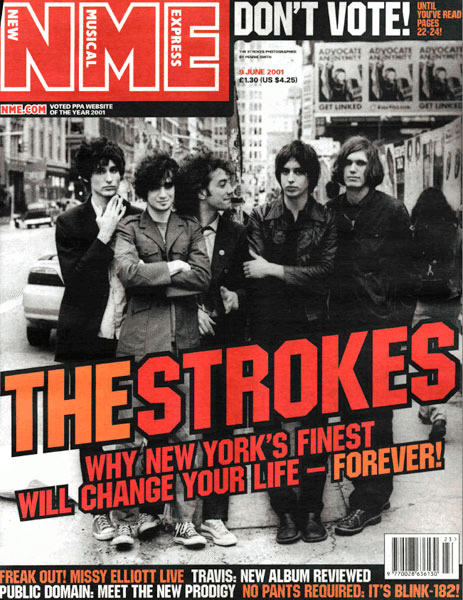
このインタビューはメンバーが写真撮影の際に喧嘩に巻き込まれる描写から始まりますが、そこにはロックファンの誰もが憧れるような、パンクで、それでいてクールなニューヨークに生きる新時代のロックスターの姿を魅力的に映し出されていました。
ジュリアンはこのインタビューの中でストロークスがロックを救うバンドだとされているというくだりで、「この類のハイプは全部クソだ。」と語っています。すでにストロークスは各種メディアのハイプに悩まされており、そこで『Is This It』(これがそれ?)という皮肉に満ちたタイトルでアルバムをリリースするに至ったと考えられています(実際にメンバーがそう発言したものは見たこと無いのですが)。
この少し前に行われた、2度目となるイギリスツアーでは後にイギリスからのストロークスへの回答とも評されるザ・リバティーンズのピート・ドハーティとカール・バラーが観客として訪れていました。

カール・バラー : 彼らはイングランドのラフ・トレードにいた。それが大きかったんだ。それで俺たちはリバプールのギグに見に行ったんだ。電車に飛び乗ってね。彼らのEPが出たところだったんで、駅の売店から盗んで、行く途中で歌詞カードを見ていた。俺たちは ’’このアメリカの奴らめ、俺らはその服を着てるんだ、これをやってやる’’って感じだったよ。
このリバプール公演を見たピートとカールはストロークスに影響を受け、リバティーンズを再出発させることとなり、ほどなくしてリバティーンズはストロークスと同じラフ・トレードと契約を果たします。
しかし、彼らの実際の関係は微妙だったようで、リバティーンズがストロークスのオープニングアクトを務めたこともありましたが、ニックやジュリアンはそこまで好意的な意見を残していません(私が知らないだけかもしれませんが...)。
彼らの関係はともかくとして、ピートは影響を受けたバンドにアルバムをリリースするかしないかのタイミングのストロークスの名前を挙げ、2002年には1stアルバム、『Up the Bracket』をリリースし、イギリスにおけるガレージ・ロック・リバイバルを象徴するバンドとなっていきます。
2001年6月25日、「Hard To Explain」と「New York City Cops」の2曲を収録したシングルをアルバムからの先行カットとしてリリース。全英シングルチャートの16位にランクインするなど、確実にイギリス国内でのストロークスの熱は高まっていきます。
コナー・オバースト(ブライト・アイズのボーカリスト): あの夏、2001年の夏は向こうでは本当にストロークスの夏だった。俺たちはツアーでイングランドに行っていて、そこで初めてオリジナルのTシャツを着て歩いてる人を見たんだ。俺は思ったんだ、「ストロークスだ!ストロークスってあのストロークスか?それともプールのストローク?」。あのレコードはアメリカではまだ出ていなかったけど、俺たちが演奏するどこのクラブでも、ドアを開けて入った瞬間に彼らはそれを流していた。 『Meet Me In The Bathroom』P188より
その2へ続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
