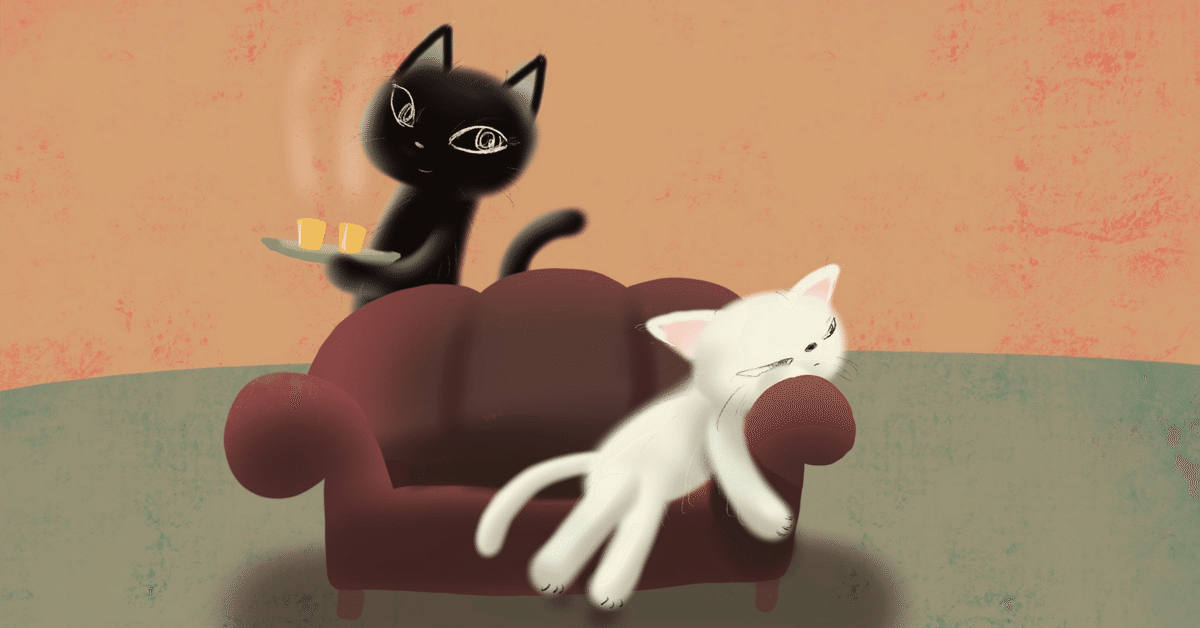
[読書ログ]「きみの話を聞かせてくれよ」
村上雅郁/作
カシワイ/絵
あらすじ
新船中を舞台に黒野良輔とその友人たちを描く青春群像劇。共感できる悩みや思いが、7章7人の主人公によって紡がれる。
(詳しいあらすじは、フレーベル館HPからどうぞ)
感想
不思議な話だなと思った。
不思議というのは、3種類の意味がある。
ひとつめは、黒野くんの存在だ。黒野くんが短編ごとに登場して、登場人物たちに寄り添い、話を聞いていく。
黒野くんとは何者なのか。
黒野くんとは何なのか。
この不可思議さが、物語の雰囲気をやさしく、穏やかに包みこんでいる。
黒野くんの存在自体が不可思議さを持っているが、わたしが不思議だと思ったのは、不可思議さを秘めた黒野くんの存在が物語のなかで異質な存在として浮いていないことだ。むしろ物語の日常の中にうまく馴染んでいる。
一見、登場人物たちを見透かしたような黒野くんの言動は、物語にとって都合の良いコマとも見えてしまいがちだが、この作品ではそれがない。うまく馴染んで、この世界の中で生きている。作者の技量によるものだと思う。
ふたつめは、メッセージ性の強さだ。
黒野くんや、先生、その他登場人物たちを通じて、作者のメッセージ性がこれでもかとふんだんに練り込まれていると感じた。特にラストの章のメッセージ性は色濃い。
作者の著書をいくつか読んでいるが、どれも心理描写や情景描写がすばらしく、叙情的感性の鋭さが、児童文学とぴったりとフィットしていて、共感性の高い文章だなあと感じていた。
どの作品からもメッセージ性を強く感じ、本書もその例外ではなかったのだが、不思議なのは、そのメッセージ性が説教臭くないことだ。教訓性を欠片でも感じると、萎えてしまいがちな内容でも、それを教科書的な表現にならずに描いている。
みっつめの不思議は、やさしさ。
わたし個人の話だが(これまでもずっと私個人の感覚の話なのだけど)、やさしいだけの話は苦手意識がある。というか、反発心さえある。
現実は全然やさしくなんてないし(誰かにとってはやさしいかもしれないけど、自分にとってはやさしい人って本当に少ないものだと思っている)、やさしい人はやさしくなっている背景があるものだけど、その背景は美しいものだとは限らないから、”やさしいだけの人”は存在しないと思っている。複雑な、そこに至るまでのあらゆるぐちゃぐちゃの感情があってこそ、やさしいというアウトプットが出来る。
それなのに、物語の中だと、みんなが底抜けに良い人で、みんながやさしくて、妬みや怒りや裏切りや苦しみも悲しみも何もなくて、物事が丸く収まる。小学生のころから、そういう本を読むと、「嘘じゃん」と思っていた。今思っても、結構ひねくれていると思う。
村上さんの著書は、やさしいのに、やさしさで紛らわす雰囲気がない。
包み込むような眼差しに、こちら側が勝手にやさしさを感じて、なぜか許されているような、不思議な居心地の良さを感じてしまう。
以上3つの不思議が、絶妙なバランスをもって成立している。
このバランス感こそ、村上さんの作品の魅力なのだと思う。
中高生時代に息苦しい思いや、かなしい思いをした大人たち、今現在苦しさや、やるせなさを感じている人たちにとっては、穏やかな許しを与えてくれるような、そんな物語だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
