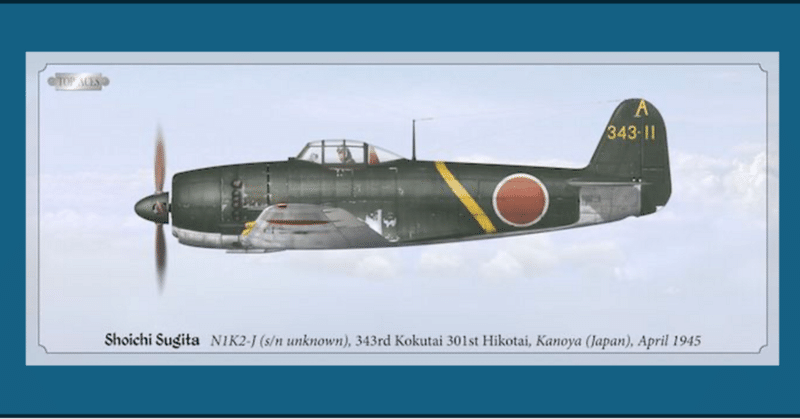
杉田庄一物語 その66(修正版) 第六部「護衛」 ヴェンジェンス作戦
ところで、暗号解読によって連合艦隊司令長官が前線視察をするという絶好の機会を得た米軍は、どのように作戦を計画し、実行したのだろうか。
「提督ニミッツ」(E・B・ポーター、フジ出版)によれば、米軍太平洋艦隊無線部隊が最初に山本長官視察に関する無線を傍受したのは四月十四日早朝となっている。米軍情報主任参謀のエドウィン・レイトン中佐は、「耳を疑いたくなるような無線傍受に成功した」という連絡を受けた。解読され、翻訳された日本の通信文に書かれていたのは、山本長官が前線を視察するという内容だった。レイトン中佐は、ただちに米国太平洋艦隊司令長官のニミッツ大将のところにかけつける。即入室を許可されたレイトン中佐は電文を渡して、
「なつかしの友、山本の件であります」と伝えた。電文には「連合艦隊司令長官、四月十八日左記によりバラレ、ショートランド、ブインを巡視せらる。0600中攻(戦闘機六機を付す)にてラバウル発、0800バラレ着・・・(詳細な旅程が続く)」
と書かれていた。ニミッツは電文に目を通した。まだ不明な部分も多い状態である。
ニミッツ提督は、巨大な太平洋全図を眺めながら考えていたが、すぐには「攻撃せよ!」と言わなかった。山本を失ったときの日本海軍、いや日本の戦争遂行への影響を慎重に考えていた。
ニミッツにとって山本は旧知の仲だった。日本に何度も訪れており、裕仁天皇に御狩場に招かれたとき、山本は案内役だった。また、ニミッツは東郷元帥に対して深い尊敬の念を抱いており国葬にも参加している。ニミッツほど日本海軍を知っている海軍の高級将官はいないと言ってもいい。日本海軍はどう動くのか、これまで米軍はやられっぱなしだった。真珠湾攻撃のあとの米海軍を立て直す役目をニミッツは負ってきた。寄せ集めの兵器や時代遅れの戦闘機も動員してなんとか日本軍をくいとめ、ようやくミッドウェーで奇跡的に勝利を得た。ここで山本を潰せばどうなるのか。逡巡の後、決断した。
「あいつをやってみるか」
レイトン中佐の頭の中でも、山本撃墜が敵にとって大きな打撃になることは疑いないと思われた。天皇を別にすれば、山本ほど日本の一般大衆から崇拝を受けている人物はいなかった。部下たちからは偶像視されるほどであった。・・・レイトン中佐は、山本が戦死すれば、日本海軍の士気をくじき、国民にも衝撃を与えるだろうと考えた。米海軍の人物情報資料にも、敵側の指揮官である山本について、「抜群に有能、熱心であり、頭脳俊敏」と記されていた。山本長官を攻撃する「ヴェンジェンス作戦」はかくして動き出した。Vengeanceは「復讐」の意味である。
第十六任務部隊司令官ハルゼー提督は参謀たちと討議し、ガダルカナル島のヘンダーソン基地にあるP38戦闘機ならば迎撃が可能であるという情報を得る。暗号解読による作戦であるため、偶発的な攻撃を装う必要がある。また、パイロットにも詳細を知らせないようにしなければならない。
ニミッツからの通信文を受け取ったソロモン諸島航空部隊司令マーク・ミッチャー提督は、作戦計画立案をフィールド・ハリス海兵隊准将に命ずる。ブイン近くに空中待機し飛行中に襲撃するか、掃海艇でショートランド島に向かうところを襲撃するかで意見が分かれた。掃海艇を撃ちもらすこと、撃沈しても助かる可能性があることなどから空中で待機し撃墜する作戦になった。作戦可能な飛行機は海軍でも海兵隊でもない陸軍航空隊所属のP38しかない。しかも、ギリギリの燃料で待機しなければならず、作戦成功の鍵は日本側の時間の正確性にかかっていた。そして、山本は常に時間を守る性格だった。
山本長官遭難後、南東方面艦隊司令長官草鹿中将は、米軍に暗号が解読されていたのかと疑念を抱き、そのことを確かめるためのおびき寄せ作戦をたてる。草鹿は、山本長官遭難以前にも暗号が漏れているのではと思うことがあり、暗号担当の軍令部第四課に問い合わせをしていたが、絶対にあり得ないという返事をもらっていた。
しかし、山本長官の遭難があまりに偶然すぎることから疑念を拭い去ることができなかった。そこで、草鹿の前線視察を装って、囮の百式司令部偵察機をガッカイ島に出し、護衛の零戦十八機で待ち構える作戦をたてた。もし、P38に襲われても百式であれば逃げ切れると判断しての作戦であった。作戦前日の十九日には、ムンダ基地に「草鹿中将以下幕僚がムンダ基地に向かう」と山本長官の時と同じような体裁で暗号電報を流した。
四月二十日、前回の山本長官機の当日の動きに合わせて八時にラバウルを出発し、ガッカイからウイツクハム方面を飛んだが敵は現れなかった。暗号電報に釣られなかったのだ。九時四十五分にブインに着き、「作戦取止メ」となった。六小隊十八機の指揮官は、森崎予備中尉で、辻野上、日高、柳谷も編成に加わっていたが、杉田と岡崎は外れていた。十八日の戦闘で被弾した機体の修理が終わっていなかったのだ。
米軍では、山本長官襲撃は極秘扱いにしてあり、「偶然遭遇した日本軍機との単なる空戦」ということにしてあった。当然、餌に食いつくわけがなく、作戦は空振りに終わる。結局、暗号解読について日本軍は疑念を抱きつつも、そのまま使い続けることになる。
四月二十二日、二〇四空はノーウエ泊地上空哨戒、青葉上空哨戒、陸攻隊直掩と三方面への作戦を展開している。早朝七時三十分に日高義巳上飛曹を小隊長として零戦三機が駆逐艦「青葉」の上空哨戒任務に出撃している。ようやく搭乗機の修理を終えた杉田は二番機で、三番機は浅見茂正飛長だった。三機は、八時三十分にカビエンに着き、十時に出発、十時四十分から十二時四十分まで任務にあたり、十四時四十五分にラバウルにもどっている。敵とは遭遇していない。
同日九時三十分に宮野大尉を指揮官として別動の零戦十一機が陸攻隊直掩任務に出撃したが、天候不良によってブインから引き返している。P38が現れるのを待ち伏せするためなのか、この日から連日ブイン方面に十二〜十八機で出撃しているが敵機とは遭遇していない。杉田も翌日のブイン哨戒の編成に入っている。また、この日から野田隼人飛曹長以下九名が飛行艇でトラックまで新機受領に赴いている。彼らは二十四日までトラックにいて、新しい零戦で戻ってきた。
四月二十三日は、五時五十分にラバウルからブインへ進出する。宮野隊長のもと十八機で発進し、途中敵とは遭遇しなかった。このときは、辻野上豊光上飛曹の二番機として杉田は編成に入っている。同日、九時から日高上飛曹を隊長としてブイン上空哨戒任務の一直につく。二直は十一時三十分から宮野大尉のもとで出撃しているが、杉田は編成からはずれている。
四月二十五日、午後、後任の司令長官として古賀峯一大将がトラック島に停泊する戦艦武蔵に着任し、久しぶりに長官旗がマストに掲げられた。表向きは横須賀鎮守府長官の前線視察ということになっていた。しかし、いつまでも秘しておくことはできない。およそ一月後の五月二十一日に山本長官の戦死が大本営から発表された。
「連合艦隊司令長官、海軍大将山本五十六は、本年四月、前線において全般作戦指導中、敵と交戦、飛行機上にて壮烈なる戦死を遂げたり。後任には海軍大将古賀峯一親補せられ、既に、連合艦隊の指揮を執りつつあり」
当時予科練だった笠井智一は、山本長官戦死の報によって隊内が大きく動揺したという。そしてその三日後に、戦局悪化のため四ヶ月はやく予科練を卒業させられている。
山本長官戦死は、国民全体にも大きなショックと虚脱感をあたえた。半藤一利は「B面昭和史」(半藤一利、平凡社ライブラリー)の中でこの日のことを次のように記憶していたと書いている。
「五月二十一日はじつはわたくしの誕生日、おやじが中学校入学祝いも兼ねて両国国技館に生まれて初めての大相撲観戦に連れていってくれていたのである。夏場所の十日目。そして午後三時すぎ、山本長官戦死の報が館内に流され、ただちに取り組み中止。協会役員や力士が整列、総員起立で一分間の黙祷、館内は粛然となった。思いもかけないことに遭遇したことになる」
六月五日に山本長官の国葬が行われ、葬儀委員長は米内光政だった。
<引用・参考>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
