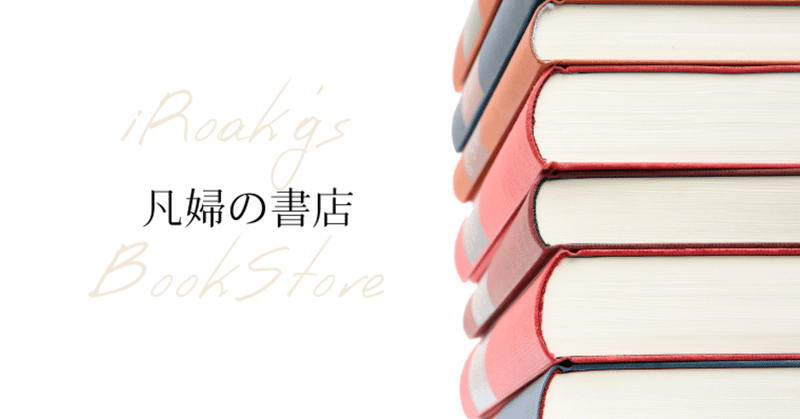
面白かった本の話をしよう #本 #漫画 #ビジネス
……今、現在は共働きで子供もいるので、そんなに読んでないです。
年間で、書籍(何ていうの?漫画でもラノベでもない本)は10〜12冊くらい。月イチペース。
漫画、ラノベ諸々を含めると300冊前後。約1日1冊くらい。
多いのか少ないのか解らないけど、少なくとも「読む人」の中では少ないと、思う。
大体、年一回別サイトでその年面白かった話をまとめてはいるんだけど、その枠を外して考えてみようかと。
感想文、と言えるかは解りませんがお付き合いください。
とりあえず、下記の作品について語ります。
「あっ、コイツ趣味合わねえな」ってことにならない為にタイトルをご紹介しておきます。
■コミック:『機動警察パトレイバー』ゆうきまさみ
■ライトノベル:『ブギーポップ・イン・ザ・ミラー パンドラ』上遠野浩平
■サイエンス:『人は海辺で進化した』エレイン・モーガン
■ノンフィクション:『名将宮崎繁三郎 不敗、最前線指揮官の生涯』豊田穣
■ビジネス:『USJを劇的に変えた、たった1つの考え方 成功を引き寄せるマーケティング入門』森岡毅
コミック:『機動警察パトレイバー』ゆうきまさみ
もうね。これについてはね。
「好き」なんです。
それ以外に説明のしようがありません。
パトレイバーは、OVAが2シリーズ、TVアニメ、劇場版2作、と、このコミック版があって、しかもそれぞれが別の時間軸というか、設定やストーリーが少しずつ違います。
コミック版が原作、と思われている方もいるかもしれませんが、これもパトレイバーの1つであって原作ではありません。
ついでに、ロボット作品と誤解されやすいですが、どちらかと言えば人間模様にスポットの当たってる作品だと思います。
レイバーという大型作業用ロボットが広く使われるようになった近未来(?)の東京で、レイバーを使った犯罪も増えた事を受けて、警視庁はレイバー部隊「特車二課」を結成した。
が、ポジション的には交通整理とかをする“現場”になるので、メンバーは新人や問題児が集められた……という話。
主人公は泉野明という新人女性警官。
1番印象的なエピソードは野明が「本当に自分は誰かの役に立ってるのだろうか?」と悩むエピソード。
当時学生だった私でも何となく理解できるエピソードでしたが、20年以上経った今でも解る!解るよ!となるエピソードです(むしろ共感度は増してる)。
忙しい時には気にならないけど、ふと立ち止まると考えてしまう。
自分としては与えられたものを頑張っているつもりなんだけど、私は本当に誰かの為になることをやってるのだろうか?
その手応えが欲しくて、野明が空回りしてしまうお話です。
余談ですが、パトレイバーのイベントでアニメ版の脚本などを手掛けている伊藤和典さんのトークショーを見に行ったことがあります。
来てるのがガチなオタクの人(もう、秋葉原がオタクの聖地になる前からオタクだった人たち)ばかりで震えたのを思い出します。
いや、良い作品です。
みんな大好き!パトレイバー!(無理矢理)
ライトノベル:『ブギーポップ・イン・ザ・ミラー パンドラ』上遠野浩平
そもそも、このシリーズは衝撃だった。
ライトノベルといえば、少年向けは角川スニーカーのあかほりさとる作品、少女向けは講談社ティーンズハートの折原みと、だった時代から考えれば衝撃だった。
オシャレで、ダークで、ライトノベルってこんなテイストあるんだ、みたいな。
やはり、シリーズ一作目の『ブギーポップは笑わない』は面白かったですが、個人的に好きだったのは、この“パンドラ”。
一作目と同様、視点の違う短編で構成されていて、読み手は様々な視点を追いながら、出来事を把握していく。
「パンドラの箱」のストーリーを絡めながら。
パンドラの箱に本当に最後に残っていたものは何か?
夢中で読んだ記憶があります。
電撃文庫の看板作品でしたね。
あの頃はノリに乗ってた。
サイエンス:『人は海辺で進化した』エレイン・モーガン
これも、学生時代に読んだ本。
今でも古本屋とかで手に入るのかな?
サイエンス系の本は面白いものの、新しいものが出てしまうと古い情報(誤った情報になるケースも)になるので難しいのですが。
ヒトゲノム解析が私が生きてる間に終わるとは思わなかったし(技術の進歩で解析が早くなった)、ネアンデルタール人が我々と同じ種であったか、というのも二転三転してるし。
この本は、猿から人へ進化したその過程の“ミッシングリンク”に当時新説を唱えた本です。
猿から人へ進化した。
それは、解る。
しかし、なぜ、体毛は退化し、二足歩行を常とするようになったのか。
二足歩行は確かに物を扱うのに便利だけども、移動するのには4足の方が早い。腰への負担も大きい。出産も難しくなる。
体毛が退化して、代わりに服を着ているのは本末転倒。
エレイン・モーガンはその“空白”を人類の祖先は海辺へと生活の場を移したのではないか、と推察した。
海へ入り生活をしたことで、体温を奪う体毛は退化し、長く息をする為に浮力を使って二足歩行をするようになったのではないか、と。
元々は映画監督の岩井俊二さんの『ウォーレスの人魚』という小説を読んで、この“アクア説”を知ったのがきっかけでした。
私もどうやってこの本を手に入れたか記憶が定かではないので、もしかしたらもっと専門的な本があるかもしれませが、解りやすく、面白かったです。
ノンフィクション:『名将宮崎繁三郎 不敗、最前線指揮官の生涯』豊田穣
最悪の作戦と言われたインパール作戦を指揮した宮崎繁三郎中将の生涯。
戦争を扱う本の難しい所は、視点によって善人にも悪人にも思えてしまうところ。
ただ、この本は現代のサラリーマンには共感できることも多いんじゃないかな、と。
インパール作戦は(拙い説明ですが)、ガダルカナル島の戦い等と同じく、当時の日本陸軍が補給経路を考えないまま兵士をインドへと進軍させ、結果、多くの兵士が武器もなく、食料もないままに、敵に囲まれて死んでいった、という作戦です。
そして、念の為。
宮崎繁三郎中将はそのインパール作戦を「指揮した」のであって「発案し、実行した」訳ではないのです。
映画『硫黄島からの手紙』の栗林中将と同じですね。
勝ち目のない戦いに、どう善戦していくか。
わずかでも勝たなければ生き延びられない極限の状態で、諦めずに投げ出さずに、綿密な情報収集を行い、わずかでも勝利を掴んでいく姿は、この景気の先が見えない現代でもがく我々に「投げ出すのは早いのではないか」と思わせてくれます。
また、宮崎繁三郎の言葉で人材の事を語った言葉で「量より質、質より和」というのは興味深かったです。
優秀な人であれば、それだけで良いのではないか、と思ってしまいがちですが、集団で作戦を遂行するに当たってチームワークを尊ぶ人は優秀な人を凌げることがあるのか、と。
凡人の私がちょっと勇気づけられた本です。
ビジネス:『USJを劇的に変えた、たった1つの考え方 成功を引き寄せるマーケティング入門』森岡毅
泣く子も黙る、USJをV字回復させた立役者、森岡毅さんのマーケティング本です。
そもそも、森岡毅さんをちゃんと知ったのはスタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーがやっているラジオ番組『ジブリ汗まみれ』にゲスト出演された時。
とにかく、お話が面白かった。
こんなにお話が面白いなら、著書もさぞ面白かろう、と。
会社の状況(予算とか環境とか)、ターゲットの選定、時期、諸々をどう考えていくのか、というのを事細かに書かれています。
最終的な目的地は現在も大人気のハリー・ポッターのエリアを作ることだったのですが。
私と同世代の方は記憶にある方もいらっしゃると思いますが当時のUSJと言えば「これ、もうダメなんじゃ…」というレベル。
オープン直後こそ、話題になりましたが、オープンの数年後で不祥事が続いたりしていたし。
話題になるものも少なかったですしね。
だから、予算もそんなにない。
でも収入は上げなければならない。
モノを売るにはどうしたらいいのか、という勉強になります。
「良いものを作る」というよりは「どうやって売るのか」というものが詰まっていると思います。
と、言う訳で。
全5冊を語らせていただきました。
もしかしたら、「え、面白かった小説はないの?」と思った方もいるかもしれませんが。
すいません。
本を読むのは好きなのですが、小説をあまり読みませんで……(文学部だったのに)。
漫画とラノベ以外はほぼノンフィクション。もしくは思想系(文化・宗教等)でして。
ネタがありませんでした。
これを読んで、同じ作品をお好きな方、「これが好きなら、この本好きじゃない?」と思ってくださった方がいらっしゃるったら是非、教えて下さい。
ありがとうございましたっ!
よろしければサポートをお願いします。
