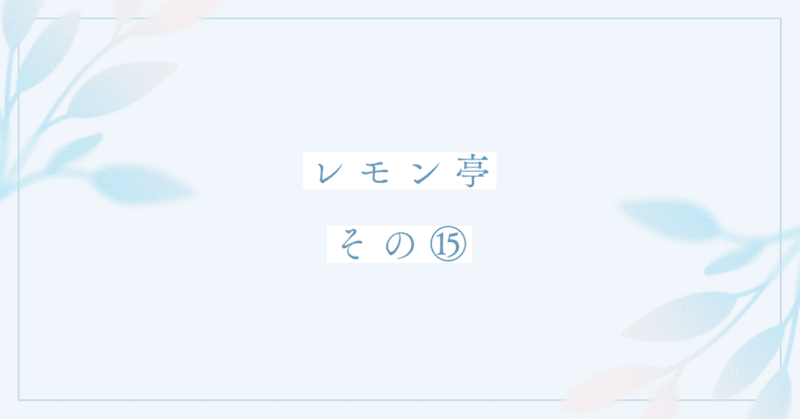
【第12話の⑮/⑯】レモン亭 /小説
その日、小森からのメッセージを見て、俺もだが久本をそれは驚いただろう。今日、三井さんとしてレモン亭にやってきたのが、土井ちゃんのお姉さんだというからだ。プロポーズされ順風満帆な土井ちゃんのお姉さんが来てるなんて、そんなことあるのか。面識がないとはいえ、知人があの席に座ることがあるなんて予想だにしていなかった。俺は斉藤税理士事務所の前の歩道から三井さんを見ていたが、思わず事務所に入り、小森と斉藤さんと驚きを共有する。
「ほう、君たちとこうやって面識を持っていてよかったよ。これは面白くなってきた。」見たまえ、そう言って左手を彼女の方に伸ばして続ける。
「お知り合いのお姉さんは、深刻な何かを抱えていそうだ」斉藤さんが言うように、せっかくの綺麗な顔が枯れた花のよう見える。レモン亭にいる久本はいまどういう気持ちでいるのだろうか。
9時を回ってもまだ謎の作業は続いていたが、やっとコーヒーに手を伸ばした。やっと終わったのだろうか。とその瞬間、突然土井ちゃんのお姉さんは立ち上がって視界から消えた。おい、どうした、何があったんだ。今までにない展開に困惑が大きくなりかけたとき、お姉さんが1階に降りてきた。
今、車道を挟んで対面の歩道にいる。何があったのか。その時だ、「ゆか」と大きな声が聞こえたのは。その声のするほうに目をやると、北側に10メートルほどにある信号機の下に、一人の男性がいた。髪は長くスラっと背が高く20代に見える。両手を高く掲げこっちだと言わんばかりに手を振っている。
「ありがとうな。君は俺の恩人だ。幸せになるんだぞ」そう言った男性の顔は土井ちゃんのお姉さんとは対照的に晴れ晴れしている。
「何言ってんのよ救われたのは私のほうよ、馬鹿」間髪入れずお姉さんも返す。しかし、はっきりとした口調ではなく泣きながら喋っているかのような、つまりながらどもりながら、まるで絞り出したかのようで、俺にはそう聞こえた。彼女は人目も憚らずあの男性を見ながら泣いている。
信号が青に変わり車がまた流れだす。その男性はビルとビルの間に消えていこうとした。俺は直感的に全速力で彼を追いかけていた。交差点を東に曲がったとき、その男性が歩いているのが見え少し安堵した。聞かねば。俺は息も整わないなかで彼の前に回り込み、頭を下げた。
「私は武田と言います。どうしてもレモン亭が何が行われているのか、土井さんは何をしにきたのか、知りたいんです。助けて欲しいんです」いきなりでびっくりしたことだろう。その男性は俺の目をじっと見て静かに聞く。
「土井さんの知り合い?」
「いえ、違いますが、土井さんの妹さんとは知らない中ではありません。今日、お姉さんがレモン亭に現れて本当にびっくりしまして。何が行われているのですか」その男性はまた俺の目をじっと見る。
「今どうしても聞きたい、武田さんなりの特別な事情があるようですね」俺は、深くそしてゆっくりとうなずいた。
「由香の知り合いなら無下にはできないね。ボナベンチュラというサービスがあって、僕も知り合いに教えてもらったんだけど、特別な人に、大事なメッセージを届けるものなんだ。ほらあそこに信号があるだろう。レモン亭から見えるあの信号の色でメッセージを伝えられるんだ。由香は読み取り表というものを手元に持っていて、時刻毎の信号の色によって読み替えて言葉をつないでいくんだ」その男性はボナベンチュラについてさらに詳しく教えてくれた。そして興味があるなら、ということで連絡先も教えてくれた。電話番号でメールアドレスだ。俺は深々と頭を下げてお礼を言う。
なんという展開だ。これは今晩予定している反省会は反省会ではなくなるぞ。俺は踵を返しレモン亭に向かう。この信号が、この信号がメッセージになっているのか。三井さんは8時からじっとこの信号を見ていたのだ。下から見上げている分にはなんの変哲もない、どちからといえば年季の入った信号にしか見えない。しかし、ボナベンチュラはどうやって信号の色を自由に変えることができるのだろうか。警察の知る人ぞ知るサービスなのだろうか。信号が赤になった。レモン亭側に渡ろうとしたときにふと気づいた。ないのだ、横断歩道が。信号がない横断歩道はよく見かけるが、こんな街中にあって信号があるのに横断歩道がないということはあるのか。もちろん歩行者用信号機もない。
いやいや、この交差点は何かおかしい。今まで全く気付くことすらなかった。ここはどこにでもある誰も気に留めることがない交差点ではない。日常に溶け込むようカモフラージュされているが誰かの意図が織り込まれている。目には見えないがここには何かがあるのだ。今までの停滞感をくつがえすたくさんの発見と川村さんの笑顔を思い浮かべ、いますごい高揚感に包まれている。横断歩道のない道を渡っている俺はまるでレッドカーペットを歩いているかのような誇らしい気持ちでもいた。
(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
