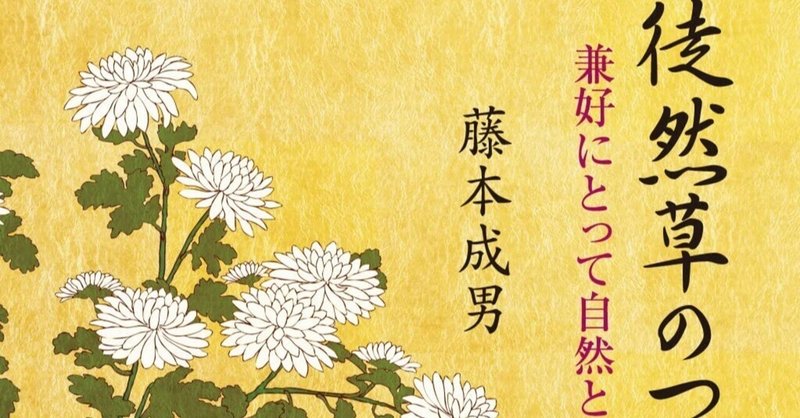
本の記録 『徒然草のつれづれと無為』兼好にとって自然とは何か
ほとんど検索にかからないマイナーな本です。
参考になった文章を紹介します。
身ひとつ、心ひとつをそのままにしておくことは、もはや時間という重苦しい無聊【(ぶりょう):心配事などがあり気が晴れない】もなく、時間が時間であるということによって起こる煩わしさもない。そこにあるのは、選び取られた閑暇【ひまであること】であり、自覚された閑暇であり、豊かな閑暇である。
「つれづれわぶる」ということの意味を突き詰めた末に、「ただひとり」であろうとすることによって、時間が時間を感じさせないまでに透明化された。空白の閑暇からすべてが生き生きと映し出され、ただそれを如実に見ればよいのである。空虚であったが故に、そこにかえって何ものにも換えがたい柔軟性を得たのである。その「無」のうちに、限りない豊かさが生まれる。いわば蘇東坡のいう「※無一物中無尽蔵」である。
※無一物中無尽蔵:人は何も持たずに生まれ、何も持たずに死んでゆく。すなわち、何もないことは無限にあるということである
『時間が時間を感じさせないまでに透明化された』に私は共感しました。
「つれづれの境地」の最終点は、止まった時間であり時間の流れの消滅では無いでしょうか?
兼好(鎌倉時代末1280~1350年頃)の生きた時代は、現代ほどではないが人々はすでに慌ただしく生きていた。
忙しく生活する日常からドロップアウトし、半隠居生活を送った兼好。
俗世間(群衆)の富や地位や名誉を巡る争いから逃れ、独り自分と向き合う。
それによって心が浄化されたのではないでしょうか?
俗世間(群衆)から離れたからこそ、見えてくるものがきっとあると思います。
兼好の意識に強く働くのが「ただ今の一念」である。今、目の前にある現実にじかに向き合っているかどうか、と自らに問わずにいられないのである。そうでなければ、その目の前のほんとうに大事なことを見過ごしてしまうかもしれない。そのためには、まさに「ただ今」に目覚めていなければならない。
肝心かなめのことは何かといえば、この「今」を疎かにせず、「今」がすべてだと思えるかどうかであり、それこそが本来の「無為」に生きるということなのだ。
とり逃がしてはならないのはまさにこの「ただ今の一念」であって、長く伸びた時間、日月などというものではない。今日は今日でしかなく、今は今でしかない。今日、今の他にはないのであって、問題はそれに真正面から向き合っているかどうかである。そして、明日がない、今の後がないということが身に沁(し)みてわかるのは、自らの「ただ今の一念」において、死を逃れられぬ現実として自覚したときである。
『明日がない、今の後がないということが身に沁(し)みてわかるのは、自らの「ただ今の一念」において、死を逃れられぬ現実として自覚したときである。』
戦争がない平和な日本では、死が遠い存在になっています。
日本人の多くは、平均年齢の80~90歳まで生きて当たり前と思っています。
その常識的な人生観が、「ただ今の一念」の尊さを見失う原因になっていると思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
