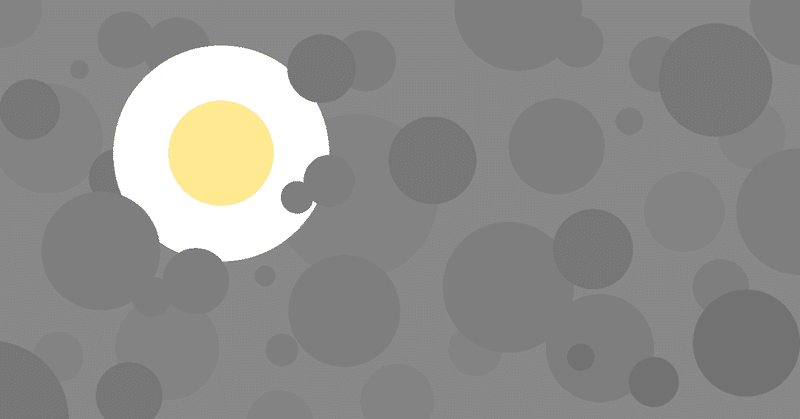
月のお姫様は竹から産まれない
ほんとにばからしい。なにがそんなにばからしいかって、それはなにも音読のしゅくだいそれ自体のことをいってるわけではありません。かちゃかちゃ、とんとんと音立てて、夕ご飯のしたくに精を出しながらニュース番組を耳でみているママにむけて、ふつうより大きな声を出してこくごのきょうか書を読み上げる。まい日のことだから、ママも聞いているのかいないのかわからないし、それよりもなんで声に出して読まなくちゃいけないのかがわからない。「、」があったら少し止まるとか、「。」があったらもっと止まるとか、「「」」があったら気もちをこめて読まなきゃいけないこととか、めんどうくさいとおもう。もく読でいいのにと、いつもおもう。わたしは音読がきらいだからつい、わる口を書いてしまったけれど、わたしが今ほんとにばからしいとあきれていることはべつにあります。それはなにかというと、今日、音読のしゅくだいで読んだ『かぐやひめ』というお話のことです。
今日のこくごのじゅぎょうで『かぐやひめ』というお話をべん強しました。光る竹のなかには女の子がいて、これからどういう風になるのかなと、わくわくしながら読んでいました。でも、とちゅうからはおかしなことが書いてあって、ばからしい気もちになりました。月のおひめ様が竹なんかから生まれるわけがないからです。
――月のお姫様は、月から産まれるに決まってるじゃない。月から産まれるからこそ、月のお姫様たりえるのよ。
これはママから聞いたほんとのことです。わたしがママに、わたしはどうやって生まれてきたの?ときくと、ママはきまってこういいます。
――あなたは月から産まれたの。だから、あなたは月のお姫様なの。
ママはうそつきじゃないので、これはほんとなんだとおもうのですが、学校のみんなは、子どもはママとパパからうまれるといっています。なので、それでもやっぱり気になってしまって、わたしは少しかんがえてから、ママはどうやって生まれたの?ときいてみました。
――ママもあなたとおんなじよ。月から産まれたの。だからね、私も月のお姫様だったのよ。
ママはすごくまじめな顔でそういうので、わたしはほんとのことなんだとおもうことにしました。でも、ママがもうおひめ様じゃないのはどうしてなのかな、ともおもいます。わたしが読んだことのある本には、たくさんのおひめ様が出てきました。白雪ひめとか、シンデレラとかです。いろんなおひめ様がいていいのにな、とおもうからです。
ここまで書けば、どうしてわたしがおこっているのかが分かるとおもいます。『かぐやひめ』は月のおひめ様をばかにしたようなうその話で、それは、月のおひめ様であるわたしのことをばかにしているのです。とはいえ、『かぐやひめ』なんかをほんとの話だとおもっているひとたちに、月のおひめ様はわたしです、といってもしんじてくれないとおもいます。なので、毎朝わたしがやっている、月のおひめ様の「つとめ」のことを書こうとおもいます……
ナツキは、むかしの自分がつけていた日記を読み返していた。その日記帳は艶やかな緑色の装丁が施されている、かの「学習帳」と呼ばれるの類のものだ。B4サイズの用紙の束、その中心を縫い留め、折り曲げてできたB5サイズのノート。「折り曲げる」という力業によってあるべき姿を定められるも、その不条理な宿命に立ち向かい無垢の紙束へ戻らんとして「ひとりでに開く」という抵抗の意思表示をやめない、あのノートである。棚に並べられ、使用者に買われ、酷使される。その工程を経ることで、当時のとがりきった反抗心を体現したかのごとく反り返った体躯は、他の紙束たちからの重圧に押しつぶされてぺしゃんこになる。やがて、その重圧を痛いとも苦しいとも感じなくなったとき、彼は押しつぶされる側から、押しつぶす側へと回ることになるのだろう。たとえその転回が無自覚であれ、その壮挙を遂げた時点で彼は「装丁された紙束」から「学習帳」へとキャリアアップするのである。晴れて一人前のノートとなったかれらの勲章は、「望まれる姿を無意識的に演じることのできる器量」としての平坦さだけではない。諸々の軋轢に擦られ、角が取れたことはその面構えにも反映されている。はずかしいくらいにぴかぴかだった緑色の光沢は掠れ、ところどこが白く剥げており、また別のはずかしさをたたえている。そして「学習帳」のトレードマークともいえる、中心に据えられた極彩色の花の写真も同様に掠れており、もとよりどこに自生しているとも知れぬ木花の判別をいっそう困難にしているのであった――などということをナツキがかんがえていたかどうかは知る由もない。それでもなお、「むかし」の自分がつけた「むかし」の日記帳であるからして、与えられた冠詞のとおり、それに準じた経年劣化を生じていたことは確かである。
その日記帳の古ぼけた感じをいくばくか強調して書いてはみたものの、ナツキがふり返っている「むかし」というのは、それほどむかしのことではないかもしれない。けれども、加速度的に過ぎ行く時間の流れの中にあっては、彼女が「むかし」とおもうのも無理もないことだといえる。ここで、x軸が右に伸びる数直線をイメージしていただきたい。おもいうかべた背景が黒板なら白色のチョークで、あるいは学習帳やホワイトボードなら黒色のインクで、ながーい矢印が描けたことだろう。これは「人間がとしを重ねていくたびに、時の過ぎるのを速く感じる」ことを図式化しようという試みであるから、当然その矢印には「年齢」の目盛りが振られていくこととなる。そして、「重ねていくたび」という部分から、その目盛りどうしの間隔は右へ行くにしたがって狭く、狭くなってゆくことがわかるだろう。今ここから明らかにしたいのは、「成長段階における数年間の体感時間」は「程度成熟した段階からの数十年間の体感時間」と同程度の濃度を持つ、ということである。それに加え、「むかし」という語は少なからず「幼少の頃」という意味合いをも含むものである。成熟段階の子どもは、目まぐるしい速さで更新を続けるプログラムなのであり、新しくない様々な記憶や考えは無意識のうちに「幼少の頃」へ切り落とされ、「いまの自分」とは分離を余儀なくされるわけである。そのような具合であるから、中学一年生であるナツキが小学二年生の頃に書いた日記をみて「むかし」を感じたことに関しては、これ以上追及しないでいただければとおもう。
どうして彼女がむかしの日記を棚から引っ張り出すに至ったのか。その契機となったのはやはり『かぐや姫』なのである。とはいえ、『かぐや姫』の絵本を読んだりなどをしたわけではない。ナツキは今日の国語の時間、『竹取物語』を勉強したのだった。真四角の教室、かたく冷たい机椅子の整列、チョークが黒板を小突く音、なんにでも竹をつかうらしいお爺……。当の状況に妙な既視感をおぼえた彼女はそれからの半日ほどを、記憶の回廊を順路に逆行しながら流し見する迷惑な来客として過ごす羽目になってしまったのである。もっとも、その脳内ギャラリーにほかの観客が見えようはずもなく、唯一の客であり当回廊のオーナーたる彼女は、夜間の美術館を警備巡回するかのような様相で不審な思い出の影を探し回っていたのである。国語のじかんから放課、そして部活動のあいだまで。そう、部活動――どこからともなく出現し、生徒たちの自由意思を蝕み続ける力「部活動加入への強制力」。その見えざる力に感づく間もないまま流されたナツキは、卓球部への入部を果たしたのであった。ナツキが卓球部を選んだわけはいたって短絡的で、安直なものだといって差し支えないだろう。
――“人間の反応時間の生理的限界0.1秒、それが反応時間!反応時間を反射時間に可能な限り近づける、つまり0.1秒で反応すること!卓球は世界最速の反射神経を競い合うスポーツだ!”――
これは、かのスポーツおよびその競技者の青春を描いた熱血スポコン漫画に登場する卓球部顧問の台詞であり、この名作に触れたことで「ピンポン」もとい卓球への興味、または幻想を抱いていたナツキは、愚直に入部を決めたのである――そして想像以上にハードな鍛錬(これは得てして、万物がそうなのであるが)、例えば瞬発力を高めるため短距離の走り込みであったり、差し込む日差しによって天然のサウナと化した体育館での基礎練習である。これらを終えてさあ下校だと、したたる汗をスポーツタオルで拭いながら、彼女はいつのまにかぬるくなっていた蒸し風呂から退いた。そして、濃淡の際立つ、水彩で描かれたみたいな紫色の空の中で、妖しく光を放つ望月を無視できようはずもなく、友達部員といっしょにお月さまを見上げてみたのだった。入部間もない彼女らはいまだ素振りばかりで、実戦経験をもたない。そんな新米部員たちが月の裏側にみていたのは、プラスティック製の小さな――緑や青の塗装が施された長方形のフィールド上をリズミカルに跳ね、飛び交うような――また別の月だったかもしれない。その中にあってもひとり、ナツキだけは、ありのままの「月」を直視していたと断言できるだろう。「月のお姫様」を自称していたむかしの記憶へやっとこさたどり着いた彼女は、思わず声をこぼしていた。
――ナツキ、どうかした?忘れ物でもした?
そう尋ねられても、ううんなんでもないと作り笑いで応えるしかない気まずさから、ナツキは顔じゅうの毛細血管に赤い血潮が集まってくるのを感じていた――かようにナツキが赤面したのは、ある種の気まずさだけでなく、じつは一足遅れてやってきた「はずかしさ」のためであったようにもおもえるのだ。ここでいう「はずかしさというのは、『小学二年生になってまでも「月のお姫様」を自称していたという、なんともかわいらしい過去』のことではない。現時点での最新バージョンたる今日のナツキにもまつわる「はずかしさ」がそこには存在していたのである。この「はずかしさ」がいかようであるかを明らかにするためにはまず、「むかしの日記」にて記載されていた、幼き月のおひめ様の「つとめ」について説明する必要がある。
かくして「むかしの日記」に目を通すに至ったナツキは、それを踏まえたうえで――そしてその「つとめ」について――「いまの日記」へ以下のように書き綴っている。
――国語の授業で『竹取物語』をやった。なんかまえにも同じような出来事があったような気がして、ずっともやもやしてた。今日はきれいな満月で、それを見たときにやっと、小学校で『かぐや姫』読んだときだーと思い出した。太陽に照らされる月が私の心を照らしたんだ、なんて、むかしのわたしが考えそうなことをいま思った。家に帰ってから、『かぐや姫』のことを書いてる日記を探して読んだ。もう小学生なのに、まだ自分のことを「月のお姫様」とか言ってて、笑う。名前に「月」って文字入ってるし、ほんとに信じちゃったんだなー。お母さんの言うことをちゃんと聞けるいい子ちゃんだったんです、、じつは。あと、「つとめ」とか書いてておもしろい。背伸びしてまじのお姫様みたいな言葉使っちゃって、かわいいな~私!でも、この「つとめ」についてはちょっとまじめに考えてしまう…
小さい頃の私は、目玉焼きが大好物だった。そうはいっても、どんなものでもいいわけじゃない。お母さんが作ってくれる半熟の目玉焼きが、特別好きだった。やわらかいんだけどしっかり火が通ってて、焼き目はぱりっとしている。まんまるの白身の中心に乗っかった、まんまるの黄身(これは盛ってるんじゃなくて、ほんとに丸いの。もうほぼ円。コンパス使ったみたいに!)。いまの私はもう算数じゃなくて数学を勉強しているから、この白と黄色の関係は「同心円」って呼ぶことを知ってる(天才か)。一直線にならんだ2つの円、これはなんだか日食みたいに見えるなとも思う。白身が太陽で、月が黄身(ちょっと月が小さいかな)。むかしの私は日食なんて言葉は聞いたこともなかったけど、その半熟お月さまに恋をしてたの―なんたって私は「月のお姫様」だったんだもの☆――。この目玉焼きを毎朝お母さんに焼いてもらってね、毎朝欠かさず食べていたの。もちろんお姫だから、ナイフとフォークを使ってね。これが私の「つ・と・め♡」。
結局、ナツキはまじめに書き切ることが出来なかった。とはいえ、まじめに考えなかったわけではない。考えたうえで書かないことを選んだのだ。ナツキは自分がやってきた「つとめ」を客観視することで子どもらしさやばからしさを感じるとともに、その「つとめ」を中学生になってもやめられないでいる己に対して、やり場のない「はずかしさ」を覚えていたのである。むろん、毎朝目玉焼きを食べる習慣が恥ずべき事実であろうはずもなく、ナツキの「つとめ」にはいまだ語られざる工程があるのだ……。彼女はすでに消灯し、布団を顔まで被っている。そして、『私はもう、いやはじめから「月のお姫様」なんかではないのだ』と自分に言い聞かせながら、蛍光灯が発する仄暗い残光をみていた。そのうちに視界がまっくらになったのは、残光すらもが消え寝室に闇が降り立ったからか、それとも彼女が月へ降り立ったからか?いや――彼女の瞼がその瞳を覆い切ったからだ。
*
今朝もまた、こなれた手さばきでフライパンを火にかける。カヅキが作らんとしているのは、くだんの「日食の目玉焼き」だ。ナツキがそれに執心し、つくってほしいと頼むようになってからというもの、カヅキは毎朝欠かさずに目玉焼きを作り続けているのだった。そうして連続性を与えられた非日常が、次第に日常のなかへと組み込まれてゆくように、ナツキの執着心が薄まり元来の目的を見失った今でもなお、カヅキの習慣は続いているのだ――少なくとも、ナツキはそう認識している。それと同様に、ナツキのほうも目玉焼きを食べるという習慣が続いており、いまだ「つとめ」を断つことができずにいる一因ともなっているわけなのだ。
ところで、目玉焼き作りというのは非常に簡単そうにおもえる。実際、卵を割り入れることさえできれば、なんとかかたちにはなる。こんなにも手軽な料理であるから、子どもが――とりわけ目玉焼きが大好きな女の子が――わたしにもつくらせて!などとのたまうのは、欠けて見える月が実際に抉れているわけじゃあないことくらい、月のお姫様が竹からうまれないことくらい、子うさぎがかわいいことくらいあたりまえのことなのである。そしてまた興味津々、意気揚々といった様相で目を輝かせる幼子の望みを一蹴し、絶望の底のゴールネットに叩き込むことなど子うさぎに餌をやることくらい容易いが、そんな子うさぎを締めずに捌き、美味しいパエリアに仕立て上げるような惨たらしい真似は出来ようはずもない。かくして幼きナツキは「おてつだい」の皮をかぶった、止めどなく溢るる好奇心に突き動かされるばかりの「邪魔」を、母親たるカヅキからすれば微笑ましいことこの上ないわが子の調理実習の初陣を、見事成し遂げるに至ったわけである。この場合、見習いシェフの作り上げた作品がどれほど惨憺たるものであろうとも、その出来具合のいかんに関わらず無二の思い出として美化されるものだといえよう。そして料理長の技巧の熟達具合を再認識した見習いシェフは羨望の眼差しでもって見つめ、弟子の将来性を再認識した料理長は期待を込めて見つめ返す、というのが典型であるが、ナツキの場合はそうもいかなかった。というのも、彼女はただの目玉焼きが作りたかったわけではないからだ。大小二つの円がその中心をぴったりと重ねた「日食の目玉焼き」は彼女が思い描く完成像の絶対条件なのであり、その理想とは天と地ほど、月と地球ほども差がある自身の作品を前にした彼女は、不機嫌を隠せなかった。
それから彼女は目玉焼き職人となることを志し、様々な手法や道具を用いて実験を続けた。そのなかで、自身の思い描く完成像に寸分違わぬ「同心円の目玉焼き」が生まれたこともあった。しかしながらカヅキの「日食の目玉焼き」が持つ全細胞が共振し、それに惹かれることが二重らせんに刻まれた規定事項であるかのような――ヒトが「一目惚れ」で恋に落ちる機構と同じように――そんな魅力を感じることはなかった。そこにあるのは自分の手で手間暇かけてつくりあげたという「愛着心」だけであり、まんまるの黄身ももお月さまには見えなかった。
「わたしもできるようになりたい」という希望はいつしか「どうしてわたしにはできないんだ」という悲嘆へと置き換わっていった。そうして“完璧に均整の取れた「同心円の目玉焼き」が好きなのではなくカヅキの作る「日食の目玉焼き」が好きなのだ”と結論づけたわたしは、職人の道を諦めたのだった……
なんてことをナツキは考えていたかもしれないし、べつにそんなことはないかもしれないが、いつのまにか学校指定のセーラー服をまとい、ステレオタイプな「家庭の朝の風景」の一部となっているこの物語の主人公は今朝も飽きずに、テーブルという名の宇宙空間のうえの、天の川銀河たる丸皿に乗っかった、平たい月と太陽に見惚れていた。そして白と黄色の小さな天体を焼き上げた創造主カヅキはというと、自分の分の目玉焼き――これはごくありふれた類の、アメーバーみたいなかたちのやつだ――それとサラダやパンやらをすでに平らげてしまい、お洗濯やおめかしなどをやっているところであった。つまり、別次元よりナツキを観察している我々を除いて、彼女を視界に認める者は誰一人いなくなったわけだ。満を持して、とでもいうべきだろうか。これより、毎朝人目を忍んでひそかに続けられてきた、ナツキの「つとめ」が執り行われる。たとえこの機会を逃してしまったとしても24時間後にはまた見られることだろうが、べつに待たねばならぬ理由もない。月のお姫様の「つとめ」とやらを一緒にみてみようじゃあないか。
ナツキは知っている、今宵の月のかたちを。今更こんな寝言を発しようものなら、そんなのあたりまえじゃないかという非難の声が上がるだろうことは承知のうえだ。たしかに、彼女は昨晩が満月であったことをその目に認めていた。あまつさえ、その輝きにむかしの記憶を呼び醒まされてもいるから、暮れに浮かんだ丸いシルエットを忘れていやしないはずだ。したがって、満月の右側からその13分の1程度を削ったものが今宵の月のかたちだと導き出せる……確かに、そういった主張は的を射ていると言わざるを得ない。しかしながら、ここで述べたい事柄が明白な事実の再確認に尽きるはずがないことは、皆様お察しの通りだ。仮に昨晩の月の形状を覚えていたとして――たとえそれが満月だったとして――数十ものアウトテイクを重ねたうえでしか成立しえないような、背筋から指先までを繊細に統制し洗練された優美な動作でもって、ちょうど今宵の空に浮かび上がるはずの月のかたちそっくりそのままに、目玉焼きの黄身を切り取ることが果たして可能だろうか?
ナツキはいともたやすく、さも毎日の習慣であるかのように、突き詰められた自然さのなかで、その妙技をやってのけた。何を隠そう、これこそがナツキの「つとめ」である。彼女は「日食の目玉焼き」と対峙すると、その黄身をきょうの月のかたちに切り取らずにはいられないのである。ナツキを奇行へ走らせるこの衝動は、「むかし」のわたしが「日食の目玉焼き」に出会ったときから変わらずに、彼女を駆り立て続けている。自らを「月のお姫様」と称し空想に生きていた当時はなんの問題もなかった「つとめ」は形骸化し、現実世界とたたかう彼女の悪癖となり果ててしまった。なおもその悪癖から抜け出せないのは、「つとめ」に睡眠欲や性的欲求などの根源的欲求と同様の、まるで遺伝子レベルでそう決まっているかのような――もちろん「つとめ」は食事の一環であるが、それに伴うのはただ食欲を満たすのみに留まらぬ快感だ――そんな気持ちよさを得られるためだ。かような衝動や快感を発生させる「日食の目玉焼き」のその尋常ならざる魅力のひみつは材料のたまごにあるのではないかと、ナツキは推し量っている。幾多の試行の結果ナツキが作り上げた「同心円の目玉焼き」には、愛慕を超える魅力はなかった。カヅキは「日食の目玉焼き」について何かを隠している。これはただの勘だ。性徴の兆しが身体の随所にあらわれ、「こども」から「女」への移行段階の過渡期にある「少女」の勘。
とはいえ、こんな分析や予感など何の意味も持たない――正確には、一切の意味を持たなくなってしまうときがすぐ後ろに迫っている。そして、このお話もひとつの区切りへと辿り着こうというわけだ。そこで、いちおうの「クライマックス」を迎えねばならない。「虚構」であるこの駄文を読み終えたあなたは否応なく「現実」へと引き戻されることとなる。つまり、「虚構」の終わり=「現実」のはじまりといえる。これは夜が明け朝がやってくるような、夢うつつのまま朝食を食べ終えた生徒が摂取した栄養分でもって真の覚醒を果たすような……そう、お月さまはもう沈まねばならない時刻なのだ。
平皿にぽつんと佇むちょっぴり欠けた駆け込み満月は、いま銀のフォークに掬われたところだ。しなやかな腕のうごきが、それをやわらかな唇の内へと運び入れる。お月さまを受け取った赤い舌は、その身を天へと昇る龍のようにうねらせて、欠けた月を奥のほうへと押しやる。ナツキは首のまわりの筋肉を弛緩させ、のどを拡げ、そして――
お月さまを丸のみにした。
おおきな異物たる小さな月が、食道を押し拡げながら通過してゆく。耳の下からのど仏、そして胸へと。意外にも苦痛はなく、ナツキの脳内報酬系の活動は最高潮へ達していた。この形骸化した「つとめ」がはしたない悪癖であることや、カヅキが隠しているであろうたまごの秘密が、さらにナツキにお父さんがいないことさえもが、もう全部どうでもいいことのようにおもえてしまうこの瞬間が、ナツキはたまらなく好きだった。半熟のたまごを噛みしめたときの膜の内よりあふれ出た濃厚な蜜が口内に絡みつき、とりわけその舌を蕩かすような――奇しくも、かのお月さまは顔パスでもってエナメル質の検問を回避したわけだが――そんな表情をたたえながら、彼女はその悦楽に浸るのだった。かようなエクスタシーを巻き起こしながら、お月様は胃酸の海へと沈んでいった。
以上の過程をもって、本日のナツキの「つとめ」はつつがなく締めくくられた。「むかし」のナツキがこれを「月のお姫様」の「つとめ」などと表現していたのは、月に見立てた「日食の目玉焼き」の黄身を切り取りその部分だけを食べてしまうことによって、月の満ち欠けを操作しているかのように錯覚したからである。朝方のうちにそのいくばくかをかじられその形をゆがめられた月は、そっくりそのままの姿で宵闇に現れるというわけだ。
このようにして月の朔望を意のままにする「月のお姫様」に、“太陽が出ている昼の間、月は地球の裏側に隠れている”などという宇宙の秩序を説いても意味がないことは明白でろう。もし彼女が一思いに「日食の目玉焼き」へちいさな拳を振り下ろそうものなら、その晩には爆砕した衛星のかけらたちが煌めき、閃き、夜空に降りそそぐことになるのだから。
かような脅迫的手段でもってナツキは秩序そのものと化すなり、“太陽が幅をきかせる昼の間、月は「月のお姫様」の体内で身を潜める”ことと相成った。そのからだに月のパワーを宿した「月のお姫様」は、いかにも「月に代わって」現実世界とたたかってゆくことになるのだ――。
*
『私はもう、いやはじめから「月のお姫様」なんかではないのだ』と、頭ではそう理解しながら、ナツキは今日も形骸化した「つとめ」をやめられずにいる。その愚かさと、奇行に及び快楽を感じている後ろめたさこそが彼女の“はずかしさ”であった。かような負い目を与えながらも、それを上回って余りある快楽を提供し続けるカヅキの「日食の目玉焼き」。そのひみつについては――また次の機会にお話しすることにしよう。
続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
