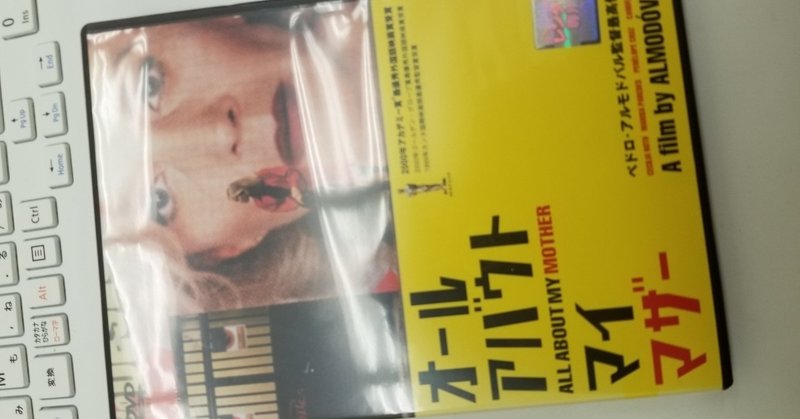
映画『オール・アバウト・マイ・マザー』を見ました
『オール・アバウト・マイ・マザー』を見た。1999年のスペイン映画。原題はTodo sobre mi madreだけれど、スペイン語にこだわる必要を私自身が感じられないくらい、世界的にヒットしたし、多くの人に知られている作品。
私がこの作品を見るのは3回目。1回目は、日本での公開時。ちょうどスペイン語を専攻した大学を卒業した後で、友達もほとんどいない東京で就職したころに、ひとりで映画館で見た。当時ものすごく話題になっていて、「立ち見でもよければ」と入れてもらって、通路の階段に座って見た記憶がある。
2回目に見たのは、自分が最初の子どもを産んだ後。映画館の階段に座って見た『オール・アバウト・マイ・マザー』で受けた感激があまりに大きくて、自分が母親になった立場で見てみたらどう思うだろうかという興味でDVDを見た。
今、こうして当時の気持ちを思い出して書いているだけで、ついさっき観終わった3回目の感想がかすんでしまうくらい、1回目、2回目の映画鑑賞体験は、私にとって強烈だった。
1回目の鑑賞時、私は「母から生まれたすべての人へ」というコピーにとにかく感動していたし、自分が母親になれる可能性のある性別に生まれたことをなんてすばらしいことなんだろうと思った。心の底から、女に生まれてよかったと、思った。母親になること。それを、感動的なこと、素晴らしいこと、誇らしいこと、そういう類の「行為」として受け止めていた。と思う。
では、実際に、2回目に子どもを産んだ後で見たときの感想は、どうだったかというと、私はひたすらに、ロラの子を身ごもったロサを愚かな女だと思った。最初に見たときになぜこの映画を見て母親になることが素晴らしいと感激したのか、過去の自分を恥じるくらいだった。そのときの私は、ロサはロラに恋をしたのであって、恋をすると女は理性が働かなくなる、とそういう解釈で映画を見た。
ああ、人というのは経験によってこれほどまでに感じるもの、考えることが変わるのか…。
今夜、さっき、今。最後の出産から今年で10年になろうとしている40代半ばの私が、もう一度この作品を見て思ったのは、この映画が孤独を描いているということだ。女性であることや、母親になることや、恋をすることは、女優たちがスペイン人であることとか、話されているのがスペイン語であることとか、そういうことと同じように、明らかだけれどもそれを描いているわけではないこととして、私の中で解釈の対象からはずれてしまった。だいたい、この映画に恋をすることなんて描かれているか?と考えてしまうほどだけれども、でもロサがマヌエラに対して温もりを求める態度や、大女優のウマがヘロイン中毒のニナのことを「夢中なの」と認めるあたりは、やはり恋と言っていいと思う。どちらも女性から女性へという関係性だけれども。
25年前の私が、ただただ「母親になる」ことに感激して、言葉にできなかったように、今の私はまだ、孤独については書けることがない。人生には孤独というものがあるのだということを、たぶん知っているし、この先、自分ごととしてイヤというほど味わうのかもしれない。
でも、たぶんそれは、あこがれていた「母親になること」が、今となっては「行為」ではなくて「現象」のようなものであり、態度であったり、日々の決断であったり、無意識にいつも頭のどこかにあることだったりするのを意味しているのと同じように、孤独は、きっとこのさっきの人生のどこかにありながら、「起こる」ことではなくて気づくと一緒に日々を過ごしているものなのではないかな、という気がしている。
※この映画について、友人でもあるカウンセラーの高橋ライチさんと、「語り合うスペイン・ランチ会」というイベントをします。2月18日(火)のランチです。ここに書けなかったこと、書いた後で気づいたこと、あなたの視点から聞かせてほしいこと、たくさんシェアしたいと思っています。詳細はPeatixページ(下記リンク)をご覧ください。ご参加、お待ちしています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
