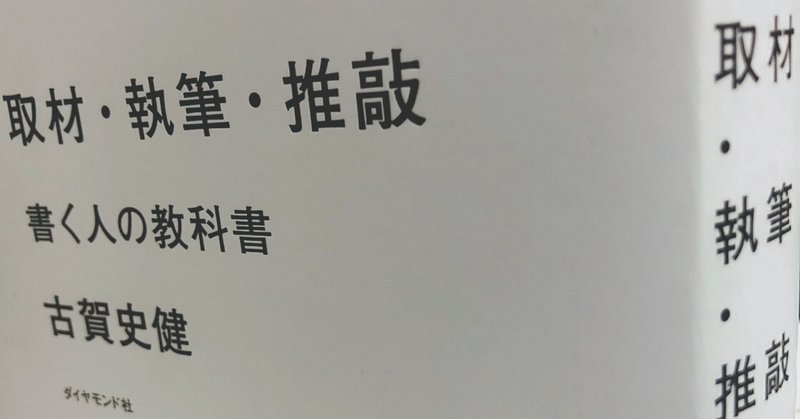
古賀史健『取材・執筆・推敲−書く人の教科書』を読んだ
初めて教科書を「買った」ことを意識したのは、大学に入学した時だった。
日本で暮らし、大学まで進学した人の多くも、ほぼ同じタイミングではないかと思う。自分で稼いだわけではないにしても、自分の財布からお金を出して、大学生協か大学の傍の古本屋かで、教科書と交換してもらう。
たしか、最初はクラス指定の語学の教科書を買ったはずだ。その手の本は、高校までの教科書と変わらないような、分かりやすそうな薄っぺらいものだった。しかし、自分で受講する科目を決めてから買った本の中には、辞書以外に初めて触るような厚さの専門書もある。一応は一般書の体裁をとっているものの、「受講生以外に買う人がいるのだろうか」と訝しくなるようなマニアックな本もある。
特に、大学2回生から本格的に学び始めた法律の教科書は、どれも分厚かった。特に後期は、毎年その頃に新しいものの出る『ポケット六法』と一緒に全科目の教科書を揃えれば、学生の間では「鈍器」だとか「人の首に向かって落とせば人を殺せる」だとか、物騒なジョークが飛び交ったものだった。
分厚い教科書は、重いし、場所も取る。授業は1日に何科目もあるから、必然的にそんなものを何冊も持ち歩くはめになる。勉強するだけで肩が凝るのに、この持ち運びで余計に肩が凝る。徒歩通学の私でも嫌になるほどだったのだから、隣県などから通ってきている同級生は一体どんな気持ちなのだろうかと思っていた。
もちろん、中には、「今時どうして電子書籍化しないのか」と文句を言う同級生もいた。しかし私は、法律の教科書というのは市場が小さく出版社が電子書籍化を急ぐ理由はないだろうと思ったし、そもそもパンパンに張った肩に大きなバッグを引っ掛けてこの「鈍器」を持ち歩くのが嫌いではなかった。上に書いたようなジョークを言いながら生協の紙袋を2枚重ねにしていた同級生達も、なんだかんだこの凶器のことが好きだったのではないかと思う。
私が分厚い教科書のことを好きだったのは、一般的な紙の本を手に入れるときの所有の喜びのほかに、「半年後の自分の頭には、この重さの知識が入るのだ」という興奮があったからだ。
試験前の追い込みの時にやることといえば、教科書の通読だった。とはいえ、500ページくらいあると、まっとうな1日では終わらない。試験当日の朝方まで教科書を読み、15分だけ仮眠を取って大学に行く。そんなこともしばしばだった。ベッドにうつ伏せになり、文字通りかぶりつくような姿勢で教科書を読んでいた身としては、「教科書を食べるほど勉強する」という表現はよく理解できる。
* * *
さて、「書く人の教科書」という副題のついた本書である。
コンセプトとして、「もしもぼく(注:著者)が『ライターの学校』をつくるとしたら、こんな教科書がほしい」を出発点としているそうだ。
この教科書も、ずいぶん分厚い。最後のページ番号は476。いわゆる六法系科目の教科書1冊とそう変わらない。さらに、232ページというほぼ真ん中に付録がついている。この付録の位置も、論の展開の中で最適な位置であることはもちろん、そのうえ本全体のほぼ真ん中という、できる限り読書体験を邪魔しない場所にあるのが素晴らしい。最初や最後に近い場所に本文より硬いものが挟まっていると、開いた状態で机に置いた時のすわりが悪い、というのは、語学の本などで経験したことのある人も多いと思う。
さらに、ごく薄いグレーに真っ黒の文字が配されたシンプルな装丁。表紙の紙質はしっとりとしていて、黒文字は箔押しで触覚も楽しい。暇さえあれば撫でていたくなるような本で、物質として既に優れている。所有の喜びを、十二分に満たしてくれる。そしてこの分厚さが、読了後の自分のアップグレードを大いに期待させてくれた。
はたして、この本はそんな期待に十分すぎるほど応えてくれた。私は本書の定義からしてライターではないし、ライターを目指しているかと言われてもまだ半分くらいしか頷けないが、取材・執筆・推敲によって良い文章=コンテンツを生み出すために踏むべきステップ、注意すべきポイント、持つべきマインドがよく理解できた。テクニックの紹介はほとんどないが、それは経験の中で身につけられるものだから、まずはライターの営みを体系化する、という点に振り切っているのは正しいと感じる。
さらに、多少抽象度を上げて読むことで、著者の言う「『書くこと』で世界を変えようとする」とまでいかなくても、言葉で自分や他人をほんの少しだけ変え続けている人、つまりほぼ全ての人にとって学ぶ価値のある本だと思う。
例えば、新商品の企画書を書くなら、業界の現状の情報を集めたり(取材)、開発したい商品の具体を詰めて説得力を持たせたり(執筆)、役員会に相応しい資料に仕上げたりする(推敲)だろう。仕事の外の日常生活をとっても、大事な人に大事なことを伝えるなら、相手について知っていることをフル活用し(取材)、時には伝える内容さえ変え(執筆)、伝え方をブラッシュアップして伝える状況まで考える(推敲)だろう。私の会社員としての仕事でいうなら、職務上入ってくる「情報をキャッチせず『ジャッジ』」し、利害関係者の「話を『評価』」せず、「課題の『共有』」をしたうえで「説得から納得」へと進化する必要があると感じたし、起案資料を「書き上げる」とはこういうことかもしれない、というヒントさえ得ることができた(この2文のかぎかっこ内は全て本文からの引用)。それに加えて、今一番興味のあるライターという職業について学べたのだから、心情的には3,000円+税は安すぎる。
総じて、私にとってこの本は良い本だった。この本との出会いに感謝し、たくさんの文章を書いていきたいと思った。そして、この先の私の人生に、かつての試験前のように、この本を食べるように再読しなければならない日が来るだろう、いや、来て欲しい、と思った。
ただ、漢字の開き方だけは、どうしても私の肌に合わない。ほぼ日刊イトイ新聞や、最近noteでバズる文章と似たものを感じる、あの開き方だ。なんとなく、過剰にイノセンスを演出してくる感じがして、どうにも苦手なのだ。まあ、私が10年も法律を学んでいて「時」と「とき」では意味が違う、などという世界にどっぷり浸かっていたせいかもしれないが……。
けれども、この漢字とひらがなの比率が、ものすごく読みやすいのは確かだ。私はものすごく遅読家なのだが、1時間で100ページほど読める本には久々に出会った。著者も文章の「視覚的リズム」という言葉を使って、漢字・ひらがな・カタカナのバランスに気を付けるべきだと語っている。「合う・合わない」と「すらすら読める・読めない」はこんなにも違うのだ、と初めて気付いた。こんな表層的なレベルでも学ぶことがあり、しかもそれを学ぼうという気にさせてくれる(第1章を読むだけで分かる)のだから、すごい本である。ごちそうさまでした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
