
読書のすすめ vol.295
ありきたりなタイトルですが、今日はあえてこのテーマで書いてみたいと思います。
正直、読書というと高校生の頃から大学生にかけては、ある程度の量は読んでいましたが、大人になってからはなかなか読む時間を取れていません。
そんな人も多いのではないでしょうか?
しかし、読書をすることには多くの利点があります。
本を読むことを勧められるのは多いけど、実際にどんなメリットがあるのかは聞く話は人それぞれです。
私なりの読書のすすめ、どうぞお読みください。
時間を作る感覚が生まれる

みなさんが本を読むタイミングはどんな時でしょうか?
時間があったら〜とよく言いますが、そう言った時間は大抵訪れることはありません。
時間は待っていてやってくるものではなく、自ら作るものですから。
時間があったら〜の時間は、幻の時間です。

タイムマネジメントでいうところの第2象限です。
読書は大事なものと分かりつつも、緊急ではない第2象限に属するので意識して時間を作らない限りはやってきません。
逆に意識して本を読む時間を生み出せる人の多くは、自分の時間を作ることに長けている場合が多いです。
時間を生み出すと言った感覚を自然と持ち合わせているのです。
ですから、読書をするというのは意図せず時間を生み出すスキルを手に入れていることと同義なのです。
鍛えられる想像力

これもまたよく聞く話で、読書をすると想像力が鍛えられると言います。
これは、メラビアンの法則という有名な法則に則って考えるとしっくりきます。
メラビアンの法則とは、人が言語情報を読み取る時には聴覚、視覚、思考で読み取るデータ量に違いがあるといった法則です。
人とコミュニケーションをとっていても、大体の場合、相手の表情やボディランゲージで言葉の意味を理解するのが55%、音のイントネーション、勢い、高さなどで意味を理解するのが38%、言語を言葉として理解しているのが7%といった法則です。
つまり、文字や言葉というのは、その文字自体が情報伝達として利用されるのはとても要素として低いものになっています。
これを考えると、本というものは普段7%程度しか伝わっていない文字だけを利用して、情景から感情、ストーリー全体を示しているわけです。
単純に数値だけではないにせよ、この93%の部分を想像力で補足していると考えると、どれだけ普段利用していない脳の部分を読書で使っているのかは、明白です。
人を味わえる

私が読書にハマったきっかけは、中学生の頃に東野圭吾の『魔球』という小説を読んでからです。
初めて小説らしい小説を読んだということもあり、読み終わった時には達成感がすごかったのを今でも覚えています。
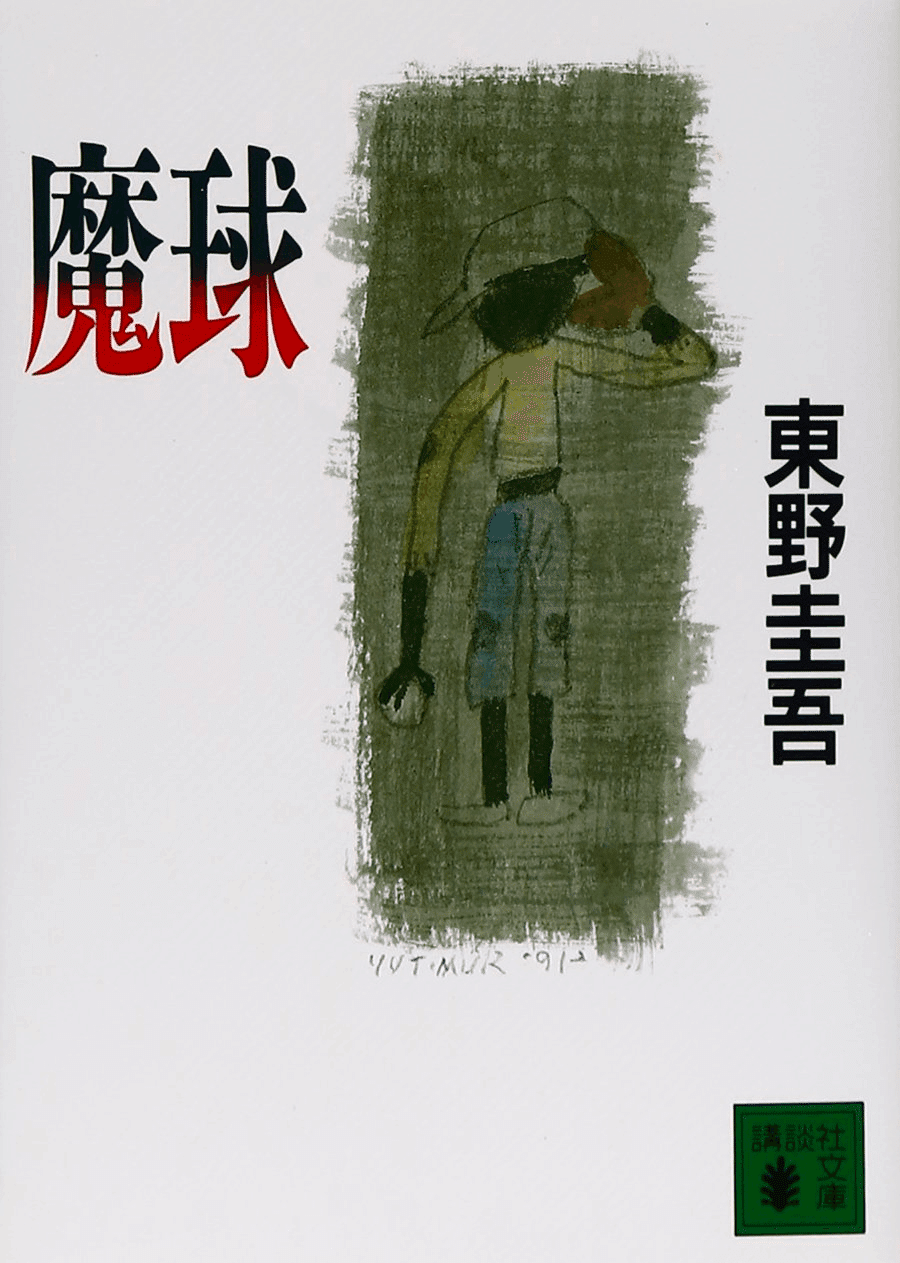
加えて、その物語の現実離れした衝撃に心がとても揺れ動きました。
あっという間に東野圭吾ファンになり、大学生までに出た東野圭吾の作品はほぼ全てを読みました。
おかげで実家には50〜70冊くらいひたすら東野圭吾の作品があります。
さぁ、そこまで東野圭吾作品を読み込むとどんなことが起きたのか。
私はあることがきっかけで東野圭吾作品を読まなくなってしまったのです。
それは、『疾風ロンド』を途中まで読み進めたところで起こりました。

まだ、全体の2/3ほどしか読み進めていなかったのですが、なぜか話の終わりが見えてしまったのです。
これまでの東野圭吾作品の終わり方から、自然と頭の中で終焉を描けるようになり、東野圭吾の描く作品イメージがわかるようになってしまったのでした。
それは、私が東野圭吾作品を楽しめる最後の瞬間であると同時に、私の思考の中に東野圭吾の思考が落ちた瞬間でもありました。
つまり、読書というものは極めていくと、その著者自身の思考が潜在意識に吸収され、言うなればその人の描く人生や思いを自分が手に入れることになるのです。
これが読書の究極形だなと感じます。
たった1度の人生の中で、さまざまな人の視点を持ててしまったら、とても思慮深い人になりませんか?
読書をすすめる最大の理由は、こういったところを通して、自分の人生が豊かになることにあります。
ぜひ、みなさんも読みやすいものからでも構わないので、まずは本を読む時間を作るというところから始めてみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
