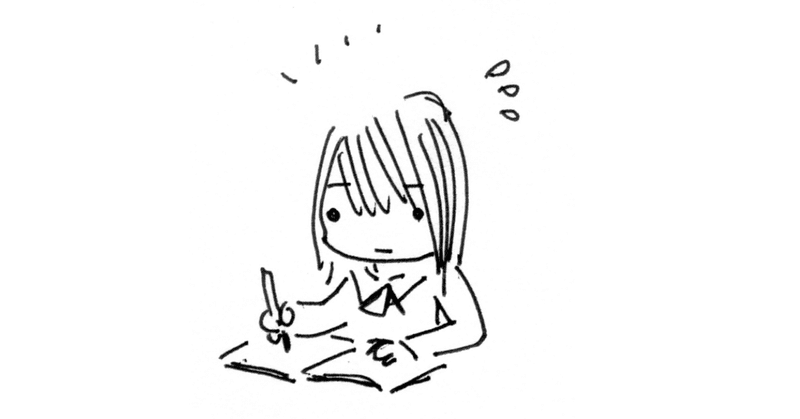
静岡県「公立高校入試」に向けて・・・英語のリスニング問題はメモをとらない方がいい?!(公立高校入試、英語リスニング問題対策)
こんにちは、富士宮教材開発(井出進学塾)です。
今回は、公立高校入試レベルの英語リスニング問題についての記事です。
当塾は静岡にあり、もう15年以上、入試問題や(それに準じる学調とよばれる県内テスト)を、くわしく分析してきました。
ですから以下の内容は、少なくても静岡県の公立高校入試においては、自信を持って、この通りだといえます。
また、塾の現場で、数多くの生徒さんたちの成長過程をみてきた上での内容でもあります。
静岡県以外の公立高校入試でも、同じ段階(中学3年生終了程度)のテストですし、同じく公(おおやけ)のテストで、練(ね)りに練られてつくられているはずなので、同じことが言えるでしょう。(まだ分析しきれていませんが、大学入学共通テストでも、おそらく同じことがいえると思います。)
結論を、先に言いましょう。
英語のリスニング問題で、「メモは・・・
・・・とらない方がいい」です。(本当は、「メモなんて、とるな」くらい、言いたいところですが、さすがに、それはやめておきます。)
以下、その理由について、解説していきます。
リスニング問題対策に必要なこと・・・
分析は、簡単です。
もし仮に、みなさんがリスニング問題で、大きく落としてしまったことがある・・・としましょう。
そのとき、どのようにダメだったのか?を、ふり返ってみましょう。
(これが、解決策を見出すための、必要な正しい分析だということは、わかりますね。)
よく聞かれるのが・・・
「速すぎて、ついていけなかった。」
「途中で、おいてかれちゃった・・・」
・・・などという声です。
(そもそも、ついていけなかったどころではなく、最初からちんぷんかんぷん・・・というレベルの生徒さんもいられると思いますが、それは、また別の問題なので、そのことについては、おいおい説明していきます。また逆に、しっかりついていける、というレベルの生徒さんについての話も、からめていきます。)
話を、もどしましょう。
リスニング問題で、途中でおいていかれる理由・・・
わりと、はっきりしています。
ほとんどの場合、途中でおいていかれてしまう理由は・・・
「日本語に直しながら、聞いているから」
・・・です。
ここで、リスニング問題に求められている能力について・・・認識を改めましょう。
リスニング問題で、求められる(得点力につながる)能力は、聞き取る力では、ありません。
英文を、英文のまま理解する能力です。
例えば、放送文で・・・
「Koji, what will you give Tomoko for her birthday?」
(参考:26年度静岡県公立高校入試過去問)
この文章を、頭の中で「コウジ、あなたはトモコの誕生日に、何を贈るつもりですか?」と、わざわざ日本語に直さなくても、・・・
この話し手は、コウジに、トモコの誕生日に何を贈るのか聞いているのだな・・・と、認識できないといけません。
「Koji, what will you give Tomoko for her birthday?」という文のまま、内容を理解するということです。
多くの生徒さんの場合、「日本語に直そう」とした時点から、放送文においていかれ始めます。
そこそこ、しっかり勉強している生徒さんで、リスニング問題が苦手という場合、・・・
「日本語に直しながら聞いちゃダメ。英語は英語のまま理解しようと意識しましょう。日本語に直そうとした瞬間、放送文においてかれるよ」
・・・というアドバイスだけで、飛躍的に得点力が上がることが、よくあります。
結局のところ、求められるのは英語の総合力なのです。
会話文で読まれる英文は、当然、長文問題などの英文よりやさしめの英文です。
ですので、ふだんから、しっかり勉強している生徒さんが、「英語を英語のまま理解」できないような英文は、読まれません。(あるかもしれませんが、その場合、正答に関わりがない部分・・・のように工夫されています)
ふだんから、しっかり勉強していれさえすれば、ほんの少しの心の持ち方のちがいで、リスニング問題でも確かな得点力を手に入れられます。
(「ドラゴン桜」という漫画でも、成績優秀な生徒に、無理矢理リスニング対策をやらせる必要はない、というエピソードがありました。まったく、合理的な話です。)
逆に、勉強量の少ない生徒さんに、「英語は英語のまま理解しろ」・・・と、いっても難しい話ですよね。
それこそ、総合力です。
現実的な話として、そういう生徒さんに関しては、リスニングがどうの、メモがどうの・・・ではなくて、総合的な英語の力の問題となります。
総合的な英語の力をのばさずに、リスニング問題だけできるようになろう・・・というのは、ムチャというか、ひどく効率の悪い話です。
厳しいことを言っているようですが、そんなことはなく・・・
これを読んでいるあなたが、今まで学校の授業をしっかり受けていて、学校の宿題なども、しっかり提出しているのならじゅうぶんに大丈夫です。
もし不安があれば、勉強量を、もっと増やせばいいだけです。
努力は、必ずむくわれます。
話を、本題(メモについて)にもどしましょう。
「英語を、英語のまま理解」しなければいけません。
よっぽど高い英語の力をもってでもいないかぎり・・・
かなり、意識して、集中して聞いている・・・必要があります。
「メモをとっているよゆうなど、ないはず」
・・・というのが、1つの大きな結論です。
メモなんて、とらなくてよいです。
その分、より集中して放送文を聞きましょう。
また、メモをとる、という操作は、「日本語に直す」という操作にもつながりやすいので、その点でもマイナスですね。
一方、「メモを、とっておかないと話を覚えておくのが、たいへんなのでは?」・・・という反論や疑問は、とうぜんあるかと思います。
しかし、少なくても静岡県の公立高校入試問題においては、メモしなければ答えられないような複雑な文は出てきません。
一例として、平成27年度のものをみてみます。(くどくなるので、少しだけにします。)
女性の声と男性の声の、2人の対話文というパターンが一般的です。(これはきっと、多くのところでそうでしょう。)
選択肢はア~エの4つで、それぞれ「絵(イラスト)」が与えられています。
今回は、女性の声が「由美」で、男性の声が「マーク」でした。
放送文(リスニング問題で読まれる英文)の内容を簡単に説明すると
1問目:マークの朝食は、ごはん、みそしる、卵で選択肢のエ、
由美の朝食は、パン、バナナ、牛乳で選択肢のウ、でも、今朝はねぼうしてパンをぬいたので、バナナと牛乳だけの選択肢イ
・・・これだけです。
メモをとるまでもない・・・というか、集中して聞きながら、指で、(マークはこれ)、(由美はこれ)、(でも今朝はこれ)、など考えながら選択肢をおさえていったりする方が、よっぽど効率がいいですよね。
2問目にいたっては、選択肢の絵がすべて女性なので、由美のことです。放送文で最初にマークが、自分が、あれした、これしたなど述べますが、これらは、すべて流せばいいです。
由美の行動だけ、順番に指で押さえるなどして、確認していけば十分わかります・・・というか、その方が、わかりやすいでしょうね。
以下、きりがないのでやめておきますが・・・
出題者側が、「メモをとることを求めてはいない」ことは、分析の結果から明らかです。(なお、弊社では静岡県公立高校入試について、毎年、英語だけでも最低35ページ以上の分析および解説を作成しています。)
・・・と、いうことですが、
「メモは、とらない方がいい」ような気がしてきたけど、まだまだ、そう言い切るのは怖い。もう少し、納得したい・・・という人も、いるかもしれません。
そういう方のために、もう少し補足しておきましょう。
「効率的なメモのとり方がある」という幻想
こういう仕事なので、本屋で参考書のコーナーを眺めみることが多いのですが、私が、もっとも残念だなと思うコンセプトは・・・
高校生向け英語の「速読(そくどく)」を、売りにしているものです。
どこが残念に思うかというと・・・
「じっくり時間をかけて意味をとれない人が、速く読んで意味がとれるわけがない」・・・と、いうことです。
もちろん、その本の筆者は、「すべてきっちりと日本語に変換しなくても、頭(文の最初)から順に意味をとっていく練習をしよう!」・・・という意図で「速読」という言葉を使っていると思います。
それ自体は、まったくいいことです。(今回テーマにしている、リスニング対策にもつながりますね。)
ただ、・・・私の偏見もだいぶ入りますが・・・
「模試で、長文の意味を全然とれなかったけど、何か、速く読める魔法のような方法があるのかもしれない」・・・という幻想を求めて、その本を選ぶ高校生の方が、少なくないように思えます。
ここまでは、言いすぎでしょうが・・・
「(これまでの模試の長文問題)
:時間が足りなくなる(ゆくり読んでいる) → 意味もとれない」
なので、この、それぞれの逆をとって・・・
「速く読む → 意味もとれる」
が「真(しん)」である・・・と、錯角しやすいですよね。
(これは、けっして責められることではないですね。そう思いたくなるのは、しかたないです。私も、高校生時代は、そういう弱さがありました。日々の勉強で試行錯誤を繰り返していけばいいです。)
しかし、先ほども述べましたが、「じっくり読んで意味がとれない人が、速く読んで意味をとれるわけがない」・・・というのが事実です。
魔法のような方法なんて、存在しません。
まずは、総合力をあげることが必要です。
それではじめて、それらの本に書かれている考え方も吸収できるようになります。
リスニングのメモについては、親御さんの方に、そういうところを感じます。(こんなこと言っていいのかな?とも、思いますが、大手塾の宣伝で「メモのとり方」などをアピールしているものも、みかけますしね、・・・まあ、いいでしょう。)
何か、リスニング問題で、「正しいメモのとり方が、あるのではないか?」「ちゃんと点がとれるようになる、魔法のようなメモのとり方があるのではないか?」・・・と、いうようなものです。
もっとも、・・・
「(うちの子は、リスニング問題で)
:メモをとっていない → 点もとれていない」
なので、この、それぞれの逆をとって・・・
「メモをとる → 点もとれる」
が「真(しん)」であると思うのは、先ほどの『速読』の例にくらべれば、理にかなっているようにみえます。
しかし、本質的には同じです。
点がとれない理由を、「メモ」に求めては、解決から遠ざかってしまいます。
あくまで、必要なのは、英語の総合力と集中力です。
「集中して聞く力」が求められているのに、そちらを軽視し、「メモ」にとらわれてしまうのは、やはり、うまくはいかないでしょう。
(なお、最近では、大手予備校の英語専門の先生でも、・・・
「メモは最低限に」や「メモは、とらなくてもいいよ」と主張する先生が増えてきたようです。そういう記事も、ここで紹介できればいいのですが、メモするのを忘れていました。また、みかけたら、改めて紹介します。)
もう少し、納得したい、という方のためにつづけましょう。
逆に成績上位層を含め、上のレベルの話をみていきます。
メモをとるのは、なかなかの能力
私などは、小さな会社でしか働いたことがないので、言いにくいところもあるのですが・・・
相手(この場合、上司や顧客)を、待たせたりせずにメモをとる・・・って、なかなかの能力です。
自分のペースで言われたことをのんびりメモをとっていたら、相手によぶんな時間を使わせることになりますからね。(みなさんも、これから先、大学などに進学してアルバイトなどすることもあると思いますが、こういうところも気をつけてくださいね。)
相手を待たせて、自分のペースでメモをとるなんて、あまりよくないことです。(もちろん、内容によっては、しっかりとメモをとらないといけない場面もありますが、そこらへんは正しい状況判断です。)
相手の話を集中して聞くのが第一です。
集中して聞いていれば、聞き逃してしまったことや、メモしておくべきだと思ったところで「もう一度、お願いします」と聞き直しても、相手に何の不快感も与えません。
(逆に、たらたらと自分のペースでメモをとりながら、何度も聞き返してくると、相手の人は、けっこう不快感をもってしまいますね。)
リスニング問題も、これに通じます。
受験生が、自分のペースでメモをとることを想定していません。
集中して聞くことが第一です。
多くの場合、放送文は2回読まれます。
集中して聞いていれば、1回目の放送で、聞き逃してしまったところや、大切なところを意識しながら2回目が聞けますので、大丈夫ですよね。
さらに、話はここから展開します。
メモをとるのが、上手な人って・・・いるんですよ。
これは、相手の話を聞くときの集中力だけでなく、どういう情報が重要なのかを見極めたりその要旨をとる能力、また事前の準備(どういう情報を想定したり、求めているかの確認)によるものです。
仕事ができる人・・・って、ことですね。
リスニング問題も同じです。
例えば、学校の先生や塾の先生でしたら、公立高校入試のリスニング問題を、英語を英語として意味をとらえながら、かつ、メモをとることもできます。
そうなのです。
十分な英語力があってはじめて、余裕ができてメモもとれるものなのです。
この記事を書き始めたとき、気になったのは、中学生・高校生のみなさんで・・・
「え~?メモをとったほうが、いいに決まってんじゃん。」・・・と思われる方が、けっこういるだろう・・・ということです。
こういう生徒さんは、英語の力があるってことです。
よゆうがあるので、メモもとれるということです。
そのレベルの方は、もちろん、メモをとったほうがより確実なので、メモをとったほうが、いいでしょう。
(ある種の英語検定テストでは、メモをとらないと、情報が複雑すぎてとても答えられないものも、あるそうです。そういうテストでは、そういうレベルが求められているということです。)
そうでなければ、集中して聞き、英語を英語のまま理解することに努めましょう。「よゆうがあったらメモ」・・・という姿勢が最善です。
中学1年のときの、最初の頃のテストのリスニング問題を思い出してみましょう。
例えば、「fish」の語が読まれたら、選択肢の中から「魚」の絵が描かれたものを選べばよいというレベルの問題が出題されました。
今、みなさんが、その当時の放送文を聞けば、よゆうをもって英語のまま理解できますし、メモもとろうと思えばとれるでしょう。
入試や学調は、公(おおやけ)の問題ですし、その内容・レベルなど精錬(せいれん)されつくした問題です。
高校入試なら高校入試で、中学3年修了相応の英語の総合力・・・リスニング問題では、それ相応レベルの英語を英語のまま理解する能力・・・が、問われます。
このことをふまえ、対策していきましょう。
リスニング対策として
以上みてきたように、リスニング対策というよりも、英語を英語のまま理解できるよう、英語の総合力を高めることが、何よりも大切です。
地道な勉強を、つみ重ねましょう。
勉強法について、1つだけ言っておきます。
「音読」を、重視しましょう。
もちろん、お使いの教科書の英文でいいです。
機会があるごとに、積極的に声に出して読んでみましょう。
人間科学的に、「聞き分けられるかどうかは、自分が言い分けられるかどうか」に、完全に一致するそうです。
これの延長で、聞きとれるかどうかも、自分がそのような内容を言えるかどうか、に関わってくるでしょう。
その意味で、リスニング対策としても「音読」は、ひじょうに有効な勉強法です。(これについては、また別の機会に別の記事でくわしくふれたいと思います。)
過去問に、挑戦してみるのもよいでしょう。
公立高校入試の過去問なら市販されていますし、リスニング問題の放送文も、ネット上で聞くことができます。
時間を決めて、何年分か、取り組んでみるとよいと思います。
その際、リスニング問題では、今回の記事で紹介したように、「英語を英語のまま理解する」ということを、意識してやってみましょう。
何年分か取り組むうちに、この「英語を英語のまま理解する」という感覚も、つかめてくるはずです。(基本的には、リスニングそのものの演習は、学校の授業や、定期テストで意識的にとりくめていれば十分、と考えています。でも、もう入試ですからね。)
リスニング問題特有の、対策やコツのようなものはないか?・・・と、いえば、・・・
・・・それは、それで、いくらでもあります。
例えば、私が以前に書いた記事を1つ紹介しましょう。(5年くらい前に、何かの販促用に書いたものですが、今回思い出して別媒体のブログにあげました。)
「むしろ、なぜ誰も教えてくれないのか不思議なくらいな 英語リスニング問題 本当のコツ (メモを取ることではありません)」
この記事では文法的な着目点をあげていますが、しかしそれも、長文問題や英作文問題にも、つながる内容です。
結局のところ、やはり、「英語の総合力」・・・ということになります。
また、最初の方で例としてみた静岡の過去問で、「選択肢がすべて女性の絵なので、男性の声で語られる自分(男性)の行動は、聞き流してよい」・・・というものが、ありました。
確かに、それぞれの問題ごとに、(一見はなやかにみえる)テクニックのようなものがありますし、そのようなテクニックを求めたい気持ちも、わかります。
しかし、これも長文問題で同じようなこと(・・・ここは読み流して大丈夫だな、と判断できること)がありますし、そういうことができていれば、自然とリスニング問題でも、できる事であります。
やはり、大切なのは、そのようなことができる「英語の総合力」です。
高校受験というのは、みなさんの人間としての経験値をあげられる、とてもよい、すてきな機会です。
よい経験(勉強)を、つみ重ねていきましょう。
以上です。ありがとうございました。
コメントなどいただけると、とてもうれしいです。
執筆:富士宮教材開発(井出進学塾) 代表 井出真歩
静岡県の公立高校入試 過去問解説教材は こちらのページで紹介しております。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
