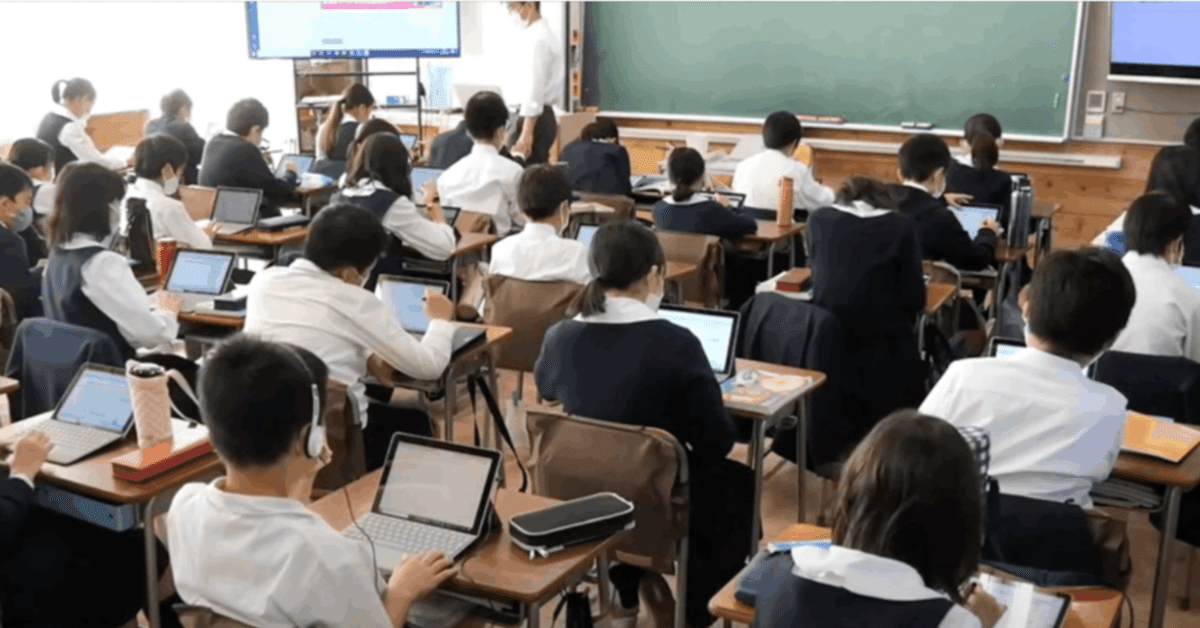
PDFじゃ意味がない
学習者用デジタル教科書をめぐって「PDF程度のものでいいから、まずは普及させることが大切だ」「各社勝手に作り込んで仕様がバラバラだからPDF程度のものに標準化すればいい」「学校のネットワークがまだまだ貧弱だからリッチなコンテンツがあって止まっては意味がない。PDF程度のもので十分だ。」といった声が聞こえてきます。
全て大間違いだと私は考えています。
何のための標準化?
学習者用デジタル教科書のビューワーの規格がバラバラで操作性が統一されていないのはその通りです。それをもって「だから教員にとって使いづらいものになっている。標準化しなければならない。」といった議論がありますが、そうでしょうか。
確かに学習者用デジタル教科書の操作性はビューワーによってかなり違います。確かに一瞬、それに戸惑うことは事実ですが、ではPDFみたいな学習者用デジタル教科書を作って標準化すればそれは解決されるのでしょうか。いいえ。事態はもっとひどいことになりかねません。
各社が実際の学習者用デジタル教科書のデモ版を公開していますから、それを操作しながら確かめてみてください。例えば東京書籍の小学校英語の教科書を見てみましょう。
ページの左上、タイトルのところにStarting Outと書いてあってヘッドフォンのアイコンがあります。ヘッドフォンのアイコンがあるのだから音が聞けるのだろうと思ってクリックすると、Starting Outというロゴとヘッドフォンのアイコンと説明が拡大表示されます。それだけです。
あ、そうか、その右にあるYouTubeの再生ボタンみたいなアイコンだな、と思ってクリックしてみると、今度は何も起こりません。え?もしや?と思ってその右のQRコードをクリックすると、ようやく音声を聞ける画面がポップアップします。
学習者用デジタル教科書が持つ操作性の問題点は、この「『常識的に考えて普通はこうなるだろう』という動きをしてくれない」ところにあります。世の中のどこのWEBサイトにこんなデザインのWEBサイトがあるんだよ、というような操作性だから戸惑うのです。操作性の標準化なんてする必要はありません。それぞれのビューワーが常識的な動きをしてくれればいいだけです。
逆に、先に例に上げたようなわけのわからない操作性が標準とされたPDFみたいな学習者用デジタル教科書になったら…誰が使いますか?
ネットワークが貧弱だからデジタル教科書はPDF程度でいい?
いやいやいや、志が低すぎるでしょう。お金がかかるのはわかりますよ。でも、それって問題の根本的な解決には繋がらないですよね? 私が危惧する最悪のシナリオ。
ひどいネットワーク環境の学校がまだまだ多い
→でも、それをどうにかするにはお金がかかりすぎる。
→じゃあ学習者用デジタル教科書はPDF程度の軽いものにして余計な機能は省こう。
→わーい、普及した普及した。
→あれ、こんなPDF程度のものじゃ使い物にならないや。
→やっぱり紙がいい!
まあ、こんなマンガみたいな話にはならないでしょうが、それにしたって。ネットワークがちゃんとしていなかったら、早晩、GIGAスクール構想なんて雲散霧消してしまうのは間違いないのですから、そっちを何とかすることにお金をかけましょうよ。
恥を晒すようですが、勤務校も先日、ネットワークのトラブルに見舞われて、数日間ネットワークが2Mbps程度になってしまったことがありました。デジタル教科書とか何とかってレベルじゃなかったです。これを解消しなかったら学校の教育が止まる、と冷や汗が出ました。
安定したネットワークの構築が急務なのはみんなわかっていることのはずです。そこから逃げて学習者用デジタル教科書を軽くする議論に進むのは到底納得がいきません。
結局、学習者用デジタル教科書なんてPDF程度でいいでしょう?
こんなこと滅多に書かないのですが、この問題については多少、頭に来ているので書きますよ。
「学習者用デジタル教科書なんてPDF程度でいい」とお考えなら、私が学習者用デジタル教科書を使って行った授業と同程度以上の教育効果を学習者用デジタル教科書無しで、或いはPDF程度の学習者用デジタル教科書を使ってどうやって達成するのか、教えていただきたいです。
どこの学級にも、学びに何らかの困難を抱えた児童はいるはずです。「読む」ことが難しい、「書く」ことが辛い、「話す」ことが苦手、「聞く」ことがどうしていいかわからない。そういった児童にとって、きちんとした機能を備えた学習者用デジタル教科書は、これ以上はない強い味方です。
「読む」ことに困難を抱えている児童が、読み上げ音声を聞きながら読んだから物語の世界に入ることができた。
「書く」ことに困難を抱えている児童が、本文抜き出し機能を使うことで「ノートに書く」作業から開放されて自分の考えをしっかりとまとめることができた。
学習者用デジタル教科書でしっかりまとめたものがあるから、それを映すことで自信を持って友達に自分の考えを「話す」ことができた。
聞く側も、学習者用デジタル教科書でまとめたものを見せながら話してくれるのでしっかりと「聞く」ことができた。
私の学習者用デジタル教科書を活用した実践はそんな場面のオンパレードです。これまで学びに困難を抱えていて授業でまったく活躍できなかった子が議論の中心になるようなことは何度もありました。
そして、そのもう一方で「特に『読む』ことに困難を抱えているわけではないけれど、読み上げ音声を聞いたら物語の別の魅力に気づくことが出来た」というように、学習者用デジタル教科書・教材がきちんとした機能を備えていることは、全ての児童の学びを広げる可能性があります。それも私の実践では何度も見られたことです。
学びに困難を抱えている児童も、そうでない児童も、みなが同じ土俵に乗って学び合うことができる。それがインクルーシブ教育の姿ではありませんか?
繰り返します。「学習者用デジタル教科書なんてPDF程度でいい」とお考えなら、私が学習者用デジタル教科書を使って行った授業と同程度以上の教育効果を学習者用デジタル教科書無しで、或いはPDF程度の学習者用デジタル教科書を使ってどうやって達成するのか、教えていただきたいです。
書きたいことを書きました。「学習者用デジタル教科書なんてPDF程度でいい」とお考えの方からのご意見をお待ちしています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
