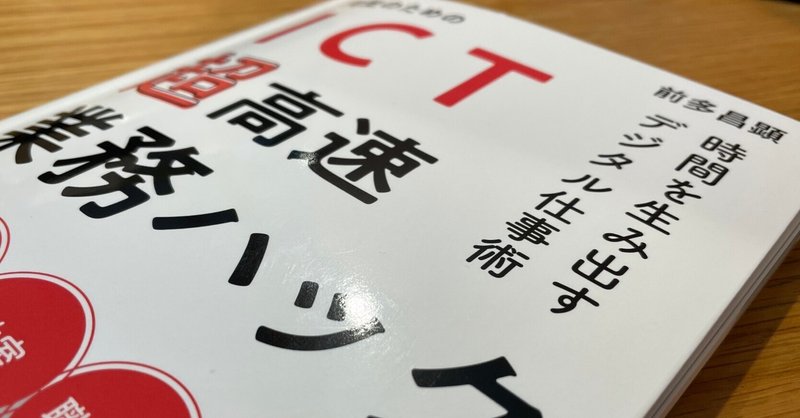
書評 先生のためのICT超高速業務ハック
やっと。やっと前多昌顕先生の新著について書く時間が取れます。
と言うか、書く時間はあったのです。でも、前多先生のこの本、パラパラっとページをめくってささっと書くのでは申し訳ないな、と思ったのですよね。だって業務改善で75事例ですよ!? これはさすがの前多先生でも苦労したのではないかな、と思ったので「だったら読む方も75事例全部とはいかなくても、興味をもったものは自分で試してからでないと書けないよな」と思ったのです。
で、どれを試そうかと目次を眺めていたのですが、もうそれだけで「凄いな」と思わざるを得ません。「なるほど、確かに業務改善の第一歩はショートカットだよな」「そうそう『Wordで文書のテンプレートを登録する』って役立つよ、俺もやってるよ」というように納得する、と言うか、正直「俺だって知っとるわい」というものもあります。
ですが、例えば「所見のネタデータベースを作る」などは考えたことがなかったです。自慢じゃありませんが、私は文章を書くことに関しては割と得意な方なので、所見を書くのって全然、苦じゃないんですよね。だから、「ネタデータベースを作ることによって楽をする」という発想がなかったのです。
しかし、これが落とし穴と言うか、私が前多先生を見習わなければならない部分なわけです。「おわりに」から引用しましょう。
私は、少しでも仕事を「楽」に進めるために、最大限の努力をしています。もしかしたら、私が短縮できた時間と、その準備に費やした時間を、合計して比較すると赤字になっているかもしれません。
しかし、私1人ではマイナスでも、私が紹介した方法を使って多くの先生方の仕事にかかる時間が短縮されたら、大幅な黒字決算です。
「俺、文章得意だからネタデータベースとかいらないし」と考えてしまう私との何たる圧倒的な人格の違い。まあ私と比べるのも申し訳ないわけですが。或いは、学校の先生でICTが得意な人の中には「僕、こんなこともできるの、すごいでしょ」というスタンスの御仁も正直いらっしゃるのですが、前多先生はもう格が違います。
「自分が獲得したスキルは人に伝えてナンボ」なわけです。「自分だけができても仕方がない。自分ができるようになったことを、どう他の人に伝えていくか」で勝負しています。だからこその書籍であり、YouTubeチャンネルなのでしょう。素晴らしすぎる。
で、実際の中身を見ていくと、なるほど確かに「これはもうやっているな」というものもありますし「これはそのままうちの環境では使えない」というものもあります。ですが、一つ一つ見ていくと、考える機会は得られますね。
例えば、私の学校はMSの365が基幹アプリになっているので、付箋ツールといったらまずはWhiteboardなわけです。ただ、あれって癖があるというか何というか、ちょっと使いづらい。前多先生はJamboardとCanvaを使った手法を紹介されていて、そのままWhiteboardにもってきても動きがモッサリするかもしれませんが、なるほど指導案を裏に置いて、という手法は面白いなと思うわけです。そこから、「じゃあ自分の環境ならどうするか」という考えるきっかけを得られるという意味でもこの本は非常に役立ちます。
私が一番ギョッとしたのは「歌唱指導用のカラオケを作る」でした。この事例、「歌唱指導用に大きな紙で歌詞の張り紙を作っていませんか」という問いかけで始まるのですが、心のなかで答えましたよ。「いや、作っていません」と。と言うか、「歌唱指導なんて『歌えるようになっとけよ』くらいしか言ったこと無いなぁ」というひどい教師なわけですが、そうか、こんなところにもICTをかませて、先生の負担を減らし、でも子どもたちにわかりやすい環境を作ろうとしているのだな、と感動しました。
ずいぶん前に、「ハモり方がわからない」という子どもたちのためにGarageBandで主旋律と副旋律を入れて、選んで聞けるようにして練習に使ったことがありましたが、なるほど、今歌唱指導しようと思ったら前多先生の手法の方が圧倒的に手軽で効果的です。唸らざるを得ません。
多分、この書籍に掲載されてりう75事例の全てがドンピシャであてはまって役に立つ、という人は少ないでしょう。でも、ドンピシャでなくてもそこからヒントを得られたりすることは多いでしょうし、考えるきっかけになるということもあるでしょう。自分で76事例目、77事例目を考えていくのも楽しそうです。
ということでめちゃくちゃオススメの書籍なわけですが、あとがきのあとをペラペラめくっていたら私の本の宣伝が出てきました。感涙。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
