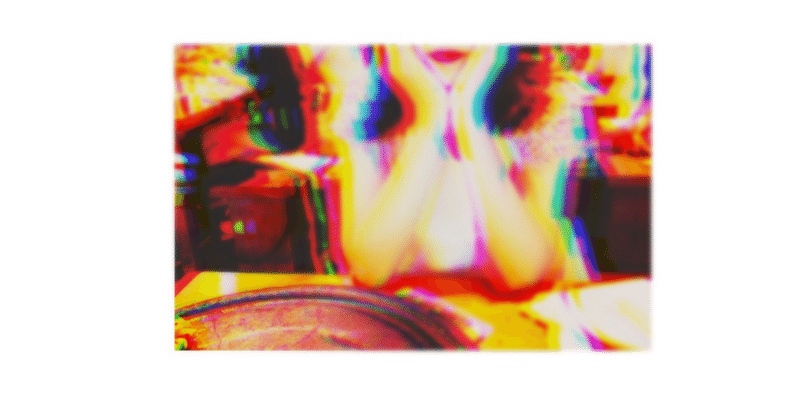
短編/あいまいもこ
まばたきするたび目が痛むと相談したくてこの場所をおとずれたはずなのに、いつのまにか別の症状を打ち明けている。
「動悸がして、息切れもします。それから注意散漫、食欲低下、不眠、なんの前触れもなく突然おとずれる………など、です」
わたしとしてはとても真面目にそれを相談しているのに、聞いている桜井先生はだめだった。彼女のことをちらりと見ると、あはは、からかいたい、と髪の生え際から人中窩、それからにやり、右の口じりに笑窪を出して、「それは突発性のあれかもしれない、うらやましい」なんて言う。
「もういいです、洗浄してください」
わたしは虫が死んだようにぐったりと診察台のうえに仰向けに寝転んだ。これ以上からかわれたくないという意思表示。すると先生はさらに毒を盛ろうと殺虫剤を片手に近づいてくる。わざとらしいほどさらに口元を窪ませながらわたしを見下ろす。ぽたり、ぽたりと眼球に薬を落とす。冷たい。しみる。きもちいい。のに、「まだごろごろする?」「はい、ごろごろします」「なんだろうね」ほんとになんだろうとわたしも思う。
紹介が遅れた。桜井先生は眼科医で、同じ病院で働いている。でもわたしは病院にいながら一日中患者さんの顔を見ない部署にいるから日常業務で接点はなくて、知り合ったのは学会に同行したとき。そのときはなんというか、柔らかい時計という感じだった。わかりそうでわからない。でもうまく説明できなくて、ほかに思い浮かぶとしたら揺らめく線虫、煌めく十年分のパフェの染み、君子の交わりは淡き水の如しが限界。
「かわいそうだから、おくすり、出しておくね」
くすくすしながら処方せんを書くふりをして、おだいじに、と桜井先生は言った。受け取った偽物の処方せんには、「縁」と書いてあった。
その夜わたしは、縁をなぞった。指で。
どうしてなのか曖昧だけど、最近、夜が苦手になった。夜は静かなもののはずが空は明るくて、無様に散りばめられた無慈悲な星々が「願いごとなんてしないでねっ」と赤くまたたきながら囁く声が聴こえてくるし、月は美しすぎて作り物みたいと思う。たとえば胸にあるふたを開けると銀色の電池があって、愛してるってだけおはなしできます満ちたり欠けたりいたします性能付きのお人形。ですがだれも触れることはできません……と淑やかに佇んでいるように見せかけて魔が本性、本物と偽物の境界を曖昧にするような…ううん、うそ月可愛い。裏側見てみたい。足跡つけたい。
吐息が洩れて、指から零れる。背中に甘い感覚が込み上げそうになるけどすぐに消えていく。
そして、かくかくしかじか云々かんぬんでした——というのはこどもの頃に味方だと思っていた言葉で、作文を書いてねと言われたら滅茶苦茶破茶滅茶に多用した。作文は苦手だったから叱られてばかりいて、日記もまともに書けたことがなくて…、となると自分のことを説明してほしくて図書室にいたのかもしれないと考えてみることがある。弾丸より速く廊下をゆっくり歩くという言葉の意味はまったくよくわからない。それなのにどうして宝物みたいに感じるのかなとか、この感情に名前をつけてほしいこの混乱を解いてほしい、あるいはさらに入り乱れて何が何やらわからなくなるほど混乱させてくれたらいいのに。…とか?
翌日、食堂にて。
「口腔外科の予約がとりたいの」
きょうのサラダはコーンサラダ。そして予約の交渉相手は歯科衛生士の鈴木はなちゃんで、彼女とは年齢がちかくて、ときどきお昼をいっしょに食べたり新食感あれこれの情報を交換する仲。
「どうして? 親不知?」
たずねられてわたしは首を振る。そのあとはなちゃんの前髪にコーンが付いていることに気づいて指摘する。と、これはヒトの脂肪だよと言って彼女は前髪を右手でぱっぱと払う。それから「とうもろこしと似ているのよね」と呟きながら落ちた脂肪を摘み上げる。てんとう虫を見つけたみたいに愛おしそうにそれを見るからわたしは不安になる。自分はなにかを勘違いして生きている?とかすかに、絵筆ですっとひとなでされたみたいな不安になって…なんだろうそれされたことないけど…、と脂肪のようなものを見ていると、「どうして?」ともう一度たずねられたから、「味覚異常がある」とこたえた。
「コロナ?」
「ううん、違うと思うけど…」と否定しながらわたしはフォークに脂肪を突き刺した。突き刺した脂肪を見せびらかしながら「これってすごく甘いよね?」とたずねてみる。はなちゃんは頷く。「どれくらい?」とわたしがつづけてたずねると、「ねえ大丈夫?」と眉をぎゅっとする。だからわたしは「大丈夫じゃないかもしれない…」とこたえた。それから昨日の眼科での診察のことや処方のことを話してみると、はなちゃんは口のなかでもぐもぐ噛み砕いていた脂肪を吹き出した。
「ひどい」
「ごめん、でも笑う」
「まじめに悩んでる」
「わかったもう笑わない」
と言いつつはなちゃんはくつくつ笑い続けて、「仕掛けは?」とたずねてくるから、その問いの意味をしばらく考えてからわたしは「探らないからわからない」とこたえた。ふーんと彼女はほくそ笑む。「もうやめて」「ごめんでもたとえば冬の朝とかさ、つま先のなかにあると思わない?」「なにが?」「え、心臓」わたしは無言。本物の脂肪にフォークを突き刺してもいいから否定したい衝動を抑えて無言。その一方で、「あ、こころ?」とつづけて彼女は笑いを止めない。奥歯まで見えそうになっていて、つまり彼女はなにか落ち込むことでもあったのだろうと思う。たとえばセックス中にうとうとねむってしまって彼氏から犯罪者並みの扱いをされたとか…、そうでもなければ他人の心臓のことをばかにしない。
わからないけど、夜、わたしは日記を書くことにした。とはいえ4た月ぬき日(嘘曜日)おてんき61番と書きはじめてしまったからはやくも心折れそうになっていて、でもつづける。証明したくて。こころは胸のなかにある。と思うのに、
〈彼女は滝の下に住んでいた。無数の水滴が太陽のひかりに反射しきらきらと輝いていて、彼女は思った。ここは明らかに取り憑かれている。〉
我ながらよくわからない。まずほんとうがないし、それに神さま視点の日記って? きもちわるい…、気味も悪いかも、とペンを真っ二つに破壊したい衝動に駆られそうになりながら、
〈どうやって滝に住むの?とたずねられて彼女はこたえる。滝ってね、冬は凍っているんだよ。〉
と書いてぅぁと震えた。だめ、むり、こんなに感情だだ漏れの読みものってないと目を覆いたくなった。あるいは潰してしまおうかと思って、でもやっぱりそれはこわくて出来ないから紙を破いてみようとする。破いてみたらきっと滝の文字から涙みたいに水がぽたぽたあふれて彼女は千切れて血飛沫がびしゃ…、ぐしゃ…ってなるって思って…、それは野蛮かも。紙を破るなんて野蛮な人間のすること、と正気…、とは言えないかもしれないけれども、〈太陽が山頂のうしろに滑り落ちていくにつれて部屋が溶けはじめ、つららで出来上がるまだらな影に身を潜めて彼女は背中を震わせていたと思われたがマシュマロ入りのグラノーラバーを楽しんでいる。〉やっぱりむりかもいやできる。もうあの頃の自分じゃない。とっとこハム太郎の飼い主になるだけのこと。でも人はそうそう変われない…、ううん、変われる。やる気の問題だよ魂に鞭を打てば大丈夫。でもあめがほしい。あめ求む。でもね…、と紆余曲折あって書き上げた日記はやっぱりうまくはいかなくて、たとえばそれは爪時計や楡の話で、木肌をぺたぺた触れたりすべすべ撫でてみるとてのひらがわずかに湿り…omg、真っ白に泡立ち騒ぐ滝壺から跳ね出されたあの魚、四(星°円…あ、ちがう...、xxx√えyyy..あ、だめ…み∧零ななな…、そして、かくかくしかじか云々かんぬんでした。と破綻した。
翌日、再び眼科。
「昨夜はほとんど眠れませんでした」
診察室の窓から降り注ぐあたたかい光のなかを出たり入ったりしながら、そわそわと歩き回るわたしに桜井先生は、「大丈夫、ただの恋です」といつもの調子で軽く言う。日記を破るべきか否かそれともいっそのこと燃やしてしまおうか、炒めようか、食べるっていうのもありかもしれない、いやないでしょう、とひとり騒ぎ立てていたことをわたしが話しても、問題ないと言う。
「ほんとうですか?」
「本当です。目がおかしくなったんじゃないかって診察にくる患者さんはわりといます」
「日記を食べる人も?」
「それは眼科にはいないけど、内科にはいるかもしれない、だから落ち着きなさい」
促されて、しかたなくわたしは診察台のうえに腰をおろした。途端に桜井先生はとある老女の話をはじめる。その老女は田中さんちのご主人の命日に毎年心臓発作を起こして病院に運ばれてくると言う。それがその田中さんっていうのは老女の家と隣同士で…という話をされてもわたしのこころはごろごろと揺れ動いて落ち着かない。むしろもっとごろごろ。とはいえこころがどこにあるのか不明。そんな人間のことは信用できないし、桜井先生の診断もまだ疑っているから「星は赤くないですよね」と何度も確かめる。桜井先生は笑窪を浮かべて「月に関していえば45億年も前からずっと美しい」と言う。何度も言わせるなと笑窪を消してちょっと本気で言う。それから口腔外科の予約も必要ない。鉛のような飯を食いましたみたいなことと言って机の上の本を傾ける。
「でも…」
とわたしは否定しかけた。けれどそのとき窓から小宇宙が羽をぱたぱたさせて飛んできて、赤い背中に黒い星を宿してくるくる回り込みながらわたしの膝に掴まった。くすぐったい。たぶんこれは…と羽を壊さないように摘み上げて凝視する。
電池に見えて愛おしい。
(了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
