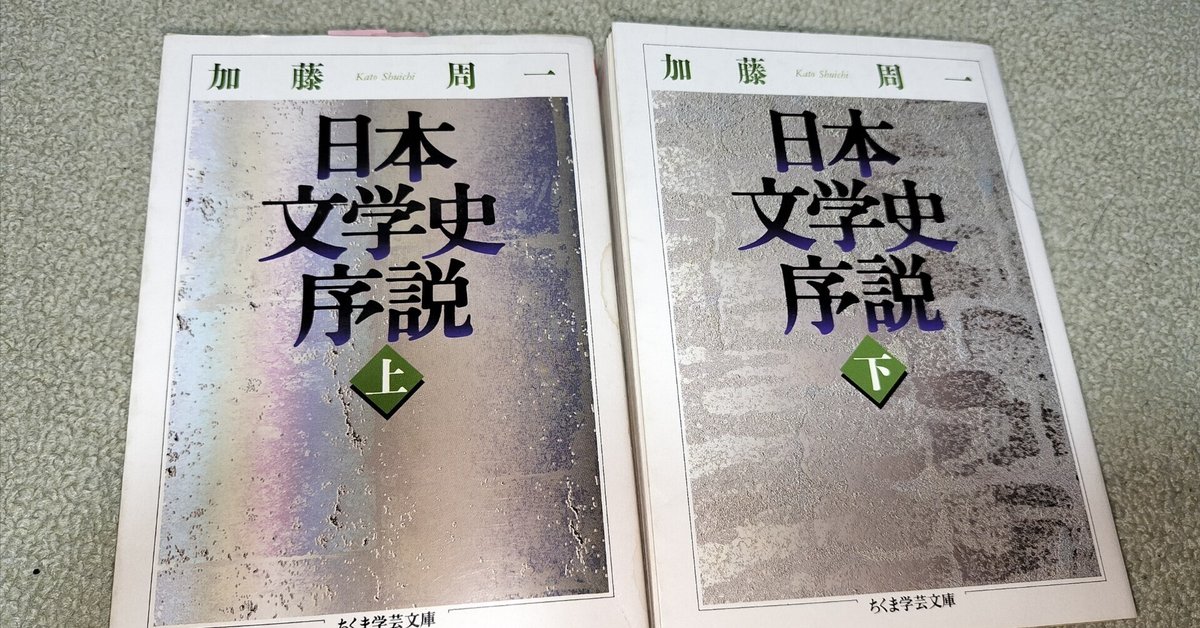
加藤周一『日本文学史序説』
日本人の心の奥底、固有の土着的世界観とはどのようなものか、それは、外部の思想的挑戦に対していかに反応し、そして変質していったのか。従来の狭い文学概念を離れ、小説や詩歌はもとより、思想・宗教・歴史・農民一揆の檄文にいたるまでを“文学”として視野に収め、壮大なスケールのもとに日本人の精神活動のダイナミズムをとらえた、卓抜な日本文化・思想史。いまや、英・仏・独・伊・韓・中・ルーマニアなどの各国語に翻訳され、日本研究のバイブルとなっている世界的名著。
上巻は、古事記・万葉の時代から、今昔物語・能・狂言を経て、江戸期の徂徠や俳諧まで。
下巻は、江戸期町人の文化から、国学・蘭学を経て、維新・明治・大正から現代まで。
文学史というよりは精神史・思想史的な本。文芸批評的なものを期待すると少しずれてしまうだろう。もっと大きな観点で、日本文化の歴史を描き出している。加藤周一の代表作という評価も当然の名著。
今回読み返してみて特に面白かったところを何点か書き留めておく。
日本文化に固有の出発点があるとして、しかし残された言葉(文学)は最古のものである万葉集や記紀にはすでに外国(主に中国大陸)の影響が深く影響している。第一章では、それらのテクスト(さらに風土記や)を丁寧に読み解いて、日本文化の固有の層を探ろうとする。この、テクストの読み方が何とも明晰で格好良い。知性というものの活動を目の当たりにできる、そんな批評になっている。
鎌倉新仏教の、日本社会の歴史に与えたインパクトの大きさを、その根拠を明らかにしつつ論じた第四章は、この長い本の白眉ではないだろうか。親鸞や日蓮の何処がすごかったのか。仏教の専門的な議論ではどうしても教義問答のようになってしまう議論を、より普遍的な論として展開する。読んでいてワクワクする楽しさ。これぞ歴史叙述の醍醐味。
明治以降を論じた十章、十一章は、費やされたページ数に比べて、時間軸は非常に短い。それだけ濃度の濃い批評となっているけれど、歴史叙述としてはほぼ動きがない。そのかわり、一人ひとりの文学者を丁寧に論じていて明治以降の文学ブックガイドとして非常に有用。
読み終えて改めて強く感じるのは、加藤の文章は本当に怜悧で明晰で張りがあって、最後までダレることなく読まされる。何よりその点がこの本の最大の魅力。優れた批評とはかくあるべしという理想形。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
