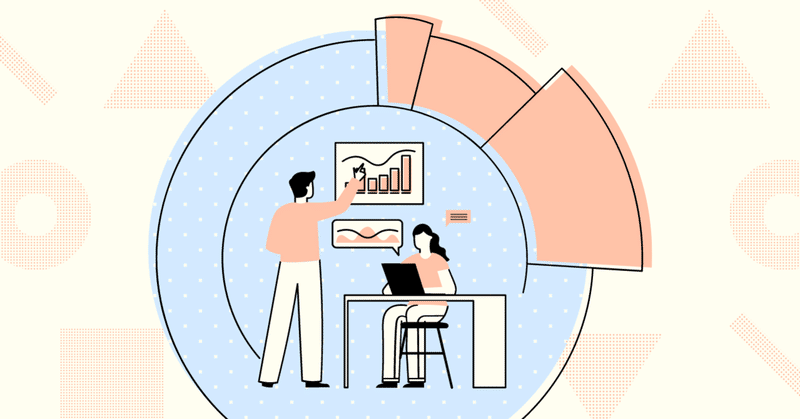
つみたてNISAの基本(日経WOMAN5月号より)
こんにちは。なごみ地蔵です☺
本日は、「投資を始めてみたい」と考えている方に向けての記事です。
日経WOMAN5月号の特別付録「老後のお金」丸わかりBOOKでも取り上げられている「つみたてNISA」について、以下の本の内容とあわせてご紹介します。
日経WOMAN5月号の概要
(画像は日経ウーマン公式ホームページより)

2021年4月7日(水)発売 特別定価730円(税込)
【特集】
「自分」が見つかる 仕事がはかどる
日記&ノートで
「私」が整う!
【特集2】
20代・30代・40代
収入が増えた人のヒミツ
【特集3】
通勤リュック女子&カタログ
【特集4】
みんなの「推し活」&リアルお金事情
【別冊付録】
「老後のお金」丸わかりBOOK
この記事では、別冊付録「老後のお金」丸わかりBOOKの内容を参考に、つみたてNISAについて取り上げます。
初心者向けのつみたてNISA
2014年にスタートした少額投資非課税制度(一般NISA)は、「非課税で運用できるのは最長で5年」という点が、投資初心者にとってハードルの高さを感じさせました。
そこで、運用期間が最長20年、毎年40万円まで、コツコツと積み立て続けることが可能な「つみたてNISA」が2018年にスタートしました。
5年間の投資で利益を出すことは難しいと感じていた方も、20年間あれば焦って売り急がず、長い目で投資に取り組むことができると思います。
つみたてNISAはメリットがある分、一般NISAと比べて非課税対象となる投資商品に制約があり、金融庁の厳しい指導のもと、消費者保護のための措置が施された投資信託に限定されています。
投資信託は、自分のお金をプロに託すという方法なため、比較的ハードルの低い投資方法と言えます。
*つみたてNISAの特徴*
【制度を利用できる人】
20歳以上の日本国内居住者等
【年間投資上限額】
40万円(一般NISAは120万円)
【購入方法】
積み立て(累積投資契約)のみ
(一般NISAは一時購入または積み立て)
【非課税対象】
長期の積み立て・分散投資に適した一定の投資商品
(一般NISAは上場株式・公募株式投資信託など)
【投資可能期間】
2037年まで(一般NISAは2023年まで)
【非課税期間】
投資した年から最長20年間
(一般NISAは投資した年から最長5年間)
【運用管理】
本人
【金融機関の変更】
できる
投資信託とは
ここでは、つみたてNISAの投資対象となる投資信託について見ていきます。
投資信託とは、みんなで出し合ったお金を集めて、それを「ファンドマネージャー」というプロが株式や債券などで運用する仕組みのことです。
一人で株式投資を始める場合、資金は自己資金のみ、情報収集から実際の売買の手続きまですべて自分で行うことになり、個人でできることには限界があります。
その点、みんなのお金を集めることで、数千万円、数億円という額になり、購入する株式の種類を増やしやすくなるため、そのうちの1社が倒産した場合のリスクを小さくすることができます。
一人では心細くても、たくさんの人が集まることによって、より頑丈な体制を整えることができ、このように規模が大きいことで強みが大きくなることをスケールメリットといいます。
投資信託の価格は、1万口あたりで表示される「基準価額」が用いられ、投資信託の運用によって利益が出ると基準価額が値上がりし、損をすると値下がりします。
投資信託の購入時に比べて基準価額が値上がりしたときに売却(解約)すれば利益が出て、値下がりしたときに売却すれば損をするという仕組みになります。
加えて、その投資信託の運用成績が良ければ、投資信託の資産の一部を「分配金」として受け取ることもできます。
一般的な投資信託と性質が異なるものの、つみたてNISAで利用することができる投資信託として、ETF(上場投資信託)とREIT(不動産投資信託)があります。
ETFとは、「投資信託内にある資産の価値によって決まる基準価額に沿って、購入・解約・買い取りなどの取引の請求を行う権利」を、証券取引所で購入・売却することができるというもので、一般的な投資信託と異なり「時価」で売買されます。
REITとは、「お金を出し合って1棟あるいは複数の物件を買い、それぞれが出したお金に応じて家賃収入を受け取る大家としての権利」を自由に売買できるというものです。
堅実な投資法
投資における基本の受け身
①積み立て
②分散投資
③長期投資
「儲かる商品を予想する」という意識を捨て、「時間を味方にして成長させる」という意識を持つことが大切です。
ライフプランに合わせて積み立てる
①積み立てたお金をどう使うか
②積み立て終了時に何歳になっているか
③お金を増やしたいという気持ちの強さはどのくらいか
投資信託の選び方
選び方その1「何に投資しているか」
①国内株式で運用する投資信託
【メリット】
・日経平均株価やTOPIXなどをベンチマークとし、その情報はニュースなどで簡単に手に入れられるので、その日の値動きがイメージしやすい。
・国内の景気との連動性が高いので、「なぜ値上がり(値下がり)したのか」が分かりやすい。
【デメリット】
・リスクが高い。
・外国の株式に比べると成長性に乏しい。
②外国株式で運用する投資信託
【メリット】
・国内株式よりも高い成長が期待できる。
【デメリット】
・国内株式よりもリスクが高い。
・国際情勢の影響を受けるので、値動きの要因を掴むのが難しくなる。
・為替相場の影響も受けやすい。
③新興国の株式で運用する投資信託
【メリット】
・潜在的な成長力が高い資産で運用できる。
【デメリット】
・先進国以上にリスクが高い。
・政情不安によるリスクも大きく、為替相場の変動も激しくなりやすい。
④国内の債券で運用する投資信託
【メリット】
・安定的な運用が期待できる。
・株式の値下がり時に値上がりしやすい傾向がある。
【デメリット】
・大きな利益を出すことは期待できない。
⑤外国の債券で運用する投資信託
【メリット】
・国内の債券よりも高いリターンが期待できる。
【デメリット】
・為替相場の影響を受けるので、その分だけリスクが高くなる。
⑥新興国の債券で運用する投資信託
【メリット】
・外国(先進国)の債券よりもさらに高いリターンが期待できる。
【デメリット】
・政府等の破綻によって、大きな損失を被るリスクが高い。
・為替相場の変動もより大きくなりやすい。
⑦REITで運用する投資信託
【メリット】
・国内の株式と似た値動きをしやすい中で、より高いリターンが期待できる。
【デメリット】
・国内の株式よりもややリスクが高くなりやすい。
選び方その2「運用方針」
パッシブ運用
・ベンチマークに連動する運用を目指すもの。
・比較的運用がシンプルで、信託報酬(=投資家が負担するコスト)も低い。
アクティブ運用
・ベンチマークを上回る運用を目指すもの。
・パッシブ運用よりもやや高いリターンが期待できる。
・運用結果がベンチマークを下回ることもあるので注意が必要。
・ファンドマネージャーが細かい銘柄分析を行う分、信託報酬が高くなる傾向がある。
・投資する銘柄の数が少なくなるため、パッシブ運用に比べてややリスクが高くなる。
「バランス型投資信託」を選ぶ際のチェックポイント
※複数の資産を組み合わせた投資信託
・資産に占める株式の割合
・新興国資産の有無
・REITの有無・割合
・自分の年齢で許容できるリスク
「ターゲットイヤー型投資信託」の選び方
※事前にある年を定め、その年が近づいてくるにつれて、組み入れ資産の比率を変更していく投資信託
①自分が生まれた年に近い西暦が示されているもの
②自分が60歳になる頃の西暦が示されているもの
最後に
「勉強しなくてもこれだけ分かればできる 5,000円から始めるつみたてNISA」の本の内容を中心に、今回はつみたてNISAの基本的な内容について記述してきましたが、いかがでしたか?
私自身、銀行員時代につみたてNISAの口座開設を勧める側の立場だったのにも関わらず、自分は未だに開設していないため、実際に始めるきっかけを作りたいと思い、今回こういった記事を出したという事情も実はあります。
今後も、つみたてNISAに限らず、他の制度の紹介・比較の記事なども書きたいと思っていますので、宜しければまた見に来ていただけると嬉しいです☺
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
「この記事を読んで良かったな」
「自分もつみたてNISAを始めてみようかな」
と少しでも思っていただけたら、
「スキ♡」やコメントをいただけると嬉しいです☺
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
