
モノが生きているとしたらデザインはどうあるべきか -物活論的デザインの倫理-
2015年にスクラップ装飾社のパンフレットのために書いた文章の原稿です(誤字脱字がそのままだと思う)。もう5年前。安藤さんに依頼を受けたのは嬉しかったです。
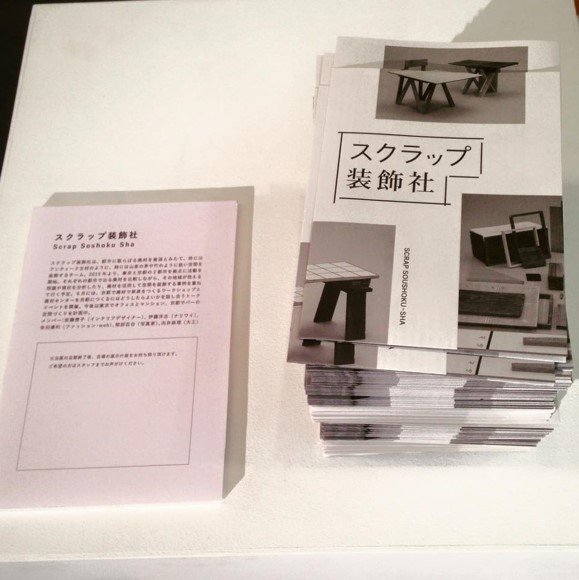
□バラックとスクラップ
今から92年前の関東大震災の直後、人々は瓦礫から廃材を拾い集めてバラックを立ち上げ生活を再開した。今和次郎たちにとってそれは、「因習からはなれた美しい建物」を実現する機会だった。彼らは「バラック装飾社」を結成してバラックの店舗やカフェを装飾して回った。
4年前の東日本大震災の後に建てられたのは、行政の提供するプレハブの仮設住宅である。人々が自力でバラックを建てることはあまりなかった。自力で建てる必要がなかったと言うべきかもしれない。しかし廃材のバラックとプレハブの仮設住宅は、この二つの震災の間の、人とモノとの関わりの変化を象徴しているように思える。震災において、普段は飼いならされたモノたち(大地、海、火、建物…)が人間にたいして歯向かってきた(奥村 2014)。関東大震災において人々は、歯向かってきたモノにたいしてバラックという直接的な応答を返すことができた。東日本大震災では、歯向ってきたモノへの対応は間接的であった。放射能に汚染された瓦礫の山は人を寄せ付けない。私たちは人が直接的に関わることが難しいモノたちを作り出してきた。90年の間に、人とモノはずっと疎遠になった。
おそらく私たちは、もう一度モノとの関わりを考え直す必要がある。そこで「物活論」という、今となっては少し奇妙な見方に立つことを提案する。それはモノが生きているという見方である。今日、新たに「スクラップ装飾社」が、現代における廃材を用いたモノづくりの可能性を探求している。ここにある什器の材料は都市から採取された廃材である。廃材はその個性を生かして即興によって組み立てられている。物活論の立場から、モノ作り、デザイン、あるいは廃材と装飾といったことに新しい光を投げかけたい。
□モノが生きているとしたら
現代においてモノは、人間にとっての道具でしかないものとして、目的についての手段でしかないものとして作られる。それが当たり前になっている。しかしそれが許されるのは、モノは死んでいると見るからである。
モノが生きているとしたらどうだろう?モノが心を持っているとしたら?モノが主体性を持っているとしたら?
こんなことを言うと、そのような仮定がそもそも空想的で無意味だと返されるかもしれない。しかし、モノが生き生きしていたり、死んだようであったりするのを、誰でも知っているだろう。そういった感覚的なクオリティーこそがモノを作るにあたって重要なのではないか?いやいや、生きていることと、生き生きしていることは異なる。客観的な事実と、主観的な感覚は異なる。そう言うかもしれない。たしかに私がこの文章を書くのは、部分的には主観的な理由からである。つまり、現在の私たちが作るモノたちが、あまりに死んだように感じられるからであり、あるいはまた「人間に虐待されている」ように感じられるからである。しかし、感覚的な世界と乖離した客観的な世界の中での合理性にどのような価値があるのだろうか?そもそも感覚的で主観的な世界と、実体的で客観的な世界という二元論はどれだけ妥当なのだろうか?
モノを死物として扱う世界観は「機械論(mechanism)」と呼ばれる。機械論は現代の標準的な世界観である。一方で、モノを生きていると見なす世界観が「物活論(hylozoism)」である。
本稿で私は以下のことを述べようと思う。機械論は、世界を「原因と結果」や「目的と手段」の論理的因果関係のみによって捉えようとする。しかし世界には論理的次元に還元できない、倫理的、美学的次元がある。そしてモノを作ることの倫理的、美学的次元においてはある種の物活論的な態度が示される。物活論を受け入れるなら、モノを作ること、デザインすることは何であるとみなされるべきだろうか?先走って言えば、この問いにたいしては次のように答えることになる。モノを作るとは、モノと人の対話であり、対話を通じた相互の学び合いである。そしてモノだけではなく私たちもまた、この対話によって作られているのである。
□機械論と物活論
物活論的は、動植物だけではなく無生物も含め、モノは生きているとする存在論的な立場である (注1)。物活論は、人類に共通して見られる太古からの基本的な世界観において一般的である。その原初的な形は、あらゆる存在に魂が宿るという「アニミスム(animism)」の宗教である(注2) 。古代ギリシャの初期の哲学は「自然哲学」と呼ばれているが、ここでも物活論的な見方が優勢であった (注3)。その後も、物活論的世界観は中世までは標準的な見方であった。
デカルトやホッブズによってモノを死物としてみる機械論的な世界観が示され、近代以降はそれが標準的な世界観として台頭した。物活論が無生物を生物の原理で説明しようとするのにたいして、機械論は生物を無生物の原理で説明しようとする。機械論的世界観の影響の下で、作ることの目的は人間の欲望を満たすことであり、モノは手段としてその目的に仕えるとされてきた。つまり人間中心主義である。
現在でも物活論は非科学的だと思われているし、哲学においても主流とは言えない。しかし物活論は近代以降も連綿と生き残ってきた。C. S. パース(Charles Sanders Peirce) や(注4)、A. N. ホワイトヘッド(Alfred North Whitehead)(注5) は20世紀初頭に物活論的な世界観を唱えている。ブルーノ・ラトゥール(Bruno Latour)は科学者の実践についての研究において、モノにも主体性を与え人と対称的に扱うアクター・ネットワーク理論(actor network theory)を生み出した(ラトゥール 1999)。また現在では「思弁的実在論(speculative realism)」という新しい哲学の潮流の一部で物活論的な見方が主張されている(Shaviro 2014)(注6) 。また近年になって人類学において数々の物活論的な制作観が提唱されてきている (注7)。
建築家のクリストファー・アレグザンダー(Christopher Alexander)は、現代建築の醜悪さが機械論的世界観に由来するとして、ホワイトヘッドの影響を受けた物活論的建築論を提示している。アレグザンダーはモノの持つ生命あるいは質的な価値に客観性を認める。つまり建築が生き生きとしているか否かは主観的な判断に依存するのではなく、モノの構成や配置がもたらす客観的な事実だとする(Alexander 2003a; 2003b)。本稿が示す物活論的な制作論はアレグザンダーの哲学に負うところが多い。
このように、物活論世界観が再評価され始めたのではあるが、一方でまた機械論的な世界観も、完全に退けることができるようには思えない。たしかにアレグザンダーが指摘するように機械論的な世界観の全面的な支配が、現代社会が生み出すモノから生命を奪っているように思える。しかし、モノを機械的な因果関係で捉える見方そのものは排除することができないだろう。アレグザンダーは二つの見方を相容れないものとして対立させているように思えるが、これは二者択一の問題ではないだろう。問題は、現在ではこの二つの世界観が乖離して、その間のあるべき関係が不明だということである。このために機械論が不当に幅を利かせるのである。つまり、一般的な立場からは、機械論が科学的で客観的な見方とされ、物活論は日常生活においてリアリティを持つとしても主観的な見方に過ぎないとみなされる。そのため前者のみが公的な議論で参照され、後者は私的な領域に閉じ込められている。
私は、C. S. パースの哲学の再解釈に沿って、デザインとは何かを考えてきた(山口 2014)。そこではデザインとは単なる問題解決というより、「習慣(habit)」の進化としての「探求(inquiry)」であると論じた。何が問題で何が解決であるかは習慣に依拠しているが、その習慣じたいの変化がデザインにおいて重要なのである。そして探求に三つの次元、すなわち、論理的次元、倫理的次元、美学的次元があり、論理的次元は倫理的次元に依拠し倫理的次元は美学的次元に依拠するとろ論じた。以下ではその枠組を用いて、機械論的な世界観と物活論的な世界観を架橋することを試みている。ただし厳密な議論よりもビジョンを提示することを目的としている。
□作ることとデザインすること、その常識的な見方
モノを作るとはどういうことか、現代の常識的な見方は、以下のようになるだろう。モノを作るとは「材料」に「形」を与えることである。モノの形は、たとえば作る人の頭の中に、アイデアとして、前もって存在している。だからモノを作るとは人間のアイデアの具体化である。
現代におけるデザインについての常識的な見方は、作ることについての上記の見方に基づいている。つまりデザインとは「実際にモノを作る前に、作られるべきモノの形を作ること」である。モノが作られる過程は二段階に分離される。作られるべきモノの形を表す記号(設計図や模型や3Dデータ)を作る「デザイン」の段階(これもまたアイデアの具体化として見なされるだろう)と、設計図をもとに実際にモノを作る「製造」の段階である(注8)。
さらに言えばモノを作ること、デザインすることに関する上記の常識的な見方は、事実の記述であるだけではなく、規範として受け入れられている。つまり、モノの個体性や状況の単一性から切り離された明確で一般的なアイデアがあるほど良いと考えられている。そしてアイデアをなるべく純粋に具体化するほど良いデザインだと、あるいは良い作品だと考えられている。
□作ることの論理的次元
モノは道具として作られる。道具は目的のための手段である。あるいは問題についての解決である。技術とは目的と手段の関係によって世界を捉えることである(ハイデッガー 2000)。技術における手段と目的(問題と解決)の関係は、科学における仮説と事実と似たような論理的関係である(注9) 。科学が原因と結果の連関として世界を論理的に理解しようとするように、技術は目的と手段の連関として世界を論理的に構成しようとする。説明の付かなかった現象が新しい仮説によって解決されるように、社会問題がデザインによって解決される。それによって物事は論理的な関係の網の目の中に組み込まれて行く。作ることの論理的次元はこの論理的な関係性の網の目の再編と拡張である。
先ほど述べたようにモノを作ることは形の具体化として、アイデアの具体化として見なされる。そのように見なすことが、モノを目的と手段の関係に位置づけるための前提となる。どういうことかというと、形やアイデアは一般的である。つまり同じ形、同じアイデアから多くの個物を、その一事例として作ることができる。そして、一般的なもの、あるいは一般的なものの事例のみが、手段であり、解決でありうる。というのも、一般化できないモノには法則を適用することができないから (注10)。
このように、モノのデザインを目的と手段の連関の中で捉えることもまた、一つの規範として受け入れられている。「機能主義」とはそのような規範である。デザインは明確な目的と手段の連関として組織化されてなくてはならない。デザインの各部分は明確な目的(機能)をもって互いに組織化されている。何のためにあるのか分からない「装飾」は排除される。
しかしデザインは単なる問題解決として、目的と手段の連関の中でのみ理解することはできない。たとえば、デザインにおいて問題は所与ではなく、解決を与える中で明らかになる (注11)。ドナルド・ショーン(Donald Schön)は、この問題と解決が相互依存しながら進展する過程のなかで、建築家の描くスケッチといったモノが演ずる役割に注目して、設計とは「状況の素材との対話」であると述べた。設計者の行為にたいして状況の素材(たとえばスケッチなどのモノ)は意図せぬ「応答(back talk)」を返す。設計者はその応答を聞き取って、状況の認識を改め、また新たなの行為を返す(Schön 1983)。このように意図せぬモノ、つまり目的と手段の連関から逸脱するモノ、「他者」が決定的な役割を果たし、設計者はモノとの対話を通じてデザインの意図を更新していくのである。
□作ることの倫理的次元
たしかにモノは一般的な形やアイデアの一事例として、道具として位置づけられる。しかしモノは一般化できない一面を持つ。「ソレ」としか呼びようのない個物の「単一性」である。モノをあくまで個物として扱い、その単一性を際立たせようとするのが、「装飾」である(山崎 2007)。装飾はモノを単なる道具ではない何か、目的のための手段であるのみではない何かとして印そうとする。装飾においてはモノにたいする物活論的な態度が示される。
もちろん、装飾されたものが同時に手段となる場合もある。ここで言いたいのは、作ることにおける、モノに対するアプローチの二つの面である。技術はモノを目的についての手段として扱う。モノをコントロールし、支配する。ここでモノは他の同等の手段と交換可能、同じ形を持つ別のモノと交換可能である。一方、装飾はモノをあくまで交換不可能な個物として扱う。人間の目的と無関係にそれじたいとして価値があるものとして扱う。道具としてのモノは何か他のことのために存在するが、装飾としてのモノは、自らのために存在し、自らを楽しんでいる。
モノを、それじたいとして価値があるものとして受け入れること。その単一性や他者性を受け入れること。これはモノについての倫理的な態度の話である。モノは一般化されて初めて論理に組み込まれる。この一般化の妥当性が倫理的次元で問われる「誠実性
(veracity)」である。誠実性は、このときモノを一般的なタイプに属する一例に過ぎないものとしては見なさないということを含む。つまりそれは、モノについて自分が持っているイメージ(その中でモノは一般的なタイプの一例である)だけを見るのではなく、むしろそのようなイメージから逸脱するモノと直接向き合うということである 。
物活論を採用するばあいには、モノが何になりたいのかを問う必要が出てくる。じつはこれは優れた建築家たちがいつも問うてきた問いなのかもしれない。特に場所が何でありたいのか、それを決めるのは「ゲニウス・ロキ(genius loci)」すなわち「場所の霊」である(ノルベルグ=シュルツ 1994)(注13) 。
物活論的なデザインは、ショーンのいうモノとの「対話」というメタファーを文字通り受け取る。安冨によれば、対話とは「お互いが、相手のメッセージを受け取るたびに自分自身の認識を改める用意がある」こと、つまり「学習」を前提とする。相手についての像を勝手に作って固定化し押しつけ、それ沿わない相手の対応を否定することは、対話と学習の過程を停止させる「ハラスメント」である(安冨 2008)。このように考えるならば、一方的にモノに形を押し付けようとする機会論的なモノづくりは常にモノへの「ハラスメント」なのである(注14) 。
モノとの対話の媒体は人間の言語ではない。モノの非言語的応答を聞き取る能力が設計者には求められる。これは次に述べる美学の課題である。
□作ることの美学的次元
モノは一般的なタイプに属する一例として見なされて初めて、道具として目的と手段の論理的な関係に入る。その際に、モノを一般的なタイプに属する一例に過ぎないものとしては見なさないという「誠実性」が、モノに対する倫理であった。そこでモノをデザインすることはモノとの対話として見なされた。では美学とは何かというと、それは必ずしも所謂「美」に関わるものではない。美学は感性についての学であり、私たちとモノの世界における感じ方、あるいは「表現性(expressiveness)」についての探求である。モノを対象化する以前の主客未分の状態において、感じ方が探求される。私たちの感じ方の限界が、モノとの対話において、モノの応答を聞き取る可能性の限界となっている。何らかの仕方でその存在を感じることのできない事にたいして誠実であることはできない。特にモノを作るときに重要なのは対象が不確定で曖昧な理想である。なんらかの理想が感じられるのではなくては、そもそも問題は存在しない。理想に対する現実の反作用が、取り組むべき問題を与えるからである。
インゴルドはモノを作るとは「世界の肌理を見つけだし、その展開をなぞる」ことだと言う(インゴルド 2011)。それはモノを作ることにおけるこうした感覚的な次元であり、暗黙知(tact knowing)の次元である(ポランニー 2003)。モノの肌理を見つけるには、モノに住み込み、モノと一体化する必要がある。美学的次元におけるモノとの対話では、モノと私の区別が曖昧になり互いの声は溶け合う。
□廃材
以上をまとめると、モノを作ったりデザインしたりすることには、モノを技術的に扱う論理的次元の他に、モノを交換不可能な個物として捉える倫理的次元と、モノと一体化する美学的次元がある。機械論は論理的次元のみを考慮するのにたいして、物活論においては倫理的、美学的次元が考慮される。このことは、デザインの実践について、どのような具体的な含意を持つのだろうか?
一つは、材料の扱い方である。材料の規格化は機械論的世界観に基づいている。それじたいは多様である自然素材に形を押し付けることで、規格化された材料が作られている。現代の消費者が購入する工業製品のほとんどは規格化された材料から作られている。規格化されているので材料は交換可能である。この規格化にとって交換不可能な素材の個性は、排除すべきバラツキである。規格化によって材料を十把一絡げにコントロールすることが可能になる。こうした規格化が、「モノが虐待されている」という感じの源泉にあるのかもしれない。
物活論的デザインにおいては材料の個性の多様性を進んで受け入れる。それぞれの材料にそれぞれ対応すべきだろう。このとき多様性にとんだ、生き生きとした材料として、「廃材」が見いだされる。廃材とは使われなくなったモノ、目的と手段の関係から排除されたモノである。廃材はもちろん規格に従わないため、機械論的には嫌われてきた。しかし廃材の持つ形の多様性、歴史(物語)の多様性、時間の与える質感といったものは、物活論的デザインにおいては中心的なテーマになりうる。物活論的デザインは、モノとの対話のなかで、モノのもつ、多様性、歴史、個性を調和させることである。
□リノベーション
人は生命を無からは生み出せないように、モノを無から作ることもできない。モノを作るとは、すでにあるモノを育てていくことである。たとえば新築で住居を建てる場合ですら、その住居を単体で考えるのではなく、住居を含む「近隣」や「まち」をどう育てることができるかを問うべきである。しかし既にある建築を改修するリノベーションにおいては、既存のモノとの連続性がより明らかに意識されるだろう。つまり、既存の建築をいかに育てるかということがリノベーションにとっては主要な関心事になる。
育てることは、継続的な関わりを要する。作って完成した後は維持するのみというのは、機械論的な見方である。物活論的な見方からすれば、モノに完成は無く、常に成長の途上にある。育てるとは育てる側の抱く完成形を作られる側に強いることではない。「生命の根源的な自発性の発露に則らなければ、そもそも学習が成立しない」と言われている(河野2013)。人が成長するのは、強いられて何かをするのではなく、自分の価値基準に沿って自発的に行うときだけである。同様にモノの自発性の発露に則らなくては、モノを育てることはできない。
□モノとの対話としての「つかう」こと
モノは作られて完成ではなく、使うことを通じて成長していく。使うこともまたモノとの対話として見なすべきである。モノの奥深くにまで使う人が「関わる」ことができることが重要である。修理できること、改良できること、あるいは使う側のスキルに応答することなどである。最近の製品が使う人の関わりを拒むものであることは残念なことだ。車やバイクや電子機器はだんだんと、使う側にスキルを要求せずに簡単に使えるようになる一方で、素人が修理できないものになってきている。モノとの対話においては、予期せぬ関わりを受け入れて認識を改めることが必須である。プログラム通り、マニュアル通りの対応を取ることは対話をもたらさない。このことが人とモノの両方に求められるのであり、人はモノをそのような包容力をもったものへと育てていくべきである。
□DIYと即興
物活論的デザインのためには、デザインするプロセスや作るプロセスのあり方、そして組織形態はどうあるべきだろうか?
機械論においては作ることはデザインの具体化であった。その場合デザインはすでに決定されており、あとはそれをモノに押し付けるだけなのである。物活論的においてこうした一方通行は許されない。モノに命令するのみでモノの応答を聞き取らないのは誠実ではない。作る人がモノの応答を聞き取り、これを次の行為に反映させるにはどうしたらよいだろう?つまりフィードバックのループを生み出すためにはどうしたらよいだろう?そのためには作る人がデザインするのが好ましい。DIYのように使う人がデザインして作るのであれば、よりモノからのフィードバックは密度の高いものになり、モノとのより親密な対話が可能になるだろう。
しかし大きなモノを一人で作るのは難しい。ある程度は、全体をデザインする人にたいして多くの作る人が従う、ということは仕方が無いかもしれない。しかしその場合ですら作る人が自己裁量でデザインすることを大幅に許すべきであろう。そのために混乱が生じることは無いだろうか?そこでデザインをジャズの譜面のようなモノとして見よう。ジャズではコード進行や基本的なメロディは決まっていても、あとはインプロビゼーション(即興、improvisation)によって、その場に応じて演奏する。インプロビゼーションとは前もって見えないとことである。設計者は大まかなデザインを与えるだろう。しかしそのデザインは作るひとの自由な解釈を許すものである。詳細な形は前もって見えず、モノとの対話の中で、作り手の即興で生じて行く。
作り手たちの組織形態については深く考えるべきであろう。モノを一般的なタイプに属する交換可能な一例のみとしてしか扱えないことと、人を一般的なタイプに属する交換可能な一例のみとしてしか扱えないことは相関している。社会と精神には相互依存的な関係がある。おそらく生産/消費、労働/余暇といった機械論に基づく二元論的な見方を捨てなくてはならない。物活論的モノづくりはこうした二元論では捉えられない。この意味でワークショップ形式によるモノづくりの可能性が注視される。
□楽しさと作ることの自己目的的性質
モノを作ることやデザインするプロセスを、そのモノによって実現する事態についての手段のみとして見なすことは、それじたい、機械論的な見方である。モノを作るとき、しばしば夢中になって我を忘れる。そういうときが一番楽しい。そのことは作ることにおいて些細なオマケではない。作ることにおいて最も重要なことである。モノを作ったりデザインしたりすることは、労働ではなく楽しみでありえ、したがって、それ自体が目的となりうる。ワークショップにお金を払って労働しにくる参加者がいるのは、それが楽しいからであろう。ミハイ・チクセントミハイ(Mihaly Csikszentmihalyi)は夢中になって楽しむような状態を「フロー(flow)」と呼んでいる(チクセントミハイ 1990)。フローの条件としてチクセントミハイはフィードバックの存在を指摘する。つまりモノとの対話である。単に労働を、単なる命令の実行として見るなら、そこにはモノと対話する余裕もない。作る人が自発的に行うこと、自分の価値判断に従うことが大切になる。
□物活論の課題
物活論を受け入れたらデザインはどうあるべきかを考えてきた。デザインはモノとの対話として見なされる。しかしデザインをモノとの対話として見るとき、デザインと作ることと使うことは切り離すべきではない。デザインの中だけでなく、作る中で、あるいは使う中で、モノの形は成長する。そして、モノとの対話とは人とモノの双方の学び合いであり、人の精神や人の抱く目的もこの対話の中で成長する。
このように考えると「スクラップ装飾社」による廃材と装飾に注目した活動は、物活論的なモノづくりの探求として見ることができる。ここで設計者は作り手でもあり、対話と即興を通して、廃材を装飾に変えている。廃材とは、目的と手段の関係から排除されたモノである。装飾とは、目的と手段の関係を離れて、自らの生命を楽しむモノである。
最後に物活論の問題について考える。おそらく、問題だらけである。たとえば、物活論的なデザインにおいて、作られるものがどうなるのかは、作る前には分からない。このことは必須である。しかしそんなことを設計者がクライアントに言うとしたら、無責任ではないだろうか?しかし責任(responsibility)とは「応答可能性」であり、対話にたいして開かれていることである。この意味で責任を理解すれば、作る前に形を固定して何があっても変えないというほうが無責任なのである。
また、物活論は神秘主義と重なっている。モノの感じていることを、モノは人間の言語で説明してはくれない。モノの感じていることを信じ込むことは迷信につながりうる。現代でも人間は物神崇拝をやめてはいないが、近代の機械論によって、いくらか迷信から自由になったのかもしれない。物活論が非理性的な「空気」の支配に結びつかないとも限らない。「空気を読む」というときの「空気」である。山本は第二次世界大戦の日本の敗因の一つを「空気」に流され易い体質に求め、また「空気」を生み出す原因を、彼が「臨在感的把握」と呼ぶアニミスム的感覚に求めた(山本 1983)。さらに言えば、プラトンが、世界を生成するものとして見るそれまでの物活論的な自然哲学に反して、世界を意図的に「つくられた」ものとして見る存在論を示したのは、当時衰亡しつつあったアテナイの「成り行きまかせ」的な政治状況にたいする批判でもあった(木田2000)。
たしかに、即興でモノを作るとは、その場の「空気」に流されて成り行きまかせにするということになりかねないようにも思える。このことはしかし、機械論の優位を示すものではない。「空気」の支配はある種の感性によっている。これに抗うのは理性だと山本は言う。しかし空気に逆らって思考するのもまた、別の感性を要するのであり、理性のみが「空気」の支配からの脱却を可能にするのではない。むしろ論理上は「空気」の支配はいかようにも正当化できるだろう。この規則に機械的に従えばあらゆる破滅を回避できるというような、完全な規則は存在しない。意識に上る規則ではなく、潜在意識的な習慣、私たちの暗黙知を信頼するしかない。それが支配的な「空気」に抑圧される人やモノの声に気づく感性をもたらす。その上で「空気」の支配を正当化する論理には論理で対抗すれば良い (15)。
理論的な問題が解決されたとしても、では実際のモノづくりにおいてどのように物活論的な見方を実現するのかという、実践的な問題が残る。これに関しては人々の世界観の変化を伴う漸進的な仕方しかないだろう。しかしそのような変化はすでに始まっているのではないだろうか。今日、世界各地で、DIY、モノづくりのワークショップ、廃材を使ったモノづくり、空家のリノベーションといったことが見直され、新たな意味を吹き込まれて展開されている。こうした活動が、モノづくりの新しいあり方、人とモノの新しい関係のあり方を巡る探求であるとき、そこには共通して物活論的なモノへの態度が共有されているように思う。
参考文献
伊藤邦武(2006)『パースの宇宙論』岩波書店
インゴルド,ティム(2011)「つくることのテクスティリティ」『思想』No. 1044, pp.187-206
奥村大介(2014)「ささめく物質:物活論について」『現代思想』Vol. 42-1, pp.116-129
木田元(2000)『反哲学史』講談社学術文庫
キャリコット,J.ベアード(2009)『地球の洞察』みすず書房
ケリー,K.(2014)『TECHINIUM:テクノロジーはどこへ向かうのか?』みすず書房
チクセントミハイ,M.(1990)『フロー体験,喜びの現象学』世界思想
河野哲也(2013)「当事者研究の優位性:発達と教育のための知のあり方」石原孝二編『当事者研究の研究』医学書院
長坂一郎(2013)「クリストファー・アレグザンダーの後期理論の思想的背景:ホワイトヘッドのコスモロジーと『神』」『日本建築学会計画系論文集』78 (686), pp. 925-933
ノルベルグ=シュルツ,クリスチャン(1994)『ゲニウス・ロキ』住まいの図書館出版局
ハイデッガー,M.(2013)『技術への問い』平凡社
ポランニー,マイケル(2003)『暗黙知の次元』ちくま学芸文庫
ホール,T. S.(1990)『生命と物質』(上)平凡社
丸山真男(1998)『忠誠と反逆』ちくま学芸文庫
門内輝行(2004)「関係性のデザイン-つくることから育てることへ」『設計工学シンポジウム講演論文集』日本学術会議人工物設計・生産研究連絡委員会設計工学専門委員会
ラトゥール,B.(1999)『科学が作られているとき』産業図書
安冨歩(2008)『生きるための経済学』NHKブックス
——(2013)『合理的な神秘主義』青灯社
山口純(2014)「設計プロセスにおける論理学的,倫理学的,美学的次元の関係 : C.S.パースの規範学に基づく探究としての設計プロセスのモデル」『日本建築学会計画系論文集』79 (703), pp.1881-1890
山崎正和(2007)『装飾とデザイン』中央公論社
山本七平(1983)『空気の研究』文春文庫
Alexander, Christopher (2002a) The Phenomenon of Life: The Nature of Order, Book 1, Routledge
—— (2002b) The Process of Creating Life: The Nature of Order, Book 2, Routledge
Gell, Alfred (1998) Art and Agency, an Anthropological Theory, Oxford University Press
Hoos, Ida, R. (1979) Societal Aspects of Technology Assessment, Technological Forecasting and Social Change 13, pp. 191-202
Ingold, Tim (2000) The Perception of the Environment, Routledge,
Leopold, Aldo (1968) A Sand County Almanac and Sketches Here and There, Oxford University Press
Protzen, Jean-Pierre, and Harris, David J. (2010) The Universe of Design: Horst Rittel's Theories of Design and Planning, Routledge
Schön, Donald A. (1982) The Reflective Practitioner, Basic Books
Shaviro, Stevens (2014) The Universe of Things, University of Michigan Press
注
1)当然ながら、何をもって生きているとするのかが問われるだろう。人や動物は血脈を看て生きているかどうかが判断されるが、もちろんモノが生きているというのは、この意味においてではありえない。現代において生命は、「自己複製」といった「作用」の面から説明される。個体の死も心肺あるいは脳の機能の停止によって定義されるだろう。しかし古代ギリシャにおいて生命は「作用」だけではなく「霊魂」を含意した(ホール1990)。物活論においてモノが生きているというときの生命は、「作用」より「霊魂」、「心」、「精神」、「経験」、「感じ」、「意識」、「主体性」、それ自体としての「価値」などを意味するだろう。この意味で物活論は、あらゆる存在が心を持つという「汎心論(panpsychism)」である。
2)丸山によれば、世界の宇宙創造神話の発想に流れる基本的な動詞として「なる」、「うむ」、「つくる」がある(丸山1998)。宇宙を「なった」ものとして植物のメタファーで捉えるか、あるいは「うまれた」ものとして動物のメタファーで捉えるか、あるいは「つくられた」ものとして人工物のメタファーで捉えるか、である。このうち「なる」と「うむ」は世界を生命のメタファーで捉える物活論的あるいはアニミスム的な見方であり、日本、中国や、ギリシャ、ローマなどの神話に共通する。一方で、「つくられた」ものとしての世界という考えはユダヤ教やキリスト教において現れたものである。
3)古代ギリシャの「自然哲学」における「自然(physis)」とは「生成」の意味を持つ。自然は生命的原理を内在して、それに従って生成消滅するものとして見なされたのである。こうした自然哲学に抗って「つくられた」ものとしての世界という見方を提示した哲学者がプラトンである(木田2000)。プラトンは目に見える現実を、永遠的な形(イデア、idea)の影に過ぎないものとして見なしたが、これは制作者の抱く形に沿って作られた人工物をモデルにした見方である。また、生命はモノに内在するのではなく、外から付与されたものであるという後の機械論につながる見方を示した。作ることは、材料に形を与えることだという考えを明確に定式化したのは、アリストテレスである。しかしアリストテレスにとって、この材料(質料、hyle)とは単に受動的なものではなく、その内に形(形相、eidos)を孕み(形相はアリストテレスにとって精神と同じである)、その目的(telos)へと向かう。
4)パースは例えばこう言っている。「思考は必ずしも脳と結びつけられるものではない。それは、蜂、結晶、そして純粋に物理的な世界のなかに現れている。そして、対象の色や形などが本当にそこにあるというのを否定できないのと同様に、思考が本当にそこにあることを否定することはできない。」(Peirce)このようなパースの物活論的な立場は、伊藤によればカドワースの「形成的自然」の理論に由来する。それは「自然のなかに見いだされる物質的な機械論的因果性の底には、形成的自然という精神的な原理がはたらいており、この原理によって機械論的な自然現象のみならず、生命や精神のはたらきも説明されるようになる」というものである(伊藤 2006)。パースのコスモロジーはこの形成的自然を「第一性」、「第二性」、「第三性」というカテゴリーによって説明しようとするものである。第一性は可能性、偶然性、潜在性、自発性、感じ、質、といった、他と関係なく存在するものの存在様式、第二性は事実、反作用、粗野な力といった、第一のものと無媒介的に存在する第二のものの存在様式、第三性は法則性、表象、習慣といった第一と第二を結びつける第三のものの存在様式である。パースの考えでは、宇宙とは可能性(第一性)と事実(第二性)との関係の中で常に変化の過程にある、生きた習慣(第三性)なのである。そして探求とは習慣の形成過程である。探求はアブダクション、演繹、帰納という三つの推論形式からなるが、これらは三つのカテゴリー間の産出関係として理解される(山口2014)。そしてこの探求とこの三つの推論形式は(つまり思考は)、人間に固有なのではなく、モノの世界にも偏在する。私は設計を探求として見なすことによって、それを自然の形成過程の内に位置づけようとしている。人間の科学や技術の進化もまた、宇宙の論理的な法則性(習慣)の形成過程の一部なのである。技術が自然の進化の一部だと言う考えはK.ケリーの著作にも見られる(ケリー 2014)。
5)ホワイトヘッドが問題視するのは、機械論がもたらす世界の「二元分裂(bifurcation)」である。機械論は世界を機械論的に扱える部分とそうでない世界に分ける。前者は科学が扱う客観的な世界であり、「推論的自然」あるいは「因果的自然」と呼ばれる。後者は「木々の緑、小鳥たちのさえずり、太陽の暖かさ、椅子の固さ、およびビロードの感覚」などからなるような主観的世界であり、「夢的自然」あるいは「現れ的自然」と呼ばれる。17世紀にロックは前者を「第一性質」、後者を「第二性質」と名付け、前者を実体の本質とする機械論を示した。デカルトはこの物質的実体と精神が全く独立して存在するとして、物質的実体を「価値」の領域から完全に閉め出した。このようにして価値に関わる主観的な精神の世界と、価値と無関係な客観的な物質の世界が二分されたのである。二元分裂を避けるためにホワイトヘッドは、第二性質、つまり質や価値もまた客観性的事実であると考え、アレグザンダーはこれを受け継いだ(長坂 2013)。
6)思弁的実在論はクァンタン・メイヤスー(Quentin Meillassoux)、グラハム・ハーマン(Graham Harman)、レイ・ブラシエ(Ray Brassier)、イアン・ハミルトン・グラント(Iain Hamilton Grant)らの主張する立場であり、彼らの思想は当然異なるものの、第一性質と第二性質の対立についてのカント(Imanuel Kant)の解消の仕方を批判する点で共通する。カントは「物自体」を認識することはできず、人間の精神が現象を構成するとした。客体は主体と独立して存在しない。世界は人間と独立して存在するのではなく、人間が世界を見る見方が形作っている。思弁的実在論においては、このように客体を主体の相関物として見る見方が「相関主義(Correlationism)」と呼ばれ批判される。シャビロによれば、思弁的実在論は相関主義を退けるために、消去主義(Eliminativism)か汎心論を取ることになる(Shaviro 2014)。前者は全く思考のない世界を想定する(メイヤスーとブラシエ)のに対して、後者は思考が世界に偏在する(ハーマンとグラント)と考える。
7)アルフレッド・ジェル(Alfred Gell)は、芸術作品などの人工物を、単なる作用の対象ではなく、作用の主体でもあるものとして見る立場を示した(Gell 1998)。ティム・インゴルド(Tim Ingold)は、作ることとは形を材料にあてはめることだという制作観を否定した上で、さらにまたジェルの立場もまだ不徹底だとする。人と物が相互に作用するという見方にはまだ主体と客体の二元論が残っているというのである。そしてインゴルドは、作ることとは「世界の肌理を見つけだし、その展開をなぞる」ことであり、モノの形は作ることに先立って存在するのではなく、作る実践の中で「育つ」のだと見なす(インゴルド 2011, Ingold 2000)。他にも人類学においては、アクター・ネットワーク理論を用いて人間中心主義を脱しようとする多くの試みがなされている(床呂・河合編 2011)。
8)デザインと製造の分離は、ルネサンス期に建築において現れ(その先駆者は建築家レオン・バティスタ・アルベルティである)、さらに産業革命における機械の導入によって人工物一般の製造に要請した。とはいえ、実際のところ、デザインと製造は完全に分けることができないのが通例である。特に建築では建設段階でデザインの詳細がつめられるのだし、場合によっては大きな変更が加えられる。ただし、そのような「手戻り」はできるだけ排除すべきものとして見なされている。いずれにせよ設計者は製造にまで何らかの責任を持つのが通例であり、設計者の作品は、純粋な「形」というより、その具体化としてのモノとしてみなされることが多い。このことは音楽家の作品が五線譜によって純粋な形として保持されると見なされるのとは異なる。音楽の場合、その具体化は演奏家の自由な解釈に任せられることが多いだろう。ただ近年の3DプリンタやFabLabのムーブメントは、デザイナーが形のみを提供し後は作る人が好きなようにアレンジして製造するという、音楽に近いデザインのあり方へ向かっているように思う。
9)目的から手段への推論の形式は、事実から仮説への推論の形式と同じでありアブダクションと呼ばれている。アブダクションは演繹と帰納とともに探求を構成する(山口 2014)。
10)何だか分からない、「ソレ」としか言いようのないモノは、目的と手段の関係に位置づけることができない。そのようなモノは通常のデザインのプレゼンテーションには適さない。デザインをクライアントにたいしてプレゼンテーションするときには、それを問題にたいする解決として正当化することになるだろう。そして問題解決として明確に表現するには、デザインを一般的なアイデアの具体化として明確に表現することが重要になるのである。
11)デザインを問題解決として合理化しようというアプローチが、設計方法論の研究が1960年代に開始された当初の標準的な立場であった。しかしこの方向性の限界はすぐに明らかになった。それは問題を定式化した後の解決について数理的に扱うことができたとしても、重要なのは何が問題であるかであり、この問題の定式化は数学的に扱えないということだった。デザインの問題は数学の問題とことなり常に不確定性をはらむために、決定的な定式化が不可能である。ホルスト・リッテル(Horst Rittel)はそのような問題を「意地悪な問題(wicked problem)」と呼んだ(Protzen and Harris 2010)。設計の目的を論理のみで正当化しようとすると、その目的を手段とする高次の目的を設定せざるを得ず無限後退に陥る。したがって、目的は結局のところ論理とは異なる次元で設定されることになる。つまりそれは倫理による。何を目的とすべきか?この問いに対してデザインが提出するように求められるのは、倫理学に求められるような抽象的な答えではなく、具体的な答えである。それは将来における特定の状況などである。ある状況についての記述から、その状況が倫理学的な規範と整合するかを論理的に考えることができる。しかしそれはその状況を誠実に捉えることを前提としている。問題を、たとえば解決の容易さという都合で定式化し固定し、問題が別様である可能性を排除するとしたらどうだろう?それは問題に対する誠実な態度とは言えない。しかし実際にそのような不誠実な態度がしばしば蔓延したのである。とくに都市計画などにおいては、数理的に扱える定量的な部分にのみ注目し、定性的で数理的に扱えない部分を無視するという態度が広まった。そういう態度を社会学者のアイダ・フース(Ida Hoos)は「数量化マニア」と呼んでいる(Hoos 1979)。手段の「真理性(truth)」は、目的と手段が妥当な論理で結びつけられていることにある。どれだけ不誠実な問題についても真理性を持った解決を与えることができる。倫理的には正しくない目的について、論理的には正しい解決を考えることができるのである。しかしそのような解決の真理性にどのような価値があるのか?
12)これは人間の場合では当然の態度である。人が他人を評価し、「あいつはA型人間だ」とステレオタイプ化する。このとき、彼を典型的なA型人間としてしか扱わないのは誠実な態度ではない。
13)「場所」や「問題」だけではなく、設計者が生み出そうとしているデザインすら、それは現実の事実としては存在していないにも関わらず、それ自体としての主体性を持つと見なすことができるだろう。それは設計者の意図やアイデアから逸脱し、あたらしい意図やアイデアを要請する。
14)考えると、私たちは倫理的配慮の対象を広げてきた。デカルトは動物を機械だと見なしたが、今では動物は倫理の対象である。動物の痛覚についての配慮なしに人間の目的についての手段のみとして扱うことは、「動物虐待」とみなされることがある。アルド・レオポルド(Aldo Leopord)は土地を倫理の対象とすることを唱えた。つまり土地を人間のための手段ではなく、それ自体として尊重すべきものとして扱うことを。そして彼は、人間は土地の支配者ではなく土地という共同体の一員であるべきだとした。現在ではベアード・キャリコット(Baird Callicott)がレオポルドを引き継いで環境倫理を展開している(キャリコット2009)。彼らの主張は、生物としての痛覚を持つかどうかを重視する功利主義的立場からの主張ではないので、無生物にも倫理的な配慮の射程が拡張される。土地とことなり地球上の一地点にあるわけではない、移動するモノも、また倫理の対象として、それじたいとして尊重されるようになる可能性はある。そのときモノを人間の目的のための手段のみとして扱うことは、「モノの虐待」と呼ばれることになるかもしれない。
15)このような考えを安冨は「合理的な神秘主義」として提唱している(安冨 2013)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
