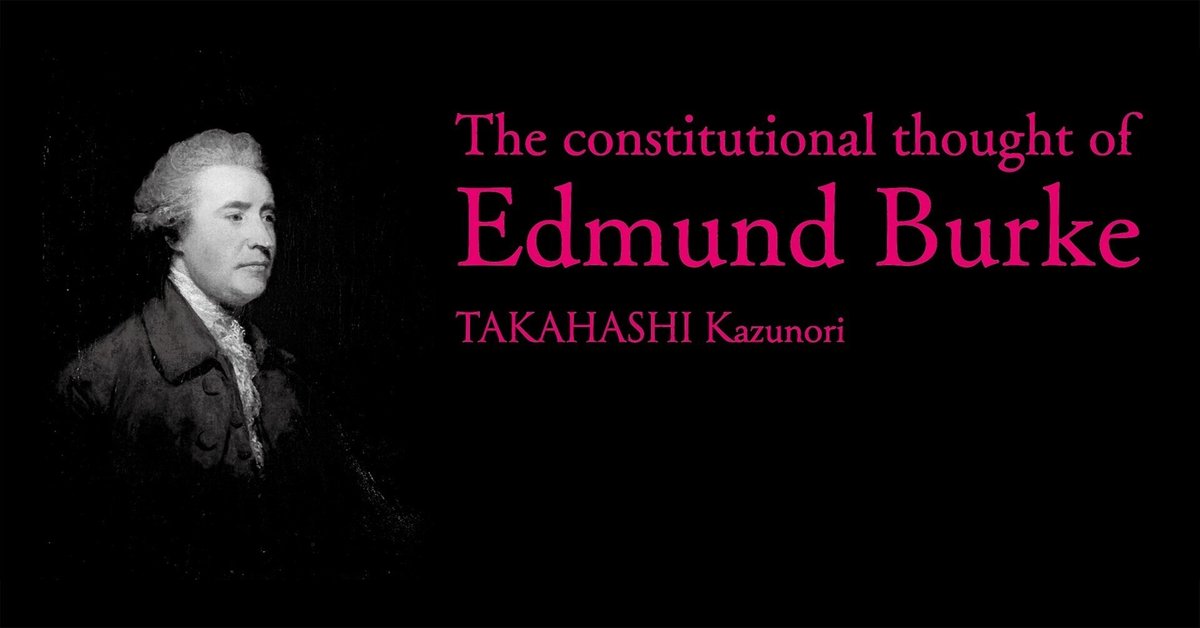
高橋和則著『エドマンド・バークの国制論』より「序文」を公開!
2024年8月の新刊、高橋和則先生の単著『エドマンド・バークの国制論』より「序文」を公開いたします。
政治的ロマン主義の源流あるいは保守主義の父祖と位置づけられてきた思想家バーク。本書は、その著述を〈国制〉の観点から読み解き、従来のバーク理解を刷新しようとする意欲作です。バークとプライス、ペイン、シィエスらが論戦をくりひろげた18世紀ヨーロッパの言説空間を立体的によみがえらせる高橋先生の行論にご注目ください。
*転載にあたり、注を再編集しております。
序 文
エドマンド・バークはアイルランドで1729年に生まれ、イングランドで1797年に没した、18世紀イギリスの美学者、政治家、政治思想家である。本書はこのバークの政治思想の理解を試みる。
バークの政治思想と言っても、その他の思想家と同様に、あるいはそれ以上に多面的であることは疑い得ない。彼は美学者でもあるが、その点についてはおいておくとして、こと政治に限っても彼の思想を包括的に論ずることは容易ではない。
そのバークの思想を考える際に、これまでしばしば言及されてきたことについて触れておこう。バークの、とりわけフランス革命論が、ロマン主義に多大な影響を与えたことは周知の事実である。ドイツを中心地としてヨーロッパ全体に及ぶ、文学、芸術、思想の領域で広がりを見せたこの思潮において、とりわけ政治的なそれは反フランス革命の姿勢をとった。フリードリヒ・フォン・ゲンツがバークの主著『フランス革命についての省察』の翻訳を行ったことがその一つの重要な契機をなしていよう。このロマン主義的、さらには歴史主義的解釈は主としてドイツ系の論者によって推進された。マンハイムの『保守主義的思考』やマイネッケの『歴史主義の成立』が挙げられるが、しかし例えばカール・シュミットはその著書『政治的ロマン主義』において次のように指摘している。「バークやド・メーストルやボナールのような人々を、アダム・ミュラーやフリードリヒ・シュレーゲルと同じ精神的知性の範疇に入れる今日よく見られる叙述がどれほど誤っているか」は明らかであり、フランス革命に対する態度の点でも「バークにおいて、革命の際に彼を支配した情熱は、革命に壮大な劇もしくは自然現象を見ていたロマン主義者たちの美的感情ではなく、彼にとっては革命は、神と人間の法に対する憎んでも余りある侵害なのである」。ここでシュミットは、政治的ロマン主義者たちが自らの思想を展開するにあたって、バークの議論を契機の一つとしていたことを否定している訳ではない。しかし逆に言えばそれは契機の一つに過ぎず、質的には劇的なまでの変容が見られ、もはや同列に論ずることは困難になっていると論じているのである。シュミットの指摘がどこまで的を射ているのかは別個に検討しなければならないが、いずれにせよバークの政治思想を理解する上で政治的ロマン主義との関係を無造作に取り上げることには大幅な警戒が必要だということは念頭に置く必要があろう。
他方、一般的にエドマンド・バークは「保守主義」の父祖として知られている。とりわけ彼の『省察』が保守主義の「聖典」と位置づけられていることは説明するまでもなかろう。その意味ではおそらく政治的ロマン主義よりも遥かに、保守主義という政治的イデオロギーはバークの政治思想を理解する上で意義のある概念であると言うことができる。しかしその際に、バーク自身は「保守主義」という概念を用いたことはないという事実にも目を向ける必要があるであろう。リフォーム・トゥ・コンサーブ、つまり保守するためには改革が必要であるというフレーズがバークのものとしてしばしば挙げられ、それが保守主義の一つの原理として扱われているというのは事実である。だがバークの生きている間、保守主義という概念はまだなかった。政治的な意味での「保守主義」という概念は、シャトーブリアンの発刊した雑誌、『ル・コンセルヴァトゥール』に端を発すると見られるように、バークの後に現れ、イギリスで受容されたのは1830年代であるとも指摘されている。むろん概念そのものよりも、その原理が先に登場することは珍しいことではないし、おそらくバークと保守主義もそのような関係にあると捉えることは無理のあるものではない。しかし保守主義という政治的イデオロギーは、それ自体内部に複雑な多様性を含んでいる。思いつくままに挙げるだけでも、マイケル・オークショットの『保守的であること』、カール・マンハイムの『保守主義的思考』、ロバート・ニスベット『保守主義──夢と現実』といった著作があり、保守主義の多様性とそこに潜む一貫性を整理し理解するだけでも一大作業であることは疑いを容れない。その上にバーク自身は使っていないとなると、単に困難だというだけでなく、むしろバークの政治思想がいかに受容されたかという受容史に裨益するものではあろうが、バークの政治思想そのものの理解に役立つ範囲を余り大きく見積もる訳にはいかないのではないだろうか。いわゆる「バーク・リヴァイバル」と呼ばれる現象が70年代アメリカで起きたが、それは多分に冷戦期のアメリカにおける共産主義批判とリンクしており、そのことが研究成果を無価値化する訳ではないにしても、研究者の保守主義に対する志向、関心をバークの思想に投影したところが大きいということもまた否めない。
以上からも、ここで直接的にロマン主義や保守主義との関係でバークの思想を理解するという態度をとることはしない。例えばすでに犬塚元が指摘したように、「バーク思想を何何主義と解釈することは今日さほど生産的営為とは思われない」というのが至極妥当に思われる。
バークの著作を、置かれた状況との関わりにおいて時間軸にそって検討したものとしては、バークの著作集として現在最も網羅的なクラレンドン・プレス版『バーク著作演説集』の編集にも参与しているウィリアム・トッドのものがあるし、コナー・クルーズ・オブライエンの手になるアンソロジーも評伝的性格を持っている。だが依然としてF・P・ロックの研究が決定的なものと言えよう。だがわが国に限ってみても、小松春雄、中野好之、岸本広司、真嶋正己らの優れた研究がある。私もこれらの研究に大幅に依存しており、詳細はこうした基本的著作に譲ることとしたい。
さてバークの政治思想を理解する上で極めて重要な論点の一つとして国制(constitution)論がある。従来、バークはイギリスの国制を神聖化しており、それに基づいて自らの政治思想を構築しているとも論じられてきた。だが果たしてそれは本当なのだろうか。後に検討するが、革命期にあるフランス人から、フランスはイギリスの国制を模倣すべきかと尋ねられた折、バークはその必要はない旨、返答している。その点だけを見ても、従来の理解には少なからず疑問符が付くのではないだろうか。アメリカ独立においてもフランス革命においても、国制(constitution)は大きな論点であったが、バークはそのいずれにおいても主要な論者であった。
本書は、以上の点を踏まえ、バークの政治思想を国制の観点から分析する。まず第一章では、初期バークの国制理解を検討する。バークは当初ダブリンのトリニティ・カレッジで教育を受けた(1744年から48年)後、ロンドンに4つある法曹学院(Inns of Court)の中のミドル・テンプルに1750年に進学している。この経歴からもわかる通り、バークはコモン・ロー法学の教育を受けており、その頃からコモン・ローや国制に関して知識を獲得し、理解を形成していったことは疑いない。その理解がいかなるものかを知る手がかりは残されている。すなわち、初期に執筆され出版されることがなかった、国制や法に関わる著作、『イギリス史略』と『イギリス法の歴史』である。主としてこれらから初期バークの法と国制の認識を読み取ることとしたい。
ついで第二章では、アメリカ独立期のバークの国制論を吟味する。アメリカ独立は18世紀イギリスにおける最大の政治的事件であり、独立の是非に関する論争も過熱した。その論者の中でも、ここでは独立擁護の立場をとったリチャード・プライス、トマス・ペイン、そしてバークを取り上げる。彼らの議論はいずれもイギリス国制についての検討を含んでおり、それに基づいて論理を組み立てている。だがイギリス国制の理解や評価は三者とも異なっていた。本章では、プライスの『市民的自由』、トマス・ペインの『コモン・センス』に現れたイギリス国制理解と比較しつつ、「アメリカ論」と総称される一連の演説と著作からバークの国制論を分析することとしたい。
最後の第三章は、ヨーロッパ全体を震撼させたフランス革命に際しバークが展開した国制論を、主著『フランス革命についての省察』を中心に検討する。プライス、ペインとバークはアメリカ独立に際しては、独立擁護という同じ陣営だったために論理の違いは後景化していたが、このフランス革命に直面してバークが革命批判を展開したため、革命擁護のプライス、ペインとの論理の違いが明確化し激しい論争となった。二章と同様、プライス、ペインの論理と比較するが、ここではさらにフランスのアベ・シィエスの議論も検討する必要がある。というのも、一方でバークは憲法制定権力(pouvoir constituent)論を展開したシィエスを革命の理論的主導者と名指しして批判しているからであり、また他方で革命を擁護しているペインとシィエスは論争しており、多少なりとも言説空間が複雑化しているからである。本章でシィエスのフランス国民議会での思想的立場の分析を行いつつ、複雑化した言説空間を解きほぐし、バークの国制論を多少なりとも明確化したい。
注
[1]フリードリッヒ・フォン・ゲンツ「『フランス革命についての省察』への序文」『ドイツ・ロマン派全集第20巻』国書刊行会、1992年。
[2]Carl Schmitt, Politische Romantik, Dunker und Humblot 1925(大久保和郎訳『政治的ロマン主義』みすず書房、1970年、44、146頁)。
[3]犬塚元「エドマンド・バーク、習俗(マナーズ)と政治権力」『国家学会雑誌』110巻7・8号、1997年、607-8頁。
[4]William B. Todd, A bibliography of Edmund Burke, St. Pauls Bibliographies, 1982.
[5]Conor Cruise O’Brien, The great melody: a thematic biography and commented anthology of Edmund Burke, University of Chicago Press, 1992.
[6]F. P. Lock, Edmund Burke: Volume 1, 1730-1784, Clarendon Press, 1998; Edmund Burke: Volume 2: 1784-1797, Clarendon Press, 2006.
[7]小松春雄『イギリス保守主義史研究』御茶の水書房、1961年、中野好之『評伝バーク──アメリカ独立戦争の時代』みすず書房、1977年、岸本広司『バーク政治思想の形成』御茶の水書房、1989年、同『バーク政治思想の展開』御茶の水書房、2000年、真嶋正巳「E・バークのフランス革命批判と『保守』の思想」『憲法研究』32号、2000年、同「バークとアイルランド 1793–97」『エール』20号、日本アイルランド協会学術研究部、2000年、同「バークとアメリカ植民地問題 1766–70」『社会情報学研究』9号、2003年、同「バークの強圧諸法批判と『アメリカ課税』」『社会情報学研究』10号、2004年。

高橋和則 著
『エドマンド・バークの国制論』
A5判上製/396頁/定価(本体5,400円+税)
ISBN978-4-588-62549-7
2024年8月23日刊行
