
【DAY 13】深く考えさせてくれる映画 「トリコロール/青の愛」
a film that put you in deep thoughts.
深く考えさせてくれる映画
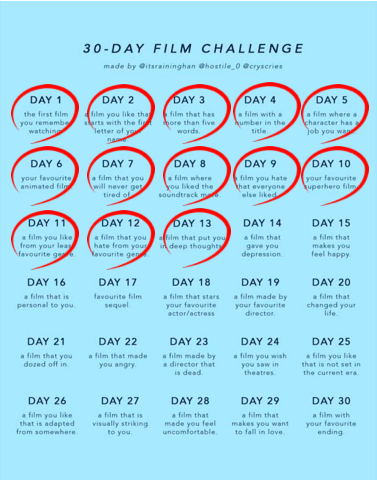
「トリコロール/青の愛」(1993)
クシシュトフ・キエシロフスキー監督
ジュリエット・ビノシュ、ブノワ・レジャン、エレーヌ・ヴァンサン、フローレンス・ペルネル、シャルロット・ヴェリ、エマニュエル・リヴァ
交通事故。急カーブを曲がりきれずに車が大破、高名な作曲家である夫と小さな娘は即死、ジュリー(ジュリエット・ビノシュ)だけが生き残った。それを知った彼女は、入院する病院で自殺を試みるが、自らは死ねないことがわかった。退院後、家族で暮らした屋敷を売りに出し、夫が手掛けていたEU統合を祝福する交響曲の楽譜は廃棄、パリのアパートを借り、全てをリセットして暮らし始めた。
+++
監督はポーランド出身の巨匠、クシシュトフ・キエシロフスキー。フランス国旗の三色旗をテーマにして3部作の映画を撮ることに。「青」はその1本目で、「自由」をテーマとしている。一般的に、青・白・赤は、フランス共和国憲法の標語である「自由」「平等」「友愛」と結び付けられるらしく、映画のテーマも、それに準じているようだ。その後、「トリコロール/白の愛」(1994)、「トリコロール/赤の愛」(1994)と続いたが、これらが遺作となってしまった。
+++
唐突な死別に、失意のどん底にいる。でもジュリーは泣けない。屋敷の処分をするときにお手伝いさんが「奥様の代わりです」と泣いてくれるけれど、ジュリーは泣けない。泣かない彼女の涙は、いろんなものに置きかわる。唯一屋敷からアパートに持ってきた青いガラスが連なったシャンデリアであったり、角砂糖に染み込むコーヒーであったり、路上演奏者のリコーダーの音色であったり。
ある日の深夜、外から騒ぎの音が聞こえる。窓からそっと覗くと、路上でひとりの男が複数の酔漢にリンチを受けているようだ。なんとか逃げ出した男は彼女のアパートのエントランスへと逃げ込んだ。どたばたとした足音が、徐々に上の階へ近づいてくる。ついに彼女の部屋があるフロアで追いつかれたようだ。複数の破裂音と、そのあとの衣擦れの音、そして「しいん」となった。
恐る恐るドアを開けるが、そこには何もなかった。何かひどい暴力が行われたのであれば、そこには何かしらの争いの残り香があるはずだけど、いっさい何もなかったのだった。これは、ほんとうに起きたことだったのか、彼女にとっての何かの啓蒙だったのか。この出来事のせいで、彼女は気の良い娼婦(シャルロット・ヴェリ)と知り合い、夫の秘密を知ることになる。
+++
ジュリーは母親がいる施設を訪問する。ずっとテレビでバンジージャンプや綱渡りの番組を観ている。すっかり痴呆が進んでいて、彼女を彼女と認識してくれない。ジュリーは娘を無くしたが、母はジュリーを忘れたのだった。そんな中、新居のアパートに苦手なネズミが出る。とっさに踏み潰そうかと思ったが、ネズミには小さな赤ちゃんたちがいた。
ジュリーは孤独にプールで泳ぐことが日課になる。真っ青な公共プールで、クロール・背泳ぎを繰り返し、ざばんとプールサイドに上がろうとしたとき、突然の立ちくらみのように、交響曲のフレーズの一部がジャーンと響き渡る。これは、スコアに書かれた音符だったのか、それとも彼女の頭の中にあった音楽なのか。結局、交響曲を作っていた天才現代音楽家は、夫だったのか、妻だったのだろうか。孤独は自由で、自由は創作なのか。
+++
「映画は、高尚なものじゃなくて、所詮はエンタメ」とずっと言いはっている僕は、隠喩だらけのシリアスな映画が、元来あんまり好みじゃない。例えば、あるシーンで、道端で死んでいる犬が画角に収まっているとする。これを「これは主人公の最期を表しているのだ」と見立てるのは、観客の自由だ。「いや、これは現代社会の忠誠の不在を象徴しているのだよ」という別の意見があってもいい、それも自由だ。
でも、僕としては、「死んだ犬」は「死んだ犬」として、そのままフラットに観たくて、喩えの正解はあれこれ考えないし、そういう議論に加わっても、言葉少なに大人しくするようにしている。
けれども、この映画だけは、なぜだか不思議と、何度でも観入ってしまうし、あれこれ考えてしまうことになる。たぶん、20歳のまだいくぶん多感な時期に、この3部作を隅から隅までじっくりと観たからなんじゃないかな。「隠喩ばかりのシリアスは合わない」と自分の傾向を決めつけてガラガラと入り口の門自体を閉じてしまう前に観たから、この映画にだけは秘密のキーができたようだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
