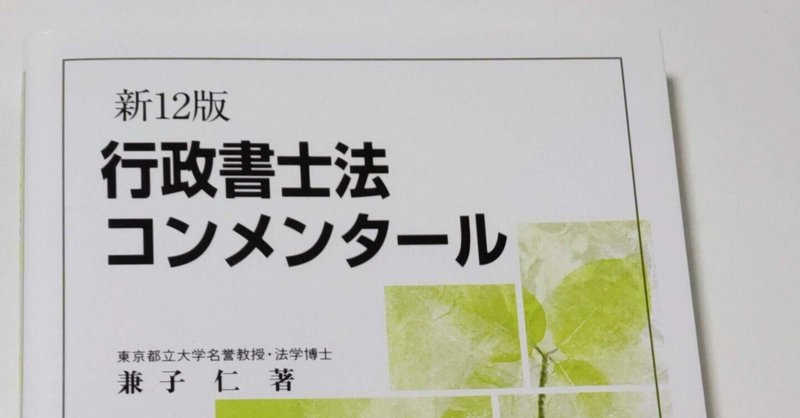
行政書士試験で行政書士法を出せば、少なくとも業際問題解消のアリバイ作りにはなる
行政書士試験に晴れて合格できましたが、すぐの独立開業は考えてはいません。とはいえ、将来的にはそれも視野に入れて、今現在は色々と書籍を買い集めて、ネットでの情報を集めて、自分の今の能力の棚卸しと、これから身に付けるべき能力の検討をしつつ、日々を過ごしています。
書籍については現時点で最新の物を購入したとしても、いざ独立開業したときには法改正などで使えなくなっている可能性もあります。ですので、どうせ無駄になる可能性があるなら、今は業務内容だけ把握出来れば良いと思って中古本ばかりを色々揃えています。
それに、行政書士の業務は多岐に渡るため、相続・後見、法人定款・許認可、内容証明、入管・在留・帰化などなど、書籍を買おうとすればいくらでも対象が増えてきてしまい、お金もいくらあっても足りません。
だからこその中古本ですが、ただ1冊だけは新刊のものを買いました。

行政書士法コンメンタールです。Amazonでも楽天ブックスでも入荷待ちの状態でしたが、hontoでは送料がかかるものの在庫があったので急いで購入しました。今ではhontoでも入荷待ちみたいですね。
この書籍にしろ、あるいは行政書士開業支援本にしろ、誠実なものはいずれも、行政書士がやってしまう問題として業際問題を掲げています。
本来は弁護士・司法書士・社労士・税理士などが独占業務として行う業務を、それらの資格登録が無い行政書士がやってしまって問題を起こすケースは今も減っていないそうです。というか行政書士が増えている以上は今後も増えるのでしょうね。
食い詰めて分かっていて他士業の範囲に手を染めてしまうという行政書士もいるのでしょうけれど、単に分かっていないとか、これくらいは良いだろうと思って手を出す行政書士もいるでしょうし、これについては倫理観の問題とは言え、まず最初の入り口たる行政書士試験においても問うべきでしょう。
現在の行政書士試験では行政書士としての倫理や職掌を問う設問は課されていません。行政書士法も範囲に含めるべきだと、一介の一般人としても思うのですけれどね。
去年・今年とファイナンシャルプランナー3級ついで2級の試験を受けましたが、国家資格・士業でもないファイナンシャルプランナーの試験でも必ず毎回、一番最初の問題はこの業際というか、ファイナンシャルプランナーとして手を出してはいけない業務は何か、ということが問われます。
もちろん、試験で行政書士法を出したら問題を起こす行政書士が消滅するわけなんてありませんが、少なくとも行政書士に合格する人間は皆、行政書士法を学ぶはず、という前提は出来上がります。今の一般知識等の問題を2問ほど削って、行政書士法に置き換えてもバチは当たらんでしょう。そしてその2問どちらも間違えたら、他はどんなに高得点でも不合格ということにしたら、少しはマシになるんじゃないですかね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
