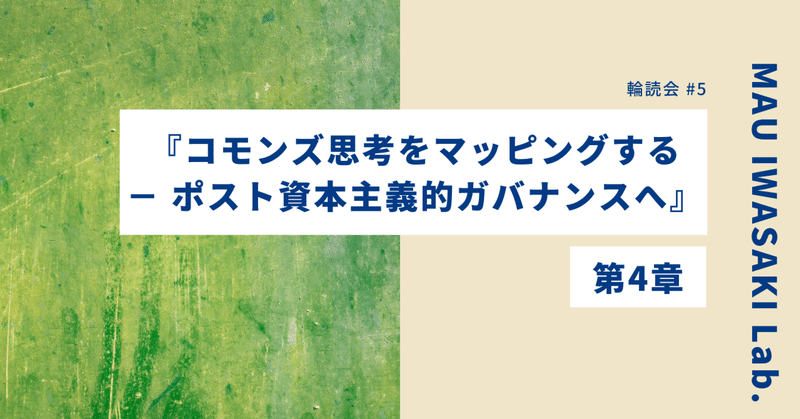
コモンズ思考をマッピングする 第4章
研究室で輪読を行なっている『コモンズ思考をマッピングする ——ポスト資本主義的ガバナンスへ』の第4章「生態系コモンズの囲い込みとカウンター・ヘゲモニー」について、全体のサマリ、ゼミでの議論内容、読んだ感想をまとめていきたいと思います。(文責 M1 石井)
サマリー
ハイ・モダニズムvsコモンズ・アプローチ
この章では、第3章でも取り上げられていた生態系コモンズの囲い込みについて、いくつかの事例を紹介しながら解説されています。どの事例でも共通していることは、ハイ・モダニズムvsコモンズ・アプローチの構造です。
ハイモダニズムの代表的な事例は、先住民の知的財産権を囲い込んだり、種子の多様性を奪ったり、大量の設備投資を必要とさせるバイオテック企業、大規模農業を行い、小規模農業を不利な立場に置くようなアグリビジネスなどが挙げられます。
こうしたハイ・モダニズム的なアプローチのカウンター・ヘゲモニーとして、コモンズ・アプローチとも言える取り組みが、世界各地で起こっています。こうした事例に共通する思想・キーワードとして、小農主体、ボトム・アップ的な活動、アグロエコロジーといったものが挙げられます。
コモンズ・アプローチの具体的事例
この章では、具体的な事例として、アンデス、インド、ブラジルの例が取り上げられています。それぞれを簡単に紹介します。
アンデス:先住民の伝統的知識をバイオテック企業から守る「ポテト・パーク」
ジャガイモはアンデス原産で、数千種類もの品種があると言われています。しかし、先住民が代々受け継いできたこうした品種や加工法といった知識は、知的財産権の取得など、バイオテック企業による盗用の危機に瀕しています。そうした先住民の生活と知恵を守るため、ポテト・パークという保全地区が設定され、ジャガイモの品種を守るだけでなく、それと密接に関わってきた景観や慣習法など暮らし全体を保護し、知識を記録しデータベース化することで、バイオテック企業の脅威に対抗しようとしています。
インド:種子のコモンズを守る「DDS(The Decan Development Society)」
インドでは、緑の革命による大規模農業導入後、思うように収穫が上がらず苦しむ農家が増え、自殺者の増加につながったという問題がありました。元々デカン高原では、気候に合う雑穀が多く育てられていました。しかし、小麦や米といった作物の種子を先進国から輸入し、それに合う化学肥料や灌漑設備、農業機械などへの財の投入が増えた結果、借金が増え、土地がやせ細って収穫も伸び悩み、小農たちを苦しめることになったのです。
こうした事態を受け、デカン高原の気候と小農に合った農法を取り戻す、DDSという草の根活動が生まれました。DDSは雑穀の種子を農家の女性同士で交換し合ったり、知識を共有し合ったりするなど自助的な組織として活動することで、食料主権を取り戻すことができました。
食料主権とは
食料主権は、フードシステムをコントロールする権利を持つのは企業や市場ではなく、生産者・流通業者・消費者だということを強調する政治活動です。農業がより産業的になり、グローバルフードシステムにおいて大企業が支配力を強め、輸入品や加工食品に偏った食事になってきたことに対する反動として成長してきました。 食料主権運動の中心的な存在である、国際的な農民組織ビア・カンペシーナ(La Via Campesina)は、今ではさまざまな背景を持つ81か国2億人のメンバーを抱く規模にまで成長しました。
ブラジル:アグロエコロジーによりどころを求めた「土地無し農民運動(MST)」
ブラジルでは、大地主や多国籍企業などが強い権力を有していたことへの抵抗として、遊休農地を占拠し、土地の権利を求めるMSTという運動が生まれました。彼らはアグリビジネスやソ連のハイ・モダニスト的な農業の失敗を目にし、アグロエコロジー路線をとることになります。彼らは、小農同士の学び合いや学校経営も行い、農業、教育、コミュニティ形成に至るまで、学びと実践を通じて農民が主体化することに重点を置いています。
宇沢弘文の社会的共通資本とオストロムのコモンズ・アプローチ
最後に、日本の著名な経済学者である宇沢弘文の社会的共通資本とコモンズ・アプローチを比較しています。
宇沢は、社会的共通資本とは、医療、教育、農村など、人間的社会の基礎となるものは市場原理に委ねられるべきではなく、異なるルールで管理・運営されるべきものだと主張します。これは、オストロムのいうCPR(共用資源)の考え方に近いものだと言えるでしょう。
しかし、これまでも農産物などは市場経済に流通する商品として扱われており、切り離して扱うことに無理があるのではないかと筆者は指摘します。
先の事例に代表されるような、小農の権利、食料主権とアグロエコロジーといった考え方に出会っていたならば、「社会的共通資本としての農村」という考えも再構成される余地があったのではないかと筆者は考えています。
ゼミでの議論
文化の盗用
強い立場の者が、弱い立場のものを搾取するという構造は、残念ながら長らく続いてきましたが、今まで収奪されてきたものに目を向けたり、そうした文脈から脱するといった考え方として、最近「文化の盗用」が話題になっています。
直近ではラルフローレン社がメキシコの先住民のデザインを模倣した製品を販売し、文化の盗用であるとメキシコの大統領夫人が批判したことがニュースになったという話題が上がりました。
日本の中山間地域における農業と暮らしの変化
インドにおける緑の革命のようなことは、日本でも戦後の農業政策で行われましたが、どういった変化があったのでしょうか。
修士研究で滋賀県長浜市の中山間地域である余呉地区でエスノグラフィー調査を行ったメンバーは、以下のような話を聞いたといいます。
助け合いの文化が薄れた
機械化前は何人かで集まって、みんなで互いの田んぼを助け合っていた。特に収穫時期になると今日は田中さんちの稲刈り、明日は山田さんち、といったような関係性があった。1960年前後を機になくなっていったらしい。
農地改革による「個別化」
かつて小農だった人は、専業農家の人に土地を貸し、専業農家が大規模化した。農協でローンを組んで機械を購入し、人と助け合うこともなく農家の「個別化」が進んだ。
自律的ではなく他律的
MSTのコミュニティの教育では、探究型の教育がひとつの指針として挙げられています。「日本でも探究型学習の導入が進むなかで、似た潮流もあるのだろうか」「昨今レジリエンスという言葉もよく使われ、自決権的な流れが見られる」といった話がありました。
一方で、アクターネットワーク理論のような考え方では、自律的ではなく互いに他律的であるという考え方をしており、自然の一要素として人間があります。
自然の一要素としての人間と捉えるのは、アニマリズムや八百万の神といった思想とも近いのではないでしょうか。
アグロビジネスへの抵抗をレポート
気候変動や食糧、エネルギー、戦争といった地球規模の課題に対し、新たな発想で挑戦する人をレポートしているNews Picksの「地球極限GREEENイノベーションジャーニー」という番組が面白い!という話題提供もありました。
感想
遺伝子組み換え作物の危険性やインドの農家の自殺問題は断片的に知ってはいたものの、それがどういった背景や社会システムで生まれているのかを、本輪読を通じて理解することができ、改めて自分ごととして考えなければいけないと感じました。
都会で暮らす私たちにとって、農ある暮らしを実践したり、共有資源の管理に参加したりすることは容易なことではありません。
しかし、農薬や化学肥料の使用を控えた農作物や、できるだけ近い産地で生産されたもの、こだわりや責任を持って生産されたものを購入するようにすることで、こうしたコモンズ・アプローチに微力ながら賛同し、協力していけるのではないかと感じました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
