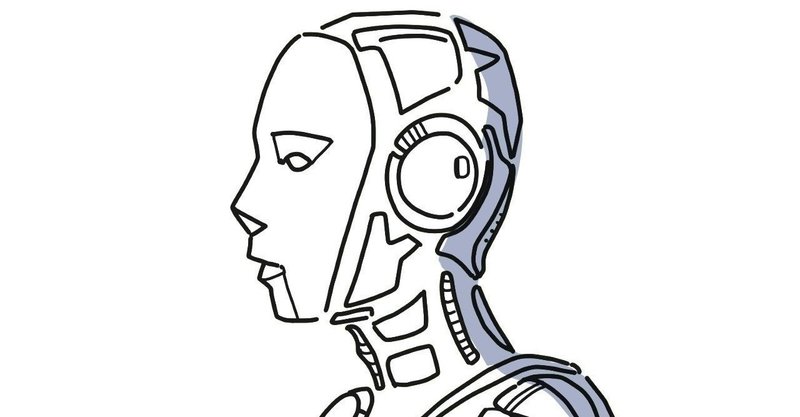
未来に先回りする思考法
■書籍の紹介
未来に先回りする思考法
著者:佐藤 航陽
■はじめに
なぜ、99.9%の人は未来を見誤るのか。
「飛行機の実現までには百万年から一千万年はかかるだろう」
ニューヨーク・タイムズがこの記事を掲載してわずか数週間後、ライト兄弟は人類で初めて空を飛び、この予測を覆しました。
この話を、当時の人々は笑いました。一流紙でジャーナリストを務めるほどのエリートが、なぜそんなことを自信満々に書けたのだろうと。
しかし、他の人々も、ジャーナリストより賢ったわけではありませんでした。野心に満ちた人々が宇宙船の開発にとりかかると宣言したとき、99.9%の人は全く同じことを言ったそうです。
「宇宙船?そんなものは夢のまた夢だ」と。
そして現代を生きる私たちも、未来を見誤るという意味では、宇宙船を夢と言った過去の人々を笑うことはできません。
数年前、現在日本で2000万を超えるユーザー数を誇るFacebookに対して、「日本人には実名で登録するSNSは流行らない」と言っていた人は少なくありませんでした。
今では多くの人が使っているiPhoneにしても、発売当初は「おサイフケータイが使えない」「赤外線がないなんてありえない」などの理由から流行らないという意見が多数派だったことを私たちは都合よく忘れています。
なぜ、人々はこうも繰り返し未来を見誤るのでしょうか。
その原因は人々の「思考法」にあります。人は、今目の前で起きていることからしか将来のことを考えることができません。しかし、FacebookとiPhoneの普及を多くの人が予想できなかったように、現在の景色という「点」を見て考える未来予測はだいたいにおいて外れます。
なぜなら、現実は人間が認知できないほどの膨大な要素に溢れ、かつそれらが互いに複雑に影響しあって、社会を進化させているからです。それをすべて把握することは、人間の脳の機能ではまず不可能です。
一方で、わずかながらではありますが、驚くほどの先見性を発揮して大きな成果を上げる人もいます。たとえば、スティーブ・ジョブズは1980年代、当時30代だったことから、すでに個人がスマートフォンを持つ未来を予言し、それを自分の手で実現させることを決めていました。彼らは現在という「点」を見て考えるのではなく、長い時間軸から社会の進化のパターンを捉え、その流れを「線」として繋がげて、意思決定をしています。その後の世の中の流れを追っていくと、あたかも、彼らは未来に先回りしていたかのようにみえます。
0.1%の人は「世界が変化するパータン」を見抜いている
未来に先回りすることができる0.1%の人たちを調べていくと、99.9%の人とはまったく違った思考法を用いて、未来を見通してることがわかりました。両者を分けているのは、パターンを認識する能力です。彼らはテクノロジーに理解が深く、経済、人の感情など複数の要素を把握し、社会が変化するパターンを見抜くことに長けていました。
■すべてを「原理」から考える
すべては「必要性」からはじまる。
「イノベーションこそが今の時代に必要だ」という意見は、業界を問わずよく耳にします。イノベーションが社会を進化させるということについては、おそらく異論はないでしょう。しかし、その割には日本で次々にイノベーションが起こっているようには思えません。イノベーションは、何を原動力に生まれるのでしょうか。
イスラエルはわずか人口800万人程度の小さな国ですが、ナスダックに上場する企業はアメリカの次に多いという不思議な国です。実はイスラエルは知られざるイノベーション大国で、第二のシリコンバレーとも言われています。
たとえば、Googleが約10億ドルで買収したアプリ「Waze」はイスラエル発のスタートアップです。そのほかにも楽天が9億ドルで買収した、世界3億人以上の利用者を誇るメッセンジャーアプリ「Viber」も同じくイスラエル発です。実際、シリコンバレーのスタートアップであると対外的に見せていても、本社機能はイスラエルにあり、シリコンバレーのほうが支店というケースは、よく見られるのです。
現地のベンチャーキャピタリストに、「どうして人口800万人の国が、こんなにうまく、継続的にイノベーションを生み出せるのか?」と聞くと、シンプルな答えが返ってきます。
「Necessity(必要性)」だと。
中東は政治的な緊張関係があり、周辺国とも争いが絶えません。そのため政府・民間・大学・軍など全員が協力して収入を確保し、アメリカをはじめとする諸外国への影響力を保ち続けなければ、国として危機に陥ってしまいます。つまり、イノベーションを起こすための必要性が、どこよりも切実に存在しているのです。
また、人口の1%にすぎないユダヤ人が、ノーベル賞受賞者の20%を占めるのか、それは、決して先天的な素質によるものではありません。彼らの賢さは、数千年の長い迫害から生き延びるために必然的に身につけざるを得なかった「知恵」なのです。歴史上、故郷として保証されている土地を持たなかったユダヤ人は、生活の糧を得るために土地に依存しない記入という業態を発展させました。彼らが発展させた金融技術は、厳しい状況下を生き抜く「必要性」が生み出した副産物であり、そのひきがねとなったのは迫害や差別といった人間の理不尽さです。「知識」は彼らがその理不尽さに対抗するために必要に迫られて身につけた武器でした。
この人口わずかな国が、イノベーションを起こし、ノーベル賞を受賞し続ける根底には、切実な「必要性」があります。
そして、すべてのテクノロジーもまた、その誕生の背景には「必要性」がありました。火も文字も電気も、それが生存する上で必要だったからこそ作り出されたものです。また、生物の進化もすべて基本的にはこの「必要性」に基づいています、一見変な形をしいてる昆虫や動物も、すべてその環境に適応するために必要な進化を遂げた結果なのです。
■この世の「不確実性」から逃れることができなのも理解する
Googleには有名な「20%ルール」が存在します。
就業時間の20%は、会社から指示された業務以外の自分の好きなプロジェクトなりアイデアに時間を費やしてよいというルールです。外部からは、このルールはGoogle社員に与えられた太っ腹な福利厚生のように捉えられがちです。たしかに、創造性に溢れた社員を引き付けるたけの戦略としてはとても優れています。
しかし、本当のこの仕組みの目的は「リスクヘッジ」のためのものだそうです。
Googleを率いるような優れた経営者も、いつも正しい決断をし続けられるとは限りません。企業が大きくなればなるほど、創業者たちでさえ、すべての市場を正しく把握することは難しくなってきます。ネットの市場は変化が速いので、トップが意思決定をひとつでも間違えば、途端に時代に乗り遅れるリスクがあります。
「だから、数万人いる社員の業務時間の20%をそのリスクヘッジにあてるんだ」と、Googleのあるマネージャーが話していました。もし仮に創業者の意思決定が間違っていたいとしても、数万人の社員の20%の時間を費やしたプロジェクトの中に正しい選択があれば、起業は存続できます。企業の80%のリソースを経営陣の意思決定どおりの仕事に費やし、残りの20%のリソースを社員の意思決定に任せる。これにより、企業全体がおかしな方向にならないようにバランスをとっているのです。
この仕組みは、Googleの経営陣ですらも常に正しい意思決定することは不可能だ、という前提に立ってつくられています。どれだけ多くの経験を積んでも、この世界の「不確実性」からは逃れることができないのならば、いっそのことそのリスクも理解した上で組織をつくるという理詰めの選択の結果が、あの「20%ルール」なのです。
不確実性とリスクの本質を分析した『ブラック・スワン』の著者ナシーム・ニコラス・タレブは、投資について、資金の85~90%を確実性の高いものに投資し、残りの10~15%はあえて投機的な、不確実性の高いものに投資してバランスを取れと語っています。このGoogleの20%ルールも、「人間の不確実性は制御できない」という同じ価値観のもとに設計されています。
この考え方において最もリスクのある選択とは、一見すると合理的に思える選択肢にすべてを委ね、一切のリスクと不確実性を排除しようとすることです。リスクや不確実性を完全に排除する考えそのものが最大のリスクを生み出します。一方で、本当に合理的な判断とは、自分が完全に合理的な選択ができるという考えを諦めて、不確実性を受け入れつつ、意思決定を行うことです。
■未来に先回りする意思決定法
本当に大きな成果を上げたいのであれば、真っ先に考えなければいけないのは今の自分が進んでいる道は「そもそも本当に進むべき道なのかどうか」です。いくら現状の効率化を突き詰めても、得られる効果はせいぜい2~3倍が限度です。時代の急速な変化によって、かつて自分が選んだ道が最適解ではなくなっているということはたびたび起こります。
現状をひたすら効率化し続けることは、目的地への近道を探すことを放棄した思考停止の状態とも言えます。現実の世界は、迷路のようにたったひとつの道しかゴールに繋がっていないわけではありません。目的地へのルートは、無限に存在します。
物事は惰性で進みがちです。「どうすれば現状のやり方を効率化できるか」と考える前に、「今も本当にそれをやる価値があるか」を優先して考える癖をつけるといいでしょう。
大きなリターンを出すためには、適正な時に適切な場所にいることが重要です。人間ひとり努力によってできることは非常に限られています。
短期間で大きな企業をつくりあげた企業経営者には、意外な共通点があるそうです。彼らが、コミュニケーション能力が高く、リーダーシップや人望に溢れるスーパービジネスマンであることは稀です。その代わり、共通して持っているのが「世の中の流れを読み、今どの場所にいるのが最も有利なのかを適切に察知する能力」です。
未来に先回りするために重要なことがあります。
原理から考える思考法を身につける
原理から考えるためには、そのシステムがそもそもどんな「必要性」を満たすために生まれたのかを、その歴史をふまえて考える必要があります。現在の景色だけを見て議論しても、それはただの「点」にすぎません。長期的な変化の「線」で考える必要があります。
手段が目的化することを防ぐためには、今やっている活動がどんな課題を解決するために誕生したのか、常にその原理を意識しておく必要があります。もし、その課題を解決するためにもっとも効率的な方法がすでに存在するのであれば、今の活動を続ける意味はありません。「原理」とは船が海に流れていかないようにするための碇のようなものです。原理に常に立ち返ることができれば、自分の乗った船が流されることはありません。
■まとめ
本書を読んで、直近で教わっている「本当の●●」シリーズにすべて結びついていると思いました。
必要性は、人間の欲求から発生するものが多いため、「本当の理由」に繋がり、不確実性は「本当のポジティブ」とはでやったリスクヘッジを考える話に繋がるなと感じました。
5年後の組織を考えるときに、漠然としてしまいどこから考えたらいいかで思考が停止してしまいましたが、まずはIPOするために必要な組織の状態はどうのような状態か「必要性」から考えてみたいと思います。
