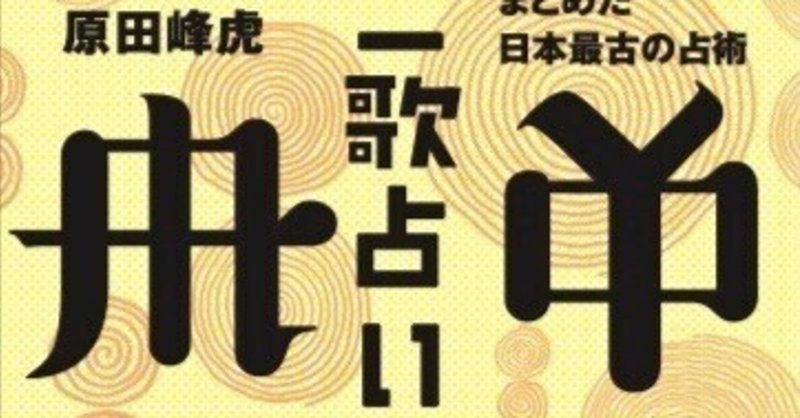
【ホツマ辞解】 〜大和言葉の源流を探る〜 ⑦「うらなふ」と「ましない」 <94号 平成29年12月>
「ふとまに」の辞解は難解で、解釈も諸説有ります。その解明の前に「うらない」と「まじない」をホツマで考えてみましょう。
名詞の「占い」は原典に記述が残りませんが、「うらなふ」という用言は、数例あります。
『うらなひて つきかつらきの いとりやま』ホ4
『ココトムスヒは 占ひて 佳き日に因み 調ゑて』ホ16
『コヤネふとまに うらなえは やせ姫よけん やひのゐは なかのやとなる』ホ27
『きみさかえんと たのしみて イキシコをして うらなはす』ホ33
『きのくにに 神まつらんと うらなえは 往くは良からす 御幸止め』ホ38
27アヤで、コヤネがフトマニで占っていると明示されているように、ホツマでは「占い」とは「フトマニ」で、神意を諮ることを云うようです。
「うら」と云う語句が重要で、「本質・本源・基」を意味します。それは「巡りなす」宇宙構造の中心を指していて、「フトマニの原理」の「基」と読み取れます。
関連語には、「うらかた(占形・卜象)」「うらとふ(占問う)」があります。
「占」の手法は、詳細不詳ですが、「籤引き」「骰子」風なもの以外にも「亀占」や「粥占」があったようです。
『よろの うらかたは あふとはなると かめうらは みつわくわかぬ』ホ24
『すのよろは をけのとんとの かゆうらに 騎弓(のりゆみ)はしら 詠うよろこひ』フすよろ(107)
一方で「呪い」の語源であるであろう「ましない」には、
『各々ともに 詠はしむ いな虫祓ふ わかの呪い』ホ1
『ハタレ破るの 呪いの タネお求めて 授けます』ホ8
『オノコロとましなふのアヤ』ホ18
等の用例があります。これらを考察すると、すべて折伏の目的を持つ「歌・言葉・文字」と関係します。
その「字数」や「語音感」あるいは「重複した意味(掛詞)」がカギであると気付きます。「申(ま)し綯(な)い」すなわち「言葉/文字/歌に、敵を圧倒させる意味を絡める」行為を「ましない」と呼称していたと思われます。
「占い」は神の心に近づくため、「呪い」は敵を遠ざけるため、と真逆の言葉だったのです。
(駒形「ほつまつたゑ解読ガイド」参照)
++++++++++++++++++++++++++
「うらない」と「まじない」について考えてみました。アマテラス大御神は、教ヱの父であるトヨケ大神から、「うらない」の極意を伝授されています。その「うらない」は、「モトアケ」と称される円相図、いわゆるフトマニ図をつかって、諸事万般の吉凶を占うものでした。
この頃の吉凶とは、「天の神様が、どう観ていらっしゃるか?」をさぐるものです。「モトアケ」には、天界の柱となり、その働きを分担して司る四十八の神々が配置されているので、クジを引くことにより、その霊妙な神意を読み取っていたのです。
一方の「まじない」も、現代とは語意のニュアンスが違います。「占い」が神に近づくためだとしたら、「呪い」は敵、もしくはケガレを遠ざけるための作法であったようです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
