
思いが上手く伝わらないのは思いやりを忘れたから?!「異端の福祉」書籍紹介
長年連れ添った親子でもすれ違いが起きたりしますので、赤の他人にはは想いが伝わらずに裏目に出る事があっても当たり前ですが少し凹んだりします。
この投稿も勘違いを受けないように推敲に推敲を重ねましたが文字だけで想いを伝えるには難しくボツしようかとも思いました。しかし想いを伝えるために文章等で表現することが大切と公開しました。
裏目に出てのは慣れや面倒さから一連の事を機械的に処理することとで「最初にあった初めての方への思いやりの丁寧な説明を省いていた」ことが要因に感じています。
これまで色々な会社や職場とめぐり逢いがありましたが2022年11月にご縁から入社した会社紹介します。
就労継続支援B型事業所
他事業ですが同じグループの就労継続支援B型事業所で製作したストールが手元に届き実物を初めて触りました、興味ある方はサイトをご覧頂ければ嬉しいです。


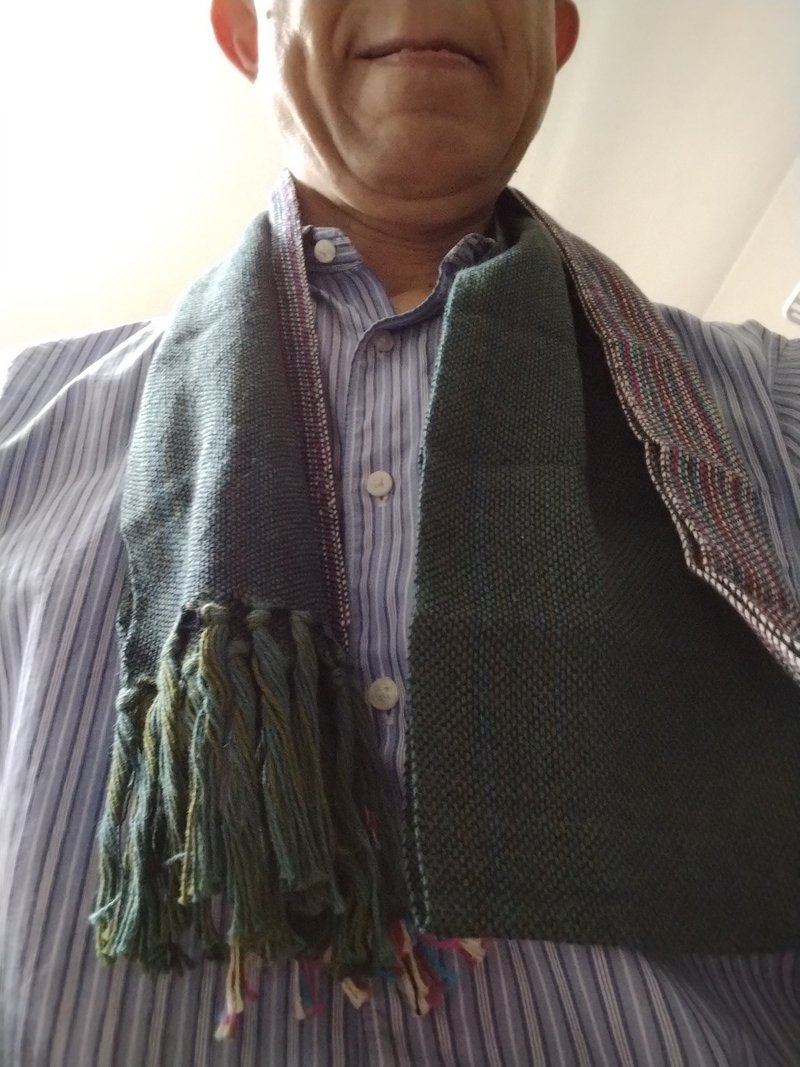
株式会社土屋
入社のきっかけは株式会社土屋(グループ)の代表の理念をオンラインで拝聴して、それに共感したことです。動画は多数公開されていますが書籍は動画と異なり文章を読み進めると当初の熱い気持ちを思い出されます。

『異端の福祉「重度訪問介護」をビジネスにした男』を読んで感じた事
本書は5章に分かれていて1つ1つ物語が繋がっています。それぞれの章の感想を述べていきます。
【はじめにを読んで】
私が最初に重度訪問介護に出会いフルタイム勤務になったのは2015年1月でした。社会福祉法人とNPO法人を持つ非営利団体でしたので所属する障害者メンバー個々に応じた支援を行った5年でした。会社組織でビジネスに着目した代表とは異なる経験でした。
【プロローグ 本当の強さを求めて―
福祉の道へ】
代表はプロボクサーを目指すも断念して一般企業に就職しましたが違和感を感じる中で一冊の書籍と出会い福祉に興味を持ち障害者運動に関わります。
私が重度障害者と言える方と会ったのは20代半ばの1989年頃に授産施設(現就労継続支援A型施設)開所時の職員募集していた障害者団体が設立した職場でした。福祉のイメージとは裏腹に夜な夜な障害者運動のあり方を巡って酒を飲みながら議論が交わされる時期でした。
CP(脳性麻痺)の車椅子の方とは障害のために上手く話す事が困難でしたが、自分の声を聴けと話す時は何のサポートも無しで泣きながら聴き取った記憶が懐かしいです。厳しい状況でしたが健常者と障害者が共に生き共に働く理念の元で交わされた議論は障害を持つ方と接する時に欠かす事の無い貴重な体験でした。
【第1章 重度障害者の介護へ-目の当たりにした過酷な現実】
代表はアルバイトで重度障害者の現実を知り施設の弊害や地域で暮らす方が1970年半ばに現れてきました。介護スタッフとして共に生きることを学び相手に障害があっても本音で向き合うことの大切さに気づかれ実践されました。障害者の「当事者主権」と自ら運動を起こしてきました。反面健常者の偏見と古風の考えがそれを妨げて来ました。
私が「共に生きる」社会を目指した障害者運動家に重度知的障害などで自ら意思を発せられ障害者を思いはどうやって運営に反映させるのか?と議論をふっかけた頃を若気の至りと懐かしく思い出します。当事者が何を感じ何を願うかは常に自問自答しつつ試行錯誤するしかないと言うのが現在の気持ちです。
健常者もそうですか運営に関して活発に意見を言いたい人が居たりお任せされる方が居たりで一口に重度障害と言って個性があるのでそれらを考えると話す事の出来ない方の介助は難問もありますが、言葉にならない「通じた合えた」と思える瞬間の感度体験が忘れられずに続けているとも聞きます。
ショックを受けたのは「人工呼吸器をつけない選択をするALS患者が7割」でした。重度訪問介護を受けられ方はつける選択をした3割の方でそこに至るまでの当事者の葛藤は全く知りませんでした。
重度訪問介護のスタッフを全国で増やす事が1つの生存選択者を増やすための役割、使命と感じました。私は一介助スタッフなので公的には目の前の利用者(土屋ではクライアント)さんの安心安楽の生活支援ですが個人的にはそんな想いをされている方々と想いを多くの方に知って頂く活動をボツボツ行っています。
【第2章 国の制度ができてもサービスが受けられない働き手不足の重度訪問介護】
私が苦手とする重度障害者を支え支援する「歴史」が書かれています。1981年国際障害者年 自力生活の考え方が日本に広まり、重度障害者にとっての「自立」、重度障害者ヘルパーについて書かれていました。
私は当初高齢者介護より障害者介護の方が難しいので介護職員初任者研修(130時間のカリキュラム·旧ホームヘルパー2級)、介護福祉士実務者研修(旧ヘルパー1級)、介護福祉士を取った時でも更に重度訪問介護は更に資格が必要と思っていました。
実際にはヘルパー3級(20時間、3日間で習得)で重度訪問介護が出来るので利用者さんのスキル不足の人も居るの話しに納得しました。それは重度訪問介護の歴史を知り座学も含めて何百時間も学ぶ初任者研修と比較すれば頷ける事でした。
気になる事もありました、重度障害の当事者ならまだしも医療ケアが必要で親御さんの意向に沿って支援する方の場合は当事者から学ぶ事も出来ず時には親御さんの子供を思う気持ちから厳しい目を向けられる方に対して組織ぐるみてのフォローを願っています。
代表は障害者運動のほかに労働運動やホーレス支援をされて少しずつ疲弊されドロップアウトされ社会的支援を受けられ、認知症グループホーム勤務で復活されました。現場と経営者の板挟みの経験を経て重度訪問介護事業に関わられました。
私は10代に職場のろう者との出会いがきっかけで手話を始めて難聴者との出会い要約筆記を始まり盲ろう者ガイドヘルパーや点訳活動、その他福祉ボランティアで多忙だった時期があります。
気づかぬうちに疲弊して活動停止に至りましたが50歳にそれまでと畑違いの介護職に転職することで当時を思い出しました。
代表は奥様に起きた大事故がきっかけで障害者福祉に回帰され2015年初頭に「社会からから置き去りにされた人たちの"隠されたSOS"の多さに気づかれました。2020年頃に独立を決意されて現会社を設立されました。
私の弟は脳腫瘍の除去手術が元で植物人間になって2021年10月にこの世を去りました。手術前の遺書でもしもの時は自然死を望まれていました。
弟の奥さんから生前意識が無く呼吸器が必要な方を引き受ける施設がなく病院を数ヶ月ごとに転々としないといけない苦悩を聞きました。
その話が無意識に残っていたのか半年後の2022年5月に高浜代表のセミナーで重度訪問介護会社を運営している事を知り視聴しました。6月にweb求人説明会、7月にweb面談、11月入社に至りました。
重度訪問介護に関わる方には色々なタイプ、経験を持つ方が居ますが当事者と関わりつつ試練を経験された方がトップに居るのは心強い感じがします。高浜代表が言われる「組織で一度失敗しても再度、挑戦出来るか場と環境を与える」心情は本書を読んで理解出来た気がします。
対外的に犯罪を犯して刑に務した方を支援する団体でありながらメンバーの一度の不始末で追い出した話しを思い出しました。
【第3章 誰もやらないなら自分でやるしかない-重度障害者が自宅で過ごせる介護事業を立ち上げる】
体表は2020年8月重度訪問介護事業を従業員約700人で福岡で創業されました。事業を通して解決したい社会課題、需要と供給のバランス、資金繰りの救世主。
介護の利用で人生が変わる〜当事者とその家族のエピソード〜で3人のクライアント(一般で言われるヘルパー)の紹介がありました。
本人は話す事が出来ないので両親へのインタビューで施設とは異なり1対1で「ヘルパーは友達みたいな存在、本人中心のリラックスした生活を実現」された方。
重度訪問介護への移行に苦労された方や無理と言われた在宅生活を実現出来た方や強度行動障害が1対1のケアで落ち着いた事例など支援に役立ちそうな内容です。
訪問介護は施設とは異なり各家庭の個人情報に関わる事も多く、なかなか他の支援状況や具体的な内容が聞ける機会が少ないのでとても参考になりました。
【第4章 利益の出る仕組みをつくり、
従業員には高い給料を支払うことでサービス品質を高める-「福祉は清貧であれ」という業界の常識を覆す】
社会課題解決(目的)と営利追求(手段)を両立させるオンリーワンのビジネスモデル、営利企業で「支援できる人が増える」スケールメリットがあり、大組織のチームでしっかり支えます。
異業種、未経験、何歳からでも輝ける〜6人のエピソードでサッカー選手から転身された方、生死の淵を経験した方、大病を乗り越え障害児を育てたお母さんなどの体験談もあります。
介護以外のやりたいことも社会起業でチャレンジ可能だったり、自社での介護人材育成のヘルパー養成研修事業所の紹介があります。
高給与はニーズの高さと加算請求の仕組みから、利益を最大化し事業成長のためのDX、質の高い重度訪問介護提供の秘訣も書かれており、現在の社内環境の背景や歴史に触れる事が出来ました。
【第5章 会社を成長させることが社会課題を解決する-必要な人が必要な介護を受けられる社会を目指して】
進んでいない地域移行、47都道府進出後の重度訪問介護の空白地域ゼロに。そして1人でも多くの仲間を増やすために徹底的な説明と対話精神のリレー受継いでいく。組織風土をデザインするダイバーシティの実現、発信情報から社会を変えていくそして「ともにいる、ことがすべて」
人工呼吸器を拒否していた難病患者が重度訪問介護を知ることで生きる選択したケースがあり、「介護サービスは当然の権利ですから、あなたらしく生きることを諦めないでほしい。そのために、私たちはいるのです」は印象的は文書でした。
【おわりに】
「困ったときには助けてほしいととSOSを出せること、SOSに気づいたら躊躇わずに助けに行けること、それがみんな当たり前に出来る世の中を目指して、私は私の事業をこれからも行って行きます」に強い感銘を受けました。
合わせて心に残った文章を紹介して終えます。
「私たち1人ひとりは、それぞれの人生や苦難や、抗いようのない運命に翻弄される弱い存在しかありません。しかし、かたわらにいることに寄って、お互いに役割を見出し、人生の重なりあいのなかで意味を紡いでいく、かけがえのない仲間であると思います。」
「私たちのクライアント(利用者)も、ともに事業を担う仲間たちも、みんなそれぞれの苦悩と困難を乗り越えてながら生き延び、それぞれの記憶を抱きながら出会い、今、ともにいます」
本書を読み終えてあたかも人が生まれて乳児期、幼少期、少年期、青年期、そして次の段階に入ったように感じ余韻を感じさせる作品です。
創立から3年目のために成熟した会社と違い成長段階のために時に不具合が起きたりもしますがグループ一丸となって乗り越えて行く感じです。そんな職場で一緒に働きませんかと宣伝したりしました(^o^)
最後までお読みいただきありがとうございます。 もし気に入っていただけましたら「スキ」&「フォロー」もよろしくお願いします。
