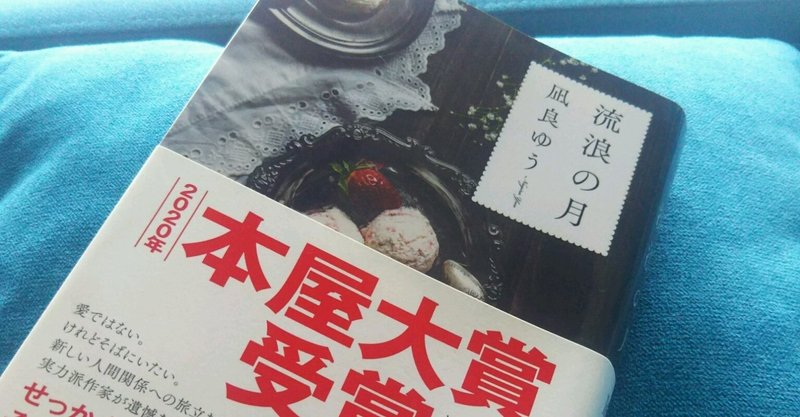
生(性)の充足と、その視点について
凪良ゆう『流浪の月』を読みました。
特に注目している作品ではなかったのだけど、相方が読んでいたので失敬しました。
作者はBL作家出身だということですが、物書きとしてのキャリアはすでに10年以上にもなるということなので、「ベテラン」と言っていいと思います。ただ、私は他の作品については読んでいないので、この小説に関して感じたことだけを、率直に書きます。
まず、この作品のモチーフというか、筋書きに関して、私の脳裏にまず浮かんだのが、『幸色のワンルーム』。少し前に色々と話題になった漫画作品です。誘拐犯と少女の交流、という筋書きの点だけに関して言えば、『流浪の月』と親近性があります。
それから、筋書きは異なりますが、桜庭一樹の『私の男』。これは、筋書きには親近性がないものの、主人公である少女の成長過程において、ある種の依存関係にある男性が物語の中心的役割を果たしている、という点において、非常に近い要素があると感じました。
『流浪の月』は、これらの作品と比べて特別新しい要素を持ち込んでいるわけでも、特異な展開があるわけでもありません。純文学的な要素があるかと思えば、ラノベ的、キャラ小説的な要素も少しあります。そういう意味では、間口が広い作品、と言っていいと思います。
本屋大賞を受賞する作品には多かれ少なかれ、こうした類のミックスジャンル的な間口の広さがあり、本作もこうした背景から、推薦されたものと思われます。また、家族観の多様性というテーマが通底音としてあるということも、最近の現代文学におけるトレンドを捉えているようで、そういった点も評価されているのかもしれません。
以下、ネタバレありです。
まず、率直に言って、物語序盤の流れは少し退屈でした。展開が読めるというのもあるのかもしれないのですが、もう少しじっくりと描いてほしい場面の描写が割とあっさりしていたり、会話の文と地の文のバランスが少し会話に偏りすぎているかな、という印象を受けました。
もっとも、ラノベ的な書き方であればこのテンポ感でちょうどいい感じなのかもしれませんが、テーマ的な重さもあるので(この点は後述)、もう少し重めに進めてもよかったのかなと思います。そこは辛口評価です。すいません。
ただ、後半にいくに従って、筆が冴え渡っていくという印象を受けました。特に、文と更紗が再会してお互いの距離感を測りかねていくところ。更紗のやっていることは、傍目から見れば「ストーカー」なのですが、なぜかここではその「狂気」が強調されていません。逆に、物語の中では狂気の役を演じる亮のDVに関しては、記述の中立性を若干損ねる形で(といっても、「事実と真実は異なる」という表現を用いて、各人の視点の相対性について留保はしている)、その狂気が強調されているようにも思える。これは、あえてそうしているのか。それとも、ストーリーの方向性を脱線させたくないがためにあえて各人の狂気の有様にフォーカスしなかったのか。
私には、これは、良くも悪くも「狂気の物語」なのだと思えるし、作品として、そちらに振り切るという選択肢はなかったのだろうか、と少し考えてしまいました。先ほどこの作品の「間口の広さ」と言いましたが、この作品のテーマ性の持つポテンシャルを考えると、間口の広さを多少犠牲にしてでも、底の底まで掘り進めてほしかったな、というのが、私の率直な感想です。
たとえば、文というキャラクターにはどことなく、複雑な二面性のようなものが垣間見られます。更紗に対して好意を抱きつつも、そこから距離を取ろうとしたり、特異な性癖を持っているかと思えば、身体的な欠損が背景にあったり。文は、ジェンダーレス(属性としての)なのか、それともそうではないのか。文の性(生)のあり方について、この作品でははっきりとした答えは示されていないように感じます。この点は、この作品のテーマ性を考える上で非常に重要なポイントだと思いますので、もう少し展開してみます。
ゲイやレズが登場する小説であれば、性というものがテーマの中心に来ざるを得ない、という思い込みは、現代文学を語るうえで非常に重要な「バイアス」を示していると思われます。なぜなら、クイアな人物とストレートな人物とで文学的な評価軸が異なり得る、という事態こそが、ジェンダーバイアスの所在を示しているからです。もっとも、であるからこそ、(現代)文学はジェンダー規範に対して、それと常に対立していかなければならない、という宿命を孕んでもいるわけです。
何が言いたいかというと、文というキャラクターは、どこにポジションを置いているのだろう、ということです。ペドフィリアなのか、それとも、ジェンダーレスなのか(もっとも、性癖としての「ペドフィリア」についてはその描き方をどのようにすべきなのか、今日のジェンダー論界隈でも議論があることも指摘しておかなければならない。千葉雅也他『欲望会議』(2018年)など参照)。更紗にとって、文という存在はどこまでも中性的であり、それゆえに「無害」であるかのように描かれているのは、文というキャラを描くにあたって公平な視点を持っていると言えるのか、どうか。
私には、文というキャラには、もっと違う側面があると考える。事実と真実は違う、と言いながら、実は、この作品では文という存在について、殆ど踏み込んだ話をしていないように私には思える。
文は更紗にとって「いい人」ではあるのだけど、彼がいい人であるのは、ジェンダーレスであるから、で、あってはならないと思うのです。それは、中性的な人は無害である、というに等しい。私には、そうした思考がこの作品から透けて見えてしまうのが惜しいと思ってしまう。
文がジェンダーレスでなければ、彼はペドフィリアになってしまうのだろうか。そうではない、と、作者は言うかもしれない。しかし、文には文の葛藤があるはずであり、この作品の表現を用いるなら、「目に見えなくて、どこにあるかもわからなくて、自分でもどうしようもない場所についた傷」を抱えた人間の有様、こそが、この作品のテーマの「重さ」であるはずです。
私は、文が「いい人」でない場面をもっと見たい。文という存在が抱える矛盾は、この作品の可能性であるように思えたのです。
視点の中立性、という点でいうと、更紗もかなりの程度、「やばい人」なわけですが、やばい人という「重さ」は感じません。本人にあまりその自覚がないこともありますし、作者がこの人物の「常識」に信を置いている、というのもあるのかもしれません。
が、一歩、この信が揺らいでしまうと、実は、この作品構造を成り立たせている筋書きは、すべてが「更紗の妄想」ということに、なりはしないでしょうか?
そんな可能性を、この作品を読んだどれだけの人が考えたかはわかりませんが、更紗を尋問した警察官たちの「疑い」を、私も抱かずにはいられないことを、ここに告白しておきます。更紗の言い分によれば、「自分たちのことは自分たちにしかわからない」わけですから、他人にもそういう知られざる世界があることを認め、だから自分たちの世界も認めてほしい、という風にも読めてしまうのです。文と更紗は、見方によっては立派な共依存の関係と言えるでしょう。
逆に、この物語が「更紗の妄想」ではないと、どうして言い切ることができるのでしょうか?文は本当にペドフィリアなのかもしれないし、更紗は本当にストックホルム症候群なのかもしれません。「各人には各人の見方があり、世界はあくまで相対的な見方でしか成り立たない」という、この作品のテーゼをもってすれば、そのような結論を回避することはできないはずなのです。少なくとも、すべては更紗の妄想である、という可能性を排除することは、作品の構造上、できない(なぜなら、物語の視点はすべて「一人称」で書かれており、各章においては各人の見た見方が提示されているに過ぎないから)。
にも関わらず、文は「いい人」で、更紗は「救われている」ように見える、とすれば、この作品には隠されたモチーフがあるような気がしてならないわけです。それが、この作品の「テーマ的な重さ」と言った意味です。
アガサ・クリスティーの有名な作品に、『そして誰もいなくなった』というのがあります。その作品では、無人島で連続殺人が発生して、徐々に犯人の候補が絞られていくのですが、叙述が非常に中立的に構築されているので、犯人がわかった後でもその特定に至るまでの記述の流れからは、犯人を導き出すプロットが必然的ではないかのような、読みが可能になっています(文藝春秋編『東西ミステリーベスト100』(2012年版)p204~、座談会での大森望の発言を参照)。『流浪の月』はミステリーではないので、人物造形に必ずしも中立性は要求されていないのですが、人間の複雑性を描くという意味での公平性は要求されてしかるべきだと思います。これが更紗の妄想ではない、というのであれば、そのような可能性をシナリオの中で排除しておくべきですし、排除できないとすれば、そのような可能性の束として作品を捉える代わりに、文や更紗の狂気をこそ、描くべきなのではないでしょうか。
私の読みは、あくまで「脱構築的な」読みです。この作品は、ある種のジェンダー小説としても読めますし、家族小説としても、恋愛小説としても成立するし、なんなら、ミステリーとしても読めてしまうのですが、そのような読みの可能性がある、ということこそが、この作品の持つテーマ性の輻輳性を示していると言えそうです。
そのテーマの輻輳性の中から、一つだけ、特徴的な点を挙げるとすれば、家族観だと思います。これは、村田沙耶香などの小説にも言えることなのですが、互いが互いを束縛する関係にはないけども、ジェンダーレスとも違う、という価値観が示されているのです(こうした関係を「家族」と呼べるかどうかという問題はひとまず置いておきます)。ただ、『流浪の月』の場合、やはり「常識人」としての立場を振り切れていないようなところがあり、それが間口の広さに繋がっているとも言えるのですが。いずれにせよ、これは非常に今日的なテーマであるということでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
