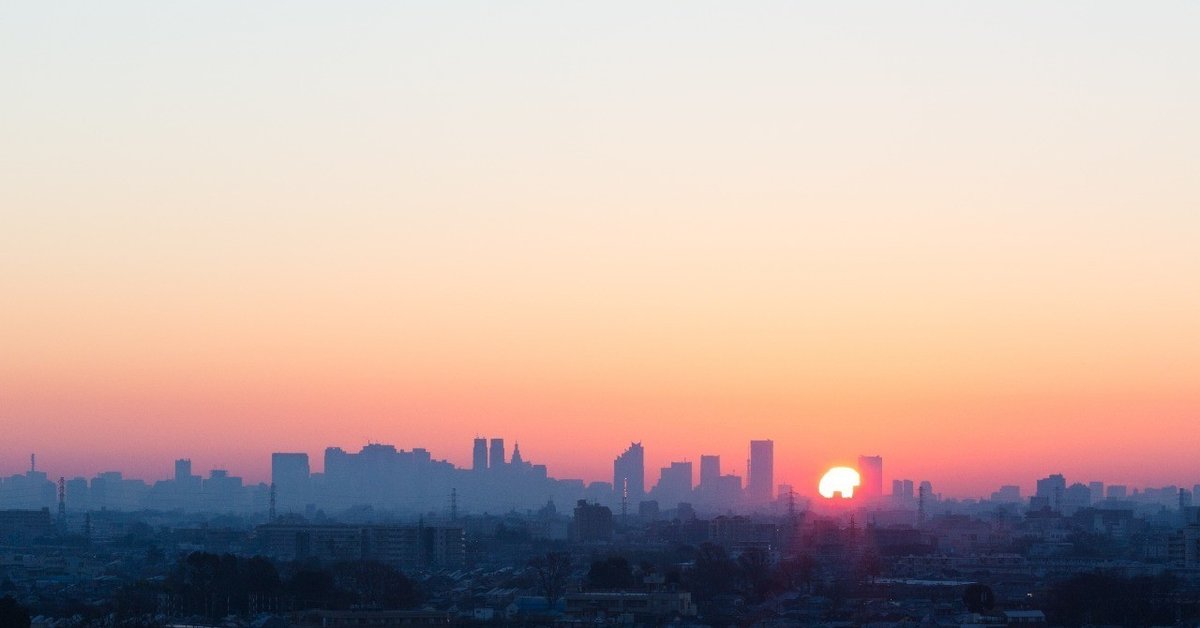
【小説】シンデレラの侍女
二月十四日の教室内は、今日だけ空気が薄ピンクに色づいている気がする。北山中学校二年一組の教室の、窓際一番後ろの席からは、クラス中がすべて見わたせた。
私はシャープペンをくるくる回しながら、ひとつ前の席の親友、有野華が、ちらちらノートから顔を上げて、教室の前のほうを見ているのを、後ろからじっと眺めていた。
教壇の先生や、黒板を見ているんじゃない。華の視線の先は、いつだって、変わらない。華は、華の好きな男子を見ているのだ。授業が始まる前から、いや、その意中の彼――成瀬渉と、同じクラスになった四月から、ずっと。
「あのね、成瀬くんが好きなの」
華が自分の恋心を私に打ち明けてきたのは、たしか十月半ばごろだった。
ふわふわした細いくせっ毛の華の髪は、背中まで長く広がっていて、陽に透けては柔らかく光る。少し茶色がかった地毛の髪とおんなじ色をした、きれいな瞳。ぽってりとした唇。ほんとうにきれいな子だな、と私は一瞬見惚れ、我に返った。
真剣みを帯びる華の表情から、(とうに気付いていたよ)とは言えなかった。華は、いつだってその全身で、成瀬を意識しているように見えたから。
成瀬は、クラスメイトの私たちから見ても、先生方や、親から見ても、非の打ちどころのない男子生徒だった。成績優秀なうえに、品行方正、おまけに弓道部では県内の上位層に食い込むほどだった。
文武両道とは成瀬のことだ、と大人たちが褒めちぎり、おまけに、すっきりと端正な顔立ちまで備えていて、同学年だけでなく、三年生や一年生の女子たちまでもから、いつも熱っぽい視線を送られていた。
いくら華が綺麗でも、優しくても、成瀬を意中の人とするのは、ライバルが多すぎて厳しいよ。私はそう思ったが、本人を前にして、非情なことは言えなかった。やめとけ、本当はそう言いたかったけど、しばらく黙って「そうなんだ」と言うしかなかった。
「ねえ、こんなことを聞くのは、本当に恥ずかしいんだけど、優架の好きな人は成瀬くんじゃないよね?」
長いまつげをふるわせながら、不安そうに聞いてきた華に、私は「ちがうよ」と言った。「いま、好きな人はいない」と。本当のことだ。
よかったぁ、と華は心底安心したように、顔をくしゃくしゃにして笑った。ふいに「恋は罪悪ですよ」という言葉が頭をよぎり、私はそれが、有名な文豪の作品の一節であることを思い出した。なぜ今その言葉がよぎったのか、自分でもわからなかったが、華の恋が、砕け散るのを、この先見なければいけないのかと思うと、胸が痛んだ。
授業が終わっても、廊下にも薄ピンクのふわふわが、ただよっている気がする。そう思いながら、休み時間なので、トイレに行くことにした。混んでいるといけないので、急いで行って帰ってこようと思い、小走りになった。用を足し、また教室に戻ろうとして、廊下の角を曲がったとき、軽く人とぶつかり、あ、と思ったときには、ばさばさと相手が持っていた持ち物が床に散らばった。
「ごめ」
と言いかけてから、相手が成瀬だったことに気が付いた。私がぶつかったせいで、成瀬が落としたものを拾おうとして――気付いた。可愛い便せんが、三枚も四枚も。ラブレターだ、と気付いたとたん、胸がすうっと冷えた。
成瀬は「こっちこそごめん」と言って、私の手を制し、「やばいもん見られちゃったな。内緒にしてね、奥田さん」と笑った。八重歯がのぞいて、ああ、この笑顔に、どの女子も落とされてしまうのだな、とすんなり理解できた。
「先生に見つからないように気を付けなよ」
私はなるべくクールな声を出すようつとめて、この場をとりつくろうと、教室に向かって駆けた。華には、このことはとても明かせない、と思いながら。
バレンタインデーが明けた翌日の朝、一緒に登校しようと華の家に迎えに行くと、華が紅潮した顔で玄関に現れた。
「あのね、優架、聞いて。昨日すっごいことが起きたの。告白が上手くいって、私、成瀬くんと付き合えることになった」
私は息を呑んだ。華が、親友の私にも打ち明けず、一人で成瀬を呼び出して、告白しただなんて、ふだんの華の大人しさを鑑みると、信じられなかった。
「よ、よかったね」
ふたまた、みつまたをかけられているのでは、というのが一番最初に思ったことだった。昨日、成瀬に告白したのは、華だけではきっとないだろう。五人、いや十人は、バレンタインデーを口実に、チョコを渡して、告白していたに違いない。
私は考える。でも、あのいい意味でも悪い意味でも頭が良く隙のない成瀬が、二股などと、リスクのある行動をとるとは、考えにくかった。とすると、本当に、華一人を選んだのか。
「成瀬くん、今日から、二人で帰ろうって。だから、優架、ごめんだけど、放課後は一緒に遊べなくなっちゃった」
いいよ、おめでと、と言いながら、私はまた別のことを考えた。
――私が、華と成瀬の恋の先行きが、難しいだろうと思う理由は、実はもうひとつあった。
成瀬の家は、彼の父が市議会議員をしていることからもわかるように、地元の名家だった。
うってかわって、華の家は貧しく、しかも父子家庭だった。華の母は、幼い華を残して、男と出奔したと昔聞いた。
中学生のうちはよくても、高校生になったら、きっと成瀬の親は、別れさせようとするだろう。私にはそういう強い確信があった。学校中の女子の誰もがうらやむ「成瀬の彼女」という身分を、親友の華が手に入れたのは、本当にお祝いしたい気分だったが、そうすんなりとことは運ばないだろう、と私は思った。案の定、二人が放課後、一緒に帰っているのが人目につきだすと、すぐさま華への陰湿ないじめが始まった。
「――今時、上履きに画鋲を入れるなんて、そんな古い手を使う人がいるなんて思わなかった」
放課後の保健室。「古い手」にひっかかって足裏に傷をつくった華は、私に付き添われて養護教諭の先生に手当をしてもらっていた。
「まぬけだなあ、あたし」
華はその美しい顔で、泣き笑いの表情をつくった。
「優架、このことは成瀬くんには内緒にしてね。恥ずかしいから」
華が絶対、絶対だよ、と念押しするので、うなずくしかなかった。
そのほかにも、華は階段でつきとばされて転びそうになったり、教科書に「死ね」と書かれたり、それはいろいろないじめを受けまくっていたが、私の存在と成瀬の存在だけが、華の救いのようだった。二人が味方してくれるから、強くいられる、と華は笑った。
「成瀬のどこがそんなに好きなの」
私は華にそう聞いたことがある。華はへらへらと照れ笑いをしながら答えた。
「かっこいいところ。――あと、私に優しいところ」
そうか、かっこいいところか。ストレートに単純明快な答えが返ってきて、私は拍子抜けした。「彼女」に選ばれた華なのだから、成瀬の何か人にはわからない特別な魅力に気づいているのかと思っていたのだ。
私から見て、成瀬という男子は、たしかに顔はきれいだし、勉強も運動もできる、品もある、だがしかし、何か空虚なものが、彼の内面を食い荒らしているようだと、以前から思っていた。
空虚に食い荒らされ、彼自身は、どこかからっぽの、中に空気だけ入っている人形のようにも思えたのだった。
顔のいい男子を見ると、そしてその男に群がる女子たちを見ると、私は、その男のどこが、彼女たちを惹きつけてやまないのか、じいっと観察してしまう。そうして、私自身、その男を深読みしすぎて、恋をしそこねる。――中学生のときに、成瀬と華を見て以来、大人になっても、その習慣は抜けない。
成瀬と華の恋の顛末が、どうなったかと言うと、二人は、高校卒業まで付き合いつづけ、高校を出たとたんに、二人してこの町から消えた。いさぎのいい駆け落ちだった。市議会議員の成瀬の親をしてさえ、二人の行方を摑めなかったらしい。
この町から消える前、華は最後に私に会いにきて、「ありがとう、すべては味方してくれた優架のおかげ」と、手作りのピアスをくれた。その日が、私が華を見た最後の日になった。
貧しいシンデレラは、王子様と、幸せになりました。めでたしめでたし。成瀬と華の物語は、まるでおとぎ話のように、私の中で、エンディングがきれいについたまま心に残っているのだけれど、私はもう一度だけ、もしも華に会えたら、問いたいと思う。
「幸せになれた?」と。
成瀬と華の大恋愛を、横目で見ていた私は、二十二歳になったいまでも、恋というものがわからなくて、いまだに付き合っている人はいない。
でも、ジュエリーケースから、あの日華がくれたピアスを取り出し、たまに手の上に転がしてみるときがあって、そのときは必ず、華のことを思い出す。王子様と結婚したシンデレラの、その先の物語はどうなったのだろう。もう知るすべのない「その先」を、私は光る小さなピアスを見ながら、ひとり想像してみるのだ。
いつも温かい応援をありがとうございます。記事がお気に召したらサポートいただけますと大変嬉しいです。いただいたサポ―トで資料本やほしかった本を買わせていただきます。
