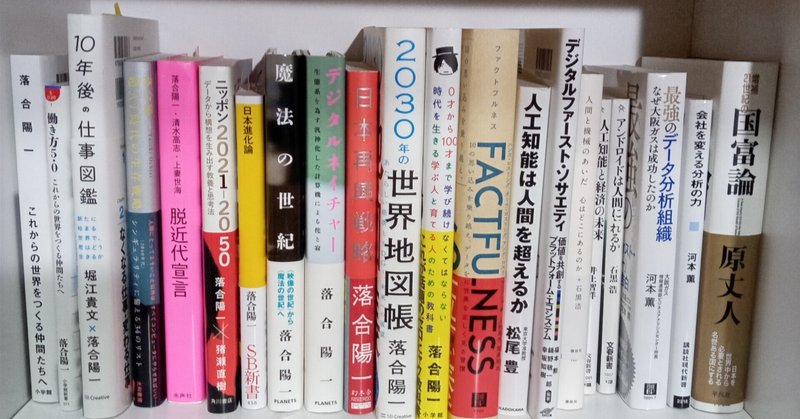
読書メモ:計装 2021年1月号 ニューノーマル時代の運転操業の革新
計装 2021年1月号 ニューノーマル時代の運転操業の革新~リモート支援技術の可能性
〇ポイント
⇒感想
〇グローバルリモートセンター:前方の机は、遠隔監視・操業に必要な情報をタイムリーに提供。モニタやヘッドセット等のデバイスが多く設置されている。後方の机はプラント設計者がデータ解析を行ったり、オペレーターの支援を行ったりする。設計者が必要とする情報を集中的に入手可能。
⇒フィールドに出る人、操作室で操作監視する人、操作室で意思決定する人、の役割が変わっていく。正社員、協力企業、そこで働く人のキャリアも多様になっていくはず。
〇データ解析プラットフォームでは、情報学や統計学の知識が十分にない技術者でも、プラントデータ解析が行える。GUIに優れたデータ解析ツールを採用
⇒概念を知った上で、ツールを使わないと、ツールに騙される。要注意。
〇中央制御室が必ずしもプラント内に構築される必要はなくなる(バーチャルコントロールセンター)
⇒フィールド作業がどれだけ減らせるか。プラントがどれだけ安定しているかが、これを実現するための克服課題だと思う。
〇プラント操業支援としてのモバイル端末。巡回支援、音声ナビ入力、位置把握。
⇒ローカル5Gに期待。でも、端末も通信もコストが高い。どれだけメリットがあるか精査が必要。人件費とデバイス費と通信費と。そして得られる効果は何か。
スマートフォン、タブレット、スマートグラス、それぞれ適材適所で使い分けることも考える。
〇クラウド上でデジタルツインによるダイナミックシミュレーションが実行され、プラントデータと共に、バーチャルコントロールセンターに伝えられる。バーチャルコントロールセンターでは、これらの情報に基づき最適な運転方法を導き出し、その結果を各拠点にプラント運転指令として伝える。各拠点は、プラント運転指令に従い操業する。
⇒実現するためには、安定化が前提条件だと思う。現場がバタついていたのでは、成り立たない。デジタル技術で抑制できるバタつきと、抑制できないバタつきを見極めて、それぞれ対応すること。
〇レポートによれば、経年劣化に関連した故障はわずか18%に留まり、残りの82%には別の原因があるとされる
⇒うちの現場はどうなっているだろうか。PMの実施レベルによっても、割合は異なってくるはず。また、故障の定義を明確しないと議論できない。変調を見つけて操業に影響しないようにメンテナンスした場合は、故障というのか、いわないのか。
〇ビジネス環境との統合
⇒運転データと経営データ(KPI)と同時に表示させる。何を見て、何をすれば、儲かるのかを考えて、設計すること
〇60%の従業員がリモートで働くことになり、少数精鋭のみがプラント内で働くことになる
⇒プラントに近いところで働く人の処遇は上がるのか、それとも、少数精鋭とはいえマシンの指示に従うだけの存在になるのか。どっちだろう。人とマシンとの業務分担を中長期的に考えてみる。ゴールとその過程の道筋を立てる。AI化学工場、人がやる仕事は、何なのだろう。一人が多様なことを思考しながらできる人の特性を生かした、業務分担は、どうなる。
〇「現場に行く前にアプリを開く」が当たり前の時代を迎えるだろう
⇒家でもスマホ、通勤でもスマホ、会社でもスマホ。スマホは体の一部となる。身体機能の拡張となる。
〇ゼロトラストネットワーク範囲を、HMI層に広げる
⇒確かに、これは安全だ。実現できれば。間にFWが入ることによる通信遅延が気になる。故障時のリスクも考慮しないといけない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
