
本屋大賞ができるまで(仮) 第2回
この4月に19回目の発表を終えた「本屋大賞」ですが、では「本屋大賞」はいったいどのようにしてできたものなのか? 「WEB本の雑誌」の「炎の営業日誌」で突然はじまった「本屋大賞ができるまで」の話をこちらにまとめて掲載して参ります。今回は2回めのまとめです。(本の雑誌社 杉江由次)
第2章 世界でいちばん熱い夜
第4話 実行委員会に立ちはだかる壁
実行委員会を立ち上げ、会議を開くにあたって最初にぶち当たった壁は、会議をする場所がないということだった。
「本の雑誌社さんじゃ無理ですよね?」
思い浮かんだ書店員さんに誘いの電話やメールを入れ、実際に会って相談しながら実行委員会のメンバーが決まってきた頃、博報堂の中野さんから会議をする場所について相談を受けた。
「本の雑誌社ですか...」
流れ的に本の雑誌社でするのが一番無難だろうし、ぼくも会社にいればいいだけなのでたいそう便利なことだとは感じた。
しかし問題は、本の雑誌社にそれだけの人数の人が入れるスペースがなかったのである。
実行委員というのは、複数の書店員さんに中野さんやシステムの志藤さんは外せず、それに連なる別の人たちもやって来る予定だった。どう少なく見積もっても15人...いや20人は集まるかもしれなかった。
ところが本の雑誌社にある共有スペースはアルバイトが使うテーブルしかないのだった。それは120センチ×210センチで、本の雑誌社では「大机」と呼んでいたけれど、丸椅子を8つ並べたら目一杯で、ここにどんなに詰め込んだとしても10人は座れないだろう。いやそもそも椅子が8つしかないのだった。
ということは椅子からあぶれた人たちは立って会議に参加することになってしまうのだが、そもそも狭い会社にはその立っている場所すらないのだった。
「三密」も「ソーシャルディスタンス」もまだ叫ばれていない時代だったが、それでもさすがにそんな場所で会議をするなんてとても考えられない。中野さんの問いかけにぼくは即座に「NO」と答えていた。
ではどこで集まるか。博報堂は田町と夜集まるには若干不便なところにあり、古幡さんのように迷う人が出てくるかもしれない。また不特定多数の人が入るにはセキュリティ上問題もあっただろう。いちばん簡単なのは居酒屋...ということになるだろうが、酒場でやっていたのでは議論は大いに盛り上がるものの、どこまで行っても酒飲み話の延長線を永遠に歩き続けることになるだろう。そこは一線を引いて真面目な打ち合わせにしなければならないと、ぼくも中野さんも気づいていた。
ならば貸会議室というのが無難だろう。実際に当時、それほどホームページが普及していないなかで、ぼくは「御茶ノ水 会議室」なんてワードを並べて検索したような記憶が残っている。ほんのちょっとだけ検索結果が画面に並んだけれど、そこには当然ながら料金というのがあるのだった。
第二の壁がここに立ちはだかることになる。
いったい誰がその料金を払うのか、ということだ。
まだその頃、名もない本屋大賞実行委員会は、有志の、というかよくわからぬ声かけに応じて、飲み会に集まるのとたいして変わらない心持ちで集まるような集団だったと思う。ぼくも中野さんもそれは同じだった。飲み会よりも少しだけ真剣に本や本屋さんや出版業界のことを語り合える。そんなワクワクする機会が得られる集まりであり、だからこれは本の雑誌社の仕事ではないし、博報堂の仕事でもない。個人的に面白そうと感じてるからやろうとしているだけだった。
そしてそもそもここからお金が生まれるなんて考えてもみなかった。あまりに考えなさすぎて、のちに叱られたり苦笑されたりもするのだが、とにかく誰ひとりとして仕事=ビジネスだとは考えていなかった。
貸会議室の料金が数千円だとしても、本の雑誌社がお金を出す、博報堂がお金を出すというのも何か違うように感じていた。
ただしそれを集まってくる書店員さんに負担してもらうというのもお門違いだと思った。なぜなら書店員さんたちも職務ではなく、交通費も自ら払い、しかも仕事の後に集まるいわゆる余暇というか無駄骨というか、その頃は何かに役立つとも考えていなかったから思いもしなかったけど、いわゆる「ボランティア」なのだった。
ぼくか中野さんのどちらかが負担するとしたらきっとぼくより給料を多くもらっているはずの中野さんになるだろうなあと検索結果の画面を見ていたところ、改めて中野さんから電話がかかってきた。
「昔、博報堂が神保町にあった頃のビルがそのまんま空いてるんですよ。神保町だったらみなさん集まりやすいですよね。そこが無料で使えるかもしれないので確認してみます」
それは神保町駅からほど近い神田錦町に建つ、博報堂第二別館と呼ばれる、後に建て替えの際には日本建築学会から「保存要望書」が出るような、アールデコ風な格調高い建物だった。
2008年に博報堂が赤坂Bizタワーに移転するまで、ぼくたちは何度もこの博報堂第二別館に集まることなるのだ。
第5話 書店員の時代がやってきた
もしタイムマシンが開発されたらぼくはあの日の会議の時間に戻って、音声レコーダーかビデオカメラを設置しておくことだろう。
2003年6月5日に開催された本屋大賞実行委員会の記念すべき一回目の会議は、のちに中野さんが「書店員さんたちがほんとにモチベーション高くて、意見が建設的で、終わったあとふだんの社内会議もこういう人たちだったらもっと前に進むのになあ」とこぼしたほど白熱した議論が取り交わされ、また古幡さんが「長かった、あの会議」と苦笑いを浮かべるほど、長時間に渡る会議だった。
仕事を終えた夜7時前、神田錦町にある博報堂第二別館と呼ばれる建物に、のちに本屋大賞実行委員会となるメンバーが三々五々集まった。入口にある守衛室で名前を記し、会議室のある三階へ階段で上がっていく。階段の手すりはまさしく歴史的建築物を思わせる堅牢なものだった。
そこに集まったのは書店員さん5人、博報堂の中野さんと嶋さん、それに中野さんの上司や部下、BDI(現在ユーピー)の志藤さんに、志藤さんの上司の秋山さん、楽天ブックスの出向から日本出版販売に戻った古幡さん、そして浜本とぼく。
まったくそれまで面識のなかった朝日新聞社の広告部の人たちもいた。中野さんが声をかけ、朝日新聞とも組んで何かできるのではと目論んでいたのだと思われる。どんな理由かわからないものの朝日新聞社の人が来たのは一回目の会議のときだけでその後やってくることはなかった。
さて、ここから古幡さんが長かったと苦笑いを浮かべる会議を再現しようと思う。思うけれど残念ながら記録がない。記録がないので記憶で書くしかない。それが残念でならない。ぼくの人生であれほどエキサイティングした会議は他になく、中野さん同様すべての会議がこうして行われるのであれば、会議ほど楽しいものはこの世にないと思ったほどだ。
僕の正面に5人の書店員さんが並んで座っていた。左から順にオリオン書房ノルテ店の白川浩介さん(31歳)、ブックファースト渋谷店の林香公子さん(29歳)、青山ブックセンター本店の高頭佐和子さん(31歳)、丸善御茶ノ水店の藤坂康司さん(44歳)、ときわ書房船橋本店の茶木則雄さん(46歳)だ。実行委員の呼びかけに即座に快諾してくれた人たちであり、みな毎日売り場に立つ書店員だった。
第1回会議が行われた2003年というのは、それまで右肩上がりだった出版販売額が96年を頂点に減少し始め、6年が過ぎた頃だった。いっときの出版不況ではなく、このまま売上が下がり続けるのではと気付き出した頃でもあった。
そんな中、気を吐いていたのが書店員による販促だった。その端緒となったのは、なんといっても書店員が書いた1枚の手書きPOPから大ベストセラーとなった津田沼のBOOKS昭和堂と『白い犬とワルツを』(テリー・ケイ/新潮文庫)の出来事だろう。
「本の雑誌」2001年9月号には「書店発、驚異のベスセラー」という記事が掲載されており、ちょっと長いがその時代の空気が伝わると思うので引用しようと思う。
新潮文庫の『白い犬とワルツを』が全国各地でバカ売れしていることをご存知だろうか。新刊ではない。九八年三月に文庫化された、すでに発売から三年以上を経過した既刊本である。初版三万部。なんとこの本がここ二か月で十五万二千部!も増刷、累計二十万を突破したというのだ。いったい何が起きたのか。
実は千葉県は津田沼の昭和堂という書店の木下さんという書店員がきっかけなのである。親本を読んで感動していた木下さんは、文庫化されてもあんまり動かない『白い犬』を見て、もっと売れるし売れるはずの本だと思い、この三月に、
〈妻をなくした老人の前にあらわれた白い犬。この犬の姿は老人にしか見えない。それが、他のひとたちにも見えるようになる場面は鳥肌ものです。何度読んでも肌が粟立ちます。〝感動の1冊〟プレゼントにもぴったりです!!〉
という手書きポップを立て、文庫の棚前で平積みを開始。その途端、一日で五冊が売れるようになったかと思ったら、日が経つにつれてどんどん売れ行きが加速するものだから、店内の一等地でどかーんと十二面積みを展開。四月に百八十七冊売れて、すごいねえと言っていたのが、五月、六月にはなんと四百七十冊を売って、全書店でトップの販売数にしてしまったのだ。
これを伝え聞いた新潮社も、おおっと驚いたのでしょう。さっそく木下さんの了承を得て、木下さんが作ったのと同じ文面のポップを手書きで作成、書店に配布して『白い犬』を強力プッシュ。その結果、全国の書店でどかどか売れているというのがことの真相なのである。
つまり一書店の一書店員が全国規模のベストセラーを、それも三年前の文庫で、生み出してしまったのである。いや『白い犬とワルツを』は単行本が九五年に出ているから、邦訳以来、正確には六年目にして火がついたことになるのだ。いや、なんともすごい話ではないか。
「ベストセラー、話題作ではない本の中にも面白い本があるという棚作り、平積みをしている」と木下さんは言うが、まさかここまでいくとは想像していなかったんでしょう。「普通、売れる本というと、宣伝がすごいとか、あるいは映画化テレビ化といった外からの要因がありますけど、この本の場合、外の力を借りずに、純粋にうちの店の力だけで売れたというのが嬉しいですね」と喜びを隠さずに話すのである。書店発のベストセラーということで、新潮社営業部も浮かれ騒いでいるらしい。
本が売れない売れないと嘆いてばかりが聞こえてくるが、嘆いてばかりでは始まらない。どこにベストセラーが眠ているかわからないのだ。全国の書店の皆さん、本を選ぶ目に自信を持って、どしどし仕掛けてみてはいかがか。たった一枚のポップと平積みにするだけで、次のベストセラーを生み出すのはアナタかもしれないのだ!
『白い犬とワルツを』はその後二十万部どころか百万部を軽く超える大ベストセラーになっていったのだった。
「本の雑誌」の呼びかけに応じたわけではないが、当時の「本の雑誌」を紐解くと、毎月のように書店発の取り組みが紹介されている。
●本邦初!?の人間ポップを発見(青山ブックセンター六本木店間室道子さんが名札の代わりにポップを胸につける)=2002年4月号
●第二の「白い犬」が渋谷にいた!?(山下書店渋谷南口店による遠藤周作『わたしが・棄てた・女」の多面展開)=2002年4月号
●裏百冊の夏はただいま開催中(パルコブックセンター吉祥寺店によるオリジナル夏百フェアの紹介)=2002年9月号
●来年の夏は「裏百」で対決しよう!(ブックファースト京都店での「夏の文庫、裏百選。フェアの紹介」)=2002年10月号
●ハチクロ応援団「自腹'S」登場!(山下書店本店の永嶋恵理子さんを団長に書店横断で『ハチミツとクロバー』を販促)=2003年4月号
●書店員の時代(扶桑社ミステリーフェア冊子「全国名物書店人が贈る12の傑作」フェア及び文教堂書店の「書店発!ベストセラー創造プロジェクト」の紹介)=2003年5月号
●第三回のチャンピオン本は何だ!?(紀伊國屋書店新宿本店の「チャンピオン本」フェアの紹介)=2003年7月号
●カリスマ書店員?(読売新聞夕刊の駅売店ポスターに「カリスマ書店員」という言葉が使われる)=2003年7月号
そして2002年5月号では「全日本書店員が選ぶ賞を作ろう!」と題して、『オリンピア』(あすなろ書房)という訳書についた「全米書店員が選ぶ2000年度売ることに最も喜びを感じた本賞受賞」と『スター★ガール』(理論社)の帯にある「全米書店員が選ぶ『2000年いちばん好きだった小説』」というコピーから、日本でも両賞を作ってくれと呼びかけてもいるのである。
2003年とは、「本の雑誌」の記事だけでなく、『世界の中心で、愛をさけぶ』や『天国の本屋』などたくさんのベストセラーが書店発で誕生していた時期だった。
たとえぼくらが本屋大賞を作らなくても、誰かが書店員が選ぶ賞を作る気運が高まっていたのだ。
第6話 新たな文学賞を作るのだ
これから本屋大賞実行委員会の第一回目の会議の話を書こうと思うのだけれど、まずはじめに記しておきたいことがある。
それは本屋大賞の仕組みを作った一番の功労者は、これは誰がなんと言おうと(誰もなんとも言わないと思うけれど)、ときわ書房本店の茶木則雄さんなのである。
茶木さんが実行委員に居なかったら本屋大賞はできなかった。いや「本屋大賞」はできたかもしれないけれど、今のような本屋大賞は絶対に生まれなかった。書店員として稀有な経験を持つ茶木さんという存在がなければ本屋大賞はできなかったのだ。
2003年6月5日、神田錦町の博報堂第二別館に集まったみんなの前に嶋さんが作った企画書が配られた。これを叩き台として議論を進めましょうということになったのだが、茶木さんは猛然と意見を主張した。
対直木賞としての書店員が選ぶ新たな文学賞を作る。直木賞に対抗するなら公明正大でなければならない。密室で選考委員が決めるのではなく、書店員なら誰でも参加でき、結果もガラス張りにして発表すること。文学賞であるからには単なる人気投票ではいけない。
茶木さんがそこまで「打倒直木賞」にこだわったのは、ミステリー評論家としても活躍していたからかもしれない。ちょうどその年に起きた横山秀夫『半落ち』に対する直木賞選考委員の評価と選評への怒りがあったのかもしれない。あるいはこれまで与えるべきと思われる本に与えられてこなかった不満が溜まっていたのかもしれない。
ただしそうは言ってもどの実行委員も茶木さんの意見をそのまま受け入れたわけではなかった。
まず一冊の本を選ぶということにオリオン書房ノルテ店の白川さんが首を傾げて反対意見を述べた。書店員が本を選ぶというのはおこがましいのではないかと。もちろん全ての本を平等に扱うことはできないけれど、たった一冊の本を全国の書店でブッシュするのは違和感を覚える、1冊選ぶのではなく30冊くらいのフェアにしてはどうかと提案した。
ブックファースト渋谷店の林さんや青山ブックセンター本店の高頭さんもその意見に頷いたけれど、丸善お茶の水店の藤坂さんが諭すように答える。30冊のフェアはもうすでにそれぞれのお店でやっている、それで今の状況ならばこれまでやったことのないことをやらないといけないと。
その賞はすべてのジャンルの本を対象にするのか、あるいは小説だけなのか。小説だけならば外国文学も同列に評価をするのか。疑問が浮かんだら誰もが立場や年齢や経験に関係なく率直に意見を述べた。それに対してまた別の視点で誰かが話す。その繰り返しが続いた。思い当たるたくさんのことが話し合われ、大賞作品を一冊選ぶ文学賞としての本屋大賞がかたち作られていった。
まず、この一年に出た国内小説の中でおすすめしたいものを三冊投票してもらう。それには一位、二位、三位と順位をつける。順位に即して点数が付随されている。その点数換算はどうするか。一位はこれだという想いが強くあるから、二位と三位よりも大きめの点が必要だなどと議論が展開され、それまで黙って聞いていたBDIの秋山さんが、日本カー・オブ・ザ・イヤーの採点方法(持ち点制)などを提案したりもした。
一回の投票では単なる人気投票となってしまうということで一次投票の上位作品をノミネート作とし、それを全部読んで二次投票をすることになったのだが、そのノミネート作を何作にするのかというのも激しい議論となった。
10冊というのが茶木さんの提案だったが、高頭さんが難色を示した。自分だってそうだが多くの書店員は薄給であり、誰でも投票できるというならば、アルバイトで働いている人に最大10冊も本を買わせるのは負担が大き過ぎるのではと。
しかし、茶木さんはここでも折れることはなかった。これは文学賞なんだからそれくらいの覚悟をもって参加してほしい。おれは20冊でもいいと思ってるくらいだと檄を飛ばした。
様々なことを茶木さんが提案し、みんなで議論していった。なぜ茶木さんにそれができたのかといえば、茶木さんには「このミス」を作った経験があったからだ。
阿佐ヶ谷の書楽でアルバイトを始めた茶木さんは、八千代台の良文堂書店で経験を積んだのち、神楽坂の入り口にミステリ専門書店「深夜プラス1」を1986年にオープンさせた。またそれと並行して、ミステリー評論家としての地位も確立し、数々の書評や解説を執筆していた。
ミステリー好きの人たちや出版業界の人たちが茶木さんの周りに集まるようになっていた。茶木さんはそういう人たちとともに第一水曜日に集まる飲み会「一水会」を結成し、ミステリーや出版業界の話を肴に酒を飲んでいた。
そんな中から毎年末、「週刊文春」で発表されるミステリーランキングへの不満がたまり、「このミス」が作られたのだった。それは本屋大賞ができる15年も前のことだ。
今回、この原稿を書くに際して、この辺りの経緯を茶木さんに確認すると以下のような返信が届いた。これは本屋大賞の本筋とは異なるけれど、ひとつの文芸のイベントの貴重な記録となるため、ここに転載しておく。
まず、「週刊文春ミステリーベストテン」に対する不満があった。毎年のように江戸川乱歩賞受賞作が一位になるのはおかしいではないか。
当時、文春のミステリーベストテンは日本推理作家協会員へのアンケートで決められていて(現在は「このミス」同様に、書評家や書店員、取次の人なども参加)その結果、協会員に最も読まれているであろう(江戸川乱歩賞は日本推理作家協会主催)、その年の乱歩賞受賞作が一位にきていた。
つまりは、作品の評価ではなく、読まれた数によって順位が決まっていたといっても過言ではない、と思っています。
そもそも作家は書き手のプロであって、読み手のプロとは言い難い。そんな背景があり、それなら、読み手のプロとミステリー愛好家で真のベストテンを選ぼうではないか、と。
ちなみに、一水会では一水会通信という小雑誌を制作していて(深夜プラス1の独占販売(笑))その別冊として、人脈を頼り書評家や大学のミステリー研究会に声掛けしてベントテンを選ぶつもりでした。
これをたまたま、会員でもある宝島の石倉氏が会社の企画としてあげたところ、その企画が通り、宝島社から出版することになった。というのが経緯ですね。
茶木さんは、文芸のイベントを考えるのは経験済だったのである。そして「このミス」に続いて「本屋大賞」を作った茶木さんの文芸書売り場での功績は、計り知れないのであった。
三時間を超えた会議は、最後にこの賞の名前を決めることに議論が移っていった、
会議室の脇に置いてあったホワイトボードに嶋さんがいくつかの候補を書き記す。
ブックショップアワード
書店大賞
本屋さん大賞
そこにサブコピーの候補も記される。「全国書店員が選んだいちばん!おもしろい本」と。
高頭さんがすくっと席を立ち、ホワイトボードに歩み寄る。
「私たち書店員は、本を読むプロではないから「おもしろい」と評価することはできません。その代わり、私たちは本を売るプロです。だから、ここは…と言って、「おもしろい」を消して、「売りたい」と書き換えた。
そして自らに呼称を付けるのはおかしいでしょうと言って、「さん」を消した。
ホワイトボードに残ったのは、「全国書店員が選んだいちばん!売りたい本 本屋大賞」という文字だった。
【高頭佐和子(当時;青山ブックセンター本店、現在:丸善丸の内本店)の回想】
あの頃の私は追い詰められていました。本屋の仕事は好きだ。続けたい。しかし本はどんどん売れなくなっている。会社は下っ端の私にもわかるレベルに経営難。どんどん人が辞めていく。自分も脱出すべき?しかしうまく逃げたとしても、無資格無能でか弱い私が、この先他の職業でやっていけるのか。まあ、そんな感じです。
そこで私がたどり着いたのは、「もっと本が売れれば良い」というシンプルな考えでした。本は面白い。それは間違いないので、そのことをみんなが知ってくれれば、ガンガン売れて将来不安からも解放されるはず、と思ったんですよね。
今当時の私に言ってやりたいのは「あんたって頭の中花畑?」ってことなんだけど、ブーブー文句だけ言ってるより、書店員として売り場でやってることを、みんなで協力してもっと大きな何かにできたら面白いじゃんっていう考えは間違いではなかった気がします。
どこかの出版社の会合の時にトイレで化粧直しをしながら、ブックファーストの林さんと「書店員のみんなで賞みたいなの、できたらいいね」という思いつきを話して、その後杉江さんに『本の雑誌』で1ページなんかやらせてよ、みたいな話をしました。しばらくして杉江さんから「例の話やろうと思うので、会議に来てください」と言われたものの、なぜ博報堂みたいなちゃんとした会社で華やかな仕事をしている人たちが、狭い売り場で本を売ってる地味な人間たちと何かやろうとしているのか、よくわからないままに参加したんですよ。
飲み会の延長のような会議でしたが、全員が自分考えや経験、疑問を遠慮なくストレートに出してきました。何も決まっていないところから、書店員なら誰でも投票に参加できるというたくさんの人を巻き込むシステムにみんなの気持ちがまとまったのは、そこにいた全員が「なんとかしたい」と言う気持ちを持っていたからなのではないでしょうか。日々店頭で感じている「こんなに面白いから、もっとたくさんの人に手に取ってもらいたいなあ」という気持ちを、「売りたい」というシンプルな言葉にして入れられたのも良かったと思います。
「本屋大賞」ってホワイトボードに書いたのは、誰だったかなあ。私だったような気もします。書店員大賞とか本屋さん大賞とかいろんな案が出た記憶がありますが、私としては「本屋」っていうのが一番しっくりくるんですよ。年配の方から赤ちゃんまで気軽に立ち寄れる親しみやすいイメージですよね。なのでめちゃめちゃ嬉しかったです。
その後いろいろ大変なことがあり、本屋を辞めるチャンスは何回もやってきました。あの会議がなかったら、違う人生を歩んでたかもしれないなあ、と時々思います。
【白川浩介(当時:オリオン書房ノルテ店、現在:リブロプラス商品部)の回想】
本の売上を生活の方便とする身からすれば不遜な話ではありますが、書店員になる前は平台一等地を占める「ベストセラー」には興味がなく、書店の利用法といえば自分の興味関心のある本を書棚で探すだけでした。書店員になって仕事として「ベストセラー」の重要度を認知するようになったものの、たまたま勤務する書店が、そばに圧倒的な集客力を誇る駅ビル内にある競合店(幸いなことに自社)があることを良いことに、その店との差別化を図る意味でもベストセラー以外の売上を稼ぐというスタンスの店だったので、仕事としても相変わらずベストセラーを追いかけるより地味に売り上げが上がる銘柄を見つけてチビチビ売って一人でニヤけているような男でした。
とはいえ、杉江さんから賞の創設のミーティング参加のお誘いメールをいただいた時は、なんか面白いことが始まる!とわくわくしたのをよく覚えております。わくわくしつつも、第一回目の会議の時から「ベストセラー創生」には後ろ向きで、「1冊を選ぶんじゃなくて複数冊で、フェア展開でも……」などと言って同業の先輩(茶木さん? 藤坂さん?)から怒られた記憶があります。今から思えば甘ちゃんです。
話し合いを重ねるうちにこの活動にのめりこんでいく訳ですが、(自画自賛にもなりますが)中野さんも書いておられます通り集まったメンバーが本当に建設的かつ頭の回転と手が早く、物事がどんどん決まっていくこと、そしてこれまで知り合うすべもなかった広告業界の方と真剣にお仕事の話が出来たこと、そして、出版社や取次の方たちと、お互いの立場を想像し敬意を抱きつつも妙な立場バイアス(取引先と被取引先)抜きの対等な立場で真剣にお話できたことが大きなモチベーションになりました。
本屋の店頭からベストセラーを作る、となると、自分の店単位の発想しかできなかった(何部仕入れて、××の売り場にフェイスはこれぐらいで積んで、手書きのPOPとパネルと…といった、規模は小さくても大事な事を積み上げていく方法)のですが、他業種の方の、最初から完成した大きな絵を描いて、現実とのギャップを知恵と工夫で埋めていくという手法も大いに学ばされ、刺激になりました。毎回のミーティングのたびに新たな発見と見識が得られた、幸せな時代でした。
【藤坂康司(当時:丸善御茶ノ水店、現在:名古屋市志段味(しだみ)図書館館長)の回想】
1980年代後半広島のフタバ図書で働いていたころ、当時は珍しかった、会社の垣根を超えた書店員同士の飲み会をしてました。啓文社の児玉さんを誘ってわざわざ尾道から広島まで来てもらったこともありました。その後丸善に転職してからは福岡、京都、名古屋でその町の書店員さんたちの飲み会に参加してました。お茶の水の丸善に異動したときも、おなじように「面白い=すごい」書店員さんを古幡さんに紹介してもらおうとおもったわけです。
その飲み会のあと、何日かたってからお店に杉江さんから電話があって、「書店員さんたちのつくる賞をつくろうと思うので、藤坂さんも参加しないか?」と誘ってもらいました。が、実は半年後に丸善を退職し書店員でなくなることが決まっていたので、そのことを杉江さんにだけお話して、半年間だけお手伝いをすることになりました。
博報堂さんでの会議に何回出席したか記憶が定かではありませんが、新しい賞の名前を「本屋大賞」とすることと、投票をインターネット経由とすること、書店員である証拠として取次の番線と書店コードを記入してもらうこと、発表のときに店頭に受賞作がならぶこと、とか決めたことを覚えています。茶木さんが「打倒直木賞」とか話されてたと思いますが、個人的にはそういう過激な表現はやめてほしいなあと思ってました。
あと、書店員が投票で決める賞にどういう本が選ばれるのだろうかと、まったく想像できなかったこと。どんな本が大賞になっても、その横に書店員の「私の本屋大賞」本を並べて売ってほしいなと思っていました。
そして、一番強く思ったのは、この賞の話がもっと早い時期に立ち上がっていて、お誘いがあったら、転職しなかっただろうなということです。結局半年後に偕成社に転職し、退職するまで一度も本屋大賞にはスタッフとして参加することはありませんでした。
退職後、図書館員になったとき、本屋大賞実行委委員に復帰しないかと声をかけられたのは嬉しかったです。16年ぶりの復帰でした。
【林香公子の回想】
第一回目の会議の頃、何を考えていたか、ということで思い出してみたのですが、売場で自分が出来ることは精一杯やってるつもりだったので他の人が売ってる本はどうして売れてるのか知りたかった。
売れると思ったポイントはどこなのか、私が気づいてないいいところを理解し、アピールすれば自分の店であんまり売れないこの本はもっと売れるんじゃないか? もちろん、大成功例は出版社さんより教えて頂いたり、なんなら複製ポップをいただいたりしていましたが、そこまでじゃない話を知りたいものよねー。
といったことや、個人の好き嫌いや善し悪しといったセンシティブさに触れる話じゃなくてもっと仕事の面白みとしての本とその中身の話をする場が選ばれし者しか集えない会合や飲み会とかじゃなくて希望したら誰でも参加できる形であったら素敵じゃないかとか、だったかと思います。
そんな気持ちだったので、他の人に売りたい本について聞けるんなら無理に順位はつけなくてもいいと思ってましたが順位がないことには人を動かす形にはならないというのもそりゃもっともな話でして。会議が進むにつれての後戻りできない感に面白いとは思うけどどうしよう? と青ざめる気持ちも若干。
とはいえ、まぁミーハー心だけで本屋に入り、右も左もわからないのをいいことに直木賞が受賞作なしだなんてその分の売上どうやって作れというのか、だの重版のタイミングがどーのこーの、などとそれまで好き勝手を言ってたことに対し、ここらで、役に立つ行動の一つもとってみろ、と突きつけられてたわけですから。
今まで何も考えずに口を開いててすいませんでした、と心の中であやまりつつ自分らで決める以上、不満なんかないようにしなきゃ、ってな、やけくそパワーがすごかったんだよな、確か。
【茶木則雄(当時:ときわ書房本店、現在:書評家)の回想】
本屋大賞立ち上げのための会議に参加するにあたって、私はあらかじめ二つのことを心に決めていた。
ひとつは、一回目の会議で必ず決着をつけること。
そもそも書店員は(想像以上に)忙しいうえ、シフトの関係で日程を調整するのが難しい。皆さん優秀で一家言ある人達が集まった多人数の会議は、会を重ねれば重ねるほど、収拾がつかなくなる虞がある。だから最初から一発勝負で、と考えていた。
二つ目は、選考過程の透明化、公正化をどう担保するかだ。単なる人気投票に終わっては、「これこそ書店員の選ぶ今年一番面白い本だ」という賞の創設意義が問われかねない。
そこで、議題が具体的な選考過程に及んだとき、私はかねて用意した腹案を提示した。
候補作は全国の書店員のアンケートで10作程度に絞り、最終選考においては参加者全員が候補作をすべて読んだうえで投票する。全部読んでいない人は投票に参加できない。というものだ。さらに、読んだという証明のため、参加者は10作すべてにコメントをつける。と、そこまで踏み込んだ。
当然、反対意見が様々あった。
曰く、候補作が出そろい最終投票までの一か月程度で、忙しい書店員が10冊すべて読むことは不可能だ。
曰く、それを強制しては、参加者が極端に限られてしまう懸念がある。
曰く、読んだという証明を求めるのは失礼ではないか。
そんな感じの意見であったと記憶している。
おっしゃることは、すべてごもっともである。現場の忙しさは私も長年経験して痛感している。こういう厳しい基準を設けると参加者が減る可能性が大いにある。また、読んだかどうかの証明に至っては、失礼極まりない。
しかし、公正性と透明性を担保するにはこれしかない、と思っていた。
予想された通り、議論は紛糾した。厳しい口調での文言も飛び交った、と記憶している。
その度に、為せば成る、という意味のことを私は発言した。ときに、為さねば成らぬなにごとも、という意味のことを口走った、ような気もする。ついには、成らぬは人の為さぬなりけり、と机を叩いたような気が、しないでもない。
いまや「昨日なに食べた」と訊かれても困惑する私である。20年前の記憶が曖昧なのは致し方ないところだろう。
とまれ、激しい議論の行方を眺めながら、「これは成功したな」と内心ほくそ笑んだ。
意見の相違はあっても、全員が前を向き、新しいものを自分たちの手で作り出そうという、熱意に満ち溢れていたからだ。
細かな修正はあったが、最終的に、私の提案したフレームが落としどころになった。アメリカの陪審員裁判と同じように、全員一致の評決であった。
と、あやふやな記憶で書き綴ってきたが、ひとつだけ鮮明に覚えていることがある。
その後の打ち上げ席だ。ここは幕末の松下村塾か適塾か、というほどの気概と熱気の中で飲む酒が、すこぶる旨かったことは、いまでも脳裏に焼き付いている。
執筆者プロフィール
杉江由次(すぎえ・よしつぐ)
浦和レッズと本をこよなく愛する本の雑誌社の営業編集企画宣伝担当。著書に「『本の雑誌』炎の営業日誌」(無明舎出版)、『サッカーデイズ』(小学館文庫)が、共著に『フットボールサミット第5回 拝啓、浦和レッズ様」(カンゼン)、『冬の本』(夏葉社)等がある。「URAWA MAGAZINE」にて「URAWA DAYS」連載中。本屋大賞の裏方。Twitterアカウント:@pride_of_urawa9

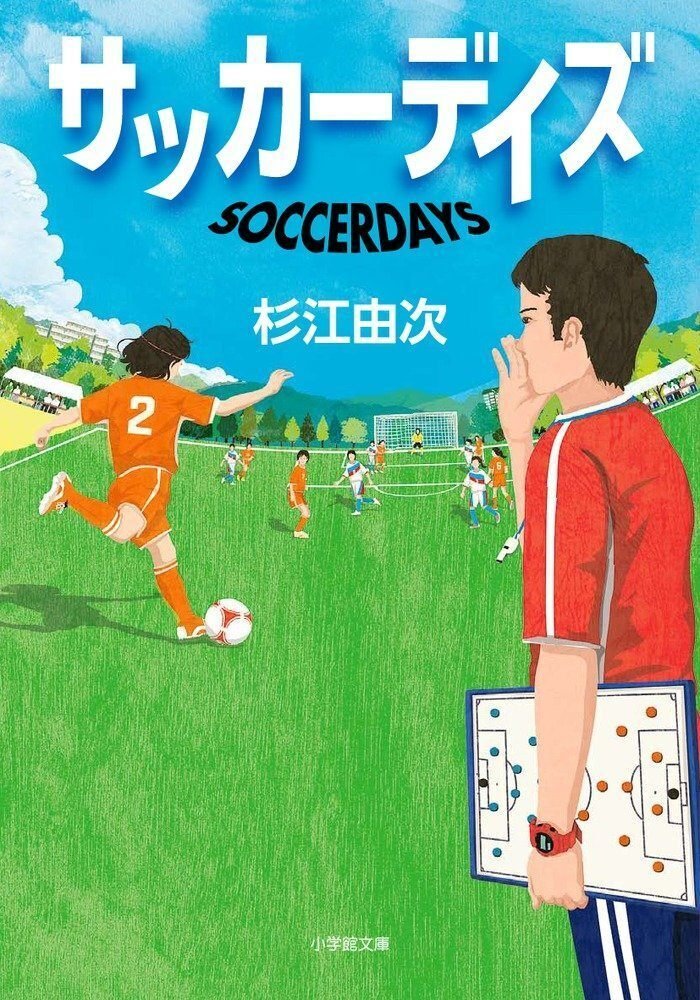
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
