
中国の金融リテラシーを変えたアントファイナンシャル-EC決済手段は如何に進化したか?
はじめに
世界のEC市場が注目を集める11月11日
支払いプラットフォームから金融サービスへの転換
消費者の使用状況に連動した金融サービスの進化
金融サービスの成長とともに成長した90年代生まれ
新しい資産形成の潮流
結びに
はじめに
中国で毎年開催される【11月11日-独身の日】、香港と上海で上場準備が進められている【アントグループ‐蚂蚁集团】、そして中国国内の若者のライフスタイルの変化。
一見すると何の関係性のない事象に見える3つですが、お互いに深くかかわりを持っており、この3点を紐解いていくことで今後の中国の消費市場の分析になりえます。
世界のEC市場が注目を集める11月11日
11月11日、中国ではもともと独身の日と定められておりましたが、その意味合いが変化を遂げたのは2009年からとなっております。2009年から11月11日は【双11】という名称で、中国国内で各ECプラットフォームで大々的なバーゲンセールやプロモーションの開催が恒例化しており、独身の消費層を狙ったイベントからすでに中国最大のECイベントの記念日となりました。

(13億個のEC小包が発送された2019年の11月11日)
【双11】はアリババグループ傘下の天猫Mallが中心に各ECプラットフォームやEC企業が参加しており、中国消費市場の成長を反映した急激な成長を遂げました。
天猫Mall【双11】1日の単独売上数からも、09年の8億1千万円から昨年2019年の4兆1804億円と5161倍もの成長を遂げました。日本楽天の2019年EC部門の年間総売り上げが3.9兆円とされており、中国【双11】の規模間が理解できると思います。

(各種公式資料より筆者作成)
【双11】はいわば中国のEC産業の成長、ひいては中国消費市場の拡大を表す一例といえます。もちろん中国全体の経済発展に伴い消費意欲や収支の面での余力があったうえでの消費といえますが、もう一つ消費需要、特に若年層の消費を刺激してきた要素があります。
天猫Mallを運営するアリババグループ、そしてアリババグループ傘下の【アントグループ‐蚂蚁集团】が提供するフィンテックサービスです。

(10月中旬から始まりつつある、【双11】の各種プロモーション。ライブストリーミングを放送を取り入れての、プロモーション活動が例年に増して積極的である。筆者作成)
支払いプラットフォームから金融サービスへの転換
2020年10月現在、アントグループは香港と上海の株式事業にて同時のIPOを進めており、IPO総額は現在の予想によると3兆6千億円にも達するとされています。IPOが完了した場合は、アントグループの企業価値は26兆円にも跳ね上がるとされており、JPMorgan の約4倍の企業価値となると見込まれております。
アントグループの中心となる業務は、アリババグループ内で使用されているプラットフォーム【アリペイ-支付宝】の運営と、アリペイと関連した各種フィンテックサービスの提供です。アリペイはもともとECを中心とするアリババグループの各種支払いために2003年に立ち上げられたサービスで、アントグループのとしての正式な立ち上げは2014年とされています。

(アリババ生態圏に紐づく各種サービスやブランド。ECから成長してきたこの生態圏の支払いにアリペイが用いられている)
ECなどのアリババが提供するサービスやキャシュレス経済でのアリペイを用いた消費が順調に拡大していきましたが、一つの課題を迎えることになります。キャッシングやクレジットといったサービスが中国国内の浸透率が低かったのです。

(2019年の段階でも人口1人当たりの発行額は0.5枚程度で、日本の1人当たり保有数3枚には遠く及んでいない。中国人民銀行およびJCB調査資料など各種公式資料より筆者作成。)
中国でキャッシングやクレジットといった信用情報に基づいた金融サービスが展開するにあたり、各消費者の信用情報をはじめとするリスク管理が必要になり、この時に金融サービスを展開し始めたのがアントファイナンシャルでした。アントファイナンシャルはアリババの創始者である馬雲氏の【銀行が変わらないのであれば、銀行を変える】という目標の下、2015年から金融サービスを拡大していきました。アントファイナンシャルが提供する金融サービスとしては【花呗】【借呗】【余额宝】が、中心となっております。

(ECや中国国内の決済に不可欠なアリペイのデータインフラの下、アントファイナンシャルは成立している。各種公式情報より筆者作成)
消費者の使用状況に連動した金融サービスの進化
2020年現在、中国国内のみでも10億のアリペイ個人ユーザーが8000万の企業及び店舗アカウントがアリペイを日々使用しており、各種金融サービスの運営に欠かせない消費者の情報が生成されています。この情報の蓄積が幅広い金融サービスの展開を後押ししました。

(ユーザーに紐づけられる信用スコア。ユーザーに公開されており、高い点数であるほど有益なサービスを利用できる。筆者の信用スコアより)
アントファイナンシャルが提供するキャッシングサービス【花呗】は、従来はアリババが運営する【淘宝-タオバオ】【天猫-Tmall】といったECサイト内での利用を目的に開発されていました。現在はサービス対象範囲を拡大し、各種支払いの際にキャッシングを行えるようになっています。
クレジットサービスを【花呗】が行うのに対し、【借呗】は現金の貸し出しそのものであるキャッシングサービスになっております。【借呗】によるキャッシングサービスはアプリ内で完結しているのと、銀行などの追加情報の登録が不要なことからキャッシングサービスへのハードルを大きく引き下げることにつながりました。
キャッシングサービスとクレジットサービスという形で消費者の選択肢を増やしたアントファイナンシャルですが、金融商品という形で資産の形成にも乗り出しております。多くのアリペイアカウントは銀行口座と紐づけられており、アリペイアカウントから直接【余额宝】に入金することによって、投資を行うことが可能になっています。投資によって得られた利益は1日単位で即座に引き起こしすることが可能になっており、その手軽さから【余额宝】は中国最大規模の金融商品になっております。

アリババのアントファイナンシャルのみならず、We chatの運営企業であるテンセントグループのテンセントクレジットなども中国国内で金融サービスを展開しております。両社ともに強力な情報収集網によって、金融サービスを下支えしています。
金融サービスの成長が変えた消費の方向性
アントファイナンシャルで運用されている資金の多くは、中国国内の金融機関がアントファイナンシャルに各種証券化して注入という形で、共存が図られています。アントファイナンシャルというプラットフォームの登場により中国の消費者、特にデジタル社会の到来とともに成長した90年代の消費は大きく変化することになりました。
日本では若者の消費力の低下や、一億総無欲社会の突入といったように、消費の中心層は若者から離れつつあるのではないかと、考えられ始めています。その一方で中国の消費の牽引は90年代生まれや80年代生まれが担いつつありました。月光族という言葉が生まれてからすでに10年以上たっておりますが、此の風流かつ皮肉な表現はすでに中国で市民権を得たといえるでしょう。月光族、それは月給を使い切ってしまうライフスタイル-生活様式です。
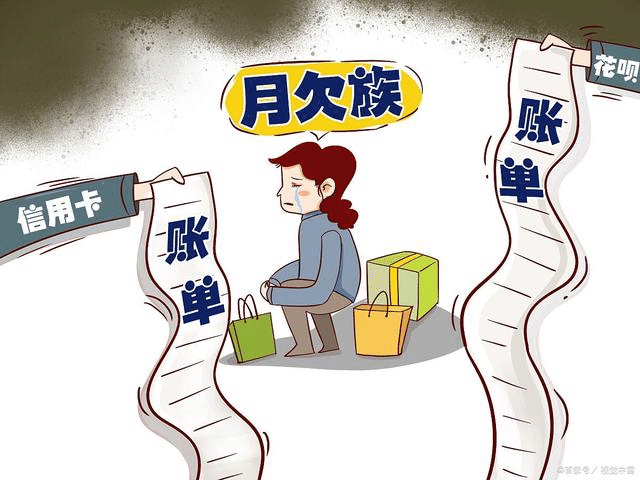
(2019年には中国人の平均負債額が13万元を超えたのではないかという報道がされた。もちろん住宅ローンの負債形状やずさんな計算に問題があったが、多くのメディアで議論された)
この月光族のライフスタイルの一助になっているのが、前述の【花呗】【借呗】ともいえます。使えば使うほどキャッシングやクレジットサービスでの優遇措置を受けることが出来るどう金融サービスは、使用障壁を押し下げました。

(2018年度に発表された、個人のクレジットサービスおよびキャッシングサービス金額の変遷)

(2018年発表の花呗使用者層の分析。同発表によると、90年代生まれの4人に一人が花呗キャッシングユーザと推定される)
中国はかつての日本と同じく、現金による貯蓄が中心で未来世代のための貯蓄文化を持っておりました。しかし時代の変化に伴い現在の中国ホワイトカラーの約2割が貯金を形成できていない、または借金があると回答しております。花呗及び借呗の使用者の95%は期限内のキャッシングやクレジットの返済を達成していますが、5%の層は利子が発生する負債を抱えていることになります。

(中国の都市部ホワイトカラーの年収は1万米ドル、約6万7千元とされている。今後の貯蓄動向は如何に?)
新しい資産形成の潮流
消費の上での変化をお話しさせていただきましたが、アントファイナンシャルがもたらした新しい資産形成-余额宝は、中国における資産概念を変えつつあります。従来は一定の資金を必要とする金融商品への投資が容易になったことで、金融商品を通じての資産形成が一般的になっているのです。

(2019年の段階で、中国国内の2人に1人がフィンテックによる金融商品を購入している計算となる)
特に前述の90年代生まれほど、余额宝による金融商品の購入に熱心であり、従来の銀行への預貯金といった形の資産形成は、今後重要度が低下するかもしれません。

(金額ベースでみても、90年代生まれは親世代よりも月1000元程、余额宝への投入額が多い)
金融リテラシーという点で見ると、中国の若年層の学習速度は、日本とは比肩できない段階に達しつつあるのかもしれません。
結びに
EC業界を支える機構として誕生し、消費の形態と資産形成の形態を変えつつあるアントファイナンシャル。中国社会の在り方を変えたこの存在は誕生して10年足らず。次の10年でアントファイナンシャルはどんな社会変革、価値観を中国にもたらすのでしょうか?
https://www.iimedia.cn/c400/63712.html
筆者連絡先
FB:https://www.facebook.com/profile.php?id=100004295732853
Wechat ID:YUKIKATOU888
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
