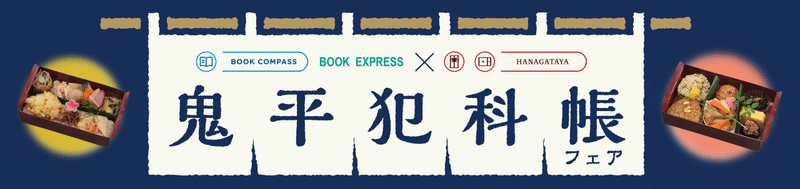「鬼平犯科帳弁当」第二弾 「佐嶋忠介弁当」発売・記念特典を特別公開!
3月22日(月)よりJR東日本の駅構内で「鬼平犯科帳」の世界を表現する弁当シリーズ第二弾、「佐嶋忠介弁当」「岸井左馬之助弁当」が販売されます。


掛紙には「鬼平犯科帳」からの名言がデザインされ、付録は人物相関図。食べてよし、読んでよし、鬼平の世界が広がる一折です。
「佐嶋忠介弁当」 1,080円(税込)
[ 献立 ]
貝柱かき揚げ、合鴨スモーク、蕎麦稲荷、筍と小海老をまとった春の鯛めし ほか
【取扱い予定店舗】※変更となる場合がございます
東京駅:HANAGATAYA東京中央通路、HANAGATAYA東京南通路弁当、HANAGATAYA東京北通路、HANAGATAYA東京八重洲南口、HANAGATAYA京葉ストリート
品川駅:膳まいエキュート品川サウス
上野駅:膳まい上野中央連絡通路、HANAGATAYAエキュート上野
また、BOOK COMPASS、BOOK EXPRESS、bookshelfにてフェアも開催しております。詳細は下記バナーからご覧ください。
販売を記念して、文春文庫『鬼平犯科帳 決定版』より二話を特別公開! こちらの記事では鬼平の部下・佐嶋忠介が活躍する「浅草・御厩河岸」を期間限定公開します。
どうぞお楽しみ下さい。
◇ ◇ ◇
浅草(あさくさ)・御厩河岸(おうまやがし)
一
現代(いま)の隅田川へ架(か)かっている厩橋(うまやばし)。これが明治二十六年に架設される前には舟渡(ふなわた)しで、俗に〔御厩の渡し〕とよんだ。
幕府御米蔵(おこめぐら)のたちならぶ西岸から東岸の本所へ、大川をわたるこの渡船は一人二文(もん)、馬一疋(ぴき)についても二文の渡銭(わたしせん)をとったそうな。
御米蔵の北端、堀端をへだてた浅草・三好町(みよしちょう)の河岸が渡船場で、これを〔御厩河岸〕という。むかし、このあたりに幕府の馬屋があったところから、この呼び名がついたのであろう。
そのころ。
渡船場に面した三好町の角に、〔豆岩(まめいわ)〕という小さな居酒屋があった。
主人は五尺に足らぬ小男で、年のころは三十五、六。名を岩五郎(いわごろう)ときけば、この店の名のいわれも知れようというものだ。
もっとも岩五郎は店の横手へ葭簀張(よしずば)りの、もう一つの店を出していて、ここに手製の草鞋(わらじ)やら大ふく餅やらをならべ、いつも一人で店番をしている。
居酒屋の方は、女房のお勝(かつ)が小女(こおんな)ひとりを相手にてきぱきと切りまわし、酒の燗(かん)から庖丁(ほうちよう)をとっての肴(さかな)つくりまで汗みずくになってはたらきぬく。
お勝はもと品川の宿場女郎あがりだとかで宇吉(うきち)という男の子を連れ子に、その上、盲目の老母までともない、岩五郎の女房になったというが、年齢は四十一歳。色のあさぐろい痩(や)せぎすの躰(からだ)を、それこそしぼりこむようにしてよくはたらくわけだが病気ひとつせず、いまは岩五郎との間にもおじゅんという女の子をもうけている。
連れ子の宇吉は去年、十二歳になった春に、芝・田町九丁目の紙問屋で大和屋作兵衛方へ丁稚(でっち)奉公にあがり、五歳になるおじゅんの世話をしながら、店の奥へ引きこもっているのがお勝の母親・お八百(やお)であった。
寛政元年夏の或る日のことであったが……。
「まことに、どうもすまぬが……み、水をいっぱい……」
垢(あか)と汗とほこりにぬりつぶされたような乞食坊主が〔豆岩〕のもう一つの店の前へよろめくように来て、丁度、店番をしていた岩五郎へたのんだ。
こころよく水をのませ、さらに岩五郎が、いくらかの銭を紙に包んであたえると、老(ふ)けた乞食坊主はむしゃぶりつくように、これをつかみとってふところへ入れたものだが、それから凝(じっ)と岩五郎の顔を見つめ、
「ふうむ……」
かすかに、うなった。
「おれの顔に何かついているのかね、坊さん」
「おう、ついとる」
「何が、ついてるね?」
「長生きの運命(さだめ)がついとる」
「ほう……嘘にも、ありがてえことをいって下さる」
「嘘はいわん!!」
坊主が叫んだ。真剣そのものの叫びであった。岩五郎がちょっと呆気(あっけ)にとられていると、さらに坊主が、
「お前さん、おかみさんのいいのをもらいなすったね。その、おかみさんが福をもって来た」
「ほほう」
「ちがうかえ?」
「いや、ちがわねえ」
「お前さん、義理の親ごさんと暮していなさるね。父(てて)ごか母ごか……どっちにしろ、そのお人は、どこか躰が悪い。足か手か……いや目でも悪いのじゃあないかえ」
ぴたり当てられたときには、岩五郎も瞠目(どうもく)した。このあたりでは全く見かけない乞食坊主だけに、である。
「ただし、迷っちゃあいけないよ」
坊主、厳然(げんぜん)となって、
「いまの暮しの基盤(もと)になっていることに、そむいちゃあいけない」
と、いった。
岩五郎はごくりと唾(つば)をのんで、坊主を見返し、
「いまの暮しのもと……」
つぶやくように洩(も)らすと、
「左様さ。では、ありがとうよ。ごめん、ごめん」
「あ……ちょっと待って下せえ」
「何かな?」
「よく当んなさる、おどろきました」
「人相、手相、易(えき)までみんな、わしのは当るのさ」
「では、坊さん。お前さんの……」
「わしのことか、ふ、ふふ……あまり当りすぎるのでいかぬのよ。いいことがあると出れば怠(なま)けてしまい、悪いと出ればあきらめてしまう。易者(えきしゃ)くずれが、こんな恰好(かっこう)で物乞いして歩く始末になるやつは、みんなそれさ」
岩五郎が去りかける老人に大ふく餅をあわてて包んだが間に合わなかった。
ようやくにたちこめてきた夏の夕闇の中へ、乞食坊主の姿は溶(と)けこみ、もうどこにも見えない。
夜になり、岩五郎は女房をたすけて居酒屋のほうではたらく。近くの武家屋敷の中間(ちゅうげん)たちや、船頭、人足などが遅(おそ)くまで酒をのみに来るので相当な繁昌(はんじょう)ぶりなのである。
夜ふけて、店を仕舞った夫婦が行水(ぎょうずい)をつかい、奥の一間で仲よく寝酒をやる。老母のお八百が目ざめると、岩五郎が茶をいれてやる。お八百がうれしげに息子夫婦へはなしかける。おじゅんは健康な寝息をたてている。岩五郎が女房の連れ子で奉公に出ている宇吉のことを心配する。お勝がよろこぶ。
まさに、乞食坊主の指摘(してき)そのもののような庶民団欒(だんらん)の図といえよう。
「そりゃあそうと……夕方にね、妙な坊さんが、おれの人相を見てくれて……」
岩五郎が語りかけたとき、戸締りをした店の戸を叩く者があった。
お勝が土間へ出て行くのを見送った岩五郎の団栗(どんぐり)のように小さな両眼が、白く光った。
このときの彼の眼の光は、山林の闇の彼方の得体(えたい)の知れぬ物音へ相対する獣(けもの)のそれであった。
お勝が戻って来た。
「お前さんの知り合いだって……」
「そうかえ」
立ち上った岩五郎の眼は、やさしく笑ってい、いつものおだやかな口調で、
「先に寝ていな」
と、いった。
岩五郎は、その知り合いと店の外で立ちばなしをしていたようであるが、それも、お勝が床(とこ)をとり終えるか終えぬうちに、もう戻って来た。
「中へ入ってもらえばよかったのに……」
「なに、大した用事じゃあねえ」
お勝は、亭主の知人だという老爺(ろうや)の、どこかの寺男ででもあるような温和で実直そうな風貌をちらっとおもいうかべたけれども、「どこの人?」とも問わなかった。
岩五郎の何事にも親身な性格は当然、彼の顔をひろくしていたし、こんなことはいつものことなのである。
床へ入ってから、岩五郎がいった。
「お勝、明日はまわって来るよ」
まわるというのは、緡(さし)売りに出ることをいうのだ。
当時の銭は〔穴(あな)あき銭〕であるから、これを藁(わら)でよった緡へ差して束(たば)ねておく。この緡の内職は火消役屋敷の小者の内職なのだが、岩五郎はこれを仕入れて売り歩く。以前は中間(ちゅうげん)自身が売り歩いたものだけれど、恐持(こわも)てにまかせて押し売ったりするものだから、近年は取締りがうるさく、したがって中間どもも、岩五郎のような男に売らせることが多くなって来ていた。
三日に一度ほど、岩五郎は〔もう一つの店〕の店番を義母とおじゅんにまかせて、緡売りに出る。盲目ながら、お八百はりっぱに店番をつとめた。
岩五郎の緡売りは、本所・浅草・日本橋から麹町(こうじまち)あたりまで足にまかせて売り歩くものだから、十把(ぱ)一束(そく)百文の商(あきな)いでも、ばかにならない。
翌日の昼下りに……。
緡売りに出た岩五郎が、浅草・福富町の浄念寺境内(けいだい)で、昨夜おそくたずねて来た〔知り合い〕の老爺と会っていた。
ひろい境内の木立に、蝉(せみ)が鳴きこめている。
老爺は、まさに、この寺の寺男であった。
「昨夜は突然で……びっくりしたろうねえ、岩さん」
と、老爺が人影のない本堂の裏手へ岩五郎をさそいつつ、いった。
「彦蔵爺(とっ)つぁん。よくわかったな、おれのところが……」
「蛇(じゃ)の道はへびよ。一月(ひとつき)ほど前に、お前が緡売りに出ているところを、ひょいと見かけてね」
「そうかえ。ま、ずいぶん爺つぁんとも会わねえ。七、八年にもなるか……いったい、どこにいなすった?」
「中国すじから上方(かみがた)にのう。ところで、岩さん。まさかお前、堅気(かたぎ)になったのじゃあるめえな?」
「何か、うめえ仕事でもあるのかえ?」
「乗るかい?」
「乗るともさ」
「うむ……お前なら気づかいはねえ、と思ったので声をかけてみたのだ。よし、お頭(かしら)に会わせよう」
「どこの親分(たいしょう)の下で、はたらいていなさるのだ?」
「ま、ついて来ねえ」
二
浅草から約一里半。
目黒不動堂の北面、下目黒村の百姓地の一角で、こんもりとした雑木林(ぞうきばやし)の中にある物持ちの隠居所のような家へ、彦蔵は岩五郎を案内したのである。
古びてはいるがつくりもしゃれているし、庭に面した一間(ひとま)へ通されながらも、種々の調度へ眼をやりながら、
(こいつは、大した親分らしい……)
岩五郎の胸が躍(おど)った。
岩五郎の場合、親分とは〔盗賊の首領〕を指している。
ここで、彼の生いたちにつき、いささかのべておかねばなるまい。
岩五郎も盗賊の子に生まれた。
父親の卯三郎(うさぶろう)は、越中・伏木(ふしき)の生まれで、女房のおまきとの間に岩五郎をもうけると、妻子を高岡の町に住まわせ、自分は薬の行商に諸国をまわるという暮しをはじめたが、むろん只(ただ)の行商ではない。
そのころ卯三郎は、上方一帯から近江へかけて〔盗みばたらき〕をしていた中尾の治兵衛という盗賊の首領の配下であったという。
こうした連中のだれもがそうであるように、卯三郎も晩婚で、岩五郎が生まれたときには四十をこえていた。
「なんとか、まとまった金をこしらえて、あとは死ぬまで、もう何もせずに親子三人、のんびりと暮してえものだ」
と、卯三郎は行商へ出るたびに女房に洩らしたが、おまきは亭主を薬の行商人だと信じてうたがわない。
卯三郎の親分(たいしょう)は、盗賊のうちでも中の下ほどのところで、あまり大仕事はやらぬ。
それだけに、卯三郎の手へ入る金(もの)もそれ相当なもので、
(もう少し稼いでから……)
おもいおもいするうち、岩五郎が八歳の夏に、おまきが病死をしてしまった。
卯三郎が、せがれをつれて江戸へ出たのは、この後のことで、それでも死んだ女房が七十両に近い金をためこんでいてくれたそうな。
卯三郎は、この金を元手にして〔独立〕することにした。
つまり、ささやかながらも配下を抱えて盗賊の首領に独立したのである。
盗みといっても、衝動(しょうどう)にまかせての乱暴な押しこみ強盗ではない。
真(まこと)の盗賊のモラルは、
一、盗まれて難儀(なんぎ)するものへは、手を出さぬこと。
一、つとめするとき、人を殺傷せぬこと。
一、女を手ごめにせぬこと。
の三カ条が金科玉条(きんかぎょくじょう)というもので、これから外(はず)れた、どこにでもころがっているような泥棒を真の盗賊たちは「あさましい」と見るのである。
なればこそ、盗みすることを、つとめするなどといい切ってはばからぬのだ。
またそれだけに仕事もむずかしく、大盗賊になると十年がかりで、ねらいをつけた商家や寺院へ網(あみ)をかける。この間の投資もなみなみのものではないのだ。
五十に近くなった卯三郎が、八人の配下を抱えて独立するためには、七十両の金も充分(じゅうぶん)ではない。
「もう少しの辛抱だ。なあに、いつまでもお前を放っておくものじゃねえ」
卯三郎は行商人としての別の顔で近づきになっていた京橋・西紺屋町の線香問屋・醒井屋(さめがいや)甚助方へ、岩五郎を丁稚(でっち)奉公に出した。
故郷の越中にも、
「親類ひとり、いるわけじゃねえ」
卯三郎だったからである。
こうしておいて、彼は上方へ飛んだが、肝心(かんじん)の〔おつとめ〕のほうは失敗つづきだったらしい。
二年ほどして一度、
「もう少しだから、辛抱しておくれよ」
江戸へ戻って、岩五郎にも会ったが、以来、ぷつりと消息を絶った。
こうした親をもち、身よりの者ひとりすらいない江戸で暮している少年が、どのような成長ぶりをしめすことか、あらためていうまでもなかろう。たとえば年に一度の休みにも帰って行く家がなく、待っていてくれる人ひとりいないのである。
醒井屋の主人も、
「実直そうな卯三郎の子だというので引き取ったのだが、どうも並はずれの強情者の上に陰気でいけない。また親も親じゃあないか。江戸に親類も三人ほどいるといっていたが、まるで嘘だよ。どうもね、薬行商の男の子なぞというものは……ああ、引き取るのじゃあなかった」
と、いいはじめる。
岩五郎は、いざ反抗するとなると主人の小言にも決してあやまろうとはせず、団栗眼(どんぐりまなこ)を白く光らせ、主人でも番頭でも臆するところなく睨(ね)めつけ、口もきかぬ。
そのころから岩五郎は「豆岩」とか「ちび岩」とか呼ばれてい、小男だという劣等感にさいなまれて何度も自殺をおもいたったほどであった。
それでも七年間、奉公をした。
醒井屋のすべての人びとから疎(うと)まれ、嫌(きら)われつくし、
(もう、これまでだ……)
十六歳の暮れの或る日。
小売店の集金にまわり、手にした十五両余の金を持って、岩五郎は二度と醒井屋へは戻らなかった。
あとはもう、無頼(ぶらい)の徒と成り果てるよりほかに道はない。
品川の宿場にいる香具師(やし)の世話になっていたころ、岩五郎は宿場女郎のお勝と知り合ったらしい。
六歳も年上のお勝は、岩五郎にとって姉でもあり母でもあり、さらに恋人でもあった。
このままで数年を経過していたら、岩五郎の人生もまた別のものとなっていたにちがいない。
ところが……。
品川へ来た翌年の冬に、折からの雪の中を宿場へ入って来た見すぼらしい旅の老人と、道でばったり出会ったとき、岩五郎はおもわず叫んだ。
「と、父(とっ)ちゃんじゃあねえのか……」
まさに、卯三郎である。
普通ならば、わが子を放(ほう)り捨て同然にしてしまった父親へ、なつかしげに声をかけるまでもない。けれども岩五郎の脳裡(のうり)には、高岡の町の小さな家で旅から帰って来たときの父と母の、いかにも仲むつまじい団欒があざやかに、強烈にしみついている。
また卯三郎も、そのころは、なめしゃぶるようにして、たった一人の息子を可愛がったものであった。
「おれが故郷(くに)じゃあね、しんこ泥鰌(どじょう)といって、小ゆびほどの小せえ泥鰌がとれる。父ちゃんは、こいつを鍋(なべ)へ入れてね、ごぼうをこう細く切って、味噌の汁をつくるのがうめえのさ。大きい鍋にいっぱいこしらえてよ。おっ母と三人で、ふうふういいながら何杯も汁をすするんだ」
と、岩五郎が双眸(りょうめ)をかがやかせて、お勝に語ったことがある。
それだけに、
(父ちゃんは、きっと仕事がうまく行かねえのだ)
信じてうたがわなかったし、事実、その通りだったのだ。
声をかけられて、卯三郎は笠をはねのけ、渋紙色の皺(しわ)ぶかい顔をゆがませ、
「お前、岩じゃあないか……」
泥雪の中へ、へたりこんでしまったものだ。
そして、息子の現状を見た卯三郎は、ついにおのれの〔本体〕を打ち明け、他人を入れずに父子ふたり、うらみをかけた醒井屋へ押込み、金百四十余両を盗み取ったのが、岩五郎の〔この道〕へ入るきっかけとなったのである。
以来、十七年。
いまは居酒屋〔豆岩〕の亭主となった三十五歳の岩五郎だが、父親はまだ生きているのだ。
だが、そのことをお勝もお八百も知ってはいない。
三
はなしをもどす。
下目黒村の風雅な家に、岩五郎を迎えたのは、五十がらみのでっぷりと肥(こ)えた老人で、色白のふくよかな顔貌はあくまでもやさしげに、長者の風格さえそなわっている。
彦蔵爺が、
「岩さん。お頭(かしら)でいなさる」
と引きあわせるのを受けて、
「海老坂(えびさか)の与兵衛(よへえ)でござる」
老人が名乗った。
岩五郎は目をみはった。
海老坂の与兵衛は、岩五郎と同じ越中の生まれで、父の卯三郎が元気で〔おつとめ〕をしていたころから、すでに親子三代にわたる盗賊界の名門? であって、
「おれも、こんなに耄碌(もうろく)する前に、一度でいいから海老坂のお頭の下ではたらいてみたかったよ」
と、卯三郎がよくいったものだ。
まさに大盗賊の典型で、盛りには八十余名の配下をあやつり、諸国を股にかけて大仕掛けな〔盗みばたらき〕も数カ所にわたって同時におこなったといわれる。
「盗む者も泣きを見ず、盗まれる者も泣きを見ず」
という大盗賊の〔理想〕をつらぬき通し、老齢に達した配下は次々に身をかためさせて二度とこの道へ引き入れず、五十余年の生涯に捕縛された配下はわずかに五名。それも決して頭領・与兵衛の隠れ家の組織をもらすことなく死罪をうけている。
「彦蔵どんとは、前に一緒だったそうだねえ」
と、海老坂の与兵衛が、いつくしみをこめた眼(まな)ざしで岩五郎を見やりつつ、
「お前さんのことも、お父(とっ)さんのことも、うわさにはきいていましたよ。卯三郎どんは元気だそうだね」
「はい。元気というわけにはまいりませんが、細々と生きております」
「いくつになんなすったね?」
「七十六でございます」
「へえ、そりゃまあ、めでたいことだ」
「ありがとう存じます」
「むりにはすすめないが、乗って見なさるかえ?」
「私でお役にたちますことならば……」
「たのみます。人手がなくてねえ。ま、この年になっていまさらとも思うが……なかなか死にそうにもない。いえばまあ最後のおつとめで、一度は散り散りになった手下の者を全部あつめるのも面倒なので、こぢんまりと十五人ほどでやりたいとおもっているのだが……」
「へえ、へえ……」
多勢の配下の面倒を見つくしてきただけに、海老坂の与兵衛は、これからわが身の余生を送るための金が不足になってきた、と、後で彦蔵が語った。
「あのお頭のおかげで、おれたち仲間がどれだけ畳の上で死ねたか知れやあしねえのだものね。おれもこの年で、いまさらと思ったのだけれど幸いに身一つだし、ろくなはたらきは出来ねえが……なんとか、与兵衛親分の役に立つような人をと思い、手づるをたぐっていたところ、丁度お前を見かけたというわけさ」
と、彦蔵はいった。
すでに、ねらいはつけてある。
本郷一丁目の醤油酢問屋(しょうゆすどんや)・柳屋吉右衛門(きちえもん)という富商がそれで、三年も前から飯たきの下男として善太郎という中年の配下を奉公させている海老坂の与兵衛であった。
このほかに佐助という配下を按摩(あんま)に化けさせて柳屋へ出入りをさせている。これも二年がかりで、いまは佐助も柳屋の主人夫婦の気に入られて、泊りがけでもみ治療をすることもめずらしくない。
もちろん、佐助はりっぱな按摩として通る技術の持主だし、盲目の演技も堂に入ったものだ。
この二人のほか七名ほどが、むかしからの配下で、あとの六名は彦蔵があつめた者らしい。
「お前さんに恥をさらすようだが、柳屋の金蔵(かねぐら)の錠前(じょうまえ)は一寸(ちよっと)むずかしくてね。以前に私のところにいた平十という男なら、どんな錠前でもあけられたものだが、いまはもうあの世へ行ってしまったものだから……」
いいつつ、海老坂の与兵衛が数枚の図面を出して岩五郎の前へひろげた。
いずれも、飯たきになって住込んでいる善太郎が描いたもので、柳屋の屋内屋外の平面図から、蔵の錠前の図まで精妙をきわめた筆致(ひっち)であった。
「なるほど……」
岩五郎は息をのんだ。
錠前外しの技術は至難のもので、大きな商家になればなるほど精巧な錠前を使用してい、それが二重三重になっているから、なまなかな盗賊ではあしらいかねる。
何年かかっての計画でも錠前があかなくてはどうにもならぬ。
それなら、店の者へ白刃をつきつけ、鍵を出させて蔵の扉を開けさせればよいのだが、そこはそれ、真の盗賊はちがうのである。
ねらいをつけた家の人びとが安らかに寝息をたてて朝を迎え、しばらくしてから、
「あっ……盗(と)られた」
と、仰天(ぎょうてん)するのでなくてはならぬ。
戸の隙間から微風のように入り、また微風のように出て行く。
なればこそ綿密(めんみつ)な計画も必要であるし、腕利きの配下もほしいのである。
近年は、白刃をぬきはらって押し入り、脅(おど)したり殺したり、女と見れば盗みの最中にこれを犯(おか)し、暴力にまかせての盗賊団が横行している。
そのことを熟知している岩五郎だけに、
(うわさにたがわぬ立派なお人だ)
じゅんじゅんと計画を語る海老坂の与兵衛の顔貌に、声に、おもわずうっとりと酔ってしまっていた。
一時は、上方すじの大親分のもとで、錠前外しには折紙をつけられた岩五郎だけに、目(ま)のあたりに見る巨賊の風格に魅(み)せられ、
(ふうむ……このお人のためなら、なるほど命がけではたらく手下も出る筈だ)
感にたえている。
与兵衛は彦蔵を信じ、いったん信じたとなると彦蔵が連れてきた岩五郎にもむかしからの配下と同様の信頼をかける。
もしも、そむかれて自分の身が危険になる、ということなどは考えても見ない。
このあたりが並の首領とはちがうところで、その度量(どりょう)の大きさは、岩五郎から見ても判然とする。
「この錠前のことを、たのみましたよ」
彦蔵と共に辞去するとき、海老坂の与兵衛が軽く頭を下げて、金十両を半紙に包み、
「まだ会ったことはないが……卯三郎どんに、みやげでも」
と、岩五郎へわたしてよこし、
「仕事(おつとめ)は、秋の風が吹きはじめてからだがね」
といった。
その夜、家へ帰った岩五郎は、めずらしく眠れないらしく、お勝は彼が輾転(てんてん)と寝返りをする気配を夢うつつに知って、朝になってから、口には出さぬが、
(どうも変だ。うちの人、なにか心配事でもあるのかしら……?)
ちらと不安をおぼえたが、それも一日きりで、以後の岩五郎の日常には変化もなく、相変らず、苦労をしつくしたもの同士がたどりついた団欒(だんらん)は小ゆるぎもしなかった。
あのとき……。
品川宿でなじんだ岩五郎が突然に消えて後、三年を経てから、お勝は高輪北町に住む大工の弥吉に落籍(ひか)されて女房となり、宇吉を生んだが、間もなく弥吉に死なれ、盲目の母と子を抱えて苦労をしたあげく、品川の〔みなとや〕という小店(こみせ)から二度のつとめに出た。
二十八になった岩五郎と再会したのも、やっぱり品川においてであった。
四
たちまち、夏はすぎた。
寛政元年八月(現代の九月)下旬の或る日のことだが……。
この日も緡(さし)売りに出た岩五郎が、回向院(えこういん)門前を歩いていると、すれちがった侍(さむらい)が岩五郎だけにわかる眴(めくばせ)をし、そのまま急ぎ足で後もふり返らずに竪川(たてかわ)の方向へ行く。
歩みつつ、侍は手にした笠をかぶった。
かなりの距離(きょり)をおいて、岩五郎は、この侍の後にしたがった。
侍の名を佐嶋忠介(さじまちゅうすけ)という。
佐嶋は、御先手組(おさきてぐみ)の与力(よりき)をつとめている老巧の人物である。
大川へながれこむ掘割りの竪川に、夕陽がにぶく光っていた。
佐嶋忠介は、わき目もふらずに二ツ目橋をわたり、深川へ向う道をすすむ。
このあたりには、旗本屋敷や大名の下屋敷が並んでいるけれども、草地や雑木林も多く、まだまだ江戸郊外の名残(なご)りを色濃くとどめている。
あまり、人影もなかった。
佐嶋与力が、つと林の中へ切れこんだ。
その姿を遠くから岩五郎はみとめている。
岩五郎は歩みの速度を尚もゆるめ、間怠(まだる)いほどの時間をかけてから雑木林へ分け入った。
林の中に、佐嶋忠介がたたずんでいる。
「かわりもないかな?」
と、岩五郎を迎えた。
「へい、おかげさまをもちまして」
「卯三郎も達者か?」
「どうやら、少しずつでございますが手足もうごくようになりまして……」
「そりゃあよかった」
笠をぬいだ佐嶋が、五十二歳にしては若々しく見える温顔をほころばせて、
「ときに……」
「へ?」
「この春には大手柄(おおてがら)をたてたそうだな。布引(ぬのびき)の九右衛門(きゅうえもん)一味をことごとく御縄(おなわ)にすることができたのも、お前の、かげながらのはたらきが大きかったと、先日、長谷川様も大層におよろこびであったぞ」
「左様で……へい、もったいねえことでございます」
佐嶋与力が長谷川様といったのは、火付盗賊改(ひつけとうぞくあらた)メの長谷川平蔵宣以(のぶため)のことだ。
火付盗賊改方は、町奉行所とは別の、いえば一種の特別警察のようなもので、すこぶる機動性に富み、江戸市中内外の犯罪を取締ることはもちろん、いざとなれば、自由に他国へも飛んで行って〔刑事〕にはたらく。この幕府職制中の役目は御先手組の組頭(くみがしら)が交替でつとめ、四百石の旗本・長谷川平蔵は現・火付盗賊改方の長官ということになる。
平蔵が役目についたのは二年ほど前からで、その前は堀帯刀(ほりたてわき)がつとめていた。
ちなみにいうと、佐嶋忠介は堀帯刀に属する与力であって、堀が盗賊改メをしていたときにはこれをたすけ、縦横に活躍をした男で、
「……忠介で保(も)つ堀の帯刀」
などと、うわさをされたほどであった。
だから、いま雑木林の中で親しげに語り合っている佐嶋与力と岩五郎は、敏腕(びんわん)の前警吏と前盗賊ということになる。
「ときにな……」
と、また佐嶋がいった。
「おれは今度、長谷川様から借りられることになったよ」
「へい」
「別に、あらたまることはないのだが、今日からお前との連絡(れんらく)はおれがする。以前の通りだ」
「わかっております」
「昨日から、おれは長谷川様御役宅内の長屋へ移っているが、かまえて訪(たず)ねて来るな。急用のあるときは、お前の店の軒先へ、そうだ、この笠をつるしておけい」
と、佐嶋与力が手にした変哲もない菅笠(すげがさ)をわたしてよこした。
ここまでくれば、この二人の関係もおのずから知れよう。
岩五郎は前盗賊の履歴(りれき)と経験に物をいわせ、火付盗賊改方の手先となっていたのである。
つまり町奉行所の場合なら、同心、御用聞きの下にいて絶えず暗黒街の情報を探(さぐ)っている下(した)っ引(ぴき)に相当するもので、盗賊仲間からいえば汚(けが)らわしい〔狗(いぬ)〕ということになるのだ。
岩五郎がそうなったについては、むろん、それだけのいきさつがあった。
七年前まで、岩五郎は父親と共に甲州一帯を本拠(ほんきょ)とする鶍(いすか)の喜左衛門という大盗の下でおつとめをしていたものだ。
この喜左衛門の配下でも頭株の真泥(まどろ)の伊之松という盗賊が、単独で江戸へ出て来て盗みをはたらいたことがあり、これを当時の火付盗賊改メ・堀帯刀が捕えた。
いうまでもなく直接に捕縛(ほばく)をしたのは与力・佐嶋忠介である。
真泥の伊之松を責めたててみると、どうも背後には大物がひそんでいる気がして、佐嶋与力は思いきった拷問(ごうもん)にかけ、ついに伊之松の口から鶍の喜左衛門一味の所在を白状させるに至った。
このとき、喜左衛門は甲州・石和(いさわ)の本拠に一味をあつめ、大仕事をするため大坂へ乗りこむ手筈をととのえていたらしい。
そこは機動性のある盗賊改方であるから、
「世のためになることじゃ。かまわぬ、甲州へ出張(でば)って鶍一味を引っ捕えい」
と、堀帯刀が命を下し、佐嶋与力は同心五名、小者十名をひきつれて甲府へおもむき、甲府勤番からも人数を出してもらい、石和の本拠へ打ちこみ、鶍の喜左衛門以下十二名を捕縛した。
この中に、岩五郎と卯三郎も入っていたのである。
折しも、卯三郎は中風(ちゅうぶ)を発して身うごきもならず、ために岩五郎も逃げ遅れ、共に捕縛されたのである。
一味が江戸送りとなって後に、佐嶋忠介が中心となって吟味を重ねたが、岩五郎のどこを見こんだものか、或る日の深夜に岩五郎のみを牢(ろう)から出して自室へ呼びつけ、
「中風の親父と共に死にたいか。それともお上(かみ)の御用にはたらき生きのびたいか?」
と、持ちかけたものだ。
むろん、岩五郎としては同業の者を売る狗(いぬ)なぞに成り下りたくはなかったが、佐嶋与力は懸命に説きふせ、盗賊たちの組織を放り捨てておいては、いまに警吏の手もおよびかねることになるし、岩五郎らのいう〔真の盗賊〕の激減と共に、殺し、強姦(ごうかん)をも合せおこなう非道の盗賊が増加する一方の現状を述べた。このことは岩五郎も遺憾(いかん)とするところであったし、誠意をこめた火のような舌鋒(ぜっぽう)をもって説きすすめる佐嶋の情熱に、
(御公儀のお役人にも、こんなお人がいたのか……)
と、感動をした。
さらに。
堀邸内にもうけられた牢内で病気に苦しむ父親・卯三郎を見ていると、どうにも居たたまれなくなり、数日を経て、
「お引きうけいたしましょう」
と、佐嶋与力へ申し出たのである。
こうして、鶍一味が死罪になった後、ひそかに岩五郎と卯三郎は牢を出され、中気の父親を浅草下谷・新寺町の長屋に住まわせ、これに小女(こおんな)をつきそわせた。以来いままで、この父親の面倒は申し送りに火付盗賊改方で見てくれている。また、それだけに岩五郎もはたらいて見せねばならなかった。
お勝と再会し、現状のごとき家業をいとなんだのも、それが〔狗〕としての探索に便利であったからだ。
そのかわり、むかしの同業者にこのことが知れれば、否も応もなく、岩五郎は裏切者として復讐(ふくしゆう)の刃を身に受けねばなるまい。
清水門外(しみずもんそと)の長谷川平蔵役宅へは訪ねるな、と佐嶋が念を押したのもこのためで、双方の連絡には相当の苦心を必要とするのである。
岩五郎と別れるときに、佐嶋忠介がふっと思い出したようにいった。
「このごろ、ひょいと耳にはさんだことなのだが、ほれ、むかしは名を売った海老坂の与兵衛が江戸にいるという……あの大泥棒、まだ生きているらしい」
岩五郎は、こたえなかった。
「そのことも気にかけておいてくれ」
「へい……」
五
海老坂の与兵衛の指揮の下に〔おつとめ〕の計画は着々とすすめられ、いまは決行のときを待つばかりとなった。
盗み出した金箱は、用意した二梃(ちょう)の駕籠(かご)へ入れ、これを駕籠かきに化(ば)けた一味の者が担(かつ)ぎ、頭領・与兵衛自身がつきそって、本郷・竹町の組屋敷がならぶ道をぬって一気に仙台堀へ出る。
そこは江戸城・外郭の濠(ほり)でもあって、ここに小舟が待ちかまえて金箱を受けとり、一味のうち約半数を乗せ、御茶の水から江戸川へ逃げようというのだ。
(なるほどなあ……)
計画がすすむにつれ、岩五郎は感嘆せずにはいられなかった。
これだけの大仕事をしながら、翌朝になるまで犯行をさとられぬために微細(びさい)な工作をおこない、一味の者もすべて安全に逃げ切るよう、海老坂の与兵衛は苦心をかさねている。
そこには頭領として、
「手下の者のすべての身になって、おつとめをするのでなくては頭領の値打ちなし」
と断ずる与兵衛の信念が、脈うっているのである。
岩五郎は、われを忘れていた。
狗の身ならば、この計画がはじめられたとき、何を置いても火付盗賊改方へ密告をし、指令を仰がねばならない。
そうでなくては、岩五郎が〔公儀〕を裏切ることになるのだ。それが判明したら岩五郎も卯三郎も捕えられ、有無(うむ)をいわさず打首になってしまうこと必定(ひつじょう)であった。
「わしにとっても、これが最後のおつとめゆえ、獲(え)たものは一年後にみなで分け合い、以後は互いに相かまわぬことじゃ」
と与兵衛はいった。
一味十五名の中で、岩五郎が知っているのは彦蔵爺のみだが、名のみをきいていた腕利きもかなり入っている。
岩五郎は蔵の錠前を外す道具をひそかにあつらえ、計画に熱中した。
彼の説明をきいて与兵衛も、
「さすがに岩五郎どんだ、きっと錠前は開(あ)くよ」
力づよく、受け合ってくれたものである。
岩五郎は、浅草にいる卯三郎にも、このことを洩らさぬ。これを知ったら老父は、
「とんでもねえ。お前は佐嶋さまの眼を節穴だとおもっているのか……どうか、やめてくれ。よいよいになったおれはともかく、お前の首が飛んだら、女房子はどうするのだ」
きっと、必死にとめることであろう。
にもかかわらず、岩五郎は深入りをしている。
(こんな大親分は見たことがねえ。なるほど、真の大仕事とはこういうものなのか……)
であった。
盗賊としての血がわき返ってくるおもいなのである。
一味の統率力もすばらしい。下目黒の隠居所を中心とする連絡にも全く村人たちの眼にとまらぬ手法がつかわれ、それが、いちいち灰汁(あく)ぬけている。一味の者たちは決行までの過程をたのしみつつ、しかも緊張が日毎に加わって行く妙味をかみしめながら、念には念を入れて準備をかためてゆくのだ。
海老坂の与兵衛は、一点のうたがいも岩五郎に対し抱いてはいない。
配下を信ずること鉄のごとし……でなければ大仕事は出来ない。何しろ脅(おど)しの刃物なぞというものは剃刀(かみそり)ひとつ持って行かぬというのである。
(だが、もう、いけねえ……)
岩五郎は、本所の雑木林の中で佐嶋忠介に会い、佐嶋から「海老坂の与兵衛が江戸へ入っているらしい」と、釘をさされてからは、夢がさめたようなおもいがした。
(佐嶋さまは、おれのしていることをお見通しなのかも知れねえ。あのお人の眼はごまかせねえ)
そうなると……。
この夏、店先へあらわれた乞食坊主の予言が急に気になり出したものである。
(あの坊さんは、おれの、いまの暮しのもとになっていることへ、そむいちゃあならねえといいなすった……)
その基盤(もと)というのは、あくまでも〔狗〕となって公儀のおために働くことなのだ。
(あぶねえ……あぶねえ……)
岩五郎は、我に帰って冷汗をかいた。
いったんは父親ともども死罪になるところを助けられたということは、重大なことであった。
おのれのみか、現在では、お勝やお八百、子供たちの運命までも背負っている岩五郎なのである。
(さ、佐嶋さまには、そむけねえ)
思いきって、あれから二日ほど後の朝、岩五郎は店の軒先へ、佐嶋から受けとった菅笠(すげがさ)をつるした。
海老坂の与兵衛の顔を見てからでは、とても密告が出来なくなる。
すると、笠をつるして岩五郎が店の中へ入るか入らぬかのうちに、彦蔵爺が顔を見せた。いまでは、お勝とも顔見知りになっている爺さんであった。
彦蔵は「すぐに下目黒へ……」と、岩五郎へささやき、にこにことお勝たちへは笑顔を見せながら帰って行く。
すでに〔おつとめ〕の決行は、九月七日の夜ときまっている。
出かけぬわけにはゆかないので、岩五郎が下目黒へ行くと、与兵衛が、
「岩五郎どん、日がのびたよ」
と、いった。
何と、本郷の柳屋へ飯たきとなって住み込んでいた善太郎が急病で倒れてしまったと、按摩の佐助から知らせが入ったのだという。
しかも、その急病は卯三郎と同じ〔中風〕だというのだから、とても役にはたたぬ。
内からの手引きなくしては、刃物ひとつ持たぬ盗みが成立するわけがないのだ。
「さ、左様で……」
この瞬間、岩五郎の面上には、ありありと落胆(らくたん)の色が浮きあがった。演技ではない。われ知らず、この頭領と、この大仕事に魅せられて夢中に日をすごし計画に加わっていた岩五郎の盗賊としての情熱が、
(何てえこった。残念な……)
の真情となって露呈(ろてい)されたのである。
「日がのびる、だけじゃあすまないよ。善太郎のかわりに柳屋へ手下の者を入れるまでには、また一年もかかろうかねえ」
与兵衛、いささかもあわてぬ。
悠然として、時を待とうというのだ。
「ま、そのつもりでいて下さいよ」
与兵衛にいわれ、岩五郎はふらふらと浅草へ帰って来、豆岩の、もう一つのほうの店の軒先を入りかけて、
「あ……」
おもわず、低く叫んだ。
軒先には、まだ菅笠がつるしてあった。
(日がのびたのなら、なにも急いで……)
おもったとたん、秋の夕闇がたちこめる河岸道を近づいて来た侍が笠の中から、
「おれだ」
何気なく岩五郎へ声をかけておいて、さっさと遠ざかって行く。
与力・佐嶋忠介であった。
岩五郎は、これに従って歩み出すよりほかに道はなかった。
膾(なます)にでもするつもりなのか、生きのよさそうな鱸(すずき)に庖丁をいれていたお勝が開け放した障子の向うから顔をのぞかせ、
「お前さん。お帰んなさい。どこへ行くのさ?」
声をかけてきた。
「すぐ帰るよ。一本つけといてくんねえな」
強(し)いて明るくこたえ、岩五郎は身を返した。
六
岩五郎の密告によって、海老坂の与兵衛一味が、火付盗賊改方・長谷川平蔵によって捕えられたのは、それから三日後のことである。
浄念寺にいた彦蔵爺ほか、頭領の与兵衛をふくめて計九名がお縄にかけられたが、残る六名は逃亡した。
その翌朝……。
御厩河岸の岩五郎一家のものが、夜逃げをした。
同時に、下谷・新寺町の長屋から、よいよいの卯三郎も姿を消した。
その夜。
江戸城・清水門外にある長谷川平蔵役宅の奥の一間で、あるじの平蔵が佐嶋忠介と語り合っている。
「病人の父親を抱えての旅でありますゆえ、岩五郎を捕えるのはわけもないことですが……」
と、佐嶋与力がいうのへ、長谷川平蔵は事もなげに、
「捨てておけ」
「は……」
「岩五郎も、よくせきのことであったのだろうよ。いままでよくはたらいてくれたほうびだ。好きにさせてやれ」
「却(かえ)って、あぶないことで」
「与兵衛一味のうち、逃げた者が六名。こやつらが、もし岩五郎の裏切りを知ったなら、只ではおくまい」
「そのことでございます」
「そのときはそのときのことよ。いまの岩五郎には、江戸で暮したくない理由があるのだろう。さて、岩めはどこへ行ったやら……生まれ故郷の越中を目ざしたのではあるまいか……」
この部屋に、もう一人の男がいる。
坊主あたまながら小刀をたばさんだ老人……と見えるが、この男、長谷川平蔵と同年の四十四歳で、平蔵とは若いころの剣術友達だ。名を岸井左馬之助(さまのすけ)といって、父の代からの下総(しもうさ)・佐倉の浪人である。
平蔵が盗賊改メに任じてから、岸井左馬之助の蔭(かげ)からの助力は大きかったといわれる。岸井は変装に妙を得て市井(しせい)に埋没し、さまざまの情報を平蔵におくりわたして犯人検挙に協力をした。
その岸井が、このとき口をはさんだ。
「岩五郎は、よい男であったな、平蔵どの」
「うむ」
「この夏であったが……おれが、例の乞食坊主の風体(ふうてい)でな。何喰わぬ顔で岩の店へころげこみ、水を所望したことがある」
「ほほう……それは、いっこうに存じませぬでした」
と、佐嶋与力。
「うむ。そのときにな、親切に水をのませてくれた上、銭を包んでくれてな」
「なるほど」
「あの男、これなら御役にたつ、と思いきわめたものだ。そのときの、彼のとりなしのあたたかさ。おもわずうれしく……おれもな、人相をいささか見るので、お前は長命の相じゃと、こういってやったものだ」
「そりゃ、まことにか?」
と、長谷川平蔵。
「うむ」
大きくうなずき、岸井左馬之助が、
「それでな、おれも念を押したものよ」
ほろ苦(にが)く笑って、
「いまの暮しのもとになっていることに、そむいてはならぬ、とな」
「ふむ、ふむ」
「何やら、感にたえた顔つきをしておったが……」
「なるほど」
庭に虫の声がみちている。
月の無い晩で、風は冷えていた。
酒肴(しゅこう)がはこばれ、長谷川平蔵が取りあげた盃へ佐嶋忠介が酌をしかけたとき、
「岩五郎が、越中のどこかの町で、中風の親父と盲目の義母と、女房と子と、安穏(あんのん)に好きなどじょう汁をすすってくれるような身の上になってくれることだな」
平蔵がいい、盃をほしてから岸井左馬之助へ、
「ところで左馬。おれが寿命(じゅみょう)は?」
と、きいた。
岸井は悪びれもせず、
「五十まで」
ずばり、いいきったものである。
平蔵は、にやりとして、こういった。
「あと六年か……やることだけはやってのけておくことだな、左馬」
◇ ◇ ◇
なお、同時に販売される「岸井左馬之助弁当」の詳細とその特典、朋友・岸井左馬之助が鮮烈に登場する「本所・桜屋敷」は、こちらをご覧ください。
◇ ◇ ◇
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?