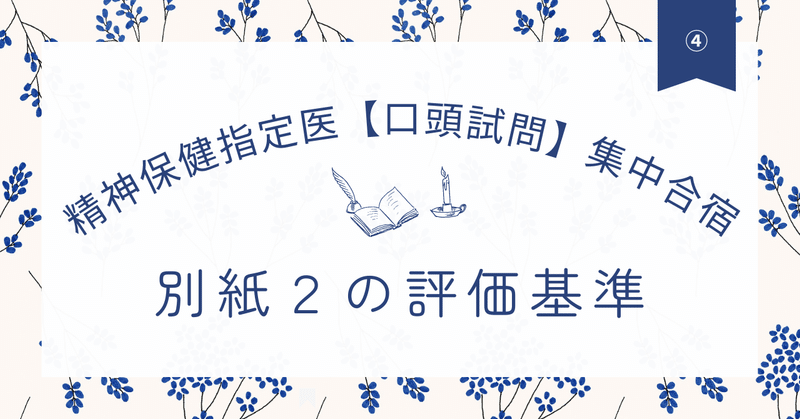
精神保健指定医【口頭試問】集中合宿④別紙2の評価基準と見直す順番
さて、残すところ、あと12日💦
今日も頑張ります。
とりあえず、絶対暗記する事項のまとめと、勉強用twitterアカウントを作ったので、ここからは、別紙2の評価基準と照らし合わせて、ケースレポートと、精神保健福祉法詳解と研修会資料を読み込んでいく作業に入ります。
別紙2によると、症例内容の評価基準として、
共通事項
① 国際疾病分類(ICD)に基づく診断名(入院時診断名/最終診断名)が記載され、患者の 症状と照らしてその診断名に妥当性が認められるか。
② 診断根拠が記載され、その内容に妥当性が認められるか。
③ 入院時に疑い病名としていた場合、その理由と最終診断を下した日付が記載され、その 内容に妥当性が認められるか。
④ 入院後の治療経過や治療内容について努めたインフォームド・コンセントの内容が適切 に記載されているか。また、その過程における主治医等担当医としての関わりや治療努力 が記載されているか。
※ 以下の点に特に留意
・ 修正型電気けいれん療法、多量・多剤大量の薬物療法、クロザピンなど慎重を要する 治療手段が用いられた場合、その理由と必要事項に関する記載があるか。
・ やむを得ず適応症以外での薬物使用を行う際には、使用の理由と本人や家族にその効 果や副作用を含めた説明を十分に行い、同意を得ているか。
⑤ 患者の症状、診断内容に照らし、治療内容に妥当性が認められるか。
と記載されています。おおむね、レポートの内容についての基準ですが、口頭試問でも、レポートの内容について聞かれるはずなので、その際にこの点がちゃんと答えられるのか、想定質問を作っていきたいと思います。また、
入院形態など症例の属性に応じた事項
として、
・措置入院
・医療保護入院
・18歳未満の症例
・任意入院に移行した 症例
・退院後に外来治療を 行った症例
のそれぞれの評価基準が載っているので、この順番に、症例を見直しながら、想定問題を作っていきたいと思います。また、
行動制限に関する事項
として、
・共通事項
・電話・面会の制限
・隔離
・身体的拘束
・任意入院者の解放処遇の制限
のそれぞれの評価基準が記載されていますが、これは、絶対暗記する事項の精神保健福祉法第37条第130号告示とかぶっていますので、すべての症例でこの項目に関しては、評価基準委照らし合わせて、確認していこうと思います。
さらに、
※ 上記の各項目については、当該項目に係る一般的な留意事項についても、口頭試問で確認を行う場合がある。
とあるので、症例と関係ない一般知識を問われることが想定されますが、研修資料と精神保健福祉法詳解の該当箇所を読んでおけば大丈夫なのではないかなと思ってはいます。
では、また。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
