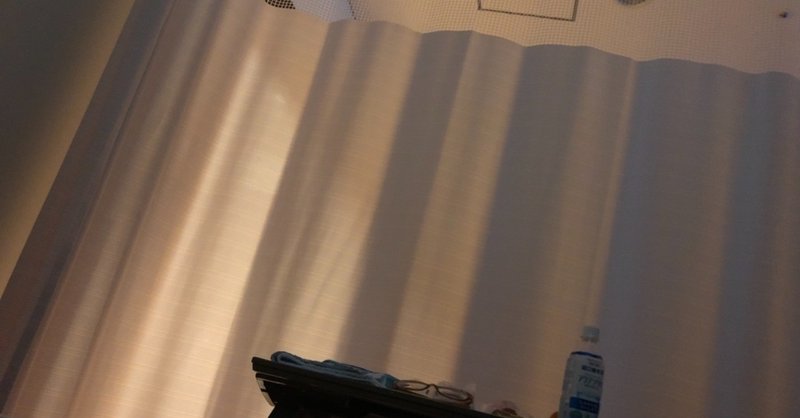
出産したら羽生結弦に泣かされた話
娘は予定日から1ヶ月くらい遅れて産まれてきた。幸い誘発を行う必要はなく、自然分娩で、初産としては安産と言えるくらいの短いお産であった。しかし、傷が深く酷く、縫合した痕が引き連れて痛み、ベッドから起き上がるのに数分かかる有様だった。産後即母子同室の方針だったので、満身創痍の状態で育児が始まった。血圧が低下し、いわゆるショック状態で輸液を受けていたのだが、担当の看護師にお産の日の夜くらいは休ませてもらえないかと打診したところ、あっさり断られた。その時は、そんなものか、と思った。
分かってはいたが、お産の済んだ夜、全く眠ることはできなかった。とにかく娘が泣き止まない。授乳しても抱っこしても駄目で、この世の終わりみたいな感じでずっと泣いている。ひたすらあやし続けて時刻は午前3時、途方にくれた私は哀れっぽい感じで煌々と明かりのついたナースステーションの周りを歩き回ってみた。一歩踏み出す度に飛び上がるほど傷が痛むので、亀のごときのろまな歩みだった。泣き叫ぶ赤子を抱きながら薄暗い病棟の廊下をゆっくりと歩く様子はさぞかし異様だったことだろう。数人の看護師と目が合ったが、特に誰からも声を掛けられることはなかった。
2日目くらいまでは何とかそんな調子で頑張ることができた。様子がおかしくなってきたのは、3日目の夕方からである。病院の1階には売店があり、買い物を理由にナースステーションに娘を預けられることを知った私は、これを使わない手はないと思った。数分でもリフレッシュできるなら御の字である。エレベーターで1階に降り、売店に向かったのは午後6時くらいだったと記憶している。ちょうど真冬だったから、既に外は真っ暗だった。1階の壁は全面ガラス張りになっており、車寄せにタクシーが何台か停まっているのが見えた。痩せた樹の影に街灯がぽつぽつと光り、見舞客がコートの襟を立てたまま、受付で黙々と書類に名前を記入していた。産後まともに外界と触れるのは、これが初めてだった。
当時の私は点滴棒がないとまともに歩けないほど衰弱していた。傷の痛みが酷く、大量に出血したせいで立ち上がるとすぐに気分が悪くなった。両手で点滴棒に掴まり、えっちらおっちら歩いていると、白衣を着た医者や看護師にどんどん追い抜かされた。彼ら彼女らは、特にこちらを顧みることはなかった。そんなものだろうと思った。病院で働いていると、その辺りの感覚は麻痺するものだ。担架に乗せてもらわないと移動も出来ないような患者や、挿管されて意識のない患者を1日に何人も診ているのだ。例え点滴棒に掴まっていようと、自立歩行ができているのなら満点である。自分で歩ける人間は、何とか自力で頑張らなければならない。
そんなことを考えながら歩いていると、ふっと樟脳の香りが鼻を突いた。私の右側を、ひとりの老人が追い抜いていった。病院から支給される簡素な浴衣姿で、首にはCVカテーテルが挿入されていた。栄養が豊富な点滴は、腕などの末梢血管からドリップすると、激しい痛みを引き起こす。老人は頸静脈という太い血管にCVカテーテルを挿れられて、中心静脈栄養を行っていた。その病状は良いとは言い難かったろう。CVカテーテル挿入は、口から栄養が取れない状態が長期にわたって続いていることの証左であった。
老人は私を追い抜き、そのまま院内の書店へと向かっていった。齢は80をゆうに越えていただろう。樟脳の香りが遠ざかり、その背中が見えなくなった時、突然鼻の奥がじんと熱くなった。
内科医として働いてきたからこそ、老人の病状が甘くないことは理解できた。そんな老人にすら悠々と追い抜かれたことが、私にとってはただただショックだった。数日前まで、私は腹が膨れているだけの健常な30代女性であった。脳内を走馬灯のように、今まで私がCVを挿入してきた患者たちの姿が駆け巡った。泣くまいと思ったが、涙が溢れた。
強情な性格なので、涙でめちゃくちゃになった顔のまま買い物をした。売店のスタッフが、ひそひそ声で私を心配するのが聴こえた。授乳の間隔を記録しておきたかったから、安っぽい置き時計をひとつ買った。電池は別売りですか、と尋ねたことを覚えている。別売りです、と答えた若い男性店員の顔は明らかに強張っていた。
翌朝の採血で、ヘモグロビンの値が輸血が必要なくらい下がっていることが判明した。客観的な数値を以って、初めて私の具合が悪いことが医学的に証明された。担当の看護師は目に見えて優しくなり、夜間の授乳時以外は娘はナースステーションで預かってもらえることになった。対応が遅い。そう思ったが、口には出さなかった。
傷と貧血のせいで多少延期はされたものの、1週間程度で退院が決まった。やっと家に帰れる、これで万事解決だと思ったが、見立てが甘かった。入院中から、私の精神はいつになく荒れていた。ふとしたことで涙が溢れてしまう。
食事中は病室のテレビを消音にしてなんとなく眺めていたのだが、ある朝、ニュース番組でアスリート特集が組まれていた。日曜の朝だったので、毒にも薬にもならないような構成の番組であった。病室の窓の外ではちらちらと雪が舞っていた。数センチ積もりそうですよ、と担当看護師に声を掛けられたことを覚えている。
美味くも不味くもない病院食を淡々と口に運びながら、私は消音状態のテレビをぼんやりと眺めていた。陸上選手や野球選手に続いて、彼は姿を現した。彼の名は羽生結弦だった。
病室の小さなディスプレイに映し出されたのは、平昌オリンピックのショートプログラムだった。足首の靭帯を負傷し、しばらく公の場に姿を見せなかった彼は、期待されていた表彰台どころか、オリンピックへの出場すら危ぶまれていた。しかし、羽生結弦はあの日、平昌のリンクに現れた。傷の痛みやリハビリによる練習の空白など微塵も感じさせない涼しげな様子で氷上にすらりと立ち、文句のつけようのない最高の演技を披露して拍手喝采を浴びた。コットの中ですやすや眠る娘を起こさぬようにテレビは消音状態ではあったが、私は羽生結弦の演技を見て馬鹿みたいに泣いた。致命的な怪我から再び立ち上がり、氷上で舞う彼に人間の強さや美しさを教えられた気持ちになったからである。あの瞬間、間違いなく羽生結弦は私のために踊ってくれた。平昌オリンピックから既に半年以上経っていたから、録画された映像だったのだけれど。
そんなふうに感受性が異常に強い状態は、その後数ヶ月に渡って継続した。男性シンガーが、君のことが世界一大切、と鼻にかかったような声で歌うのを聴くと、ばかみたいに涙が溢れてくる。とにかく全てのラブソング、愛にまつわる曲が、自分と娘のことを歌っているように聴こえるのである。新生児期の娘は、まだ瞼も浮腫んで目が開かず、薄い皮膚はその下を這う血管を透かして赤く、手足は頼りないほど細かった。こんなに弱々しい生き物を産んでしまって、これからどうなるのだろうと思った。娘がベッドから落ちて死んでしまう夢を何度も見た。ただでさえ短い睡眠時間は、悪夢のせいでもっと短くなった。育児なんてみんなやっていることなんだから何とかなるだろうと高を括っていたのに、とんでもなく深い沼に足を突っ込んでしまった気分だった。
私が感受性を尖らせまくっている間にも、時間はどんどん過ぎていった。大人にとって昨日と今日はほぼ同じだが、赤子にとっては全く別物である。いつの間にか目はぱっちりと開き、赤かった皮膚はむちむちでみずみずしく、手足も立派に肉がついて太くなった。首がすわり、喃語が出て、寝返りをして、いつの間にかお座りができるようになっている。弱々しく、全てから守ってやらねばと思っていたのに、ほんのりと白く生えてきた歯で勢いよく噛みつかれ、こちらが悲鳴をあげる日々である。娘は随分強くなった。それと反比例するように、私の感受性も少しずつ元に戻っていった。とはいえ、通常営業に戻るには、結局産後半年を要した。
産前産後のホルモン変化は恐ろしい。感情の荒波に揉まれる辛さは生涯忘れないだろう。すっかり元どおりの鈍感な人間になったので、人前で居眠りができるし、甘ったるいラブソングだって平気な顔で口ずさめる。産後3ヶ月で職場に復帰し、クリニックでの外来という比較的負荷の軽い仕事も何とかやれるようになった。午前9時から午後5時までの、極めてホワイトな職場である。産後復帰としては御誂え向きであった。
午前の外来を終えると、昼食のための休憩時間が1時間半もある。クリニックの休憩室では、いつもテレビがつけっぱなしになっている。大抵バラエティ番組が流れているが、その手の騒がしい番組があまり好きではない私は、画面をまともに見ずに黙々と昼食を摂っていた。ある日、休憩室にふと懐かしいメロディが流れた。ショパンのバラードだった。はっと顔をあげると、あの日見たのと同じ淡い水色の衣装で、羽生結弦がリンクに立っていた。金メダルを勝ち取って連覇を決めた、あの伝説の演技の再演だった。テレビ局は何度だってこのプログラムを流すし、観客は何度だって彼に夢中になる。重力を感じさせないジャンプや、滑らかなエッジワークを見るうちに、胸が熱くなって、視界が滲んだ。あの日、私が彼の演技に救われたこと、コットですやすや眠る産まれたばかりの娘の横で静かに泣いたことを、平昌のリンクで舞う彼を見るたびに、私はきっと生涯思い出すことだろう。
Big Love…
