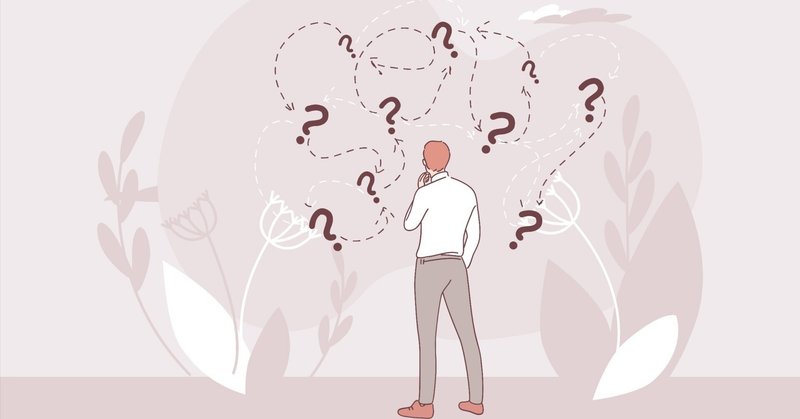
ジョブ型人事制度で失敗?
懐疑的な声の例
Googleで検索すると記事が色々と出てきます。不安を感じられるお客様からよく聞かれるのはおおよそ下記のような捉え方をされている方が多いように思われます。
決められた仕事しかしなくなるのでは?
異動させにくくなるのでは?
お給料が下がるのでは?
1. 本当に決められた仕事しかしなくなるのか?
ジョブディスクリプションの一部分だけを捉えている場合、陥りやすい誤解になります。職務価値を算定する際の指標の作り方次第ではありますが、算定時の指標としてステークホルダーとの関係性や挑戦度合いなどが折り込まれていれば組織機能から見た定常業務だけを実施していれば良いとはほぼなり得ません。もし本当にそのようなポジションがあるのであればグレードは低くなります。
また、自己理解のためのサーベイなどを通じ、自社のカルチャーやバリューから見た時のフィット感のフィードバックなども組み合わせることで利己的な振る舞いを抑制していくことも可能です。
大切なのはマネジメントが自身の組織としての計画を達成する上でどのようにリソースを最適配置していくのか、その力量が問われてくるというのが本質的な問題となります。
2. 本当に異動させにくいのか?
特定の職務にアサイメントされている以上、異動先の職務要件によってはグレードが下がってしまうのではと疑問に思われると思います。結論としてその可能性はあるのですが、運用上は色々な工夫が可能です。例えば、異動時のルールとして異動時点ではグレードは変更せず、同等の職務価値の仕事を担ってもらいながら知識やスキル面をキャッチアップしてもらう。但し、キャッチアップが進まずにパフォーマンスが上がらないのであれば徐々に適正グレードに近づけていくなどの工夫を行います。人材育成を加味したアサイメントを行う場合の対応として割とみられるケースです。
難しいのは欧米のようにジョブディスクリプションありきで運用し、職務内容ががらっと変わってしまうことにメンバーが抵抗を感じる場合です。この場合は相応の退職パッケージを用意され円満な形でレイオフになることもあり得ます。
3. 本当にお給料は下がるのか?
ジョブ型人事制度の場合、下がる可能性はあります。特に年功的な人事制度を運用してきた大手企業の場合、グレードが高止まりしている人材も多いため厳格に運用するのでれば当然ながら給与が下がることを生じてきます。ただ、一般的に10%以上下がる場合には調整給が数年にわたり支給されるためその間にリカバリーすることも可能ですし、次の道を見出す時間的な余裕もあります。
ちょっと注意が必要なのが下げることが目的化している企業です。この見極めは難しいですが、停滞・衰退期に入っている企業などでジョブ型人事制度を導入する場合には疑ってみても良いかもしれません。
会社と人の成長を信じ続ける
ジョブ型人事制度で失敗する企業は、端的に言えば「会社と人の成長を諦めている企業」の場合です。このタイプの企業は何をどう頑張っても業績は伸びないわけですから、当然ながら人件費も増やすことはできません。会社と人の成長を信じ続ける限りにおいてはジョブ型人事制度は有効に機能させられます。ジョブ型人事制度をきっかけに戦略、計画、組織設計、アサイメント、役割・職務要件、目標(OKR/MBO)、1on1、フィードバックこれらが有機的に整合していれば組織はとても強くなりますし、マネジメント力が自ずと高まります。
その意味からすると、成熟している大手企業がジョブ型人事制度を導入するよりも、成長中のスタートアップ企業や人材が足りていないローカル企業などにこそ早い段階で導入していただくことをお勧めしたいと思います。
