
『ゲット・バック』は、ビートルズ流ルーツ・ロック志向だったのか
(10 min read)
ビートルズ公式が(日本時間の)2021年6月17日深夜に発表したところによりますと、かの『ゲット・バック』ドキュメンタリー映画(ピーター・ジャクスン監督)が、今年11月25、26、27日の三日連続、それぞれニ時間の連続シリーズとして、ディズニー+で配信放映されます。
なかなか大きなニュースですよね。
ビートルズ1969年1月のゲット・バック・セッションを知らないロック好きはおそらくいないと思いますから、紹介の必要もないでしょう。それにぼくなんかが知っていることといえば、一般のファンが知っているごくあたりまえのことだけですから、特になにかを語るなんてこともできません。翌年リリースされたアルバム『レット・イット・ビー』との関係しかり。

「ゲット・バック」ということばには、いくえにも多層的に意味が重ねられていたと思います。最大のものは、おそらくこのバンドの結成当初の姿に戻りたいということだったかと。1967、68年ごろともなれば、四人のメンバーがスタジオで顔をあわせて同時に音を出す機会も減っていましたから。スタジオ録音技術の発達あればこそ、だったんですけれども。
だから、最初のころのように四人でもう一度集合して、そこにキーボードのビリー・プレストンだけをくわえ、多重録音なしの同時生演奏セッションでどこまでの音楽ができるか?というチャレンジというか原点回帰だったという、そういう意味で「ゲット・バック」ということばを使ったのでしょう。ストレートなロックンロール回帰ということで。
余談ですが、ビートルズとローリング・ストーンズという1960年代の二大UKロック・バンドと正式共演した音源記録が残っている外部鍵盤奏者は、ビリー・プレストンのほかにもう一名だけいます。それがニッキー・ホプキンス。ビートルズとは、シングル「レヴォルーション」で共演していますよね。
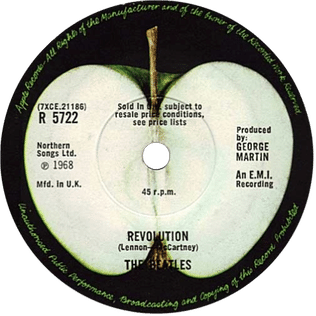
「ゲット・バック」。しかしぼくがこのことばに読みとりたいもう一つの大きな意味は、ロック・ミュージックの原点、それが依って立つところに戻りたいという、いわばルーツ・ロック志向が、この当時のビートルズにもあったのではないか?ということです。
ルーツ・ロック志向は、1968〜71年ごろの米英ロック・ミュージック・シーンで一大ムーヴメントとなっていたものですよね。
ルーツ・ロック、別の言いかたをすればスワンプ・ロックでもいいんですが、1968年ごろから、それまでのけばけばしく飾り立てたサイケデリック・カルチャーにとって代わって、ブルーズやゴスペルやリズム&ブルーズ、フォーク、カントリーなど、ロック・ミュージックのルーツを見つめなおし再構築する動きが顕著になりました。
そうしたルーツに立ち返るようにして、地味だけど滋味深い真摯な音楽を目指そうという動きが、主にボブ・ディランやザ・バンド周辺、そしてオクラホマ州タルサにルーツを持つLAスワンプ勢を中心に、もりあがりをみせていたじゃないですか。
UKロック界隈でもこの動きに敏感に反応していた勢力があって、エリック・クラプトン、デイヴ・メイスン、ローリング・ストーンズ、そしてだれあろうビートルズのジョージ・ハリスンが、ルーツ・ロック、スワンプ・ロック寄りの動きをはっきりとみせ、作品にも結実させるようになっていきました。
ジョージ以外のビートルズの三人だって、こうした動きと無関係ではなかったはずです。すくなくとも強く意識はしたでしょう。もちろんUK勢のルーツ・ロック志向が鮮明になるのは、1969年12月初旬のディレイニー&ボニーの英国ツアー以後で、ジョージの『オール・シングズ・マスト・パス』も70年5月以後の録音ですけれどね。

だから、69年1月のセッションだった『ゲット・バック』ではまだまだそこまではっきりしたサウンドにはなっていませんが、同時代の対抗馬的存在だったローリング・ストーンズは、米南部のカントリーやフォーク・ブルーズ色の濃いアルバム『ベガーズ・バンケット』を68年の12月に発表していますし、やはりルーツ・ロック色の鮮明な次作『レット・イット・ブリード』の録音も同時期にはじまっていました。

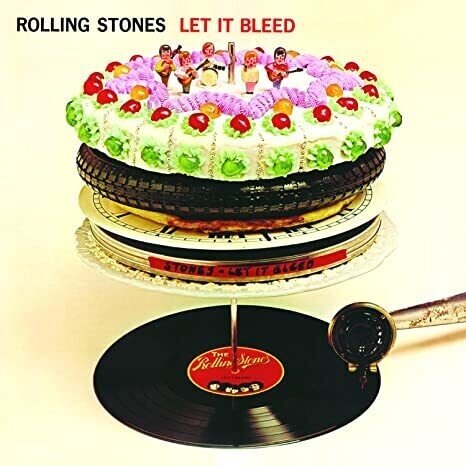
ストーンズのばあいは、ディレイニー&ボニーらの関係とはちょっと違った視点から米南部的ルーツ・ミュージックを探求していたわけですが、その際のキー・パースンは、やはりボブ・ディランだったと思うんですよね。そして、ビートルズにとってもバンド活動初期のころ、自作自演の道しるべとなっていたのがディランでした。
ディラン(とのちのザ・バンド)が本格的にルーツ・ミュージック探求に取り組んだ端緒は、あの1967年の『ザ・ベースメント・テープス』セッションから。壮大なるルーツ探求プロジェクトでした。その後の『ジョン・ウェズリー・ハーディング』(67)、『ナッシュヴィル・スカイライン』(69)と、同系統の音楽でした。

ビートルズにとってもメンターだったディランのこうした動きは、四人もとうぜん強く意識していたはずですし、当時は未発売だったとはいえ『ザ・ベースメント・テープス』の音源は耳にしていたに違いありません。

21世紀ふうな言いかたをすれば、アメリカーナ・プロジェクトだったディランの『ザ・ベースメント・テープス』セッションは、1968年ごろ以後からしばらく、ロック界各方面に非常に強い影響を与えたものですが、ビートルズも例外ではなかったと思うんですよね。
『ザ・ベースメント・テープス』セッションから直接的に産み落とされたようなザ・バンドの『ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク』が発売されたのが、1968年の7月。ここでアメリカにおけるルーツ・ロック的な動きはだれの目にもあきらかなものとして表面化したのだとみることができましょう。

ビートルズのゲット・バック・セッションは69年の1月。この時点で彼らがルーツ・ミュージック的なムーヴメントを意識し、サウンドとして表現するにじゅうぶんな材料はすでに整っていたわけです。
実際、サウンドを、そう、現時点で聴けるのは断片ですけど、『レット・イット・ビー』『アンソロジー 3』『レット・イット・ビー…ネイキッド』でゲット・バック・セッションの音の痕跡をたどってみても、きょうここまで書いてきたようなことが、ある程度は、ちょっとだったら、実感できるんじゃないでしょうか。


67/68年ごろのビートルズ・サウンドとはあきらかに違うもの、全員集合の一発録りというバンドの原点に立ち返りながら、同時にロック・ミュージックのルーツもふりかえって再構築していくさまがみてとれるように、ぼくは思いますね。
フル・アルバムとしてはいまだ公式に未発表のままの『ゲット・バック』ですけれども、音楽面ではそんな方向を向きつつあった、ボブ・ディランらを媒介にしながら、同時代のほかの米英ミュージシャンたちの動きを強く意識して、ビートルズなりのルーツ・ロック志向を表明していた、そんなセッションだった、という推測は成り立つでしょう。
もちろんこんなことは、上で書きましたようにいままでに公式発売されている断片を聴いて、同時代の周辺の動きも勘案しながら、勝手に論を立ててみただけのことです。
ですから、ちゃんとしたことは、今年11月に三日連続で配信される『ゲット・バック』の正式版をじっくり聴いてみないとわからないことです。おおいに期待したいところですね。そして、映像作品としてだけでなく、音楽をピック・アップして、アルバム『ゲット・バック』として、CDやサブスクなどで正式リリースしてほしいと、強く強くお願いしておきます。
(written 2021.6.19)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
