
【満員御礼】今こそチェックすべし!未来のユニコーンがそれぞれの“ツノ”を披露しました
澄んだ瞳で未来を見つめ、はやあしで駆け抜け、あとは隠し持った“ツノ”が育てばユニコーンになる。
そんな成長企業が刺激を与え、新しいことにもひるまず挑戦する文化が、広島県に広まりつつあるのをご存知でしょうか。
「ものづくり県」として成長してきた広島県で、製造業に続く新たな成長産業の柱を育成する事業のひとつが、「ひろしまユニコーン10」。
2月16日(木)には、ユニコーンへの成長を目指す広島の15社が、投資家、支援者、大企業などに向けて、自らの“ツノ”となりうる事業を発表しました。
会場となったコワーキング施設Hiromalab(広島市中区)は、この盛り上がりよう!

すでに県内で、スタートアップ企業やイノベーション創出にここまで関心が高まっています。
閉会後の交流会でもたくさんの出会いが生まれ、新たなイノベーションの香りに満ちていました。

今はユニコーン未満。でもいずれ世界に飛んでいくかもしれない企業を、今のうちに要チェック!
当日のピッチやトークセッションは、YouTubeでご覧いただけます。
さらに、3月9日にはアクセラレーションプログラムの成果発表会を開催します。採択12社は、約4カ月の間でどれほど“ツノ”を成長させたのでしょうか。
詳細とお申し込みはこちら↓↓
広島県、そして「ひろしまユニコーン10」では、ユニコーンに匹敵する企業を生み出すべく、挑戦する企業をこれからも応援していきます!
ここからは、登壇企業のうち3社のピッチと、トークセッションをご紹介します。
▼HIROSHIMA UNICORN10ピッチ
合同会社ゲルバイオ
代表社員 小原 政信さん
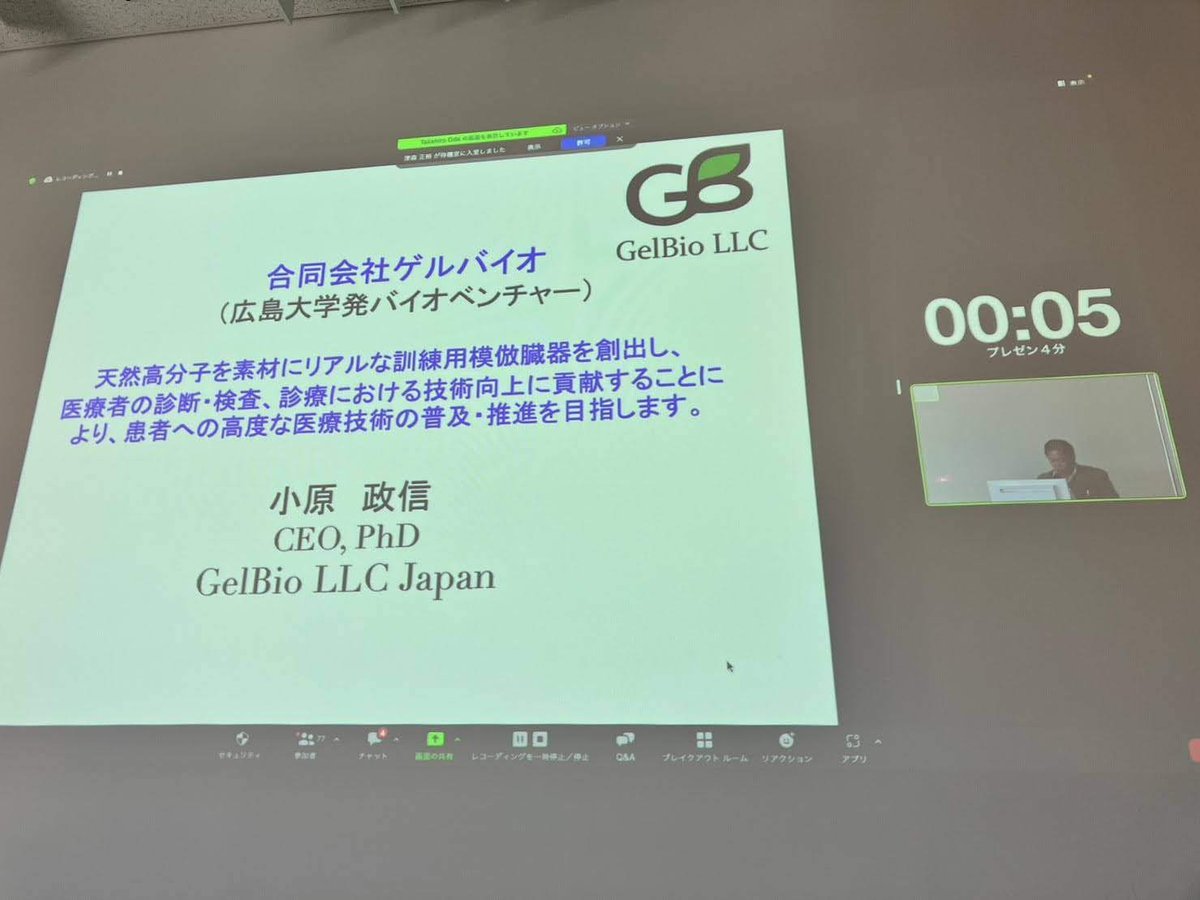
低廉で高品質、動物を用いずに大量生産できる模倣臓器が世界的に求められています。当社では、安心で安全の天然高分子素材と独自のハイドロゲル工学技術を基盤に、訓練用のリアルな模倣臓器を創出し、高度な医療の普及・推進を目指しています。模倣臓器モデル「BOT」は、甲状腺エコー穿針術に耐えられるモデルなど、すでに多くの臓器モデルを作り出しています。
ナオライ株式会社
代表取締役 三宅 紘一郎さん

当社は、バイオと技術の力で純米酒の価値を高めることを目指しています。非加熱で低温浄留する特許技術で、日本酒由来のウイスキーのようなお酒「浄酎」を開発。また、立命館大学生命科学部と共同研究により、アルコールを除いた残りの部分である発酵アミノ酸エキスを活用するSAKE BIOTECH事業にも取り組んでいます。
株式会社R65
顧問 進矢 光明さん

6人に1人は老後に住むところがないという現状を打開するため、孤独死を防ぎ、安心して物件を貸し出すための身守りサービスを提供しています。不動産関係者のほか、医療、福祉関係者を巻き込みながら、イベントも開催。年齢に関わらず住みたいところに住める社会を目指します。
▼トークセッション「広島におけるスタートアップと企業の関わり方」
<登壇者>
セイノーホールディングス株式会社
執行役員 ラストワンマイル推進チーム 河合 秀治さん
株式会社中国新聞社
メディア開発局 石井 将文さん
三井住友信託銀行
常務執行役員 松本 安永さん
<モデレーター>
フォースタートアップス株式会社
アクセラレーション本部 パブリックアフェアーズグループ
マネージャー 小田 健博さん
スタートアップ企業との取組事例をご紹介ください。
河合:ドローン開発企業と資本業務提携は、単純な投資ではなく、ワンチーム、完全ハンズオンでチームを組んでいます。60人の社内メンバーは「スタートアップよりスピード感を持って進めること」がモットーです。
小田:社内の60人はどのように選ばれたのですか。
河合:社内公募のパターンもありますが、勢いで進めることもあります。北海道から沖縄まで各地で活躍するメンバーを抽出して、47都道府県に1人ずつメンバーが張り付いている状態ができています。

石井:「広島オープンアクセラレーター」で6カ月間スタートアップ企業とともに協業のアイデアを練ったのが刺激的な体験でした。そのうち、ノーコード型のチャットボットを開発した起業とともに、協業モデルとして当社独自ブランドという形で売り出しています。昨年10月からは社内ベンチャーも始まりました。
小田:オープンイノベーションや新しい取組みに対して、社内の抵抗感はありませんでしたか。
石井:10年ほど前だったら難しかったかもしれません。現在は、様々な企業を自ら調べてアプローチするほどです。

松本:上場される企業やイノベーション企業と、業務上の接点を持っており、各社のマッチングも行っています。運用商品化されたデジタル資産を管理する機関としてジョイントベンチャーも組んでいます。
小田:ベンチャー企業との接点はどのように見つけることが多いですか。
松本:「歩く」ですね(笑)。証券会社やベンチャーVCからのご紹介や、報道された企業にドアノックするなど、地道に進めています。
小田:信託銀行とシード・アーリー企業とは、どのような関係性を持てるでしょうか。
松本:大企業の各部署がどのようなニーズを持っているか把握している分、スタートアップ企業のシーズとマッチングできる可能性があります。本日ピッチされた企業の中にも、「あの企業に紹介したい」と思う場面がいくつもありました。

オープンイノベーションの形が変わり、活発になっています。
石井:肌感覚でもオープンイノベーションの取組みは活発になってきていますし、Hiromalabをはじめそのための場所もできてきていると感じます。
松本:ベンチャー企業や新世代のパワーを感じますし、それなくして日本は成り立ちません。湯崎知事をはじめ各自治体の首長も注目しているようです。
このようなピッチイベントでも、各社の課題とニーズに対して、大企業や投資家がどうサポートできるかという動きが出てくると、エコシステムが循環していくのではないでしょうか
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
