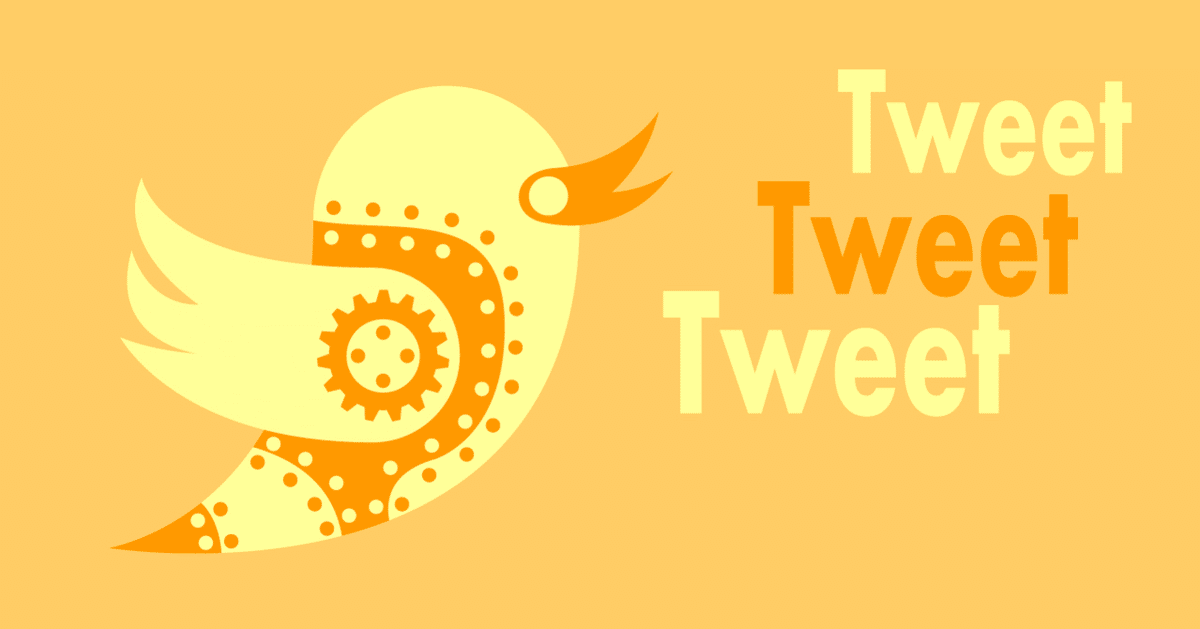
ツイッターでは何も残らない/使ったら消えるお金のように
佐藤大朗(ひろお)です。会社を休んで三国志の勉強をしています。
ある分野で、日本のインターネット文化史みたいなものを聞く機会がありまして。派生した、「名声とお金を獲得するためのインターネットの使い方」について考えてみました。
その分野では、2010年代(2010年~2019年)の10年間、インターネット発の文化が、ほぼ壊滅的で不作だったそうです。
どういうことか、考えてみました。
ぼく個人のネットとの付き合いを先に振り返ってから(ごめんなさい、すぐに終わります)、分析に入ろうと思います。
ぼくのインターネットとの関わり
ぼくは、2001年に大学に入学しました。2000ゼロ年代、大学生~大人でした。当時流行っていた、匿名巨大掲示板は、使っていませんでした。書き込みもしない、読みもしてなかったです。
2007年からウェブページ(ホームページ)を作り始め、いまも更新を続けています。やや時代遅れ感がありますが、HTMLを自分で打ち込むという形式は、惰性で続けてしまっています。
http://3guozhi.net/
(テンプレートは完成しているので、手間はほぼゼロ)
2010年から、ツイッターを始めました。これは、上記のウェブページを作る途中で気付いたことをシェアする、補助的なツールとして使っていました。ウェブページの更新告知ツールにも使いました。ツイッターに書きっぱなしの(ツイッターにしか書いていない)ことがないように、というのは、注意を払ってきたつもりです。
いわゆる名声を、ある程度は得ることができました。ネット経由で、自分が書いた本を売ることもできています。結果的にネットをうまく使えたようである、というか、ネットに救われた、ということができるでしょう。
自分史は終わりです。失礼しました。
ネット上のストックとフロー
概して、2000ゼロ年代(2000年~2009年)は、個人のウェブサイトと、匿名掲示板が流行った時代だと思います。
個人のウェブサイトは、すぐにデザインが古びて見えてしまいますが、ともあれ、検索したらいまだに引っ掛かります。のちにその作成者・管理人が、メジャー・デビューすることが多かったでしょう。
書き込んだひとが、お金と名声を得られるという点で、
「個人のストック(資産)」です。ほぼ無料で、情報を開示しておけます。固定資産税とか、維持管理費用がかかるわけじゃない。
(レンタルサーバー代などはありますが、情報開示のメリットに比べたら、ほぼ無視できるレベルでしょう)※ぼくはサーバー屋じゃないです
匿名掲示板は(当時のぼくは苦手でしたが)、まとめサイトなどが作られ、繰り返し閲覧される投稿もあったみたいです。これも、検索したら引っ掛かります。情報共有して、才能が才能を呼び、文化?のようなものが生まれることもありました。
基本的に、書き込み者は匿名なので、個人がお金や名声を得ることは難しいですが、共有財産・公共財でした。ノイズも多いですけどね。
いっぽう、ツイッターは、どれだけ瞬間的に閲覧数が上がろうと、すぐに検索しても引っ掛からなくなります。まるで、情報の蕩尽です。威信の高ぶらないポトラッチです。時間の消費であり、情報と注意力の浪費です。
検索に引っ掛かって、誰かの役に立ち続けるか。
本人が貼りついていなくても、情報自体が、ひとの役に立ったり、ひとを楽しませたりし続けるか。そのお返しとして、名声とかお金を、運んできてくれるか。
そういう観点でみると、2010年代という期間は、(きっと2000ゼロ年代以上に)みんなが時間・情報・注意力をインターネットに注ぎ込んだにも拘わらず、なーんにも残ってないんですよ。
2020年代のネットとの距離感
2010年代の大いなる徒労は、ツイッター社の陰謀だとは思いません。もちろん、「時間泥棒」ではあると思いますけど…、土足で強盗に踏み込まれたわけじゃなくて、泥棒さんに、こちらから投げ銭をしているんだから、世話ないです。笑
2000ゼロ年代、巨大掲示板に集ったひとたちが、賢明だったとは思いません。何となく、時代の雰囲気に乗っていただけだと思います。ですが、一応は、文化のようなものを共有できていたようです。
ゼロ年代のほうが、10年代よりも、楽しくやれた。2020年に入って振り返ってみると、結果は歴然です。※ディケイドは終わってみなければ評価はできないし、棺が閉じないと人間の評価もできないのです。
お金と同じで、将来のためになる、情報・時間・注意力の使い方をしないといけないと思うんです。消費・浪費じゃなくて、いわゆる投資的な使い方ってやつです。※何らかの投資系の商材を買うという意味じゃなく!
2020年代は、noteなどを書くのはアリですけど(過去記事に、忘れたころに「いいね」を頂くことがありますよね)、ツイッターに貼りついて監視するのは、もう辞めようっていうお話でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
