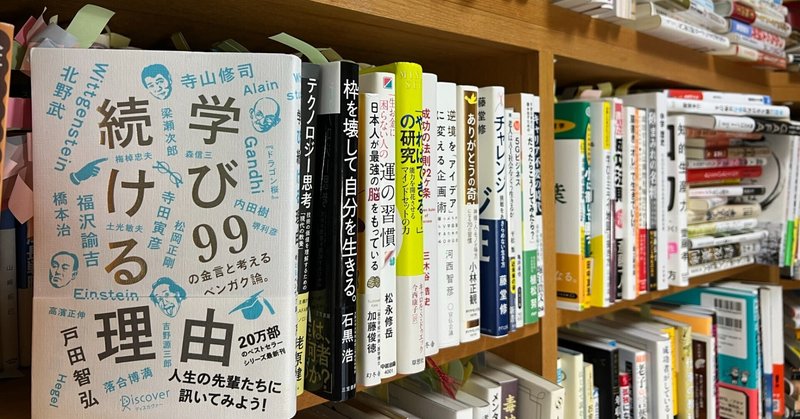
学び続ける人
今日のおすすめの一冊は、戸田智弘氏の『学び続ける理由』(ディスカヴァー)です。その中から「学びの中心は読書」という題でブログを書きました。
本書の中に「学び続ける人」という心に響く文章がありました。
《学ぶには年をとり過ぎている人は、おそらくは常にそうだったのだろう。》(ヘンリー・S・ハスキンズ/作家)
日本人の平均寿命(2012年)は、女性が86・41歳、男性が79・94歳である。これだけ平均寿命が伸びたということは、学ぶ時間と学ぶチャンスが増えたことを意味する。 私はいま、日本福祉大学の福祉経営学部(通信教育)で仕事をしている。
学生の平均年齢は40歳くらいで、もっとも多いのは30~50歳あたりの間になる。しかし、20歳程度の人もいれば、60歳くらいの人もいる。
先日、80歳の人から勉強方法についての相談を受けた。「もう80歳ですから、頭が硬くなってしまって、先生の言っていることが頭の中になかなか入ってきませんわ」と笑っていた。
この男性のように、年金を既に受給している人は何のために学ぶのだろうか。仕事のために勉強しているわけではない。もちろんお金のために勉強しているわけでもない。だからといって、 単なる暇つぶしに勉強しているのでもない。
息をするように勉強をしている。まさに達人の域に達しているように感じた。「学ぶことは人間の勤めですから」という心の声が聞こえてきた。
人生50年の時代にはひとつのことしかできなかった。しかし、人生80年の時代には、いくつものことにチャレンジできる。60歳になっても、70歳になっても、そして80歳になっても学び続ける人は、二度生きよう、三度生きようとしている人だ。自らのために、社会のために――。
「自彊不息(じきょうやまず)」という易経の中の言葉があります。自らすすんで努め励んで、休まない、怠ることはないということです。いくつになっても、息をするように学び続ける人は、「自彊不息」の人です。
道元禅師が中国に渡り修行中のとき、ある夏の暑い日、見るからに年老いた典座(台所の係の僧)が、灼熱の日中、黙々と、椎茸を広げていた。道元禅師は、「どうしてあなたのようなお年を取られた方が、この暑い中、作務をなさるのですか?若い人にやらせればいいではないですか」と言ったところ、その老典座はこう言ったといいます。
「他は是れ吾に非ず」(たはこれわれにあらず)
誰かにやってもらったのでは、自分でしたことにならないから、と。「学び」もまさに、この通りです。
今日のブログはこちらから☞人の心に灯をともす
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
