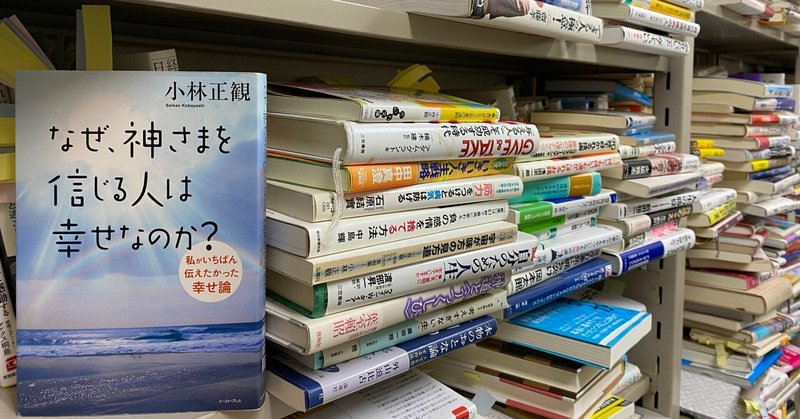
今日のおすすめの一冊は、小林正観さんの『なぜ、神さまを信じる人は幸せなのか?』(イースト・プレス)です。その中から『自分は「ろくなものじゃない」と考える』という題でブログを書きました。
『自分は「ろくなものじゃない」と考える』ということから、「下座行」という言葉を思い出しました。
信三先生の一番弟子、寺田清一氏は『師教を仰ぐ(森先生に導かれて)』 の中でこう語っています。
森先生の下座行(げざぎょう)についてのお言葉です。
■そもそも一人の人間が、その人の真価より、はるかに低い地位に置かれていながら それに対して毫(ごう)も不満の意を表さず、忠実にその任を果たすというのが、 この「下座行」の真の起源と思われる。
■下座行とは、一応、社会的な上下階層の差を超えることを、体をもって身に体する「行」といえる。 例えば「高慢」というがごとき情念は、 自分の実力を真価以上に考えるところから生じる情念といってよかろうが、 もしその人に、何らかの程度でこの「下座行」的な体験があったとしたら、 その人は恐らく、高慢に陥ることを免れうるのではあるまいか。
人の師たる人はとりわけ、この下座の体験者であり、下座の行者であることが、 何より大事なことであることだけは、このわたくしにも納得せられます。
ある時、先生にお尋ねしたことがあります。 「どうして先生は隠れた真人の発見者であり発掘者でいらっしゃるのですか」と申し上げると、 「それは舞台に立ってから眺めておるとわからぬのです。 同じ平面の平土間に立つと、よくものが見えるのです」 とおっしゃられました。
アンダースタンドとは、理解するということですが、下に立つという意味にもとれると、 どなたから聞いたことがあります。
昨今は、自己アピール全盛の時代です。 自分を知ってもらわなければ、不当に評価され冷や飯を食わされる、 と自分を必要以上に大きく見せる人も多いです。 それとは、真逆な考え方が、この下座行です。
どんなに低く見られようと、それを、微塵(みじん)も不満に思わず、淡々と仕事をし、生活することです。 人よりも一段と低い位置に身を置き、不平不満を表さないことは、己を磨く修練であり修行です。
京都の一灯園は、それを掃除を通じて行っています。 見知らぬ家々のトイレの掃除をさせてもらうことが、己の高慢心を捨て、 下座に行ずる謙虚な心をつくるといいます。 人は、一生のうちには、何度か、高慢になるときがあります。
人は自分よりうまくいっていない人、 もっと下にいる人を見ると、見下したり、高慢になったりします。 「なぜ、こんなつまらない上司の下にいるのだろう」、 「どうして、こんなできの悪い妻(夫)と一緒になんだろう」、と不平不満、愚痴を言います。 なまじ学歴や、才能が自分にあると思っている人は、この罠(わな)に陥(おちい)りやすいものです。
自分の高慢心を打ち砕(くだ)く「下座行」は、年を重ねれば重ねるほど必要となってきます。
今日のブログはこちらから☞人の心に灯をともす
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
