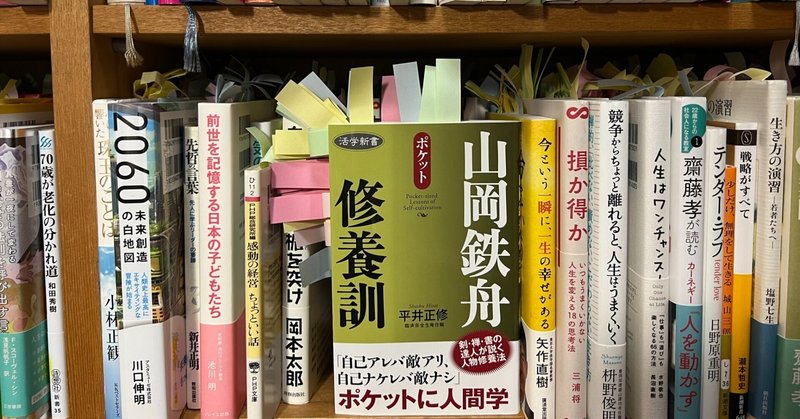
心が固くならないために
今日のおすすめの一冊は、平井正修氏の『山岡鉄舟修養訓』(致知出版社)です。その中から「冷暖自知」という題でブログを書きました。
本書の中に「心が固くならないために」という心に響く文章がありました。
《風にそよぐ荻(おぎ)の如(ごと)し。柔剛強弱此処(じゅうごうきょうじゃくここ)なり。》(山岡鉄舟)
「心は風にそよぐ荻のようであれ。 時には柔軟に、時には剛毅に、時には強く、時には弱く、そういうしなやかさが大切である」
心というものを荻にたとえている。 風が吹くまま右へ行ったり左へ行ったり、自由自在なしなやかな心が大切だという。 それは子供の心にも似ている。
子供は毎日毎日、朝から晩まで親に怒られているのにめげない。 何度注意してもいうことを聞かない。 最後は親が根負けするほどである。 人は皆、もともとそういう心を持って生まれてきた。
ところが、成長していくにしたがって体が硬くなるのと一緒に心も固くなっていく。 だから年寄は得てして頑固になる。 これは自然に固くなるというよりも、自分で固くしてしまうというほうが的確かもしれない。
私の母が湯河原のケア付きマンションに越したときの話である。 最初はそういう場所に行けば同年代の友達もできて、生活のペースも話題も合って暮らしやすいのではないかと思っていた。 ところが、そこに住んでいるのは年をとって頭が固くなっている人たちだから、新しい話題もなくて、話といえば昔話と食べ物の話と病気の話ばかりだという。
それはそれで気楽なのかもしれないが、そいう話ばかりしていると間違いなく老いていく。 学校の先生がいつまでも若々しいのは、いつも子供と接しているからだろう。 世代の違う人間と接するのは面倒なこともあるけれど、肉体的にも精神的にも自分を固くしないためにはそういうことも必要だ。
人は何もしなければ一つの考え方に凝り固まってしまう。 自分ではそれが正しいと思って生きているわけだが、その正しさとは自分勝手な正しさにすぎない。 だから百人いたら百人の正しさがあっても不思議ではない。
ところが、年をとると、それがなかなか理解できなくなっていく。 もっともっと本来の心の柔軟性、子供のめげない姿に我々は立ち返らないといけないだろう。
「俺は信念を持っている」という人を見ると凄いと思うが、信念などはなくてもいいのだ。 それが言い過ぎならば、少なくとも自分の信念をわざわざ口に出す必要はない。 「俺はこういう信念を持っている」と声高にいうのは、よほど自分に自信がないか、虚栄心の塊なのかのどちらかであろう。
相手の信念をも理解できる人ならばともかく、自分の信念だけを振りかざす人は信用ならない。 いつもしなやかな心でいたいものだと思う。
とかく我々は、人にバカにされまい、なめられまいとして、虚勢を張ってしまう。自分を大きく見せようとしたり、 偉そうにしてしまう。心が固くなっているからだ。
「柳に風」という言葉があるが、「馬耳東風」とか「暖簾に腕押し」とは意味がまったく違う。「柳に風」と逆らわずに、しなやかに「受け流す」ことだ。「行雲流水」という禅語と同じで、空を行く雲、川を流れる水のように、何事にも執着することなく、飄々と事に従って行動することだ。
「風疎竹(かぜそちく)に来る 風過ぎて竹に声を留(とど)めず」 という、菜根譚(さいこんたん)の中の言葉がある。 一陣の風が竹林に吹いたとき、竹はザワザワと音がする。 しかし、一旦風が通り過ぎてしまえば、竹林はまるで何事もなかったかのように静まり返る。
我々は、誰かに何か嫌なことを言われたり、バカにされたりすると、いつまでもそれに執着し、ザワザワとして心が静まることができない。 どんなときも、心をしなやかに保てる人でありたい。
今日のブログはこちらから☞人の心に灯をともす
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
