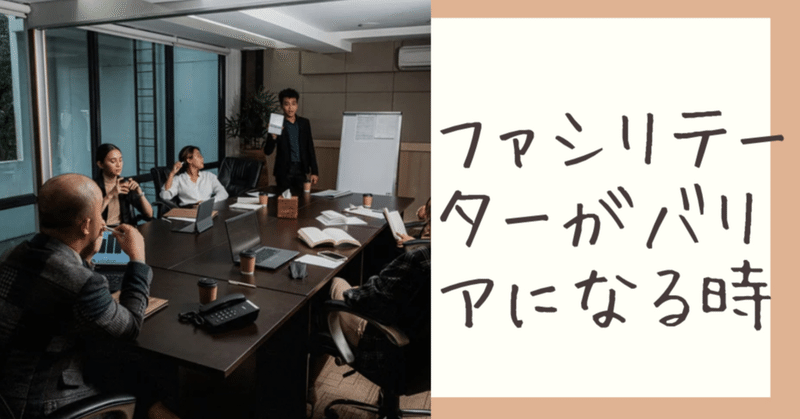
会議のバリアはファシリテーターだった。
ごきげんいかが?建替推進委員会に建替慎重派として参加した、日侶夢楽暮の順ヒロムラです。
今回の話は会議のあり方、進め方について感じた話をします。ヒロムラの主観の強い内容になっているかもしれません。ご承知おきください。
いきなりですが、先日、建替推進委員会に参加した私の感想です。
どっと、疲れました。
なぜなら、話を聞く耳を持っていない人たちの前で話をしたからです。話しても話しても、相手には響かず、無力感を感じてしまいました。
経緯は建替推進派が建替反対派(と思われている慎重派)の人の話を聞きたいと言われ、私が管理組合の理事長として、その人たちの声を集めることになってしまい、その役割をすることになりました。
2月の定例の案内書には「活発な討議をお願いします。」と書いてありました。それを読んだ瞬間、活発な討議って、、、、、対話ではないんだ。とガックリ。(後日、討議と討論の意味を私が勘違いしていたことが判明。討議って、悪い意味ではなかったけど、討つって漢字の印象がよくないな。と感じました。日本語知らず、共通言語がないと誤解が生まれることがよく分かりました。)
初めから相手に話を聞くつもりはなく、相手は戦う姿勢満載です。ある程度、覚悟はしていきました。会場に着くまでは。
会場に入った瞬間、空気が重い。
波動が合わないということをこんなにもダイレクトに感じたのは初めてです。それから、完全にアウェイの気分になりました。
建替推進委員の方々は、建替反対派の話を聞く気なので粗探しをするように話を聞きます。まるで、安保理で議長国がロシアであるような感覚です。
少しでも聞いてもらえる空気を作ろうと、アイスブレイクをしようとしたところ、余計なことは話さなくて良いと、ファシリテーターからピシャリ。
委員長がファシリテーターをするわけですが、よく観察するととにかく自分の思い通りに話を進めることが上手いのです。言葉使いも事実ではなく、ほとんど主観です。まるで洗脳作業です。(と私は感じました。)
皆さんの知ってるファシリテーターって、どんな役割ですか?私の知っているファシリテーターって、中立な役割です。
結果的に建替には反対ではなく、慎重であるということは伝わったみたいですが、私たちが求めている委員会の在り方については、受け入れられませんでした。彼らからすると、我々はどうも邪魔な存在のようです。
立場が違えば、見える景色が違うのは当然です。ただ、このままでは必ず越えられないバリアにぶち当たることは、複数の専門家を始め、慎重派には見えていて、今回の機会に推進派に問題点をお伝えしたのです。が、彼らには届かなかったようです。(現時点では。)
なぜ、こんなことになったのか、ここで振り返ってみます。
1番の問題だったのは、ファリシテーターが推進派の委員長だったこと。ではないかと私は考えます。
ファシリテーターは中立でない限り、有意義な意見交換、対話は成立しません。
建替推進において、リーダーである委員長のファリシテーターが1番のバリアだということに気がついた経験でした。
建替を多くの住民、市民が納得するよう、これからもっと、プレゼンテーション能力を磨きます!
最後までお読みいただきありがとうございました!
---------------
順ヒロムラの想い
誰もが生きやすい社会に貢献したい!
なぜなら、
私は知らず知らず、
ずーっと生きづらさを感じていたことに、
気がついたから。
人や社会に貢献することが、
幸せを感じる人生
だと、学び、知ってから、
日々実践しています。
noteでは、
ひと、まちのバリアを減らせるヒントや、
日々の気づきをお伝えします!
---------------
※企業、宿泊施設、学校などで
環境と心のバリアフリーや
組織やマインドの再構築のための
ボランティア活動活用について
講演する人をお探しであれば
DMからご連絡ください😌✨
---------------
最後までお読みいただき、
ありがとうございました!
あなたのスキが励みになります!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
