
尊敬されたいのにされない人
威張る人
威張る人というのは一見威張る理由を持っているように見えます。地位が上だとか、歳をとっているとか、その道の専門家だとか、本人としてはそれなりに理由はあるのでしょう。そして多くの場合、威張る事により尊敬されると思っています。しかし本当に力のある人は決して威張りません。
地位は現世だけで仮のものだからです。誰が本当に偉い人か、その優劣の差があるのかどうかは神仏のみが見極められる事です。
年寄りでも弱い年寄りほど、椅子に座って偉そうにしています。つまり総じて威張る人は弱い人です。もちろん人間は誰もが強くなければならないという事はありません。昔から弱そうだから男性にもてた女性はいました。しかし本来強くあるべき男性が、地位を利用して威張るのは最低の表現で弱さをさらけ出す事です。
幕末志士の思想的リーダーであった吉田松陰は自分が塾長であるにも関わらず松下村塾の塾生の誰に対しても『さん』付けで呼んで物事を押しつけるような話し方は一切したかったという事です。それでいて誰からも尊敬されていた事は有名です。
私が35歳くらいの頃、サウジアラビアのリヤドを訪問中に首席駐在員に言われて、一緒に同国の標準規格を作っている役所を訪問した事があります。到着してすぐ事務所に通されました。すると当時の日本の通産省から来たという出張員がいて、サウジ人がいる中で事務机の上に靴を履いたまま足を乗て、私達に上から目線で応対するのです。
そこで相手を見ると明らかに30歳前の童顔の男が命令口調で私達に指示をするのです。話の内容は当時の電子会議システムの見積もり依頼で、日本語による会話でしたのでサウジ人には理解できなかったと思いますが、周りにいる現地の人に対しても同じ日本人として恥ずかしく思いました。後で聞いたところによると、私は知らなかったのですが、日本では官僚の主任クラスは一般の会社の部長より位が上とされているとの事でした。
主婦同士の会話で『うちの夫は銀行の同期で出世頭なの』とか『私、クラス会で一番若いって言われたわ』などと自慢する女性がいます。これは自慢話だけで、威張らない事でみっともない人間にならなくて済みます。威張るという行為は、外界が語りかけてくる様々な本音をシャットアウトする行為です。謙虚に一人の人間として誰とでも付き合うと、誰もが貴重な知識を授けてくれます。それが自分を成熟した大人に導いてくれます。
知ったかぶりをする人
情報が巷に溢れている現代において『知らない事が無い』という事はあり得ません。つまり知らない事は別に恥ずかしくないのです。そんな時代なのについ冒してしまうのがメンバーとの会話での『知ったかぶり』です。これは避けるべきです。
たとえ『リーダーなら知っていないとおかしい』と周りから言われようと、たとえ相手が入社したばかりの新入社員であったとしても知らない事、分からない事は放置せず、その場で質問しましょう。
特に初めて会話する相手は、どのレベルで会話すべきか見極めようとしています。話し始めて『うん、うん』と分かっているような相槌を打ち続けていると、とんどん話が難しくなり、結局後から全く分かっていない事が明らかになって、時間が無駄になってしまいます。そうなると『表面を取り繕う人』『素直でない人』と見られて、これは信用が落ちます。
『それってどういう意味ですか?』と聞く事は『そんなことも知らないの?』『理解力が低いのでは?』という反応を呼ぶかも知れませんが、『聞くは一時の恥、聞かぬは末代の恥』とはよく言ったものです。『あのリーダーは素直な人だ』と好感を持って受け入れられる事も多いようです。
特にプロフェッショナルな人はむしろ、他人に頼られ、教えを請われる事は喜びであったりします。リーダーに知識がない事をあげつらう人はプロではありません。分からない事、理解できない事はどんどん尋ねればいいと思います。リーダーの勝負所は知識の量ではないのですから。
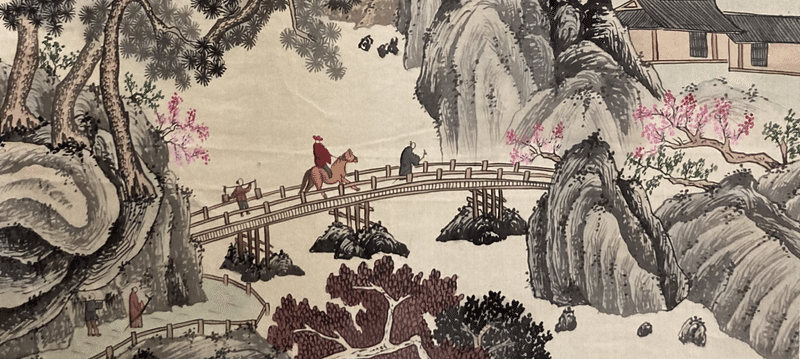
言い訳がましい人
注意をされた時に、誰が悪い、かれが悪い、関係部署の仕事が手抜きであった、時間が無かった、予算が足りなかった、体調が悪かった、天気が悪かった、等と自分の非を認めようとしない人がいます。
ひとこと『すみません、以後気を付けます』と言ってくれればそれで済むのになぜ謝って反省してくれないのか。例えば本当にそういう理由があったにせよ『すみません、私の努力不足で』とさえ言えばそれで事が丸く収まるのに。
こういう人達と付き合っていくにはこちらも忍耐力が必要です。相手が『もう言い訳も言い飽きた』という心境になるまでじっくり話をきいてあげるといいでしょう。特にこのタイプは自分の話を途中で遮られたりすると、ますます言い訳がましくなるという特徴があります。
話を最後まで聞いて、『あなたの言う事はよく分かります』と相手の話をまず肯定する。反省を促すのはそれからです。『けどね、こういう事も言えるのではないかな』ここから反撃します。相手は既に言い訳をし終えて飽きてきているから、こちらの話に耳を傾けるしかありません。じっくり話し込めば反省の言葉がぼつぼつ出始めます。
話し上手な人
一般的に言って、話し上手な人は自分の話術に自ら酔ってしまいがちです。自分の話術に酔う余り相手の事が見えなくなります。その為に相手が自分の言う事をちゃんと理解しているかどうか、どう感じているか、そんな事は関係なく喋りまくってしまいます。こうなると人と人との会話になりません。単なる演説であり、自己満足となって人には嫌われます。
また話し上手な人は自分の考えに固執しがちです。一方的に自分の考えを押し通そうとするから、ひとの忠告を最後まで聞かずに、途中で遮るようにして自分の考えを述べようとします。自分に都合の悪い事、考え方の違う人の意見には一切耳を貸しません。こんな頑固で偏った性格で思い込みの強い人が好かれるはずはありません。言い方によっては意志が強いともとれますが、本質は単に石頭な人です。
次に話し上手な人は己惚れやすい。地に足がついた努力をしなくても口がうまいというだけで世の中を渡っていけると思い込んでいる人がいます。更に口の上手くない人にはそれだけの理由で見下す。偏見が強くうぬぼれ屋、これだけでも人に嫌われるのは当然です。自分の言った事が相手にどうとらえられているかを冷静に知るには、話した後口を閉じて聞き役にまわりましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
