
或る「糸島の醤油蔵」伝 カノオ醤油(6) 稗田社長、稗田家と東屋について語る

(文中 敬称略)
■想像した以上に複雑だった、稗田家の血脈。
質問項目のシートをお渡しすると、まず社長の方から稗田家の代々の事業主について語り始められた。
◇ ◇ ◇
社長:「ばあさんがチラッと言いよったことがあったけど、えーと、ムツノは何代前になるとかいな・・・」
私:資料で見ると昭和16年にお名前が出てますね。

社長:「ああ。多分私の母・・・の母ですから、祖母に当たります」
私:なるほど。
社長:「うちはちょっと複雑でね。(持参した資料を指して)あの、ここに書いてある立樹、えーと、いや、ムツノは子供は多かったが男は全て死んだんですよ」
私:戦争でですか?
社長:「戦争とか、病気で。それで女しか残らんかったから、女が、1,2,えーと4人の娘が残ったのか。4人残ったうちの上から二番目にヤスノっていうのがおったんですよ。このヤスノが立樹という養子を貰ったんですね。で、この立樹が・・・・・えーと、おかあさん、立樹がおった醤油屋さんて名前なんやったかいね(と、女将さんに尋ねる)・・・・・あ、ヤマキ、ヤマキ醤油か。もう今はないんですけど、ヤマキ醤油さんで工場をしよった立樹をヤスノと結婚させたわけですよね」
私:なるほど、ヤマキ醤油から立樹さんがいらっしゃったと。
社長:「はい。それからその、立樹が養子に来たんですけど、ヤスノと立樹がうちの会社をしはじめたんですけど、だけど二人にまた子供ができなかったんですよ。それで、さっき残った4人姉妹の、ヤスノは立樹と結婚したんですけど、いちばん下にヒロコておったんですよね。これを後ば継がせるというか、ヤスノとヒロコが10ぐらい(歳が)違うから、どっかから養子もらわんでヒロコと養子縁組して、ここに稗田道敏と書いてある私の親父を養子に貰ったんですよ。そして立樹とヤスノの”子供”になった。だから複雑なんですよ」
二人:ほぉ・・・。
私:昔はそういうお話が多かったんですよね。
社長:「それで私は、何十年かぶりに男が生まれて大人に育ったのが久しぶりやったもんで、なんかお祝いかなんかがありよったですもんねえ(笑)」
私:磯右衛門さんが明治22年に創業されてますが、磯右衛門さんについての伝聞とか言い伝えは残ってますか?
社長:えーと、磯右衛門の次にケンジというのがおるんですよね、このケンジというのが多分ムツノの旦那ですよ。写真は無いけど、家系図に書いてあった。
私:では、世代としては、磯右衛門さん、ケンジ・ムツノさん、立樹・ヤスノさん、道敏・ヒロコさん、社長・女将さんの順番ですね。
◇ ◇ ◇
以上の話を整理するとこうなる。

事業主の系譜としては、磯右衛門→ケンジ→ムツノ→立樹→道敏→佳昌(現社長)となろうか。
それと(4)章のまとめで整理した「テーマ4:1927年に記録された2蔵は、1941年の『楢崎克来、稗田ムツノ』の二人か。1927年の時点での事業主は誰なのか。事業主の系譜は?」については、社長のお話から稗田ケンジだった可能性が高い。ケンジに何かがあって、その妻であるムツノが事業主となったのではないか。ただ、系譜を裏付ける文書などは火事で失われて詳らかにならないのかもしれない。

■意外なところで、東屋政右衛門の末裔が判明・・・・か?
私:次の質問ですが、近世から明治にかけて加布里で醤油屋を営んでいた東屋(あずまや)政右衛門と辻治助のことなんですが、地元でなにか伝聞は残ってますでしょうか。
社長:「えーとね、うん、東屋(ひがしや)さんっていうのはあって、うちの近所に、私の小さい頃はスーパーやったですが、東屋(ひがしや)さんっていうお店があったんですよ。」
私:(資料を指して)これと同じ字ですよね。
社長:「そう。ひがしや、ひがしやって言いよったですもんね、ま、個人の商店やったですよ。それは覚えがあります」
二人:へえ・・・。
社長:「それで東屋っていうのは、たぶん会社は、お店は東屋という名前やけど・・・しよんしゃぁ人は”末松さん”ていう・・・・」
二人:えええ!!!
私:いやぁ、それは間違い無く子孫の方では? 東屋政右衛門の本名は「末松」なんですよ!
社長:「ああ、ならそれだ!」
私:わぁ、政右衛門の後は、商店になっていたんですねえ。
社長:「私たちは小さい頃、買いに行きよったですもんね」
私:場所は、どの当りでしたか?
社長:「えーとね、うちの玄関出て、左に行くじゃないですか、そして突き当たりをさらに左に行って、お寺さんの近くですよ」
私:では、東屋政右衛門または辻治助と、稗田磯右衛門との直接的な関係は無かったということでよろしいでしょうか。
社長:「そうですね、その辺は聞いてないからね、ええ、私はいままで聞いたことでいけば、そうです」
(ところが、辻治助については蔵訪問後に意外な事実が判明する)
私:それで楢崎さんという醤油屋さんなんですが。
社長:「そうそう、楢崎さんという醤油屋があったらしいですよ。詳しくはわからんが。昔は、加布里には7〜8軒くらいあったらしいですからね、醤油屋が、加布里だけでもね」(末尾、追記1を参照)
二人:へえ〜。
私:表に「麹屋」の古い看板がありますけど、初代が『楠田屋本店』としてスタートした際は、麹屋としてでしょうか、それとも当初から醤油も味噌も兼業されていたのですか?
社長:「最初から兼業やったと思いますね。・・・私が若い頃は楠田屋の息子、楠田屋の息子と言われよったです。叶さんと言われんで、楠田屋さんてね」
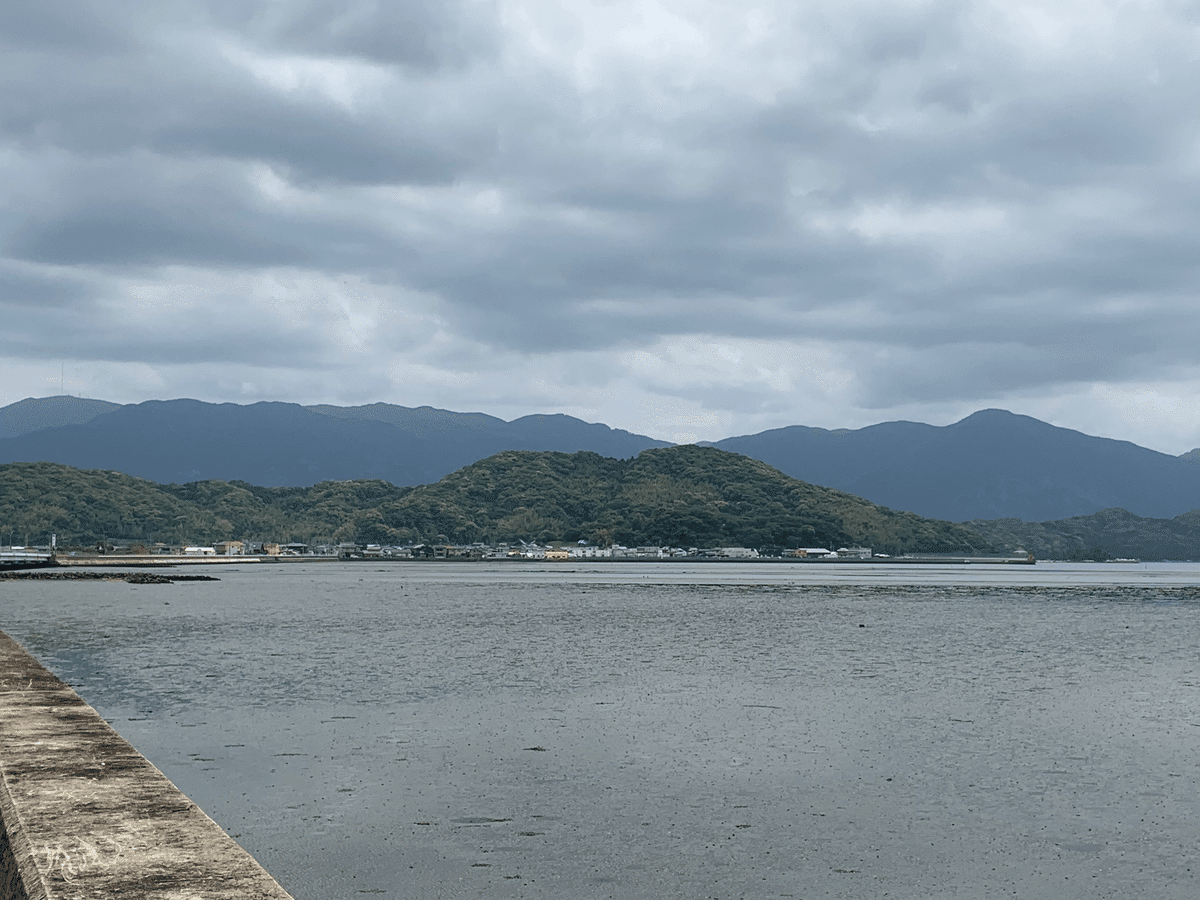
福岡市立総合図書館でさらに調べを行い『福岡県史』を確認していて良かったと思った。でなければ、一次資料に拠って政右衛門の姓が判明しなかったからだ。遠回りになるところだった。
もう100年以上前のことである。東屋政右衛門自身の事跡は明らかにはならなかったが、その末裔と覚しい方が今もいらっしゃることは解った。
それにしても往時は7軒か8軒も加布里に醤油屋があったという事実に驚く。そして加布里において、どうしてカノオ醤油だけが蔵を守りきって21世紀の今も存続し得たのか。また新たな課題が浮かんで来た。
しかし記録として残る1927年以前のこととなるので、探索はもう困難かもしれない。
続いて、カノオ醤油のかつての”生存圏”を探ってみる・・・。
■備考1(2022年7月26日追記):「昔は、加布里には7〜8軒くらいあったらしいですからね、醤油屋が、加布里だけでもね」

『大日本商工録』昭和6年版に加布里の醬油醸造元が列記されていた。これによると、楠田屋本店(カノオ醤油)の稗田賢次、楢崎克来、楢崎顕三、稗田竹次郎の4名の醸造元が確認できる。ただし『大日本商工録』の記載蔵を通年でチェックしてみると、すでに起業している蔵元の名前が入っていない場合も多くあって、記載の無い蔵元が存在する可能性が高い。
■備考2:
末松(東屋)政右衛門については、ネット上で下記の情報が検索できた。
『一般財団法人加布里末松政右衛門ふれ愛基金』
『千早新田地蔵菩薩 仏教礼拝所』
「案内板(前原市による)によると、天保4年(1833)、ここより北500m、東西約1kmにあった川洲が干拓工事により田園化されたという。 おそらくこの地蔵堂は、その年以降に干拓を記念して建立されたものであろう。
同案内板によれば、当時この地は天領で日田代官塩谷大四郎の訓令により天保3年に起工、 翌4年に築堤が完了した。総面積3768アール。 加布里の富豪東屋こと末松政右衛門と、岩本の油屋こと牛原藤蔵が協力し、私財を支出して完成させたという。 」(上記サイトより)
『糸島の干拓と千早新田 2018年8月-9月』
このサイトは本編でも引用させていただいた『怡土志摩地理全誌』の著者由比章祐氏のお孫さんが管理されている『猫間障子』というサイト。
(7)に続く。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
